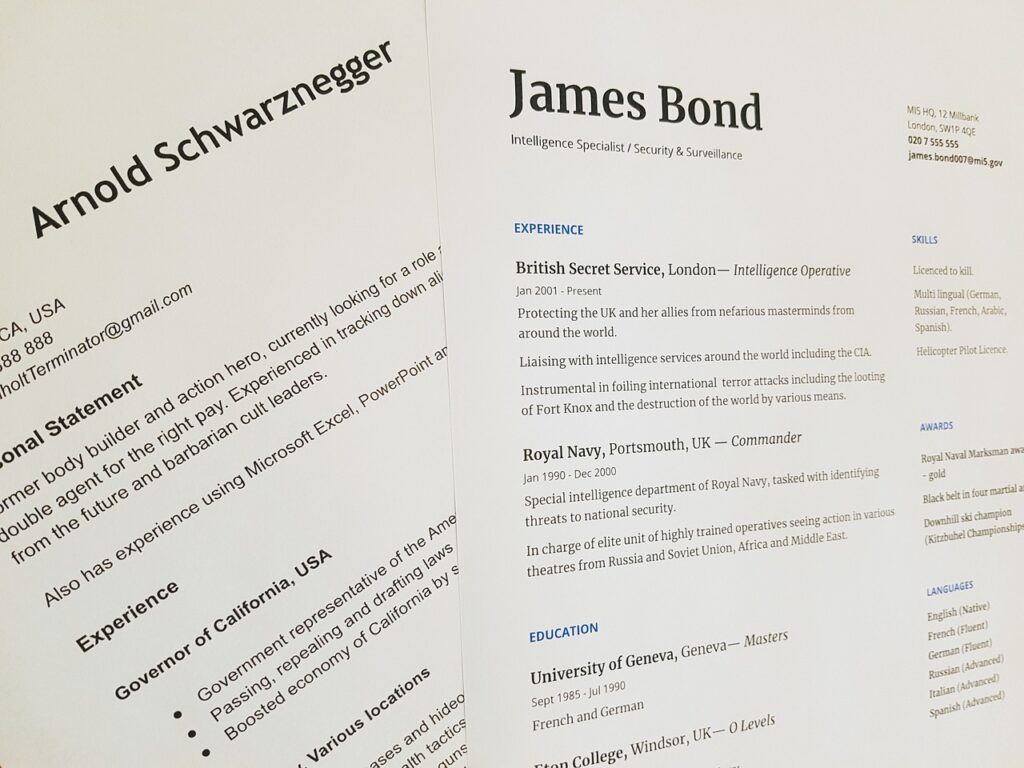【確定申告】フリマアプリで利益20万円超えたら要注意!2025年最新版「申告ルール」を徹底解説

フリマアプリの売上、確定申告が必要か知っていますか?
スマホの普及により、メルカリやラクマなどフリマアプリを使って、不用品や中古品を簡単に売却する人が急増しています。
特に年末年始や引越しシーズンとなるこの時期は、不要になった家具や家電を売って、ちょっとした副収入を得る人も多いのではないでしょうか。
でも、実はこうしたフリマアプリで得た収入には、確定申告が必要になる場合があるのをご存じでしょうか?今回は「2025年最新版のフリマアプリ収益に関する確定申告ルール」を詳しく解説します。
フリマアプリの収入が「課税」される基準とは?
まず理解しておきたいのは、フリマアプリで得たお金が必ずしも課税されるわけではないということです。
ポイントとなるのは、売却した物の性質と利益の額です。次に、どのような場合に課税対象になるのかを詳しく見ていきましょう。
日常生活用品を売った場合は基本的に課税対象外
一般的に、日常生活で使っていた家具や家電などの生活用品を売却した場合、購入時よりも売却価格が低いことがほとんどでしょう。
この場合は利益が発生していないため、課税されることはありません。
たとえば、5年前に購入した20万円のテレビを12万円で売ったとします。この場合、8万円の損失が出ている状態であり、税務署への申告は不要となります。
購入価格より高く売れたケースは「課税対象」
しかし、趣味やコレクションとして購入した希少性の高いアイテムを売却した場合は注意が必要です。こうした品物は購入価格を上回るケースがあり、その差額は利益として扱われるため、課税対象になります。
例えば、限定品の時計を10万円で購入し、フリマアプリで25万円で売却した場合は、15万円の利益が出ています。
この利益額が後述する申告ラインを超えると、確定申告が必要になります。
「年間利益20万円」を超えたら確定申告が必要(給与所得者の場合)
会社員やパート・アルバイトなど、給与所得者にとっての確定申告の基準は、「フリマアプリで得た年間利益が20万円を超えるかどうか」です。
この20万円とは、売った金額ではなく「利益(売却価格から購入価格を引いた額)」である点に注意しましょう。
20万円のラインを超える具体的なケース
実際の例を考えてみましょう。
例えば、2025年の1年間で以下の取引をしたと仮定します。
- 限定モデルのバッグ:利益8万円
- コレクションしていたアニメグッズ:利益10万円
- 人気スニーカーの転売で利益7万円
これらを合計すると24万円となり、確定申告が必要になります。
逆に言えば、年間の利益合計が20万円以下であれば、税務署への申告は不要です。ただし、課税の有無に関係なく、購入時の領収書や売却履歴を残しておくことを強くおすすめします。
自営業者や年金受給者は「年間所得48万円」を基準に注意
ここまでは給与所得者の場合についてお伝えしましたが、自営業者や年金を受給している方の場合は、状況が少し異なります。
自営業者や年金受給者が確定申告をする必要があるのは、年間の所得(収入から経費を引いた額)が基礎控除額の「48万円」を超える場合です。
また、「営利目的での転売」を行っている場合は、たとえ利益額が少額でも申告が必須です。これは営利目的の販売が「事業所得」や「雑所得」として扱われるためです。特に最近では「趣味の延長」のつもりが税務署から営利目的と判断されるケースもあるので注意が必要です。
営利目的か生活用品か、その違いを理解しよう
フリマアプリでの販売が「営利目的」か「生活用品」かを判断する基準は主に次の通りです。
- 「転売を目的として定期的・継続的に商品を仕入れて売却している」場合 → 営利目的(課税対象)
- 「普段使っていて不要になったものを単発的に売却している場合」は生活用品 → 多くの場合は非課税
明確なルールが設定されているわけではないため、最終的には税務署が判断します。自己判断に不安がある場合は、税務署や税理士に相談するのが安心です。
事業とみなされると「雑所得」か「事業所得」で申告
営利目的の転売と判断される場合、その利益は「雑所得」または「事業所得」として申告が必要になります。
雑所得は他の所得と合わせて総合課税されるため、金額が少額でも所得税や住民税、場合によっては国民健康保険料にも影響が出ます。
収入規模が大きくなると「事業所得」として申告することになり、青色申告による節税メリットも活用できます。
フリマアプリ利用時に押さえておくべき注意ポイント
最後に、フリマアプリを使って不用品を販売するときに注意しておくべきポイントをまとめました。
売買記録をしっかりと残しておくことが重要
フリマアプリでの取引については、購入時の金額や販売日時、購入履歴などをしっかり記録しておくことが大切です。
利益額の計算が必要になった場合や税務署から問い合わせがあった場合にも、客観的な資料があるとスムーズに対応できます。
曖昧な部分は税務署・税理士に相談しよう
「これって課税対象?」「申告したほうが良いの?」など、少しでも不安がある場合は、近くの税務署や税理士に早めに相談しましょう。
後から指摘を受けて税金や延滞税がかかる事態を避けるためにも、疑問はそのままにしないことが重要です。
まとめ:「申告漏れ」は未然に防げる
フリマアプリは手軽な副収入として非常に便利なサービスですが、税金のルールを理解しておかないと、後々面倒なことになる可能性もあります。
特に2025年以降、国税庁もネット取引に対する監視を強める可能性がありますので、注意が必要です。
今回ご紹介したルールをしっかり押さえて、安心してフリマアプリを活用しましょう。