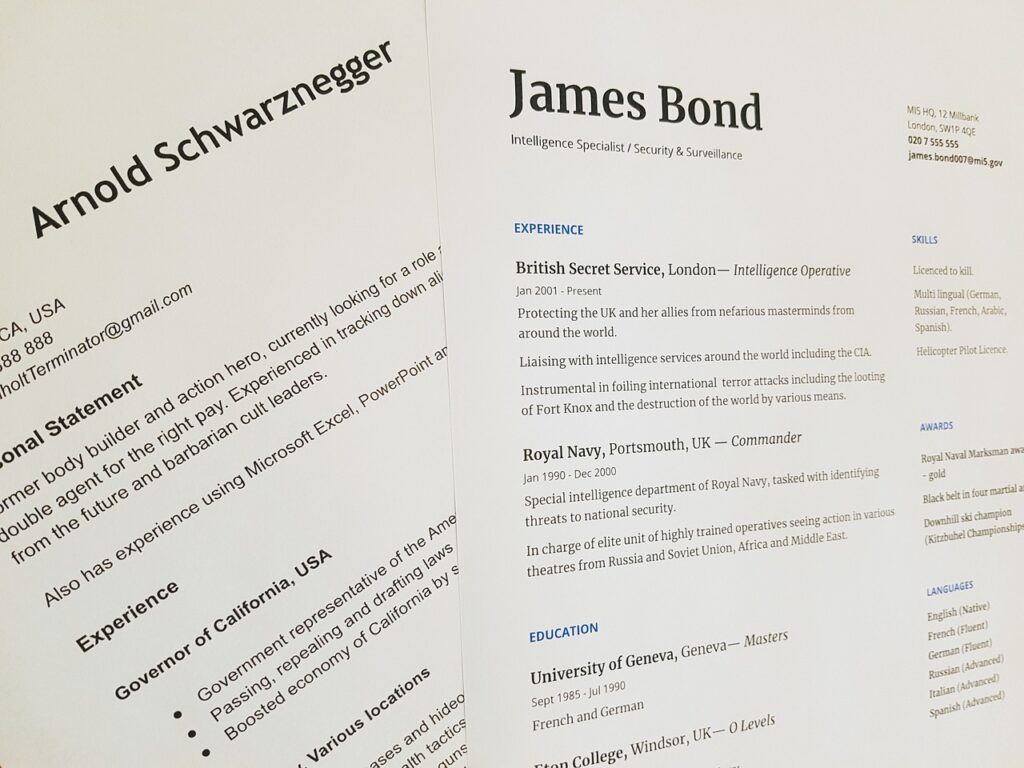【社会保険】2025年改正『産後パパ育休制度』利用で、実際に手取りはどうなる?

2025年改正『産後パパ育休』とは?
2025年4月から、『産後パパ育休』(出生時育児休業制度)の一部が改正されます。
この改正により、男性が育児休業を取りやすくなるよう、給付額や利用期間などが大幅に改善されます。具体的にどのような変更があるのか、そして実際に手取り収入にどれくらい影響するのかを解説します。
改正される主なポイント
2025年改正の主なポイントは以下の3つです:
- 産後パパ育休の給付率が従来の約67%から最大80%に引き上げられる。
- 「産後パパ育休」の取得可能期間が「出生後8週間以内」から「出生後12週間以内」まで延長される。
- 取得可能な日数が「最大28日間(約4週間)」から「最大56日間(約8週間)」に延長される。
これにより、男性もより長期間、安心して育児休業を取得できるようになります。
実際に手取りはいくらになる?具体例でシミュレーション
では、実際に給付率が80%になった場合、男性会社員が産後パパ育休を取得すると、どのくらいの手取り収入が確保されるか具体的に見てみましょう。
【シミュレーションの前提条件】
- 男性会社員(35歳)
- 月給30万円(手取りで約24万円)
- 産後パパ育休を1ヶ月(約30日間)取得
- 給付率80%(2025年改正後)を利用
【産後パパ育休中の給付額の計算】
- 給付の基準となる月給:30万円
- 給付率:80%
計算式は以下の通りです:
つまり、産後パパ育休を1ヶ月間取得した場合、手取りは約24万円となり、ほぼ普段の手取り収入(24万円)と同じ程度が確保されることになります。
給付金の80%は本当に「手取り額」と同じ水準?
育児休業給付金(産後パパ育休中に受け取る給付金)は非課税であり、所得税や住民税、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)などが引かれません。
そのため、給付率80%で計算される金額は実質的な「手取り額」となり、普段の給与から引かれている税金や社会保険料がないため、給料の手取り額に近いか、場合によっては実質的に増えることもあります。
【給与と育児休業給付金の比較例】
具体的に比較してみましょう:
| 項目 | 通常勤務(月額) | 育児休業給付(月額) |
|---|---|---|
| 額面の給与(基準額) | 30万円 | 24万円(80%) |
| 所得税・住民税 | 約3万円 | 非課税(0円) |
| 社会保険料 | 約4万円 | 免除(0円) |
| 実際の手取り額 | 約23万円 | 24万円(非課税) |
「社会保険料が免除される」ことのメリットとは?
2025年の産後パパ育休制度では、育児休業期間中の社会保険料が全額免除されます。免除期間中は年金額の計算上も支払ったものとみなされるため、将来の年金が減る心配もありません。
この制度は、本人だけでなく、雇用主(会社)にも社会保険料免除のメリットがあります。これにより、企業側も積極的に男性の育児休業を支援しやすくなっています。
2025年以降の「産後パパ育休」取得で気をつけるポイント
実際に育児休業を取得する際には以下のポイントに注意が必要です。
- 給付金は会社経由またはハローワークから支給されます。受給するには本人や会社が一定の手続きを行う必要があります。
- 給付金の算定基準は「育休前6ヶ月の平均給与額」を基準に決定されるため、残業代などで給与に変動がある場合、給付金額も変動します。
- 「手取りが減らない」というメリットを最大限活用するためにも、事前に自分の給与明細や会社の制度を確認しておきましょう。
結論:2025年の産後パパ育休で手取り収入は実質的に維持・増加する可能性も!
2025年の改正で給付率が80%に引き上げられ、育児休業給付金が非課税かつ社会保険料が免除になることにより、多くの男性会社員にとって産後パパ育休を取得しても手取り額はほぼ減らない、またはむしろ増える可能性が出てきます。
これにより、男性が家庭で育児に参加することの経済的ハードルがさらに低くなります。企業にとっても従業員が安心して育休を取れるよう支援するメリットが増すでしょう。
2025年以降、家族が増える男性の皆さんにはぜひ産後パパ育休を活用し、新しい家族との時間を大切にしてほしいと思います。