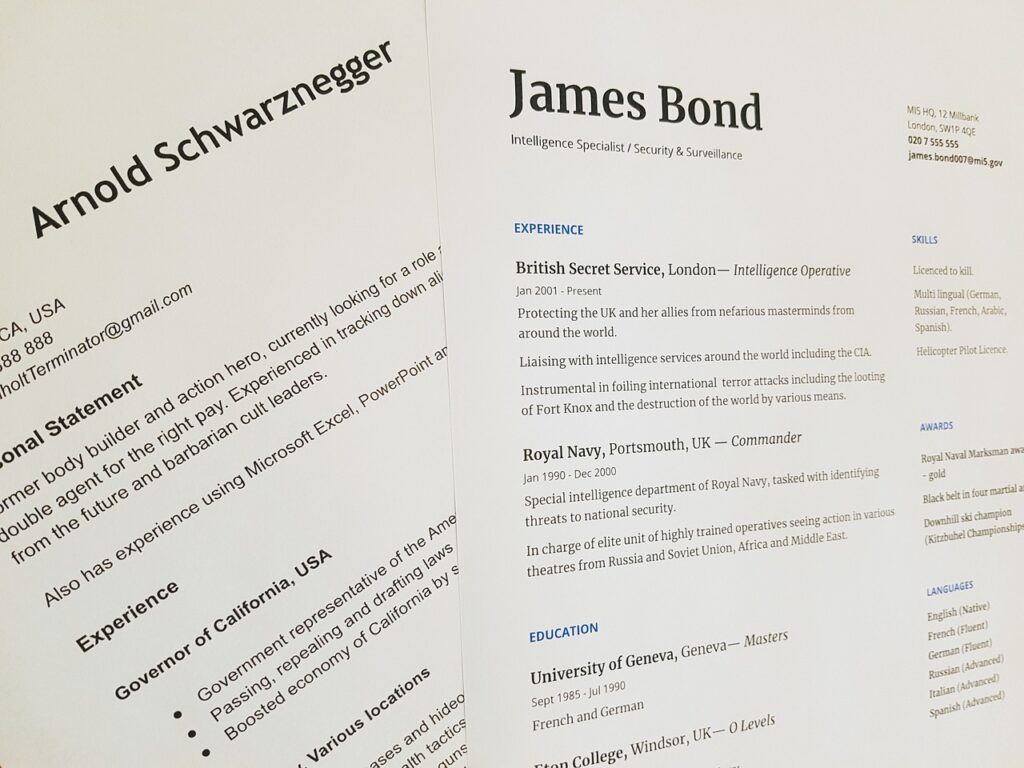『2025年4月スタート!社会保険適用拡大で収入が激変するパート主婦のリアル』

2025年4月、パート主婦の収入に大きな変化が
2025年4月から、パートやアルバイトとして働く主婦(主夫)にとって重要な社会保険の制度改正がスタートします。
これまで社会保険の加入義務がなかった層にも加入対象が広がることで、家計に与える影響が注目されています。今回は、その具体的な影響を実際の事例とともに解説します。

社会保険の適用拡大とは?
2025年4月からの改正により、これまで社会保険(厚生年金・健康保険)の対象外だったパートタイマーやアルバイトでも、以下の条件を満たす場合は社会保険への加入義務が生じます。
- 従業員数が51人以上の企業に勤務
- 週の労働時間が20時間以上
- 月収が8万8,000円以上(年収106万円以上)
- 2ヶ月を超える雇用期間が見込まれる
これまで130万円の扶養内で働いてきた主婦(主夫)にとって、非常に大きな影響が出る可能性があります。
実際に起きる手取り収入の変化とは?
例えば、週4日・月収9万円(月72時間勤務)のパート主婦のAさんを例にしてみましょう。
社会保険加入前の状況
- 月収:9万円
- 扶養内で社会保険料負担なし
- 所得税はほぼ非課税(給与所得控除内)
- 手取り:9万円(ほぼ全額)
社会保険加入後(2025年4月以降)
- 月収:9万円
- 厚生年金保険料:約8,235円(2025年見込み額)
- 健康保険料:約4,455円(2025年見込み額)
- 社会保険料合計:約12,690円
- 手取り:9万円 – 12,690円=約77,310円
加入前後で、毎月約12,690円もの手取りが減少します。年間では約15万円以上の減収となります。
手取り収入減少でもメリットはある?社会保険加入のプラス面
社会保険に加入すると手取り収入は減りますが、一方で加入によるメリットも見逃せません。
① 将来の年金額が増える
パート主婦が社会保険に加入すると、厚生年金の加入期間と支払額が増えるため、将来的に受け取れる年金額が大きく増加します。
これは老後の安定した収入源となり、長期的にはメリットとなるでしょう。
② 傷病手当金や出産手当金が受けられる
社会保険加入者は病気やケガで働けない場合、「傷病手当金」を受給できます。
また、女性の場合は出産前後に仕事を休む場合、「出産手当金」も受け取れます。いざというときに頼りになる安心感があります。
③ 健康保険の保障範囲が広がる
健康保険に加入すると、医療費の自己負担額が3割で済みます(扶養内と変わりませんが、企業によっては健康診断など福利厚生が充実している場合もあります)。
働き方を見直すパート主婦が増加
手取り減少を避けるため、働き方を見直すパート主婦も増えています。
具体的な対応策としては以下のようなものがあります。
- 勤務時間を減らし、収入を月8万8,000円未満(年収106万円未満)に抑える
- 逆に勤務時間を増やして収入を上げ、手取りの減少分をカバーする
- 勤務先を従業員数が50人以下の企業に変更する(社会保険適用対象外)
家庭ごとに適した選択は異なりますが、これを機に働き方を再検討する良いタイミングとなっています。
パート主婦が今やるべきこととは?
2025年4月の社会保険適用拡大に向けて、パート主婦が今から行っておくべきことを整理しました。
- 勤務先に社会保険加入対象となるか事前に確認する
- 加入対象となった場合の手取り収入のシミュレーションをしておく
- 家族で今後の働き方や収入の目標について話し合う
早めの対策と準備が、収入の変動による家計への影響を最小限に抑えるカギになります。
まとめ:制度改正はピンチにもチャンスにもなる
2025年4月からの社会保険適用拡大は、パート主婦の手取り収入に確実に影響を与えます。
一見すると収入減少というネガティブな変化にも見えますが、社会保険加入による安心感や将来の年金増額など、長期的なメリットも大きいのです。
制度改正をきっかけに、働き方を見直したり、家族で将来設計を考えるチャンスにもなります。今後の働き方を冷静に見直し、しっかりと準備して2025年4月を迎えましょう。