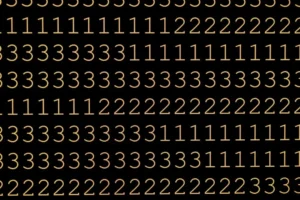学資保険 vs 新NISAのどっちを選ぶべきか?それぞれのメリット・デメリットを価値観別に徹底比較

この記事で分かること
- 学資保険と新NISAを選ぶうえでの3つのポイント
- 併用することでリスクリターンをバランス良くカバー
- 相談するならソニー生命のライフプランナーがおすすめ
と悩む方は多いでしょう。
学資保険は確実性が高くリスクが低い一方で、新NISAは運用次第で大きなリターンが狙えます。
 ねくこ
ねくこ本記事では、それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較し、どちらが自分に適しているかを解説します。
| 項目 | 学資保険 | 新NISA |
|---|---|---|
| スタートできる年齢 | – 子ども:0歳~7歳(保険によって異なる) – 保護者:~60歳前後が多い | 18歳以上 |
| リスク | 低リスク | 高リスク(相対的に/元本保証はない) |
| リターン | 低リターン | 高リスク・高リターン(元本保証はない) |
| 税制優遇 | 一般生命保険料控除の対象 | 運用益は非課税 |
| 資金の拠出期間 | 一時払い~18歳ごろまで(保険会社によって異なる) | 無期限 |
| 途中で引き出したい場合 | 可能。元本割れリスクあり | 可能。元本割れリスクあり |
| 運用にかかる税金 | 保険金は課税対象 | 拠出に関する税制優遇はなし |
| 被保険者・運用者に万が一があった場合 | 残りの保険料は免除、満期保険を受け取れる | 保証なし |
学資保険と新NISA、それぞれを選ぶ際に押さえたいポイント
お子さまの将来に向けた資産形成を考える際、自分に合った選択をするためには、まずは以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
3つのポイント
- リスクとリターンを正しく理解する
- 目的を明確にして選択肢を絞る
- 運用期間と資金計画のバランスを考える
 ねくこ
ねくこどちらを選ぶか迷ったら、まず“自分が何を重視するのか”をはっきりさせることが大切です。
この3つのポイントを押さえれば、自分に合った方法が見えてきますよ。
リスクとリターンを正しく理解する
| 比較項目 | 学資保険 | 新NISA |
|---|---|---|
| 運用期間 | 満期まで(お子さんの進学時期) | 任意 |
| 流動性(換金のしやすさ) | 低い(途中解約は返戻率低下) | 比較的高い(いつでも売却可能) |
| リスク許容度 | 低リスク・低リターン | 比較的高リスク・高リターン |
学資保険は低リスク・低リターンの金融商品です。
満期まで契約を続ければ元本割れする可能性は低く、将来受け取る金額が契約時にほぼ確定しています。
一方でリターンは小さく、現在の低金利下では18歳時に受け取れる額が「元本に多少色がついた程度」に留まるケースもあります。
新NISAでの投資は(相対的に)高リスク・高リターンです。
預金や保険のような元本保証はなく、運用がうまくいかなければ資金が減少するリスクがあります。
しかしその代わりに、運用成果が良ければ資金を大きく増やすことも可能で、インフレなどによる貨幣価値の変動にもある程度対応できます。
 ねくこ
ねくこNISAが高リスクというのは、あくまで学資保険と比べて相対的に、という意味です。
どちらを選ぶべきか迷ったら、自分のリスク許容度をまず把握することが大切です。
目的を明確にして選択肢を絞る
まず、教育資金準備の目的をはっきりさせましょう。
「確実に目標額を積み立てたい」場合は学資保険
毎月決まった保険料を払い込めば所定の時期に所定の金額を受け取れるため、リスクを取りたくない人や計画的かつ確実に教育費を用意したい人におすすめです。
「資金を増やせる可能性を重視したい」なら新NISAでの運用が候補に
新NISAは損失リスクを伴いますが、運用結果が良ければ学資保険より大きなリターンを期待でき、リスクを許容できる人になら有力な方法です。
また、教育費“だけ”でなく資産形成全般も視野に入れるなら、使途が限定されない新NISAの柔軟性が魅力です。新NISAで得た運用益は任意のタイミングで現金化でき、教育費以外の目的にも自由に活用できます。
 ねくこ
ねくこ大事なのは“目的に合った手段を選ぶこと”です。
「教育費専用に確実に貯めたい」のか「将来的な資産形成も兼ねて増やしたい」のか、自身の目的を明確にすることで選択肢が絞り込みやすくなります。
運用期間と資金計画のバランスを考える
「いつまでに、いくら必要か」を見定めて、教育資金の必要額と時期から逆算して計画を立てることも重要です。
学資保険の場合
- 運用期間:加入できる年齢や払込期間、受取時期が商品ごとに設定
- 安定性:受取額とタイミングが契約時に確定しているため、計画的に資金を準備できる
- 途中解約のリスク:途中で解約すると解約返戻金が支払った保険料を下回る可能性が高いため、長期的な運用を前提に計画を立てる必要
- 満期までの継続:一度契約を結んだら、満期まで継続する前提で計画を立て、解約リスクを避ける
新NISAの場合
- 運用期間:特になし
- 安定性:投資額が市場に依存するため、必要額に届かないリスクも。余裕を持った資金計画が必要
- 途中解約のリスク:必要な時期の少し前に売却して現金化する、あるいは利益が出た段階で確保するなど、市場の動きに応じて戦略を考える
- 満期までの継続:満期はないが、長期的な運用が効果的。マーケットのタイミングに備えることも重要。
まとめたのが以下の表です。
| 特徴 | 学資保険 | 新NISA |
|---|---|---|
| 運用期間の固定性 | 契約時に運用期間が確定、途中で変更は難しい | 投資期間に柔軟性があり、必要に応じて運用期間を調整可能 |
| 受取額の確定性 | 受取額とタイミングが契約時に確定 | 市場の動向によるため、受取額は不確定 |
| 途中解約のペナルティ | 途中解約すると解約返戻金が払込保険料総額を下回る可能性が高い | 途中で引き出してもペナルティはないが、投資収益が変動 |
| 流動性 | 流動性が低く、満期まで資金を拘束 | 高い流動性、必要な時に資金を引き出せる |
| 市場リスク | 市場変動の影響なし(保険契約時に確定) | 市場リスクに晒される、変動に応じて戦略が必要 |
| 資金計画の立てやすさ | 資金計画が立てやすく、安定的に準備できる | 市場動向に影響されるため、慎重な計画が必要 |
| 柔軟性 | 少ない、契約後は変更が困難 | 高い、運用方法や引き出しタイミングを自由に調整可能 |
 ねくこ
ねくこどちらの手段を選んでも、“必要な時に確実に使えるか”が最重要です。
学資保険の満期設計と新NISAの柔軟性を比較検討し、自分の資金ニーズと期間に合ったバランスを見極めましょう。
ローリスク重視なら学資保険を選ぶ理由
学資保険のメリット
- 安定性
市場変動の影響を受けにくく、元本割れリスクが低い - 保険機能
親に万が一のことが起きても保険料免除などで備えられる - 強制的な積立
途中解約のデメリットがあるため、計画的に貯めやすい - 教育資金の受取タイミングが明確
満期を子どもの進学時期に合わせて設定しやすい
学資保険は教育資金準備の手段として安定性に優れています。
元本割れのリスクが低く、契約時に将来受け取れる金額がほぼ確定しているため、計画通りに積み立てれば想定通りの資金を用意できます。
(預貯金よりは利回りが良い商品もありますが、)大きなリターンは望めない代わりにリスクが極めて小さいのが特徴です。
学資保険がおすすめの人
- 堅実に貯めていきたい人
- 保障も受けたい人
- 投資のリスクを取りたくない人
 ねくこ
ねくこ極めて例外的なケースまで含めても、安全性が高く安定志向の方に向いていると言えます。
保障機能で万が一に備えられる
また、学資保険には保障機能が付いている点も見逃せません。
契約者である親に万が一のこと(死亡や高度障害状態など)が起きた場合、その後の保険料払込が免除され、契約はそのまま継続して満期金等を受け取れる商品があります。
これは、親にもしものことがあっても子どもの教育資金を確保できる大きなメリットです。
さらに学資保険によっては医療特約を付加することで、お子さまの入院・手術費用などの医療保障をセットにできる場合もあります。
 ねくこ
ねくこ例えば病気やケガで入院した際に、医療特約を付けておけば所定の給付金を受け取れるため、教育資金準備と同時に医療面の備えも可能です。
こうした保障機能により、貯蓄だけでなく万が一への備えも兼ねられる点は学資保険ならではの強みです。
強制力のある積立で確実に資金を用意できる
学資保険は半ば強制的な積立の仕組みになっているため、確実に資金を準備しやすい側面があります。
契約すると毎月決まった保険料が自動的に口座から引き落とされるので、意志に関係なく積立が継続されます。
また前述の通り途中解約すると大きく元本割れする恐れがあるため、解約のハードルが高く心理的なブレーキが働きます。
 ねくこ
ねくここの「やめにくさ」こそが、計画を途中で投げ出させない強制力として機能し、結果的に目標額の達成につながります。
毎月一定額を払い込む仕組みは家計管理の面でも有用で、支出の優先順位として教育費を先取りできる効果があります。
貯金だとつい他の出費に回してしまい貯め残しがちという方でも、学資保険なら契約に沿って確実に積立が進むでしょう。
ただし契約時には無理のない保険料設定にすることが重要です。
 ねくこ
ねくこ半強制的な積立のおかげで着実に資金を用意できる一方、一度組んだ計画を途中で崩すと損失が出るため、計画通り続けられる金額か慎重に検討しましょう。
(相対的に)ハイリスク・ハイリターンを狙うなら新NISAも検討を
新NISAのメリット
- 市場の成長を取り込めれば高いリターンを狙える
- 運用益・配当金などが非課税
- 新NISAは非課税枠が無期限で、長期投資で複利効果を狙いやすい※
新NISAのデメリット
- 市況が悪化すると大きく損をする恐れも
- 非課税枠に最大1800万円の上限がある
- 途中で資金が必要になった時に、損失を抱えたまま売却するリスクも
※新NISAの年間投資枠は「つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円=合計360万円」、生涯非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は最大1,200万円)です。2024年1月の制度改正で非課税期間が無期限化され、売却すれば翌年に枠が復活する仕組みも導入されました。
一方、運用によるリターンを追求したい場合は新NISAの活用も選択肢に入ります。
新NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得られた売却益や配当金が一定枠まで非課税になる制度で、株式や投資信託の成長によって学資保険以上のリターンを期待することができます。
 ねくこ
ねくこ例えば世界経済の成長に合わせて運用すれば、長期的には預貯金や保険より高い利回りが得られる可能性があります。
ただし新NISAでの運用は市場環境によっては運用結果が悪化し、目標としていた教育資金に満たなくなったり、元本割れの損失が出たりするリスク※もあります。
※例として、リーマン・ショック級(2008年〜09年)の世界株式指数はピーク比-50%前後まで下落しました。同様の局面が入学直前(例:高校3年時)に到来すると評価額が半分になる想定も必要です。投資信託の信託報酬(年0.1〜1%台)や売買手数料も複利効果を削り、長期では数十万円単位の差が生じます。
新NISAがおすすめの人
- リスクを許容できる人
- 教育費だけではなく幅広い用途に準備したい人
- 運用次第でのリターンに期待したい人
\新NISAの基本をおさらいしたい方はコチラ!/

比較的ローリスクな「積み立て投資+オルカン」も選択肢
新NISA=学資保険と比べればハイリスクとお伝えしてきましたが、運用方法によっては比較的リスクを抑えることも可能です。
その代表が「積み立て投資+オルカン(オール・カントリー)」と呼ばれる手法です。
「積み立て投資+オルカン(オール・カントリー)」とは
毎月一定額を世界中の株式に分散投資する投資信託(全世界株式インデックスファンド)に積み立てる方法で、時間分散と国際分散によってリスク低減を図るものです。
積立投資は価格が高い時には少なく、安い時には多くの口数を買うため、長期では平均購入単価を平準化し価格変動リスクを和らげる効果があります。
 ねくこ
ねくこ「長期・積立・分散」を組み合わせれば資産形成がしやすく、値動きのリスクを抑えられるといわれています。
オルカン型のファンドで世界全体に投資すれば、一国や一部の資産に偏ったリスクも避けられます。
絶対的な安全性は預金や保険に劣るものの、新NISAでもこうした工夫をすればローリスク・ローリターン寄りの運用に近づけることも可能です。
 ねくこ
ねくこ投資初心者でリスクが心配な方は、つみたて投資枠で世界分散投資を検討してみるのも良いでしょう。

運用益が非課税
新NISAの最大のメリットは、運用益が非課税になることです。
税金で利益の約2割を差し引かれない分、長期運用による複利効果がより大きくなります。
 ねくこ
ねくこ特に、教育資金のように18年程度のスパンで運用できる場合、非課税の恩恵は非常に大きいでしょう。
長期運用を前提とすれば、一時的な相場の変動に動揺せず、じっくり保有することでリスクが平準化されていく傾向があります。
株式などの金融資産は、保有期間が長くなるほど平均リターンのブレが小さくなるというデータもあります。
短期で売買を繰り返すよりも、安定した成果が得られやすいと考えられています。
 ねくこ
ねくこ新NISAの非課税メリットを最大限活かしながら、長期的な視点でコツコツ積み立てていけば、教育資金を効率よく準備できるでしょう。
いくら貯める?シミュレーションしてみよう
以下では、学資保険(ソニー生命・フコク生命)と、新NISAで「月1万円を15年間積立した場合」のシミュレーション結果を比較しています。
学資保険:前提条件
契約者:父親
契約者の契約年齢:30歳
被保険者(子ども)の契約年齢:1歳
積立期間:15年間
保険料の受取:2回(大学入学時(18歳)に進学資金、卒業時(22歳)に満期保険料)
新NISA:前提条件
積立額:月1万円
積立期間:15年間
総投資元本:1万円 × 12か月 × 15年 = 180万円
想定利回り:年3%と年5%の2パターン
※途中売却はしない
学資保険は保険料総額や満期・学資金額があらかじめ確定しているため、各社のシミュレーションサイトから引用しています。
ソニー生命:https://www.sonylife.co.jp/gakushi-plan/simulation/selectAge
フコク生命:https://www.fukoku-life.co.jp/ad/gakushi/shisan.html
・一方、新NISAはあくまで「想定利回り」での試算になりますので、運用結果によっては増減する点にはご注意ください。
・新NISAのデータは編集部にて作成
・投資判断はご自身の責任で行い、必要に応じて金融庁登録の独立系FP等へご相談ください。
シミュレーション結果
| 項目 | ソニー生命 | フコク生命 | 新NISA (3%想定) | 新NISA (5%想定) |
|---|---|---|---|---|
| 月払保険料/積立額 | 8,800円/月 | 12,001円/月 | 1万円/月 | 1万円/月 |
| 支払総額(15年相当の場合) | 約1,795,200円 | 約1,872,156円 | 180万円 (1万円×12ヶ月×15年) | 180万円 |
| 学資金の受け取り時期 | 17歳:100万円 22歳:100万円 | 18歳:100万円 22歳:100万円 | ー | ー |
| 受取総額(満期・評価額) | 200万円 | 200万円 | 約223〜224万円(概算) | 約259万円(概算) |
| 増加額(受取−支払総額) | +約20.48万円 | +約12.78万円 | +約43〜44万円 | +約79万円 |
| リターン率(受取÷支払) | 約111.4% | 約106.8% | 約124% | 約144% |
| 課税の扱い | 一時所得 (差額が50万円以下なら実質非課税) | 一時所得 (差額が50万円以下なら実質非課税) | 非課税 (新NISA口座内の譲渡益・配当は非課税) | 非課税 (新NISA口座内の譲渡益・配当は非課税) |
返戻率(受取総額/支払総額)の観点だけを見ると、
ソニー生命:111.4%
フコク生命:106.8%
新NISA(3%想定):約124%
新NISA(5%想定):約144%
と、新NISAのほうが“期待リターン”は大きくなる可能性があります。
 ねくこ
ねくこただし、学資保険はあくまで「保険」なので、万一の際に保険料免除で満期学資金を受け取れるなどの保障機能がメリット。
一方、新NISAはリスクを取るぶん期待収益が高くなる半面、市況の影響で運用結果が変動するリスクも抱えることになります。
新NISAで元本180万円を一括運用した場合のシミュレーション
以下は、新NISAで元本180万円を一括運用した場合、年利ごとの15年後の資産推移イメージです(税・手数料考慮なし)。
| 年数 | +1%(万円) | +3%(万円) | +5%(万円) |
|---|---|---|---|
| 1年 | 182 | 185 | 189 |
| 2年 | 184 | 190 | 198 |
| 3年 | 186 | 196 | 208 |
| 4年 | 188 | 202 | 219 |
| 5年 | 190 | 208 | 230 |
| 6年 | 192 | 214 | 242 |
| 7年 | 194 | 221 | 254 |
| 8年 | 196 | 228 | 267 |
| 9年 | 198 | 235 | 280 |
| 10年 | 201 | 242 | 294 |
| 11年 | 203 | 250 | 308 |
| 12年 | 205 | 257 | 323 |
| 13年 | 207 | 265 | 339 |
| 14年 | 210 | 273 | 355 |
| 15年 | 212 | 281 | 372 |
| 増加額 | +32万円 | +101万円 | +192万円 |
 ねくこ
ねくここの表は単純な複利計算による概算です。実際は積立投資、相場変動、信託報酬等の影響を受けます。
金額以外で注目すべきポイント
リスクと安全性の違い
- 学資保険
- 貯蓄性と保障性を兼ね備えている
- 契約者が死亡した場合、保険料払込免除の仕組みあり
- 基本的に満期まで保有すれば元本割れしにくく、返戻率が100%以上となるケースが多い
- 新NISA
- 運用次第で想定利回りを下回ることや元本割れのリスクあり
- ただし、長期分散投資を行うことでリスクを抑えやすく、非課税メリットを活かしやすい
保険機能(契約者が万一のとき)
- 学資保険
- 契約者(お父さま)に万一のことがあった場合、保険料の払込免除が適用され、満期・学資金を予定どおり受け取れるケースが多い
- 新NISA
- 死亡保障・払込免除の機能はない
- 生命保険や収入保障保険などでリスクヘッジを検討する必要あり
積立可能期間の柔軟性
- 学資保険
- 払込・保険期間が契約時に固定化されるため、途中解約すると元本割れの可能性が高い
- 新NISA
- 投資の場合は途中で売却(資金引き出し)が可能ですが、市況によっては含み損が出るタイミングもあるため注意が必要
将来の学費計画・受取タイミング
- 学資保険
- 高校・大学入学など、学費の必要時期にあわせて学資金が受け取れるプランも多い
- 新NISA
- 必要な時期までに売却し、現金化しておくタイミング管理が必要
 ねくこ
ねくここれらも踏まえて、ご自身がどちらにするのか、併用してバランスを取るのかを決めて行きましょう。
ハイブリッドでリスクとリターンをバランス良くカバー
保険と投資でお互いの弱点を補完
学資保険と新NISAは対極的な特徴を持ちますが、
 ねくこ
ねくこ実際、「学資保険と新NISAの併用」も選択肢として挙がっており、両者を組み合わせることで安心感とリターンの両立を図れます。
具体的には、まず、学資保険で最低限必要な教育資金を確実に確保しておきます。
例えば大学入学金や1年目の授業料相当額などを学資保険の満期保険金でまかなえるよう契約しておけば、「必要なお金だけは必ず用意できる」という安心感が得られます。
一方で家計に余裕がある分や将来余った場合にも使える資金については新NISAで運用し、資産の成長を狙います。
 ねくこ
ねくここうすることで、安全資産(学資保険)と成長資産(新NISA)のバランスを取ったポートフォリオになり、片方に全額を託すよりリスクとリターンのバランスが良くなります。
家族構成や収入に応じた柔軟な組み合わせ
ハイブリッド運用の比率や方法は、各家庭の状況によって柔軟に決めましょう。
例えば、まだお子さんが小さく収入にも余裕がある家庭なら、新NISAで積極運用する割合を高めても良いかもしれません。
は、新NISAで教育費を準備する方法に向いています。
は、学資保険を主軸に据えて安全運用を重視するのが安心です。
 ねくこ
ねくこあとは、お子さんの人数や年齢差によっても戦略は変わります。
例えば上の子には学資保険で確実に準備し、下の子の分は運用期間に余裕があるため新NISAで積み立てる、といった組み合わせも考えられます。
家族構成や収入に応じて、学資保険と新NISAの割合や活用方法をカスタマイズすることがポイント。
家計全体の状況(住宅ローンや他の貯蓄目標の有無など)も踏まえ、無理なく継続できる配分にしましょう。
運用期間と資金配分を明確にする
ハイブリッドで臨む際は、運用期間と資金配分の計画を明確にしておくことが大切です。
学資保険部分については、契約時に満期(金を受け取る時期)をいつに設定するかを決めます。
 ねくこ
ねくこ例えば「18歳の大学入学時に合わせて満期金○万円受取」のように設定し、その金額で賄えない分を新NISA運用で補うイメージです。
新NISA部分についても、いつ頃まで積み立てていつ頃から取り崩すかの目安を決めておきましょう。
先述の通り、市場の状況によっては必要直前に評価額が大きく変動する可能性があるため、必要時期より数年前から計画的に売却して現金化するなどリスク管理をします。
 ねくこ
ねくこ例えば高校入学時に一部取り崩し、残りは大学進学時まで運用継続、といった段階的な使い分けも考えられます。
学資保険で用意する分と新NISAで賄う分を明確に区別し、それぞれの取り崩し計画を立てておきましょう。
そうすることで、いざという時に「どのお金をどのタイミングで使うか」がはっきりし、安心して両方を運用できます。
どうしても決められない!という場合、プロに聞くのも選択肢
そして、ここまでお読みいただいて、
という方は、プロへの無料相談も選択肢のひとつです。
具体的な相談なら「ソニー生命」へ相談も選択肢

ソニー生命は、学資保険に関する豊富な相談実績を持つことで知られています。
特に、お子さんの年齢や進学プランに応じた学資保険プランを提案してくれるため、親御さんのニーズに合わせた柔軟な選択肢を示してくれます。
 ねくこ
ねくこまた、担当者とマンツーマンでプランを立てられるのも大きなメリット。
学資保険の返戻率(受け取れる額の割合)や特約(保障内容)などを他社比較しながら検討できるため、保険内容に納得したうえで契約できる安心感があります。
ポイント
- 学資保険専門の相談実績が多く、担当者が丁寧にサポート
- 返戻率や保障プランを細かく比較しながら、自分に合った保険を選べる
ライフプラン全体をプロに見直してもらえる

教育資金の問題は、家計のライフプラン全体と切り離せません。
そこで、保険会社のライフプランナーや独立系のファイナンシャルプランナーにライフプラン全体の相談をするのも一案です。
 ねくこ
ねくこ例えばソニー生命のライフプランナーのように、保険・金融・税務の幅広い知識と経験を備えたプロフェッショナルであれば、子どもの将来像や家族の夢をヒアリングしながら、長期的な人生設計図を一緒に描いてくれます。
教育資金だけでなく、住宅購入や老後資金などライフステージ全般とのバランスも含めて最適なプランを提案してもらえるため、家計全体で無理なく教育費を準備する道筋が見えてきます。
満足度96%以上という高評価を得ているプロもおり、不要な勧誘をせず顧客本位でプランニングしてくれることが特徴です。
相談は無料でできる場合が多いので、
を単体で悩むのではなく、包括的なマネープランの中で考えてみるのも有効です。
 ねくこ
ねくこプロに全体像を見直してもらえば、自信を持って最適な手段を選択できるでしょう。
【Q&A】学資保険と新NISAの疑問に答える
そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
子どもの教育資金を準備するなら、学資保険と新NISAのどちらが良い?
確実性重視なら学資保険、リターン重視なら新NISAです。
自分のリスク許容度と目的に応じて選ぶのがポイントです。
学資保険を選ぶメリット・デメリットは?
メリットは低リスク・確定受取・保障付き。
デメリットはリターンが小さく、途中解約で元本割れの可能性があることです。

新NISAを選ぶメリット・デメリットは?
メリットは非課税で高リターンが狙える点。
デメリットは元本保証がなく、相場変動で損失リスクがある点です。

どちらを選ぶべきか迷ったら、何を重視すればいい?
安全確保や計画的積立を重視するなら学資保険、成長性や自由度を重視するなら新NISAです。
目的と価値観で選びましょう。
学資保険と新NISAは併用できるの?
はい、併用可能です。
学資保険で最低限の教育資金を確保し、新NISAで資産形成を狙うハイブリッド運用がおすすめです。
教育資金の準備でプロに相談したい場合はどうすればいい?
ソニー生命などのライフプランナーやFPに相談できます。
家計全体を見直しながら最適な資金計画を立てられます。

まとめ|学資保険 vs NISAか、学資保険 with NISAを選択してみよう!
| 項目 | 学資保険 | 新NISA |
|---|---|---|
| スタートできる年齢 | – 子ども:0歳~7歳(保険によって異なる) – 保護者:60歳前後が多い | 18歳以上 |
| リスク | 低リスク | 高リスク(元本保証はない) |
| リターン | 低リターン | 高リスク・高リターン(元本保証はない) |
| 税制優遇 | 一般生命保険料控除の対象 | 運用益は非課税 |
| 資金の拠出期間 | 一時払い~18歳ごろまで(保険会社によって異なる) | 無期限 |
| 途中で引き出したい場合 | 可能。元本割れリスクあり | 可能。元本割れリスクあり |
| 運用にかかる税金 | 保険金は課税対象 | 拠出に関する税制優遇はなし |
| 被保険者・運用者に万が一があった場合 | 残りの保険料は免除、満期保険を受け取れる | 保証なし |
学資保険と新NISA、それぞれの特徴を整理すると以下の通りです。
まとめ
- 学資保険はリスクを抑えて計画的に資金を確保でき、万一の保障や保険料控除といった付加価値
- 「リスクを取りたくない」「確実に教育費を用意したい人」には学資保険
- 新NISAは高いリターンを期待でき、資金の引き出し自由度や積立金額の柔軟性が魅力で、運用益が非課税で受け取れる強み
- 「一定のリスク許容度があり資産を増やしたい」「教育費以外にも自由に使えるお金を準備したい」人には新NISA
また、両者を併用することで、安定性と収益性のバランスを取ることも可能です。
最適な選択をするためには、各商品のメリット・デメリットを正しく理解し、家計の収支やライフステージに合わせて総合的に判断しましょう。
 ねくこ
ねくこ今回比較した内容を参考に、お子さまの将来に向けたベストな資金準備方法を見つけてください。
必要であれば専門家の力も借りながら、安心して教育費を備えられる道を選びましょう!
マミーフィットは、産後ママ向けオンラインヨガ&ピラティスです。
スマホがあれば自宅にいながらマンツーマンでのヨガやピラティスを受けることができます。
1回25分のレッスンから参加できるため、家事や育児の間に気軽に参加することが可能です。
元公務員のFPとして、新NISAの情報を中心に、皆さんのお金の問題を解決するために役立つ情報ををお届けしています。
本記事は2025年7月時点の制度・税制を元に執筆しています。最新情報は金融庁サイト等をご確認ください。