相続・相続放棄を失敗なく進めるための完全ガイド:期限・専門家・手続きを徹底解説

相続は大切な家族の財産を引き継ぐ一方、思いもよらぬ借金や手続きトラブルにつながる可能性もある複雑な手続きです。
特に、令和6年(2024年)に実施された、
- 不動産の相続登記義務化
- 相続税申告の10か月という厳格な期限※
など、ルールを知らずに放置するとペナルティや紛争のリスクが高まります。
※相続税の申告・納付は、相続開始(死亡日の翌日)から10か月以内です。あわせて被相続人の所得税(準確定申告)は4か月以内であり、双方の期限を混同しないよう注意してください。
相続放棄・限定承認の申述期限は原則3か月(熟慮期間)です。ただし家庭裁判所へ期限伸長の申立てが可能な場合があります。
負債の全容把握に時間を要する時は、期限内に伸長申立てを検討してください。期限徒過や財産の処分行為があると単純承認が成立するおそれがあります。


というわけで今回は、そんな万一の事態に備えたい方、また相続時にどう手続きをして良いか分からない方に向けて、相続・相続放棄を円滑に進めるための基本知識や注意点をわかりやすく整理しています。
もし、遺産分割協議で争いが発生しそうなときは、弁護士を窓口に司法書士や税理士と連携し、早めに対策を講じることが重要ですが、本記事では「どんなときに、誰に相談すればいい?」まで紹介しています。
 ねくこ
ねくこあなたに起こりそうなこととぜひ最後までご覧いただき、スムーズな相続手続きにお役立てください。
相続・相続放棄に関する主な専門家と役割

相続や相続放棄の手続きでは、書類の準備から法律問題の解決、税金対策など多岐にわたる対応が必要になります。
特に、
などは、まずは早めに専門家に相談することがスムーズな解決への近道です。
 ねくこ
ねくこというわけで、まずは相続・相続放棄に関してサポートを行う代表的な専門家と、それぞれの役割やポイントを整理してご紹介します。
状況に応じて最適な専門家を選び、安心して相続手続きを進めましょう。
| 専門家 | 対応が必要な場面 | 可能な業務 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 相続人間で紛争が発生 または懸念されるケース | 代理交渉・訴訟対応、相続放棄申述代理、 複雑な権利関係の調整など |
| 司法書士 | 不動産の名義変更が必要 (相続登記など) | 相続登記、書類収集、相続放棄申述書作成のサポート |
| 税理士 | 相続税申告が必要か判断 または節税対策したい | 相続税申告、準確定申告、資産評価、 節税スキームの提案 |
| 行政書士 | 紛争がないシンプルな相続手続き (遺産分割協議書の作成など) | 書類作成・代行、戸籍収集、 各種許認可手続きサポート |
| 土地家屋調査士 | 土地境界を確定したい、 分筆・合筆が必要なケース | 測量・調査、境界確定、 関連する登記手続き |
| 不動産会社・宅地建物取引士 | 不動産を売却、賃貸活用したいケース | 不動産売買仲介、賃貸募集、 市場価格査定 |
弁護士

相続問題において、弁護士は主に法的トラブルの解決や交渉代理を担います。
紛争リスクが高い場合や、すでに相続人同士で対立している場合には、弁護士への相談が非常に重要です。
役割
- 相続人間の紛争(遺産分割協議の対立・調停・訴訟など)の代理
法律上の交渉や訴訟は弁護士だけが行えます。感情的なもつれが生じやすい相続問題で、第三者として冷静に対応し、依頼者の権利を守ります。- 複雑な権利関係の調整、遺産調査・遺産分割協議書の作成支援
相続財産が多岐にわたる場合や、複数の相続人が存在する場合に必要な調整を行います。- 相続放棄の申述代理(家庭裁判所への申立手続)
弁護士は相続放棄の申述代理が可能です。一方で司法書士は原則として家庭裁判所での申述“代理”は不可(書類作成・手続支援まで)である点を明確に区別してください。
ポイント
- 法律上の代理交渉・訴訟が可能なのは弁護士のみ
相続トラブルが発生、または懸念される場合は早めに相談するほど有利です。行政書士は紛争性がある案件は不可。司法書士は登記・書類作成が中心で、紛争の代理交渉は不可。 - 相続トラブルが大きくなる前に予防策として利用
少しでも不安を感じたら、早期の相談が時間と費用を節約する鍵となります。
司法書士
司法書士は、不動産の相続登記手続きをはじめとする書類作成の専門家です。
役割
- 不動産の相続登記(名義変更)手続き
不動産を相続した際には、登記簿上の名義変更を行う必要があります。- 相続人が確定している場合の遺産分割協議書の作成支援
相続人がはっきりしており、トラブルがない場合に書類作成をサポートします。- 戸籍収集や書類作成の代行、相続放棄の申述書作成サポート(代理提出の可否は要確認)
自分で集めるには時間や手間がかかる戸籍謄本などの書類収集を任せられます。
ポイント
- 紛争がある場合の代理は原則できない
法律的な交渉権限は弁護士しか持たないため、相続人同士で争いになりそうな場合は弁護士に相談しましょう。 - 不動産の手続き(相続登記)の専門家として活用
司法書士は登記手続きのプロですので、不動産関連の相続に強みがあります。
 ねくこ
ねくこ相続登記は放置していると後々の手続きが煩雑になるため、相続発生後なるべく早く取りかかることが理想です。
税理士
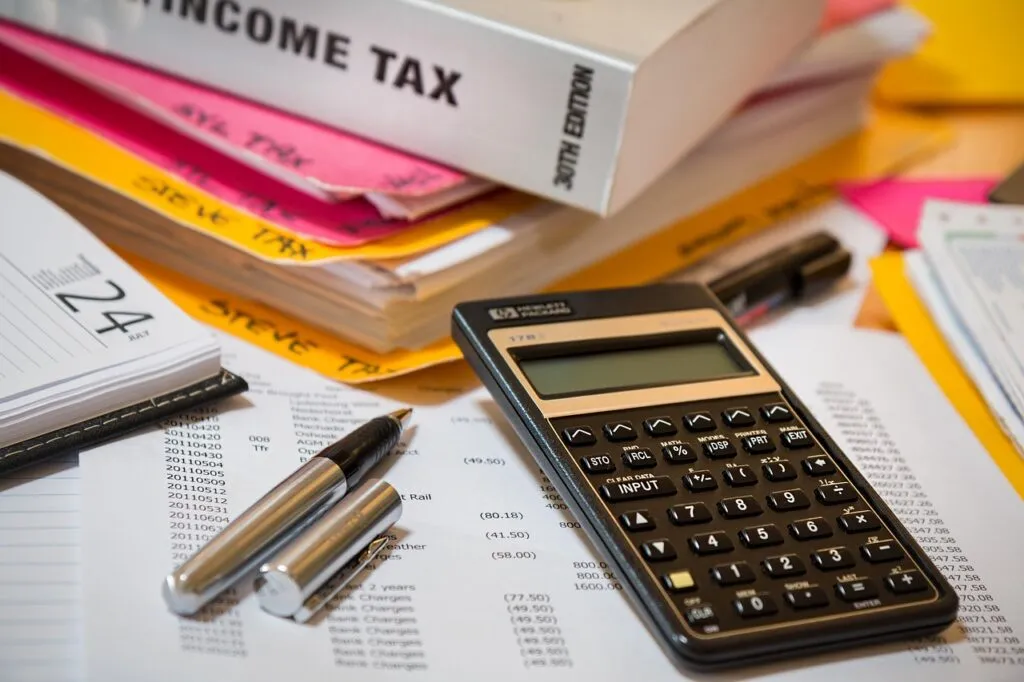
相続財産の合計額や内容によっては、相続税の申告義務が発生することがあります。
相続税の計算には専門知識が必要ですので、資産総額が一定以上になりそうな場合は早めに税理士へ相談すると安心です。
役割
- 相続税申告、被相続人の所得税(準確定申告)の手続き
税務署への申告手続きや、相続人・被相続人の所得にかかわる書類作成などを行います。- 不動産評価、非上場株式の評価などの資産評価
相続税額を算定するうえで、不動産や株式などの評価は非常に重要です。- 節税・相続税対策のアドバイス
適切な節税策を講じることで、将来の相続に備えることも可能です。
ポイント
- 相続税申告が必要になる可能性がある場合は早めに相談
申告期限は相続開始から10か月以内と比較的短いため、後回しにすると申告漏れやペナルティのリスクが高まります。 - 資産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかの判断が重要
『基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数』を超える見込みなら、早期に『相続税の延納・物納の可否』や『小規模宅地等の特例』の適用可能性も確認を。適用には要件・提出書類・期限があり、見落とすと税負担が増大します。
行政書士
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続き代行が可能です。
相続や相続放棄に際して、戸籍の収集・整理、遺産分割協議書の作成など、比較的シンプルな事務手続きに対応する場面で依頼されることが多いです。
役割
- 遺産分割協議書の作成支援
相続人全員が合意している場合に、手続きミスを防ぐために専門家に依頼すると安心です。- 戸籍の収集など書類作成手続の代行
各市区町村や法務局など、多岐にわたる書類を素早くそろえるサポートを行います。- 許認可や名義変更などのサポート
相続以外の行政手続きのエキスパートでもあるため、名義変更が必要な財産がある場合に役立ちます。
ポイント
- シンプルな相続手続や書類作成を依頼したい場合に適している
紛争リスクが低い場面であれば、行政書士へ依頼することでコストや手間を抑えることができます。 - 紛争があるケースでは対応範囲が限られる
交渉や訴訟は扱えませんので、複雑な争いがある場合は弁護士や司法書士と連携する必要があります。
土地家屋調査士

土地家屋調査士は、不動産に関する測量・境界確定・登記などの専門家です。
役割
- 土地や家屋の境界確定、分筆・合筆などの測量や登記手続き
相続で複数の相続人が土地を分ける場合など、現状把握と正確な境界確定が欠かせません。
ポイント
- 不動産名義変更に伴い、土地の分筆・合筆などが必要な場合に相談
境界があいまいなまま相続を進めると、後々の紛争リスクが高まります。 - 境界問題をクリアにしておくことで、将来的なトラブルを回避
確定測量が済んでいない場合は、早めに調査を依頼することが安心につながります。
 ねくこ
ねくこ相続を機に土地の境界をはっきりさせたい場合や、分筆や合筆が必要となるケースで頼りになります。
不動産会社・宅地建物取引士
相続した不動産を売却するか、あるいは賃貸活用して家賃収入を得るかは、今後の相続人のライフプランや資金計画に大きく関わります。
不動産会社は物件の査定から売却・賃貸仲介をトータルに支援してくれるため、所有する不動産の処分を検討しているなら相談必須の専門家です。
役割
- 不動産の売却や賃貸活用の提案・仲介業務
相続した物件を有効活用するために、適切な価格評価や市場調査を行います。
ポイント
- 相続した不動産の活用方法(売却・賃貸)を検討する際に相談
不動産の売却時期や賃貸需要など、地域の市場状況をよく把握している会社を選ぶとよいです。 - 物件の査定や市場価格の把握が可能
専門家の査定を参考にすることで、売却・賃貸いずれの場合でも最適なタイミングを判断しやすくなります。


参考:相続放棄の手続きを弁護士が解説 | 弁護士法人 賢誠総合法律事務所
専門家選びのまとめ
それぞれの専門家には得意分野が異なり、対応できる業務範囲に違いがあります。
複数の専門家が必要になる場面も多いので、まずは自身の相続問題が
- 「法律トラブルを含むのか」
- 「不動産をどう扱うか」
- 「相続税の申告が必要か」
などを見極めることが大切です。
それぞれの専門家に相談することで、複雑な書類のやり取りや法律問題も円滑に進めることが可能です。
 ねくこ
ねくこ自分に必要なサポートを明確にしたうえで、安心して相続・相続放棄の手続きを行いましょう。
資産種類別に見たチェックポイントと資産種類別の手続き早見表

相続においては、取り扱う資産や負債の種類によって必要となる手続きや注意点が異なります。
動産・不動産・その他の資産・債務など、それぞれの特徴を理解しておくことで、スムーズに相続を進められるでしょう。
ここでは、資産種類ごとの基本的なチェックポイントを解説します。
 ねくこ
ねくこ専門家の力を借りるべきタイミングを把握し、必要に応じて早めに動くことがトラブル回避の大きなポイントです。
下記のような一覧表を作成し、資産の種類と対応が必要な先を整理しておくと便利です。
| 資産・負債 | 手続き先・対応 | 相談先の専門家 | |
|---|---|---|---|
| 動産 | 現金・預貯金 | 金融機関(銀行・証券会社) | 弁護士・税理士・司法書士 |
| 株式・投資信託 | 証券会社 | 弁護士・税理士・司法書士 | |
| 不動産 | 法務局(相続登記) 不動産会社(売却) | 司法書士・税理士 | |
| その他の資産 | 自動車 | 陸運局 | 行政書士(書類代行) |
| 船舶 | 船舶検査登録機関 | 行政書士・弁理士 | |
| 知的財産(特許・商標) | 特許庁(権利移転) | 弁護士・弁理士 | |
| 未公開株 | 該当会社 | 税理士 | |
| 負の資産 | 借金・連帯保証 | 債権者(金融機関など) | 弁護士・司法書士 |
動産(現金、預貯金、株式、投資信託など)
動産とは、形があったり、比較的に変換(換金)が容易な資産を指します。
預貯金や株式などは口座の名義人が亡くなると凍結されてしまうケースが多いため、まずは金融機関や証券会社への連絡が必要です。
『預貯金の仮払い制度』により、遺産分割前でも所定の範囲で払戻しが可能な場合があります(各金融機関につき上限や必要書類あり)。葬儀費用や当面の生活費の確保に活用を検討してください。
スムーズに手続きを進めるためにも、必要書類の準備や相続人全員の合意が欠かせません。
動産の相続時に検討すべき項目
- 銀行口座・証券口座の凍結解除・名義変更
相続人全員の同意があるか、遺産分割協議書が整っているかを確認しましょう。 - 株式・投資信託は証券会社への連絡、売却または名義変更の検討
株価の変動リスクも考慮し、どのタイミングで売却・名義変更するか決定することが大切です。 - 相続税がかかる場合は税理士と早めに相談
動産は現金化しやすい分、相続税の課税対象になりやすい資産が多いです。 - 相続人間で争いがある場合は弁護士への相談も視野に
分配の割合や売却タイミングで対立するケースもあるため、早めの専門家相談が安心です。
不動産(宅地、建物、マンションなど)
相続資産の中でも、不動産は手続きや評価が複雑になりやすい資産です。
土地や建物の名義変更(相続登記)は、2024年以降義務化されており、放置すると罰則のリスクも生じます。
さらに、不動産の売却を検討する場合には、不動産会社への査定依頼や相続登記の有無などを同時に考えなくてはなりません。
不動産の相続時に検討すべき項目
- 相続登記(名義変更)の手続き:義務化の流れがあるため迅速に対応
司法書士に依頼することで、書類不備のリスクを減らし、スムーズに手続きできます。2024年4月1日施行により相続登記は義務化されました。起算点は『所有権取得を知った日から3年以内』または『遺産分割成立日から3年以内』。義務違反には『10万円以下の過料』の可能性があります。『令和6年4月1日以前の相続開始分は令和9年3月31日までの経過措置』があります。 - 売却を検討する場合:不動産会社へ査定依頼 → 司法書士による相続登記確認
どのタイミングで売却するか、査定額と実際の相場感を踏まえて判断することが重要です。 - 境界・測量が必要:土地家屋調査士へ相談
境界問題は後々トラブルに発展しやすいので、早めの測量・確定作業がカギとなります。 - 相続税評価が必要:税理士へ依頼
不動産は評価額が大きく、相続税申告の要不要に直結します。誤った評価はペナルティの対象になる場合もあるため注意しましょう。
その他の資産(自動車、船舶、知的財産、未公開株など)

動産や不動産以外にも、自動車や船舶といった乗り物、知的財産権、未公開株など多種多様な資産が相続の対象になります。
財産の種類によって担当する行政機関や手続きが大きく異なるため、どこに連絡し、どのような書類を準備する必要があるのかを早めに調べておきましょう。
その他の資産の相続時に検討すべき項目
- 自動車:陸運局で名義変更
相続人として車を継続利用するか、売却・廃車などを含め、早めに方針を決めるとよいです。 - 船舶:船舶検査登録機関での手続き
対象の船舶がどの機関に登録されているかを確認し、必要書類を取り寄せましょう。 - 知的財産(特許権・商標権等):特許庁への権利移転手続き
期限や手数料などの詳細を確認しながら、専門家(弁理士など)に相談するケースもあります。 - 未公開株:会社との調整が必要、税理士による評価が望ましい
株の評価基準が複雑であるため、税理士に依頼して正確に算出してもらうことが大切です。
債務・連帯保証など負の資産
相続では「資産」だけでなく、「負債」も受け継ぐことになります。
借金や連帯保証を多く抱えている場合は、相続を受けるよりも放棄や限定承認を選んだほうがリスクを避けられるケースも少なくありません。
相続放棄・限定承認を検討する際には、家庭裁判所へ申述する期限(3か月以内)に注意が必要です。
相続放棄や限定承認について
- 借金や連帯保証が多い場合:相続放棄・限定承認の検討
プラスの資産よりマイナスの負債が上回る場合や、不明な連帯保証がある場合は要検討です。 - 相続放棄などの手続は3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要
期限を過ぎると、すべての資産・負債を相続することになるため、注意が必要です。 - 複雑な状況の場合は弁護士または司法書士へ相談
放棄や限定承認の手続きは法的な判断が求められるため、専門家に依頼することでトラブルを回避しやすくなります。
相続には多くの手続きや書類準備がつきものです。
特に資産種類によって対応する機関や必要な書類が異なるため、早めに全体像を把握し、専門家への相談を検討することがスムーズな相続のコツです。
 ねくこ
ねくこ期限がある手続きも多いので、「どの財産にどのようなリスクや義務があるのか」 を明確にしたうえで、後回しにせず対処していきましょう。
相続・相続放棄の全体的なフローチャート

相続や相続放棄の手続きは、被相続人の逝去から始まり、財産調査や専門家への相談、遺産分割協議など、さまざまなステップを踏んで進められます。
特に相続を放棄する場合は家庭裁判所への申述期限(3か月以内)を厳守する必要があるため、事前に全体像を把握しておくと安心です。
 ねくこ
ねくこここでは、相続・相続放棄に関する基本的なフローチャートをステップ別に解説します。
以下のようなフローチャートを作成しておくと、ステップごとにやるべきことが明確になります。
被相続人の死亡確認(親族や同居者など)
・死亡診断書を添付し、死亡届を市区町村役場へ提出する(7日以内が原則)。
・公正証書遺言や自筆証書遺言の有無を確認しておく。
相続人の確定・戸籍収集(行政書士 / 司法書士 / 弁護士)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、法定相続人を確定。
・相続関係説明図の作成も含まれます。
相続方法の検討(単純承認 / 相続放棄 / 限定承認)(弁護士 / 司法書士)
・相続財産(プラス・マイナス)の調査が前提となる。
・借金などの負債が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討。
・相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要。
遺産分割協議の実施(弁護士(争いがある場合) / 行政書士・司法書士(争いがない場合))
・相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成。
・合意が得られていれば行政書士や司法書士が書類作成を支援。
・意見の対立がある場合は、弁護士が調停・交渉を担当。
・遺産分割協議書は、名義変更や税申告に必須となる重要書類。
不動産の名義変更(相続登記)(司法書士)
・不動産の名義変更は法務局での登記申請が必要。
・遺産分割協議書の内容も確認されます。
土地の境界確定・分筆/合筆(土地家屋調査士)
・土地の利用や売却をスムーズに行うためには、正確な測量と境界確定が不可欠。
・複数相続人による共有状態では、分筆してからの名義変更が有効。
・土地家屋調査士が現地調査・測量を実施し、分筆・合筆の登記も支援。
不動産の売却・賃貸活用(不動産会社 / 宅地建物取引士(宅建士))
・相続した不動産を活用する手段として、売却または賃貸を選択。
・不動産会社や宅建士が、市場動向を踏まえて適切な活用方法を提案。
・事前に相続登記を済ませておくと、手続きがスムーズに進行する。
相続税の申告・納付(税理士)
・相続税の対象となる場合、資産評価や申告書作成、税務調査対策などを行う。
・相続税の申告期限は、相続開始から10か月以内。
・相続財産が基礎控除額を超える場合、税理士による評価・申告が必要。
・特殊な財産(未公開株、不動産)などは専門的な知見による算出が重要。
 ねくこ
ねくこと、いうステップになります。
次に、ステップごとにやるべきことの詳細を説明します。
ステップ1:被相続人の死亡確認
- 死亡届の提出(役所)
- 一般的に7日以内に提出する必要があります。
- 遺言書の有無を確認(公正証書・自筆証書など)
- 自筆証書遺言があった場合は家庭裁判所での検認手続きが必要。
まずは被相続人が死亡した事実を役所に届け出るため、死亡診断書を添付し「死亡届」を提出することからスタートします。
また、この段階で「遺言書の有無」を確認しておきましょう。公正証書遺言や自筆証書遺言などが見つかった場合は、内容を精査する必要があります。
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認が必要になるケースがあるため、手続きを見落とさないよう注意しましょう。
ステップ2:相続人の確定・戸籍収集
行政書士 / 司法書士 / 弁護士が対応
- 戸籍収集 → 相続人の範囲を確定
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、相続人を漏れなく確認します。
- 財産目録(プラス・マイナス)を作成
- 銀行口座や不動産、借金など、可能な限り詳しくリストアップしましょう。
- 紛争リスクがあれば弁護士に相談
- 相続人同士で意見の食い違いが生じそうな場合は、早めに専門家を交えて解決策を探ります。
相続人を確定するためには、戸籍収集が重要です。
相続手続きの第一歩として、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を調べ、相続人の範囲を確定します。
相続関係説明図を作成すると、誰が相続人になるのか一目で把握しやすくなります。
 ねくこ
ねくこ戸籍謄本の取り寄せは役所ごとに手続きが必要で、地理的にも手間がかかることがあります。
そのため、専門家に依頼して代行してもらうと効率的です。
そのうえで、プラスの財産とマイナスの債務を整理し、財産目録を作成しておきましょう。
紛争リスクがある場合や、各相続人の取り分が不透明な場合は、弁護士に早めに相談するのがおすすめです。
ステップ3:相続方法の検討(単純承認 / 相続放棄 / 限定承認)
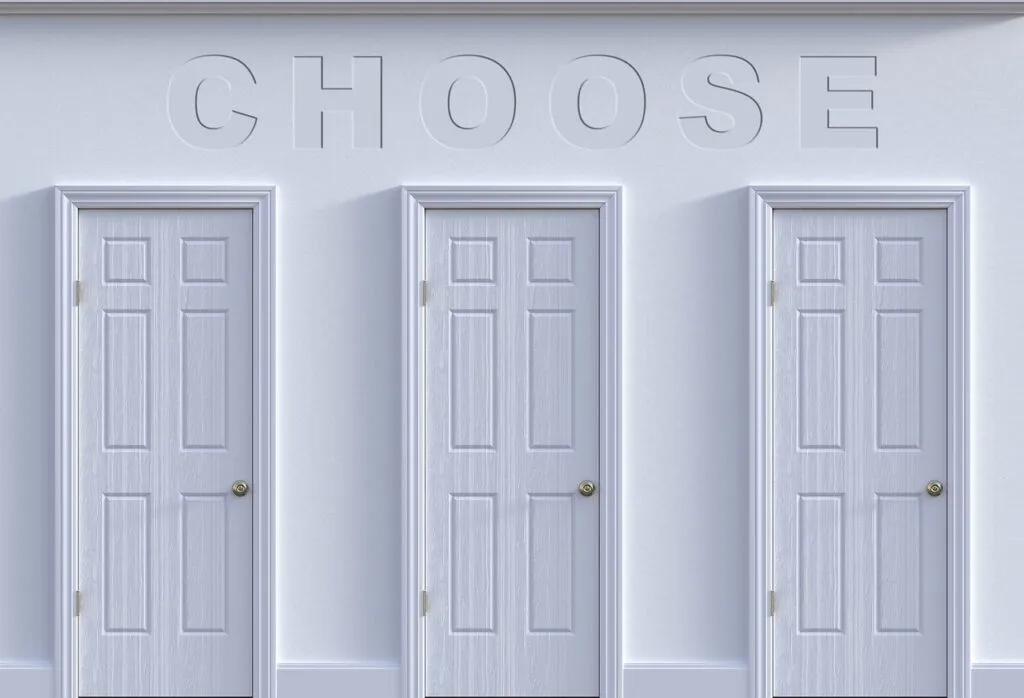
相続ではプラスの財産だけでなく、借金や連帯保証などの負債も承継されます。
もし、マイナスが大きいと予想される場合は、相続放棄や限定承認を選択する方法があります。
特に借金が多い・不確定債務があるなど、負債が多い場合は早めに検討することが必要です。
 ねくこ
ねくこリスクが高いものは弁護士や司法書士など専門家とよく相談しましょう。
単純承認を選択する場合
弁護士 / 司法書士が対応
- 単純承認を前提とした相続財産の調査と助言
- 債務の有無が不明な場合や複雑な遺産構成の場合は、専門家に相談してから判断するのが安全です。
- 他の相続人との共有財産の扱いや名義変更などの支援
- 名義変更や分割協議などの実務手続きも、単純承認後に進められることが多いため、慎重な準備が重要です。
- 財産処分による単純承認の成立リスクについての事前確認とアドバイス
- 単純承認は黙示的に成立するケースがあるため、知らずに財産を使うと撤回ができなくなります。
プラスの財産が多く、債務や連帯保証などの負債も特に見当たらない場合には、単純承認(すべての権利義務を引き継ぐ)を選択することになります。
そのため、財産の取り扱いには注意が必要です。
限定承認を行いたい場合
弁護士 / 司法書士が対応
- 限定承認の要件確認
- 家庭裁判所への手続きサポート
- 相続放棄と同じく、3か月以内に手続きを行わなければなりません。
- 相続財産の清算手続きに関するアドバイス
- 清算手続きが複雑になることも多いため、弁護士に依頼することでリスクを減らせます。
相続放棄ではすべての権利・義務を放棄しますが、限定承認はプラスの財産を超えない範囲で負債を引き受ける手続きです。
ただし、手続きの煩雑さや要件の厳密さから、利用シーンは限られています。
限定承認は相続人全員での申述が原則で、受理後は『債権者への公告・弁済・清算』等の手続が必要です。実務負担と期間が大きいため、利用局面は限定的です。
特にプラスかマイナスかわからない財産がある場合などに検討されます。
相続放棄を検討する場合
弁護士 / 司法書士が対応
- 相続放棄の要件確認
- 相続放棄した場合、一切の権利義務を放棄するため、あとになって撤回はできません。
- 家庭裁判所への申述書作成サポート
- 相続人間の調整や連絡事項についてのアドバイス
- 負債の内容が複雑な場合は、弁護士に相談すると安心です。
- 借金が多い場合や不確定債務がある場合
- プラスの財産より負債が大きいと判断される場合
には、相続放棄を検討することがあります。
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、期限は相続の開始を知った日から3か月以内と定められているため、早めの判断が大切です。
ステップ4:遺産分割協議の実施
相続放棄を行う場合は、家庭裁判所への申述後に受理されると、相続人としての権利や義務を失います。
放棄しない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割内容を決定します。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、各種名義変更や相続登記、相続税申告などに進みましょう。
- 放棄する場合:申述手続後、相続権・義務を失う
- ほかの相続人に影響が及ぶこともあるため、家族間で事前によく話し合いをする必要があります。
- 放棄しない場合:遺産分割協議書を作成 → 不動産登記・相続税申告などを進める
- 不動産がある場合は速やかに相続登記を行い、相続税が課税される見込みがあれば10か月以内の申告を忘れずに。
遺産分割協議書のみ作成したい
行政書士 / 司法書士が対応
- 書類作成のサポート
- 作成された遺産分割協議書が、今後の名義変更手続きや相続税申告などで重要な役割を果たします。
- 必要書類のチェック
- 不動産の登記移転も同時に依頼するなら、司法書士に一括で依頼すると効率的です。
- 公正証書化が必要かどうかのアドバイス
紛争がないシンプルなケースであれば、行政書士や司法書士に遺産分割協議書の作成のみを依頼する方法もあります。
相続人同士で合意が取れているなら、正しい形式で書類を作成し、実印を押すことで法的に有効な協議書が完成します。
遺産分割協議で争いがある
弁護士が対応
- 調停・審判・訴訟の代理
- 法的交渉権限を持つ弁護士が代理人となり、相続人の意向を最大限に汲んだ解決策を目指します。
- 代理交渉、和解案の提案
- 感情的な対立が続くと、手続きが長期化して費用も膨らむ傾向にあります。
- 必要に応じ、税理士・司法書士などとの連携
- 不動産や税金、登記に関する手続きは連携が不可欠です。必要に応じて相談先を増やしましょう。
相続人間で意見の食い違いが大きい場合や、すでにトラブルに発展しているケースは、法律的な交渉権限を持つ弁護士に依頼するのがベストです。
調停や審判、訴訟などを行う際は、税理士や司法書士などのほかの専門家との連携も有効です。
 ねくこ
ねくこ紛争が深刻化する前に第三者の専門家を交えて協議することで、問題解決がスムーズに進むことが多々あります。
ステップ5:不動産の名義変更(相続登記)
司法書士が対応
- 相続登記手続きの申請代理
- 司法書士は登記のプロであり、不動産に関する法務局の手続きに精通しています。
- 遺産分割協議書の確認
- 不動産の相続登記が完了しないと、売却や担保設定などに支障が出る場合があります。
- 戸籍や印鑑証明など必要書類のチェック
不動産を相続した場合、法務局で名義変更(相続登記)を行う必要があります。
2024年以降相続登記の義務化が進んでおり、放置すると将来的に罰則や売却・活用の制限を受ける可能性があるので、早めの手続きが望まれます。
| 条 件 | 期 限 |
|---|---|
| 不動産を相続した場合 | 所有権取得を知った日から3年以内 |
| 遺産分割が成立した場合 | 遺産分割が成立した日から3年以内 |
| 令和6年4月1日以前に相続が開始された場合 | 令和9年3月31日までにする必要 |
ステップ6:土地の境界確定・分筆/合筆
土地家屋調査士が対応
- 測量、境界確定
- 分筆・合筆登記関連の手続き
土地を相続する際、境界がはっきりしない状態で放置していると、後々近隣とのトラブルに発展する可能性があります。
複数の相続人で土地を共有する、あるいは一部だけを売却する場合は、分筆や合筆などの測量手続きが必要です。
ステップ7:不動産の売却・賃貸活用

不動産会社 / 宅建士が対応
- 物件の査定
- 売却・賃貸の仲介業務
- 売却前に相続登記を完了しておくと手続きが円滑に進みます。
- 賃貸管理やリフォームの提案
相続した不動産を自分で利用しない場合は、売却や賃貸などで有効活用を検討します。
不動産会社は物件の査定やマーケット情報を提供してくれるため、相続人の希望に沿ったプランを立てやすくなります。
ステップ8:相続税の申告・納付
税理士が対応
- 資産評価、申告書の作成
- 税務署への提出
- 相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。
- 節税対策や将来の相続へのアドバイス
相続税の申告が必要になるかどうかは、基礎控除額(3,000万円 + 600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかが目安となります。
評価の難しい不動産や未公開株などがある場合は、正しい算定のために税理士の力を借りると安心です。
相続には法律・税務・不動産など多岐にわたる知識が必要な場合があります。
相続・相続放棄には多くの法的手続きや書類準備が伴いますが、全体像をつかんだうえで
を理解しておくと、時間と労力、さらにはトラブルのの防止や手続きの円滑化に大いに役立ちます。
必要に応じて複数の専門家を活用し、それぞれの強みを生かした協力体制を築くことで、安心かつ効率的に相続や相続放棄を進めましょう。
 ねくこ
ねくこ自分が置かれた状況に合わせて、早めの情報収集と相談を心がけましょう。
相続や相続放棄に関する、特に注意が必要な点

単純承認となる典型例
- 相続財産の全部または一部を処分する
- 相続財産を隠匿・消費する
- 熟慮期間の経過後も相続財産を処分可能な状態を放置する、等。
日常費の引き出し・車の売却・不動産の賃貸開始なども該当し得ます。
相続や相続放棄に関する手続きには、期限や書類の不備、トラブルの発生など、多くのリスクが潜んでいます。
ここでは、特に注意すべき主要なポイントをまとめました。
 ねくこ
ねくこ期限を守らないと取り返しのつかない状況になることもあるため、それぞれの項目をしっかり確認し、必要に応じて早めに専門家へ相談しましょう。
相続放棄・限定承認の期限
相続放棄や限定承認の手続きは、相続が開始したことを知った日から3か月以内(いわゆる「熟慮期間」)に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認となり、借金を含むすべての遺産を相続するリスクがあります。
- 3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要
- 期間を過ぎると単純承認となる
- 負債状況や連帯保証の有無を早めに把握することが重要
相続放棄や限定承認は、一度手続きを終えると、原則として撤回できません。
 ねくこ
ねくこ慎重な判断が求められるため、少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家へ早期相談することをおすすめします。
不動産の相続登記義務化
2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます。
名義変更をせずに放置していると、将来的に過料(罰金)が科される可能性があり、不動産の売却や活用を円滑に進められないリスクも生じます。
| 条 件 | 期 限 |
|---|---|
| 不動産を相続した場合 | 所有権取得を知った日から3年以内 |
| 遺産分割が成立した場合 | 遺産分割が成立した日から3年以内 |
| 令和6年4月1日以前に相続が開始された場合 | 令和9年3月31日までにする必要 |
- 相続登記は放置せず、できるだけ早めに対応
- 義務違反の場合、最大10万円の過料(罰金)の可能性あり
特に、相続不動産が複数ある場合や相続人が多い場合は、書類の整理や手続きが煩雑になります。
 ねくこ
ねくこ司法書士に依頼して早めに登記を済ませることで、将来のトラブルを防ぎましょう。
相続税申告の期限
相続税の申告期限は、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内です。
遺産の評価額が基礎控除を超えるかどうかの判断がつかない場合でも、まずは資産の洗い出しを行うことが重要です。
- 相続の開始を知ったら、すぐに総資産を確認
- 相続放棄を検討中でも、資産調査は必須
- 申告期限を過ぎると、加算税や延滞税が発生する可能性あり
 ねくこ
ねくこ不動産や株式、未公開株など、評価が難しい資産が含まれる場合は、税理士に相談し、正確な申告を目指しましょう。
相続争いが起きた場合
相続人間で意見が対立し、調停・審判・訴訟に発展した場合、弁護士のみが代理人として法的交渉を行えます。
争いが深刻化すると、費用や時間がかかるため、早めに専門家へ相談し、問題の長期化を防ぐことが重要です。
- 調停・審判・訴訟対応は弁護士のみ可能
- 早期の法律相談でトラブルの拡大を防止
- 感情的な対立を避け、合理的な解決策を探りやすくなる
状況によっては、税理士や司法書士など、他の専門家と連携が必要になる場合があります。
 ねくこ
ねくこ弁護士を窓口として複数の専門家が協力するケースも少なくありません。
複数の専門家との連携
相続は、法律・税務・不動産など、多方面の知識が求められる複雑な手続きです。
複数の専門家が連携することで、スムーズかつ正確に相続問題を解決できます。
| 必要な視点 | 主な専門家 | 具体的なサポート内容 |
|---|---|---|
| 法律 | 弁護士・司法書士 | 紛争対応、相続放棄・限定承認手続き、相続登記など |
| 税務 | 税理士 | 相続税申告、財産評価、税務署とのやり取り |
| 不動産 | 司法書士・土地家屋調査士・不動産会社 | 名義変更手続き、境界確定、売却・賃貸活用など |
- まずは自分の状況を整理し、どの分野の専門家に相談すべきかを検討する
- ワンストップで複数の専門家を紹介してくれる法律事務所や税理士事務所もある
適切な専門家を早めに選ぶことで、時間とコストの削減につながります。
相続問題は手続きの多さや期限の厳しさに加え、感情的な対立が生まれやすいことも特徴です。
後回しにせず、状況に応じて迅速に対応することが重要です。
 ねくこ
ねくこ複数の専門家を連携させることで、円滑な相続手続きを実現しましょう。
【Q&A】相続・相続放棄の疑問に答える
そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
相続・相続放棄を円滑に進めるための基本知識は何ですか?
期限を守り、早めに専門家に相談することです。
- 相続放棄は3か月以内
- 相続登記は3年以内
- 相続税申告は10か月以内
といった期限があり、見落とすと大きな不利益につながります。
相続・相続放棄に関する主な専門家と役割を教えてください。
状況に応じて弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産会社が関与します。
- 法律トラブルは弁護士
- 不動産登記は司法書士
- 税金対策は税理士
など、それぞれの得意分野で対応が異なります。
不動産の相続登記はいつまでに必要ですか?
所有権取得を知った日または遺産分割成立日から3年以内です。
2024年4月以降義務化され、期限を過ぎると過料(最大10万円)が科される可能性があります。
相続税の申告はいつまでに必要ですか?
被相続人の死亡日の翌日から10か月以内です。
基礎控除を超える財産がある場合、税理士に相談し、正確な評価と早めの申告が重要です。
相続放棄や限定承認はいつまでに手続きが必要ですか?
相続開始を知った日から3か月以内(熟慮期間)です。
この期限を過ぎると、借金を含むすべての遺産を相続することになります。
遺産分割協議で争いが生じた場合、どうすればよいですか?
弁護士に相談し、調停や訴訟を見据えた法的対応をとることが適切です。
早期の対応が、感情的対立や長期化を防ぐカギになります。
相続手続きの全体的な流れを教えてください。
- 被相続人の死亡確認
- 相続人の確定・戸籍収集
- 相続方法の検討
- 遺産分割協議
- 不動産の名義変更
- 土地の境界確定
- 不動産の売却・賃貸活用
- 相続税の申告・納付
それぞれの段階で必要な書類や専門家が異なるため、事前にフローチャートを確認するとスムーズです。
借金や連帯保証など負の資産がある場合の注意点は何ですか?
相続放棄や限定承認の検討が必要です。
期限内に家庭裁判所へ申述しないと、すべての債務を承継してしまう可能性があります。
複数の専門家を連携させるメリットは何ですか?
法律・税務・不動産など各分野の専門知識を活用できるため、ミスやトラブルを避けられます。
弁護士を窓口に連携すれば、効率よく複雑な相続問題を解決できます。
まとめ:スムーズな相続・相続放棄を行い、トラブルを回避しよう

相続・相続放棄をスムーズに行うためには、まずは財産の全容を正確に把握し、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。
特に、
のように、それぞれ期限が定められており、放置すると過料(罰金)や紛争に発展してしまうリスクがあります。
また、紛争が生じる可能性がある場合は、弁護士を窓口にしながら税理士や司法書士、行政書士などと連携して進めると、問題解決が円滑になります。
 ねくこ
ねくこ期限を見落とすと本来避けられるはずのトラブルを招く恐れがありますので、少しでも不安があれば、早期に専門家へ相談し、安心して相続手続を進めましょう。
遺品整理や生前整理、特殊清掃やゴミ屋敷片付けなど、はばひろく対応しているしあわせの遺品整理は全国で即日に対応可能。専任の遺品整理士がお伺いします。
遺品整理・不用品回収・ゴミ屋敷片付けなら【クリスタ】
「遺品整理」「ゴミ屋敷片付け」「お部屋丸ごとの清掃」なら、安心の専門業者【クリスタ】にお任せください。年中無休で受付(9:00〜20:00)。お電話またはLINEでのお問い合わせ対応。必要/不要の仕分け作業から丁寧に行い、女性スタッフの対応も可能です。
本記事は一般的情報であり、個別の事案に対する法的・税務上の助言ではありません。最新法令・通達・各機関の運用は必ず一次情報で確認し、必要に応じて専門家に相談してください。


















