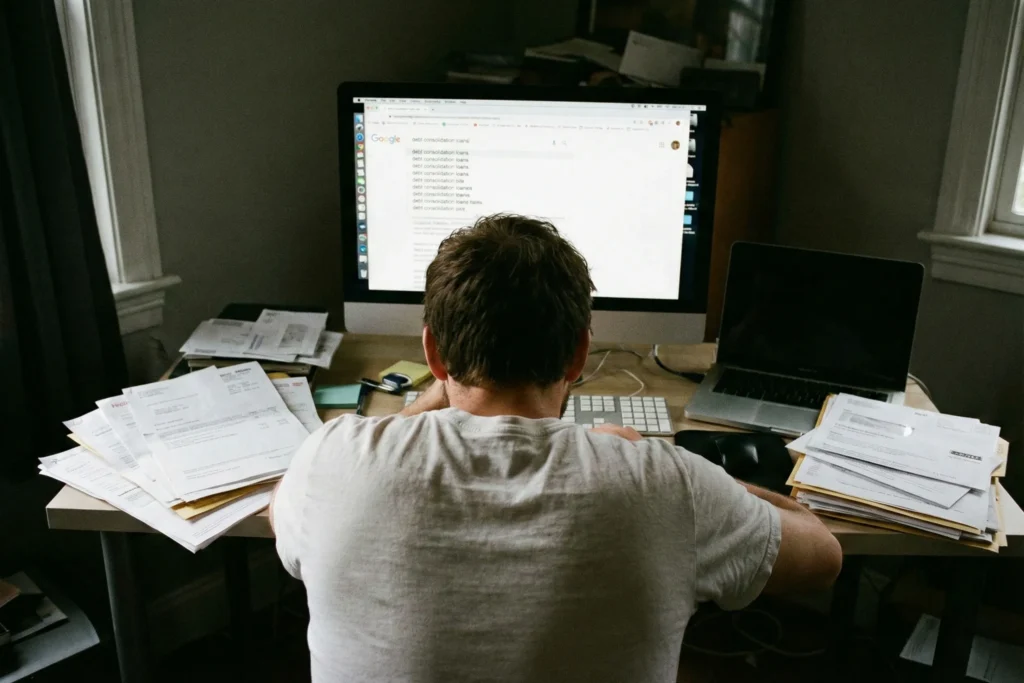【2025年11月28日】の経済・時事ニュースまとめ

2025年11月28日は、日経平均が5万円台を維持しつつ小幅安となり、為替はドル高・円安の156円台前半でもみ合う展開となっています。
前日の米国株は感謝祭連休前の取引で4日続伸となり、世界的にも株高と金利低下への期待が意識されています。
国内では10月の鉱工業生産や雇用統計、東京都区部の物価など家計に直結する指標が相次いで公表され、海外ではウクライナ情勢や中東情勢に加え、香港の高層住宅火災など、地政学リスクと暮らしの安全を考えさせられるニュースが続いています。
 ねくこ
ねくここの記事では、主要な株価指数と為替レートの動き、資産運用で意識したい一般的なポイント、国内外のニュースと私たちの暮らしへの影響を整理してお伝えします。
主要株価指数・為替レート(2025年11月28日10時時点)
| 指標 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 50,033.08円 | -134.02(-0.27%)円 |
| NYダウ | 47,427.12ドル | +314.67(+0.67%)ドル |
| S&P500 | 6,812.61ポイント | +46.73(+0.69%)ポイント |
| ドル円為替(ドル/円) | 156.28円 | -0.01円 |
東京市場の午前10時ごろの状況と、前日までの主要な海外株価・為替レートを一覧にまとめます。
※ 米国市場は感謝祭で休場のため、米株指数は27日早朝の日本時間から見て最新となる26日の終値ベースの数値です。
日経平均は5万円台を維持しつつ小反落
日経平均株価は午前10時過ぎの時点で約5万0033円と、前日終値5万0167円から0.3%弱下落しつつも5万円台を維持しています。
前日は米国株高と年末の利下げ観測を追い風に1.2%上昇しており、その反動で利益確定売りが出やすい地合いとなっています。
セクター別では、自動車やハイテク関連は底堅い一方、一部の大型消費関連株などに調整売りが出ており、指数全体としては方向感に乏しい展開です。
足元で日経平均は5万2000円台の高値圏を何度も試した後の持ち合い局面に入っており、好材料と「高過ぎるのでは」という警戒感が同時に意識されています。
 ねくこ
ねくこ日々の数百円単位の上下は、歴史的高値圏にある指数にとっては「通常運転」の揺れだと捉えたほうが冷静に状況を判断しやすいです。
米国株はテック主導で4日続伸、感謝祭で一時休憩
米国市場では26日の取引でダウ平均が3万7427.12ドルと前日比314.67ドル高、S&P500も0.7%高の6812.61と4日続伸し、主要指数はいずれも年初来高値圏にあります。
上昇の中心は半導体やクラウド関連などの大型テック株で、人工知能関連の調整が一服し、利下げ観測も追い風となっています。
米国市場は27日が感謝祭で全面休場、28日も短縮取引の予定で、売買代金が細りやすい一方で、連休明けの材料次第では値動きが大きくなりやすいタイミングです。
 ねくこ
ねくこ米株の強さは世界のリスク選好を支える一方、短期間での急騰分を巻き戻す場面もあり得るため、「上がっているから安心」とは言い切れない点に注意が必要です。
ドル円は156円台前半で小動き、日本の物価指標と日銀発言待ち
為替市場ではドル円が午前10時時点で1ドル=156円台前半と、前日夕方から小動きとなっています。
前日の米市場が祝日で材料に乏しいなか、東京都区部の物価統計や、週明けの日銀総裁講演を見極めたいという様子見ムードが強い状況です。
足元のドル円は、年内の米利下げ観測が高まりつつも、日本のゼロ金利と財政拡張の組み合わせから「円だけが買われにくい」構図が続いており、156〜158円台の広いレンジでの攻防が意識されています。
 ねくこ
ねくこ外貨建て資産や海外旅行を考えている人にとっては、急激な円安こそ一服したものの、依然として「歴史的には円安水準」である点は頭に入れておきたいところです。
資産運用をしている人がこの局面で心掛けるべきこと
株高と円安が同時に進む局面での基本姿勢
日経平均と米主要株価指数がそろって高値圏にある一方で、為替は円安が長く続いており、資産価格が全体的に「割高に見えやすい」局面になっています。
こうした局面では、新たに大きな金額を一度に投じるよりも、既に保有している資産の配分が自分のリスク許容度に合っているかを点検することが重要です。
具体的には、株式や投資信託が想定より増え過ぎていないか、現金や安全資産が十分に確保されているかを家計全体で確認し、必要に応じて時間をかけてリバランスする考え方が基本になります。
 ねくこ
ねくこ「今から乗り遅れたくない」という気持ちが強くなるほど、短期の値動きに翻弄されやすくなるため、まずは家計の土台を整えることから優先するのがおすすめです。
NISAを使う人は長期・分散・積立の原則を再確認
NISAを活用している人にとって、株価が高値圏にある局面では「焦って一括で投資する」のではなく、長期・分散・積立という基本に立ち返ることが大切です。

短期的な上げ下げは読み切れないため、毎月など一定のタイミングでコツコツと金額を分散して投資することで、高値掴みのリスクをならすことができます。
また、テーマ性の強いファンドや一部の人気銘柄に偏り過ぎると、調整局面での下落幅も大きくなりがちなので、国内外の株式や債券、現金など複数の資産に分ける意識が重要です。
 ねくこ
ねくこNISAは「短期間で大きく増やすための勝負口座」ではなく、「税金面で有利な長期の資産形成の箱」と考えると、無理のないペースを保ちやすくなります。
iDeCoや年金制度とのバランスを確認する
iDeCoなどの私的年金制度を利用している人は、公的年金や企業型DCと合わせた「老後資産全体」でどの程度リスク資産を持っているかを確認しておくことが大切です。

iDeCoは原則60歳まで引き出せない代わりに所得控除などの税制メリットがある制度であり、生活費としてすぐに必要なお金とは分けて考える必要があります。
一方で、相場が大きく動いたときに慌ててスイッチングを繰り返すと、長期で見るとリターンを損なう可能性があるため、拠出額や配分の見直しは「年に1回程度」を目安に落ち着いて行うのが現実的です。
 ねくこ
ねくこ老後資金づくりでは、短期の値動きよりも「何年・何十年と続けられるルールを決めること」の方が、結果的に資産形成への影響が大きくなります。
FXや外貨建て資産ではレバレッジ管理を徹底する
FX取引や外貨建ての投資信託などを利用している人にとって、ドル円が156円前後という水準は、少しのニュースで数円動いてもおかしくない「ボラティリティの高いゾーン」といえます。

特にFXでは、証拠金に対して大きなポジションを持つと、想定外の円高や円安が短時間で進んだ際にロスカットが発生し、元本を大きく減らしてしまうリスクがあります。
ポジションサイズを小さく抑え、重要指標や中央銀行イベントの前には建玉を減らす、あるいは一度ノーポジションに戻すといったルールを決めておくことが、長く市場に残るうえでの防波堤になります。
外貨建て投信やETFでも、為替だけで評価額が上下する点は同じため、外貨と円のバランスを家計全体で把握しておくと、円高・円安局面でも慌てにくくなります。
 ねくこ
ねくこレバレッジをかけた取引は「攻めの手段」というより、「資金管理のゲーム」の側面が強いことを意識し、生活資金とは必ず切り離して考えるようにしましょう。
国内ニュース
10月の鉱工業生産は前月比1.4%増、自動車増産が牽引
10月の鉱工業生産指数速報は、前月比1.4%の上昇となり、市場予想のマイナス0.6%程度を上回る結果となりました。
とくに自動車工業が前月比6%台の伸びとなり、生産全体を0.8ポイント程度押し上げたことが、全体のプラス要因になっています。
一方で、電子部品・デバイスなどは減産となっており、半導体需要の波や世界経済の減速懸念の影響を受けやすい分野の弱さもにじんでいます。
経産省は生産の基調判断を「一進一退」で据え置いており、コロナ禍からの回復後も、国内製造業が世界需要と供給制約のはざまで揺れ動いている姿がうかがえます。
 ねくこ
ねくこ今後も自動車や装置産業を中心に生産計画の下振れリスクが指摘されており、設備投資や賃上げの持続性を占ううえで注視すべきデータです。
東京都区部の物価は前年比2.8%上昇、伸びは横ばい
東京都区部の11月の消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)は前年比2.8%上昇となり、前月から伸び率は横ばいでした。
エネルギー価格の落ち着きや、食料品の値上げペース鈍化が見られる一方、外食やサービス、家賃などの粘り強い値上がりが全体の押し上げ要因となっています。
いわゆる「コアコア指数」(生鮮食品とエネルギーを除く指標)も2%台後半の伸びが続いており、企業の価格転嫁や人件費上昇の影響が徐々に表れているとみられます。
東京都区部の物価は全国指標に先行する形で公表されるため、今後の全国CPIや日銀の金融政策を占ううえでも重要な参考データと位置付けられます。
 ねくこ
ねくこ生活者にとっては「値上げラッシュはやや落ち着いたが、価格は高止まりしている」という感覚に近く、賃上げとのバランスが引き続き大きなテーマになりそうです。
雇用と小売は堅調だが、足元では鈍化の兆しも
総務省が発表した10月の完全失業率は2.6%と3カ月連続で同水準を維持し、有効求人倍率も1.18倍と1倍を上回るなど、雇用全体としては底堅さが続いています。
一方で、有効求人倍率は2021年末以来の低い水準まで下がり、求人件数も前月比で減少しており、省人化や最低賃金引き上げを背景に、企業側が採用計画を見直す動きも出ています。
小売販売額は10月に前年比1.7%増となり、家電など高額品の売れ行きが堅調だった一方、食品関連はマイナスとなるなど、物価高の影響が品目によって濃淡を見せています。
 ねくこ
ねくこ雇用が急速に悪化しているわけではないものの、物価高と成長鈍化のはざまで、消費や賃上げの持続力が試される局面に入っているといえます。
ストリートブランド「HUMAN MADE」がグロース市場に上場
ストリート系ファッションブランド「HUMAN MADE」を展開する企業が、東京証券取引所グロース市場に上場し、27日に記念セレモニーが行われました。
ブランド創業者でクリエイティブディレクターのNIGO氏は、1990年代の裏原宿ブームを象徴する存在であり、今回の上場も国内外のファッション関係者から注目を集めています。
「HUMAN MADE」は衣料品だけでなく雑貨や飲食ライセンス事業も手がけており、2026年には原宿に旗艦店をオープンする計画が報じられています。
 ねくこ
ねくこ投資家にとっても、IPビジネスやサブカルチャー発のブランドが資本市場で評価される例として、今後の成長ストーリーに関心が集まりそうです。
常陸宮さまが90歳の「卒寿」、穏やかな日常の様子が公開
上皇さまの弟である常陸宮さまが28日に90歳の誕生日を迎え、「卒寿」となられたことが宮内庁などから発表されました。
宮内庁は、常陸宮妃華子さまや愛犬「福姫」と共に自宅で撮影された近影を公開し、庭を散策したり、テレビでスポーツやドラマを観たりと、穏やかな日常の様子を伝えています。
ご高齢により公的行事への出席は控えめになっているものの、リハビリ体操や歩行訓練を続けるなど、健康維持に努めている様子も報じられました。
 ねくこ
ねくこ皇室の高齢化と活動スタイルの変化は、日本社会全体の高齢化とも重なっており、長く現役で社会参加を続ける「ロールモデル」としての一面も感じられます。
海外ニュース
プーチン大統領、米国のウクライナ和平案を「出発点」と評価
ロシアのプーチン大統領は、米国が提示したウクライナ戦争終結に向けた和平案について「協議の出発点になり得る」と述べる一方、ウクライナ軍が占領地域から撤退することをあらためて要求しました。
報道によると、ロシア側はドネツク、ルハンスク、ヘルソン、ザポリージャの4州からウクライナ軍が撤退することや、NATOの関与を制限することなど、従来の主張を維持しているとされています。
米国案はトランプ政権下でまとめられた草案がもとになっているとされ、領土の一部割譲を含む内容への懸念から、ウクライナや欧州の一部では慎重論も強まっています。
 ねくこ
ねくこ市場は今のところ「すぐに停戦が実現する」とまでは織り込んでいませんが、原油価格や欧州経済に与える影響を通じて、中長期的には資産価格に影響し得るテーマです。
香港の高層住宅で大規模火災、50人超が死亡
香港の高層公共住宅で大規模な火災が発生し、現地報道や当局発表によると、少なくとも50人以上が死亡、数十人が負傷する甚大な被害となりました。
火災は築年数の古い高層棟で発生し、階段や廊下の狭さ、避難経路の不足など、老朽化した建物の安全性をめぐる課題があらためて浮き彫りになっています。
香港政府は原因調査と再発防止策の検討を進める方針で、類似の建物が多い他のアジア都市にとっても、都市インフラの更新や防災対策の重要性を問いかける出来事となりました。
 ねくこ
ねくこ今回の火災が日本のマーケットに直接大きな影響を与える可能性は高くありませんが、都市部の防災投資や不動産規制のあり方など、中長期のテーマとして意識されそうです。
インドの成長率は高水準維持の見通し、7〜9月期GDP発表へ
インドでは7〜9月期(第2四半期)の実質GDP統計の公表を前に、民間予測で7%前後の高い成長率が見込まれており、世界の主要国の中でも際立った成長テンポを維持するとの見方が多くなっています。
報道によると、都市部の消費とインフラ投資が景気を支える一方、輸出は世界経済の減速の影響を受けやや慎重な動きとなっており、内需主導の成長構図が続いているとされています。
旺盛なITサービスや製造業の投資誘致を背景に、インドは「世界の成長エンジン」としての存在感を高めており、多国籍企業の生産拠点分散やサプライチェーン戦略にも影響を与えています。
 ねくこ
ねくこ日本から見ても、長期的に成長が期待できる国への分散投資という観点で、インド関連ファンドや企業への関心が高まりやすい環境が続いていると言えます。
ヨルダン川西岸でパレスチナ人2人が射殺され、国際的な批判が高まる
イスラエル占領下のヨルダン川西岸で、パレスチナ人男性2人が治安部隊に投降した後に射殺されたとされる映像が報じられ、イスラエル軍が事案の調査に着手したと伝えられています。
パレスチナ側は「丸腰の状態で射殺された」として強く非難し、国際人権団体なども国際法に反する可能性があるとして、透明性の高い調査を求めています。
イスラエルとパレスチナをめぐっては、ガザ地区での戦闘に一定の落ち着きが見られる一方、西岸での軍事作戦や入植地を巡る衝突が続いており、地域全体の緊張は依然として高いままです。
 ねくこ
ねくこ中東情勢の不安定化は、原油価格や安全資産への資金流入を通じて金融市場に影響し得るため、短期的な価格変動だけでなく、中長期の地政学リスクとして注視する必要があります。
私たちの生活に起こること
物価2〜3%台の継続は家計にじわじわ効く
東京都区部の物価が前年比2.8%上昇と、目標2%をやや上回る水準で横ばいが続いていることは、「急激なインフレではないが、賃金が追いつかないと負担感が続く」局面であることを示しています。
食品や日用品の値上げペースはピークアウトしつつあるものの、一度上がった価格が元に戻るケースは少なく、外食やサービス、公共料金などの支出は家計に長く影響を残します。
今後もエネルギー価格や為替次第で光熱費やガソリン代が変動する可能性があるため、「収入を増やす努力」と「支出をコントロールする工夫」の両方を並行して考えることが現実的です。
 ねくこ
ねくこ物価上昇を完全に避けることはできない一方で、支出の中で優先度の高いものとそうでないものを整理するだけでも、家計の息苦しさを和らげられるケースは多く見られます。
「固定費」を見直しつつ、無理のない資産形成を続ける
家計の見直しでは、通信費や保険料、住宅関連費などの「固定費」を減らすことが、短期の節約テクニックよりも効果が大きいとされています。




毎月決まって出ていく支出を少しずつ下げることができれば、その分を緊急資金の積み立てや、将来に向けた投資信託などの長期運用に回す余裕が生まれます。
ただし、保険や医療、教育費など、万一の際に生活を守るための支出まで一律に削ってしまうと、かえってリスクが高まる場合もあるため、「何のための固定費か」を確認しながら見直すことが大切です。
 ねくこ
ねくこ節約と資産形成は「我慢大会」ではなく、「ムダを減らしつつ、自分たちの価値観に沿ったお金の使い方を選び直すこと」と捉えると、長続きしやすくなります。
国際情勢の緊張とエネルギー価格の変動に備える
ウクライナ情勢や中東情勢、香港の火災のようなニュースは、一見すると日本の家計には遠い出来事に思えますが、原油や資源価格、サプライチェーンを通じて、ガソリン代や電気代、輸入品価格にじわじわ影響する可能性があります。
短期的に相場が上下しても、それが実際の請求額に反映されるまでにはタイムラグがあるため、「今月の値上げだけ」を見るのではなく、数カ月〜数年の視点で家計の変化を見ていくことが重要です。
日常生活レベルでは、エネルギー効率の良い家電の使用や、無駄な移動を減らす工夫など、小さな行動の積み重ねが長期的な負担軽減につながります。
 ねくこ
ねくこ世界のニュースに触れると不安になりがちですが、「自分がコントロールできる範囲」で家計や働き方を整えることに意識を向けると、必要以上に悲観し過ぎずに済みます。
免責事項
本記事は、2025年11月28日時点で公表されている各種統計や報道をもとに、一般的な情報提供を目的として作成したものです。
特定の金融商品や投資手法の購入・売却を推奨したり、将来の運用成果を保証したりするものではなく、実際の投資判断は必ずご自身の責任と判断で行ってください。
記載内容の正確性には十分配慮していますが、最新情報への更新遅れや第三者提供データの変更などにより、実際の数値や状況と異なる可能性がある点をご承知ください。