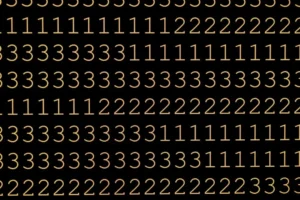え!?株式会社って社長のものじゃないの? 会社のホントの仕組み、教えます

会社は社長のもの。
なんとなく、そう思っていませんか?
特に、ニュースでよく見る「〇〇社長」という言葉を聞いていると、社長が会社のすべてを握っているように感じますよね。
 ねくこ
ねくこご自身の勤め先でも、「社長の鶴の一声で決まる」なんて言える場面があるかもしれません。
でも、実は「株式会社」という仕組みは本当はちょっと違っていて、実は会社は社長のものではない場合があるのです。
「えっ!?」と思われたかもしれません。株式会社は株主が議決権や配当などの権利を持つ仕組みですが、会社の財産は会社(法人)そのもののものです。
この記事では、
「株式会社ってそもそも何?」
「株主(オーナー)と社長ってどう違うの?関係性は?」
という疑問に、知識が0の方でも分かりやすくお答えします。
 ねくこ
ねくここの記事を読めば、会社のニュースの見方が変わったり、自分の働く会社への理解が深まったりするかもしれません!
私たちも日々の時事ニュースをお伝えしているので、ぜひチェックしてみてくださいね!
「株式会社」ってそもそも何? ゼロから分かる基本の仕組み

まず、私たちの周りにあふれている「株式会社」という存在の基本を押さえましょう。
 ねくこ
ねくこ日本にある会社の多くがこの形態をとっていますが、なぜ「株式会社」なのでしょうか?
当たり前のように「株式会社〇〇」と呼びますが、その仕組みについてまずは解説します。
会社を「作る資金」はどう集める?
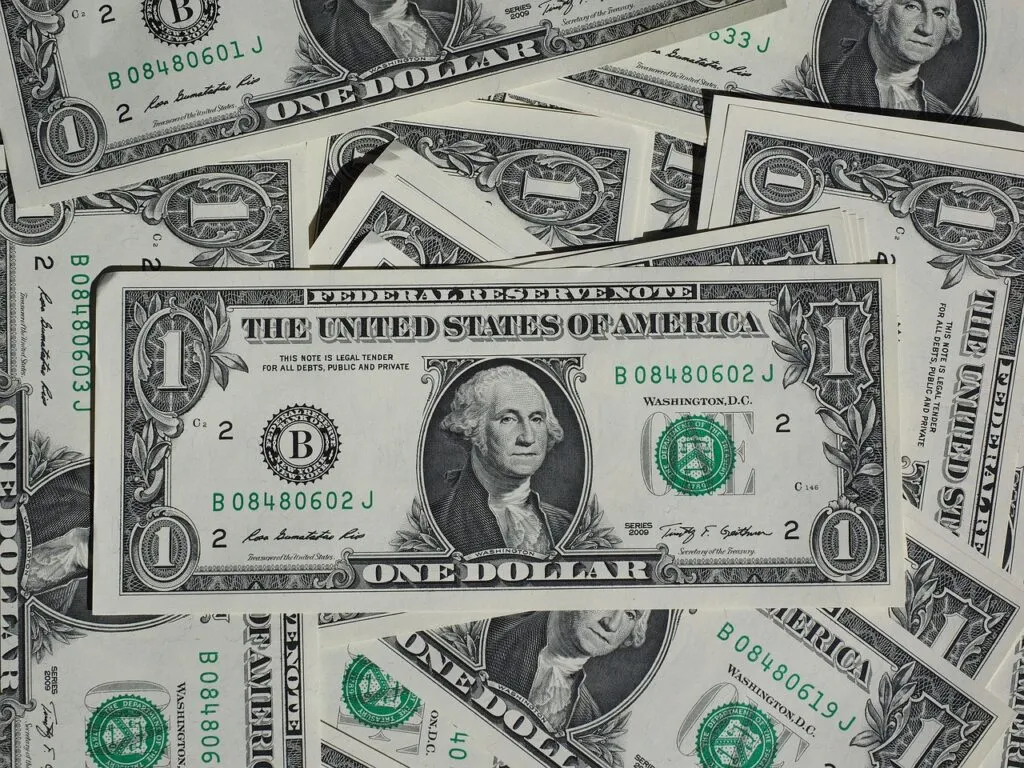
- 会社を新たに設立して事業を開始する
- 事業を拡大する(新しい工場を建てる、新製品を開発する、海外に進出するなど)
これらのことをするには、莫大な「お金(資金)」が必要です。
銀行からの借入れなど、資金を集める方法はいくつかありますが、株式会社の場合は
によって資金調達が可能な点が異なります。
株式=会社の所有権の一部
そして、「株式」とは、超ざっくり簡単に言えば「会社の所有権を細かく分割したもの」です。
株式=会社に対する持分(議決・利益配分などの権利束)。会社の“資産そのもの”の所有権ではありません。
その上で、株式を発行した会社は、
と呼びかけ、資金を集めます。
この株式を買って、会社にお金を提供してくれた人たちのことを「株主(かぶぬし)」と呼びます。
株を購入した企業が成長=株価が上がり金融資産が増える
そして、
という仕組みになっているからこそ、「株式会社である企業」と「成長のために投資する株主」の両方が得をする仕組みになっています。
 ねくこ
ねくこ株主は、個人投資家から、他の会社、年金基金のような大きな組織(機関投資家)まで様々です。
株式会社の成り立ち
「株式会社」は元々、16~17世紀頃のヨーロッパで誕生した概念です。
大航海時代、貿易船を航海させるには膨大なお金が必要でした。しかし、一人で出資すると難破などのリスクが大きすぎるため、複数の人が資金を集め、リスクを分散することで投資額<期待値を実現するためにできた仕組みです。
世界初の株式会社と言われるのは1602年の「オランダ東インド会社」で、多くの投資家から資金を集め、貿易による利益を配当として還元しました。
株主=会社のオーナーで、会社の方針を決定する権利がある

つまり、株式を買うということは、その会社の「一部」を買うこととに他なりません。
というのも、株式会社は株式の売買によって事業資金を得るため、株主がいないと実質的に活動そのものが難しいからです。
だからこそ、株式を所有している株主=その会社の一部を持っている人=「オーナー(の一人)」という構図になります。
会社全体を大きなホールケーキとするならば、株式会社は、このケーキをたくさんの小さなピースに切り分けます。
この一切れのケーキが「株式」です。
あなたが一切れの株式を買えば、あなたはそのケーキ(会社)の一部分のオーナーになりますし、もし100切れに分けたうちの10切れを持っていれば、あなたはケーキ全体の10%のオーナーです。
そして、すべてのピース(全株式)を持っている人たち、つまり「株主全体」が、そのケーキ(会社)のオーナーということになります。
株式を保有しているシェアで、その会社に対する影響力は異なる
注: 単元未満株(端株)などは議決権が無い、もしくは制限される場合があります。また自己株式には議決権が無く、種類株式では議決権の有無や内容が異なることがあります。
そして、先述のケーキの理論の基づくと
という点も覚えておきましょう。
特に、会社の株を多く持っている人や団体のことを「大株主」と言い、一般的に、会社の経営に影響力を持っていると言えます。
株式を多く持つほど、会社の方針を決める議決権が多くなり、経営に口を出す権利が強くなります。
社長がどれだけ偉そうに見えても、あるいは創業者であっても、その人が「社長だから」オーナーなのではなく、「株主だから」オーナー(の一部)なのです。
 ねくこ
ねくこ創業以来、代々一族が継承してきた企業や、非上場の企業などは、社長や会長=大株主というパターンもありますし、その場合は社長や会長=本当のナンバーワンです。
もし社長が所属する企業の株式を1株も持っていなかったり、影響力があると言えない比率しか持っていなければ、その人はオーナーではなく役員(経営執行者)です。
補足
「オーナー」というと、会社が万が一の際に責任を負わなければならないという懸念を持つ方もいらっしゃると思います。
しかし、株式会社の株主は、会社が倒産した場合でも、自分が出資した金額以上の責任を負わない「有限責任」という原則があります。これも、多くの人が安心して株式を買いやすい理由の一つです。
社長は「経営のプロ」、株主は「オーナー」である

という疑問が当然出てきますよね。
ここでは、社長に代表される役員を、株主とは別の角度から露わにしていきたいと思います。
社長(代表取締役)と役員の役割—“監督”と“執行”を分けて理解
結論、社長(代表取締役)やその他の役員(取締役など)は、株主から「会社の経営・運営を任されたプロフェッショナル」です。
その企業の営利を追求するために、株主によって選ばれた陣頭指揮を執るリーダーという役目が、「社長」「常務」「専務」といった役員たちにはあります。
そして、それらの陣頭指揮を執る「リーダーたち」は、株主が集まって行う(年に一度など)「株主総会」という場で、自分たちの代わりに経営を執行する選んでいます。
 ねくこ
ねくこそして、その経営陣の中でもトップを張るのが、一般的に「社長」と呼ばれる人です。
株主は、経営陣を選ぶための「議決権(投票権)」を持っています。
「社長」「役員」は、株主のために利益を追求する
取締役は株主総会で選任され、取締役会が代表取締役(いわゆる社長)を選定するのが一般的です(委員会設置会社など例外あり)。
社長や役員の最も重要なミッションは、
です。
そのために、経営戦略を立て、組織を動かし、日々の業務を執行していく責任を負っています。
株主から預かった大切な資産(会社)を、より大きく育てていく「運用責任者」のような立場で、そういう意味では投資信託のファンドのプロに近い役割を担っています。
 ねくこ
ねくこそして、多くの上場会社は取締役会を設置していますが、非上場・小規模会社では取締役会を置かない形(取締役会非設置会社)もあります。会社ごとに機関設計が異なります。
「取締役会」は社長の業務執行を監督する仕組みです。
これも株主の利益を守るための仕組みで、場合によっては株主総会で社長や役員を交代するということも起こります。
「株主」が持つ権利について
株主は、会社のオーナーとして、いくつかの重要な権利を持っています。
利益の分配を受ける権利(配当請求権)
会社が生み出した利益の一部を、「配当金」として受け取ることができます。
会社の重要事項を決める権利(議決権)
株主総会に出席し、持っている株式数に応じて、役員の選任や会社の重要な決定事項(合併や定款変更など)に対して賛成・反対の票を投じることができます。
通常決議と特別決議では必要な賛成の割合が異なります(例: 特別決議は通常より厳格)。
会社の解散時に残った財産の分配を受ける権利(残余財産分配請求権)
万が一会社が解散した場合、負債などをすべて返済した後に残った財産を、持ち株数に応じて受け取る権利があります。
と、いった権利を有します。
配当請求権・議決権・残余財産分配請求権に加え、一定の要件で株主提案権、会計帳簿等の閲覧請求、会社に代わって責任追及を図る代表訴訟などの権利もあります(会社の規模や要件により異なる)。

「株主」の権利や主張に対し、経営陣は上手く舵取りをすることを求められる
株主は、これらの権利を通じて、会社経営に関与しますが、いずれにせよ自分たちが出資したお金(=株式投資)が、配当金や株価の上昇という形で報われることを期待しています。
経営陣(社長や役員)からすると、短期的な利益を重視する株主もいれば、長期的な成長を期待する株主もおり、モノ言う株主、急進的な改革を求める株主など、(ときおりメディアで話題になりますが)さまざまな株主の期待に応えなければなりません。
 ねくこ
ねくこ昨今の某メディア企業などのニュースも然りですが、経営陣や事業の刷新・改革を求められることもままあります。


「上場企業」と「非上場のオーナー企業」の違い ~なぜ誤解が生まれる?~
理屈は分かったけど、やっぱりピンとこないな…ウチの会社の社長は、オーナーにしか見えないけど?(いばっているし)
と感じる方もいるでしょう。
 ねくこ
ねくこそれは、会社の規模や株式の公開状況、スタンスによって、株主と経営者の関係性の「見え方」や「実態」が異なるからです。
上場企業:たくさんの株主と経営のプロがいる会社

トヨタ自動車、ソニーグループ、任天堂…こうした誰もが知るような大企業は、多くが「上場企業」です。
「上場」とは、自社の株式を証券取引所という公的な市場で、不特定多数の投資家が自由に売買できるようにすることです。
上場することで、株式を公開することで世の中の幅広い層から大規模な資金調達が可能になりますし、会社の知名度や信用度も向上します。
 ねくこ
ねくこその代わり、株主は非常に多岐にわたり(個人投資家、国内外のファンド、銀行、保険会社など)、その数は数万、数十万、時には数百万に上ります。
このような会社では、
という役割分担が、比較的明確になっています。
社長自身も株主の一人であることは多い(トヨタなど)ですが、全株式を持っているわけではなく、多くの株主の意向(株主価値の向上)を意識した経営が求められます。
また、投資家保護の観点から、厳しい情報開示ルール(決算情報の公開など)も課せられます。
上場企業のメリット・デメリット
メリット
① 資金を集めやすくなる
- 株式市場で多くの人から資金を調達できるため、銀行などから借りるよりも有利な条件でお金を集められます。
- 新しい事業や設備投資に使う資金を確保しやすくなります。
② 信用や知名度の向上
- 上場企業ということで信用度やブランドイメージが高まり、取引先や顧客との信頼関係が築きやすくなります。
- 優秀な人材も集まりやすくなります。
③ 株主が株を売りやすくなる
- 株主(創業者など)が自由に株式を市場で売却できるため、資金回収や利益確定がしやすくなります。
デメリット
① 経営の自由度が低下する
- 株主や投資家の意見を聞きながら経営を行う必要があるため、経営の自由度が制限されます。
- 大株主や投資家からの圧力により短期的な利益を追求しなければならないこともあります。
② 上場維持のコストが高い
- 定期的な財務報告や監査、コンプライアンス(法令遵守)など、多くの手間と費用がかかります。
- IR活動(投資家への情報提供)にかかる時間と労力も増えます。
③ 情報の公開義務がある
- 会社の経営状況を定期的に公開する必要があり、競合企業にも情報が伝わるため、戦略的に不利になる可能性もあります。
- 上場会社には法令・取引所規則に基づく開示義務(決算等の法定開示・適時開示)が課されます。機密情報まで常時公開するわけではありません。
 ねくこ
ねくこサントリーやコーセー、YKK、JTB、佐川急便、竹中工務店などは、実は非上場の有名企業です。
非上場のオーナー企業➡社長=大株主が一般的なケース

一方、日本には上場していない会社(非上場企業、未公開企業)も星の数ほど存在します。
多くの中小企業や、特定の分野で大きなシェアを持つ優良企業の中にも非上場企業はたくさんあります。
上場企業においては、創業家が経営に関与している企業の割合は約48.9%とされているのに対し、非上場企業を含めた日本の全法人のうち、90%以上がファミリービジネス(創業家が所有し経営にも関与する企業)と推定されています。
これらの会社、特に創業者やその一族が経営している会社では、
が非常に多く見られます。
この場合、「社長(経営者)」と「筆頭株主(最大のオーナー)」が同一人物であるため、実質的に「社長=オーナー」として振る舞うことが可能になります。
そのため、
というメリットもある一方で、
というデメリットもあります。
 ねくこ
ねくここれが、良くも悪くも「会社は社長のもの」というイメージが生まれる大きな理由の一つです。
しかし、ここでも法的な仕組みは同じです。
その会社の所有権は、「社長という役職」に付随しているのではなく、あくまで「株式を保有していること」に根差しています。
もし社長が株式を他の人に売却したり、相続が発生したりすれば、会社のオーナー構成は変わりますし、株式会社である以上、所有権の源泉は常に「株式」なのです。
【Q&A】株式会社の仕組みの疑問に答える
そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
株式会社って社長のものじゃないの?
いいえ、株式会社は株主のものです。
社長は経営を任された人であり、所有者ではありません。
株主ってどんな人?何ができるの?
株主は会社のオーナーであり、利益配当や経営への議決権などの権利を持ちます。
株式を多く持つほど影響力も増します。
社長の役割って何なの?
社長は株主に選ばれた経営の責任者で、利益を追求し会社を成長させるプロフェッショナルです。
上場企業と非上場企業では社長の立場は違うの?
上場企業では社長は多数株主に任された存在、非上場企業では社長自身が大株主であるケースが多く、実質オーナーの場合もあります。
株式を持っているだけで会社の経営に関われるの?
はい。
株数に応じて株主総会で議決権を持ち、社長や役員の選任や経営方針に対する意思表示が可能です。
まとめ:新しい視点で、企業や株式の動向を見て行こう

今回は、「株式会社は誰のものか?」というテーマを深掘りしてみました。
- 株式会社は、「株式」を通じて多くの人から資金を集め、事業を行うための仕組み。
- その会社の真のオーナーは、株式を保有する「株主」である。
- 上場企業ではオーナー(株主)と経営者の分離が進んでいる一方、非上場企業では社長=大株主が多く、一体に見えやすいが、所有権の原理は同じ。
「会社は社長のもの」という直感的なイメージとは異なる、株式会社の本来の姿をご理解いただけたでしょうか。
株式会社は、多くの人々の協力と信頼によって成り立つ、社会を支える重要な仕組みなのです。
この視点を持つことで、経済ニュースの裏側にある力学が見えたり、自分が働く会社の立ち位置や、株価の変動の意味合いなどが、少し違って見えてくるかもしれません。
また、「気になる企業の株式を買ってみる」というのも非常に面白いです。その会社の一角として参画することもまた、企業の成長の先にある社会貢献にも寄与する切欠になるかもしれません。
 ねくこ
ねくこ私たちも日々の時事ニュースをお伝えしているので、ぜひチェックしてみてくださいね

本記事は一般的な解説であり、特定の投資・法的助言を目的とするものではありません。投資判断や法的手続きは、一次情報(会社法・取引所規則・各社の開示資料)をご確認のうえ自己責任で行ってください。