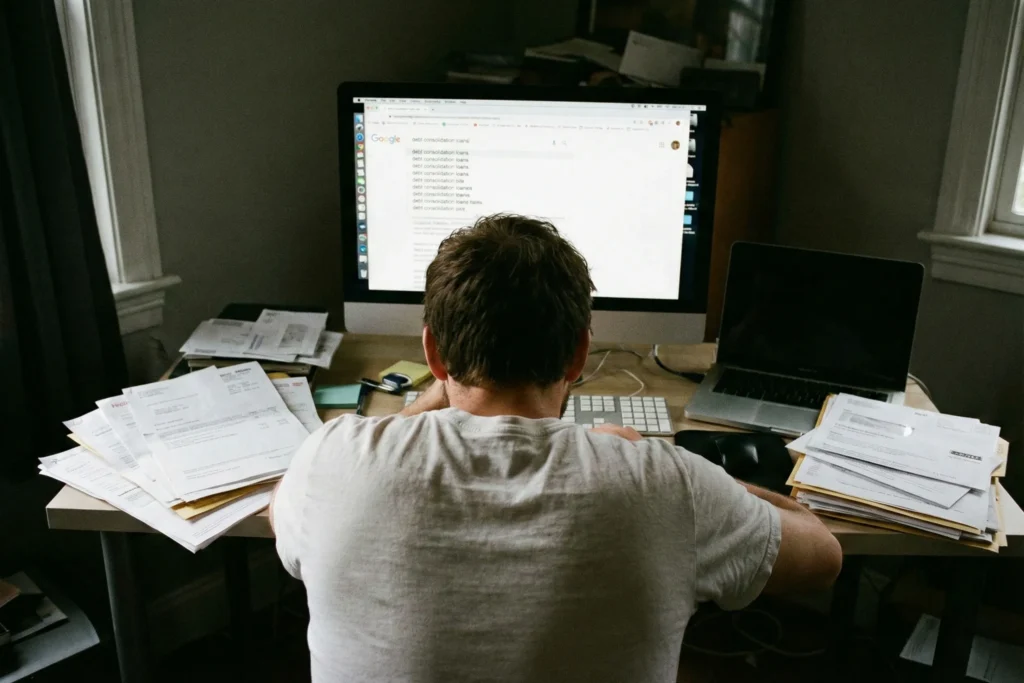出産費用の自己負担無償化へ、厚労省が制度設計を本格検討 2026年度めどに導入目指す

厚生労働省は、出産にかかる費用の自己負担を実質無償化する方向で具体的な制度設計の検討に入りました。
2025年5月14日にも開催される妊産婦支援を話し合う有識者検討会で、議論の内容を整理したとりまとめ案を提示する見込みです。
 ねくこ
ねくこ政府は2026年度をめどに、出産費用の保険適用の導入を含む支援強化を目指しており、今回の動きはその一環となります。
出産育児一時金50万円も、45%が自己負担超えの現状
現在の出産費用は、帝王切開など一部の医療行為を除き、正常分娩は公的医療保険の適用外となっています。
その代わりに、出産時には「出産育児一時金」として50万円(2023年度から増額)が支給される制度がありますが、近年、出産費用は全国的に上昇傾向にあります。
厚生労働省の調査によると、全国の出産事例の約45%で、実際にかかった費用がこの一時金を上回っているのが現状で、特に東京都や神奈川県など都市部では、正常分娩の平均費用が一時金の50万円を超えるケースが多く、妊婦の経済的負担が増大しています。
無償化への具体的な方法:保険適用や一時金増額など多角的に検討
出産費用の自己負担無償化に向けて、厚生労働省は複数の具体的な方法を検討しています。
一つの案として、正常分娩も公的医療保険の適用対象とし、現在3割となっている自己負担分をゼロにする方法が挙げられています。
また、出産育児一時金をさらに増額する方法も検討の俎上にあります。
 ねくこ
ねくここれらの方法について、今後、審議会などで詳細な議論が進められ、来年の通常国会での法改正を目指す考えです。
「標準的な出産費用」の定義や地域差への配慮が課題
無償化を進めるにあたっては、「標準的な出産費用」の範囲をどこまでとするかが重要な論点となります。
現在は「お祝い膳」などのサービス費用が入院料に含まれているケースもあり、これらの費用を標準的な費用として含めるかどうかの精査が必要です。
また、麻酔を使って陣痛の痛みを和らげる「無痛分娩」を保険適用の対象外とする場合には、別途支援策の拡充を求める声も上がっています。
 ねくこ
ねくこさらに、出産費用には地域差が大きいという課題もあります。
全国一律の診療報酬を設定した場合、都市部など費用が高い地域では分娩を取り扱う医療機関が減少する可能性も指摘されており、慎重な制度設計が求められます。
政府「こども未来戦略」の一環、首相も意欲
今回の出産費用の無償化検討は、政府が2023年に定めた「こども未来戦略」に盛り込まれた少子化対策の柱の一つです。
同戦略では、2026年度をめどに出産費用の保険適用導入を含む支援策の強化を検討する方針が示されています。
石破茂首相もかねてより「出産の標準的な費用について妊婦の方に自己負担が生じないよう検討する」と述べており、政府全体として出産費用の負担軽減に強い意欲を示しています。
厚生労働省は、14日の検討会での議論を踏まえ、年末までに具体的な制度案を取りまとめる方針です。