なぜ、高市新総裁が決まって日経平均が上がったの?理由を易しく解説

2025年10月4日、自由民主党総裁選で高市早苗氏が勝利した翌営業日の2025年10月6日(JST)、日経平均は約+5%まで上昇する場面があり、10月7日未明時点の報道ではドル/円=150.3前後まで円安進行と伝えられました。
一方、2024年9月27日、自民党総裁選で石破茂氏が選出され翌10月1日に首相に就任した際は、9月30日の東京市場は日経平均が前日比1,910円安の37,919円(-4.8%)で終了しました。
このように、一国の政治リーダーが決まっただけで株価が急伸もしくは急落したり、為替が急変したりするのは一体なぜでしょうか?
何となくニュースを眺めて「そうなんだ」と受け入れることは簡単ですが、その背景にある政策の違いや投資家心理を読み解くことで、金融リテラシーやポートフォリオ構築に役立ち得ます。
今回は市場(投資家たち)が、金融政策のハト派(利上げに慎重)姿勢や拡張的な財政運営を予想し、
- 割引率が下がる:株の値段は、会社がこれから稼ぐであろう利益を「いまの価値」に直して計算します。そのとき使うのが“割引率”で、これは「金利」みたいなもの。金利が低くなると「未来の利益の価値」が高く見積もられるため、株価が上がりやすくなります。
- 日本経済の総需要(家計の消費+企業の設備投資+政府支出)の需要が増える:政府が公共事業や補助金などでお金を使うと、モノやサービスを買う人(=需要)が増えます。そうなると企業の売上や利益も増えやすく、「景気が良くなりそうだ」と期待されます。
- 円安で輸出企業が潤う:円の価値が下がると、海外で稼いだドルやユーロを円に換えるときの金額が増えます。そのため、トヨタやソニーのような輸出企業の利益が増えやすく、株価も上がりやすくなります。
という3つの期待が同時に織り込まれました。
 ねくこ
ねくこ本記事では、これら株価のメカニズムを初心者向けに解説し、テーマ株の動きや長期的なリスクも含めて丁寧に解説します。

本稿は一般的な市場解説です。投資判断はご自身で、必要に応じて登録業者や有資格専門家へご相談ください。
「金融緩和期待」と「割引率低下」が株価を押し上げた

高市新総裁の誕生を受けて市場が最初に反応したのは「金利が上がりにくくなるかもしれない」という見方でした。
彼女の政策スタンスは、いわゆる“金融緩和寄り”で、日本銀行が急いで利上げをする可能性は低いと受け止められています。
 ねくこ
ねくこ金利が低いままだと株の構造上、企業の将来の利益がより高く評価されやすくなるため買い注文が多く入り、多くの投資家に買われることで株は価値を高めて価格が上がる。
これが主な企業の指標である日経平均株価を押し上げた主な理由のひとつです。
割引率低下は株式評価を押し上げうる一因に

高市氏は候補者の中で最も拡張的な金融政策を掲げており、「当面、利上げは必要ない」と繰り返し述べてきました。
「拡張的な金融政策」とは
景気を刺激するためにお金の流れを増やす政策のことで、簡単に言うと「世の中に出回るお金を増やして(=金利を低いままにして)、企業や個人がお金を使いやすくする政策」のこと。
市場が「金利は当面上がらない」と判断すると、企業の将来利益を現在価値に割り引く際の「割引率」が下がります。
企業が将来どれだけ利益を出せそうかを「今の価値」に直して考える
投資の世界の場合、たとえば、1年後に100円もらえる約束があるとしても、もし金利が5%なら「今もらえるお金に換算すると約95円の価値しかない」と考えます。
でも、金利が2%しかなければ「今の価値は約98円」となって同じ100円でも高く見え、この“将来のお金を今の価値に直すための利率”を、専門的には「割引率」と呼びます。
つまり、金利が下がるとこの割引率も下がり企業の将来利益がより高く評価され、その結果、株価が上がりやすくなるという仕組みです。
 ねくこ
ねくこ言い換えると、金利が低いときは「未来のお金の価値が下がりにくい」ため、企業の将来利益がより魅力的に映るのです。これが“金融緩和期待が株価を押し上げる”という意味になります。
この仕組みを理解すると、金融緩和期待が指数上昇に寄与した可能性が指摘されます。
日銀の利上げ後ずれ観測が投資資金を呼び込んだ
高市氏の当選後、円は米ドルに対して約2%下落(円安になった)し、金利先物市場では年内利上げの確率が6割から4割程度に下がったと報じられています。
金融政策がハト派に傾くと、銀行預金や国債など安全資産の利回りが伸び悩み、「株式の方がリターンを得られる」という心理が強まります。
多くの機関投資家はポートフォリオの資産配分を見直し、低金利が続く間は株式比率を高める傾向にあります。
 ねくこ
ねくこ短期的に利上げが後ずれするだけで、資金が債券市場から株式市場へ移動しやすくなります。

「拡張的な財政政策」への期待が需要を押し上げる
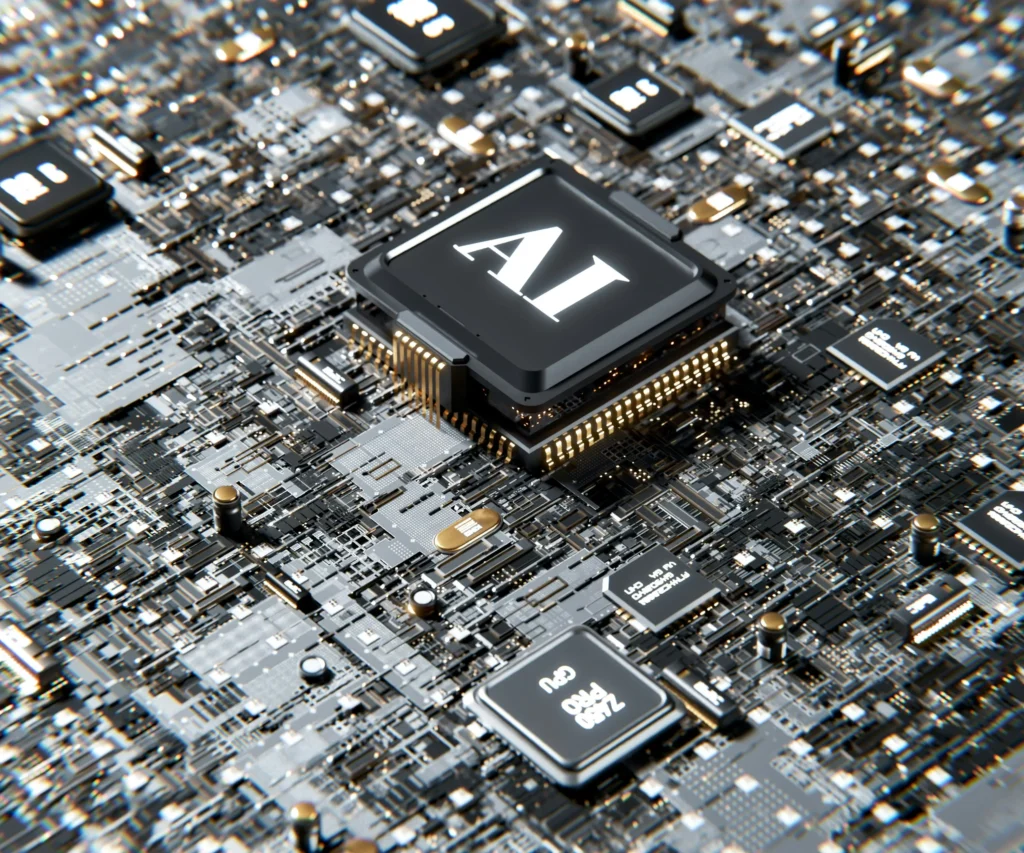
金融政策だけでなく、政府がどれだけお金を使うか、つまり「財政政策」も株価を左右します。
高市新総裁の誕生で注目を集めたのが、この「拡張的な財政政策」への期待です。
簡単に言えば、国が積極的にお金を使って景気を支えるという考え方で、企業の売上や利益を押し上げるきっかけにもなります。
 ねくこ
ねくこ特に日本では、アベノミクス以降この“財政+金融”のダブル支援が株式市場の上昇を支えてきました。
「アベノミクス」寄りの財政拡大路線
高市氏は師匠である安倍晋三元首相の経済政策「アベノミクス」に強い敬意を表し、
- 国債による財政出動
- 大胆な公共投資
を公約に掲げています。
中でも高市氏は「防衛力強化」「原子力発電の再稼働や次世代炉」「半導体産業」「人工知能(AI)」などの戦略分野に重点投資を行う意向です。
「半導体銘柄」への影響例
実際、10月6日(月)場中〜大引けにかけて、指数寄与度の大きい半導体株が上昇し、具体的にはアドバンテスト(6857)が10%超高、東京エレクトロン(8035)が6%超高の値を付けました。
さらに、10月7日(火)の寄り付きでもAI・半導体株が相場を押し上げ、日経平均とTOPIXが最高値更新の動きと確認されています。
こうした財政拡大策は、企業への補助金や公共事業を通じて直接的に需要を押し上げる働きを持ちます。
例えばインフラ整備や防衛装備の発注が増えれば関連企業の売上は増加し、雇用や賃金にも波及効果が生まれます。
 ねくこ
ねくこ財政支出が民間投資を誘発すると経済全体の成長率が高まり、企業の将来利益見通しが改善します。
投資家はこの「業績押し上げ効果」を先取りし、今のうちに当該銘柄株に資金を振り向けることで、財政拡大の恩恵を受けようという心理です。
「防衛関連銘柄」も高騰
さらに、高市氏の勝利を受けて防衛関連の三菱重工業が約11%、大型鍛造品を手掛ける日本製鋼所が約15%上昇しました。
これは仮に防衛費拡大や原子力復興といった政策が実現すれば、大型受注が見込める企業に資金が集中するためです。
こうしたテーマ株の急騰は日経平均全体の押し上げ要因になりますが、期待が高まった後に政策が実行されない場合は反動安もあり得ます。
 ねくこ
ねくこ特定業種だけに投資する際は、政策決定プロセスや実行のタイムラグを考慮し、長期的な視野で臨むことが大切です。
株式初心者は、政府の方針が特定セクターの追い風になることを理解しつつ、過度な集中投資は避けるよう心掛けましょう。
投資家心理とリスクプレミアムの変化

さらに、政治的な不透明感が払拭されると、投資家が要求するリスクプレミアム(株式に求める上乗せ利回り)も縮小します。
高市氏の勝利によって「誰が次期首相になるのか」という不確実性が解消され、政局の先行きがある程度見えたことで投資家の警戒感が和らぎ行動指針が示されたため、株式市場への資金流入が促されました。
ただし、現状の与党は参議院・衆議院ともに過半数を割っており、政策実行には連立相手や野党との調整が必要とタフな局面が予想されます。
また、日本銀行の金融政策に対する発言権は限定的であり、財政規律を重視する党内勢力との綱引きも予想されます。
 ねくこ
ねくここのため、期待先行の部分が大きく、今後の政策論議や外部環境次第では再びリスクプレミアムが拡大する可能性があることを忘れてはいけません。
「円安」も輸出企業の業績期待を押し上げた

さらに、日本市場の状況として、日経平均株価を構成する企業の多くが輸出中心企業であることも挙げられます。
特に相対的に円の価値が低い状態である「円安」は、輸出関連企業にとってはプラスに働くことが多い要素です。
 ねくこ
ねくこ高市新総裁が金融緩和に前向きな姿勢を示したことで、「円の価値が下がりやすくなる(=円安方向に傾く)」という見方が市場に広がりました。
円安がもたらす「外貨建て利益」の増加
実際、米ガーディアン紙によると高市氏の勝利後、円が対ドルでほぼ2%下落して150.3円まで安くなり、長期国債の価格が下落して利回りが過去最高に近づいたと報じています(出典)。
為替レートは企業収益や投資家心理に直結するため、円安が進むと海外で稼いだドル建てやユーロ建ての利益を円換算した際の金額が増え、輸出企業の利益見通しが改善します。
日経平均を構成する企業の多くは外需比率が高く、円安は製造業や自動車、精密機器など幅広いセクターに恩恵をもたらします。
 ねくこ
ねくこもちろん、円安は輸入品の価格も上げるため生活者目線では良いことばかりではないという実情もありますが、少なくとも海外投資家も日本株に関心を示し、株式市場全体の買い材料にはなっています。
為替チャンネルと株価の関係は?
先述の通り、為替相場は企業業績に直結します。
日本国内企業が“いくら売り上げたか”は日本円でカウントされるため、この単純な仕組みから、円安は輸出企業(やインバウンド需要)の利益をかさ上げしやすく、株価にも反映されるのです。

一方、円安は原材料やエネルギーなど輸入品の価格を押し上げ、国内企業のコスト負担増や消費者物価の上昇につながります。
日本はエネルギー資源や小麦などの各種原料の多くを輸入に頼っているため、円安が続くと電気料金やガソリン価格が上昇し、内需企業の利益圧迫や家計の購買力低下を招くリスクもあります。
 ねくこ
ねくここうした両面性を理解することで、為替と株価の関係をより深く捉えられるでしょう。
財政拡大&金融緩和政策の「副作用」と今後のリスクは?
景気を支える政策には、必ずプラス面とマイナス面があります。
財政支出を増やしたり、金融緩和を続けたりすると、短期的には景気を押し上げて株価も上がりやすくなりますが、その裏側では「副作用」も動き始めます。
 ねくこ
ねくこ特に日本のように国債残高が大きい国では、金利や為替の変化が政策の効果を増幅させることもあれば、逆に負担を大きくすることもあるのです。
ここでは、そのリスクと今後の注目ポイントを整理します。
財政拡大の副作用:長期金利が却って上昇してしまい国債が売られるリスク
政府がお金をたくさん使う先述の「財政拡大」は、景気を良くする面がある一方で、“副作用”もあります。
先述の「国債による財政出動」や「大胆な公共投資」を行うために、国は原資確保のために新規で「国債」を発行してお金を調達しようとします。
すると、市場に出回る国債の量が増えることで、国債が市場においてあり触れたものになるため、相対的な価格が下がりやすくなります。

国債は「お金を貸す約束の紙」
国債とは、国が「◯年後に元本と利息を返します」と約束して発行する“借用書”のようなもので、私たちは国債を購入することで日本国に利子付きのお金を貸すことができます。
たとえば額面10,000円の国債を、年利1%・10年満期で発行したとすると、持っていれば毎年100円の利息がもらえて、10年後に10,000円が戻ってきます。
株式会社が株を発行して資金を調達するのと同様、国は国債を発行して資金調達を行います。
市場では、国債は売ったり買ったりできますが、国債の利回り(=金利)は、経済の状況や政策によって変わります。
例えば、先述の財政拡大政策などによって「景気が加熱しそうだ」という見込みが市場心理に浸透したとすると、企業や人がどんどんお金を使うようになり、今度はモノやサービスの需要が増えて物価(インフレ)が上がりやすくなります。
インフレが進みすぎると、モノの値段ばかり上がってお金の価値が下がってしまうため、政府や中央銀行は「これ以上の過熱を抑えよう」と考え、世の中のあらゆるものの金利を上げる(利上げ)方向へ向かいます。
金利が上がると、ローンや借入のコストが上がってお金を使いにくくなり、市場のお金の周りが鈍くなるため景気の勢いが少し落ち着きます。

すると、例えば現状1%の金利で買っている“割に合わない”国債を売ってでも、利上げの数値が反映された2%の国債を購入し直したり、高金利通貨や海外債券などの他の金融商品へシフトしようという動きが投資家の中で現れてしまいます。
国債は国が借主かつ原則として元本保証※という性質を持つため、投資家は安心して売却方向へ向かってしまうというシナリオです。
※ 国債には市場で価格が変動する一般の利付国債と、個人向け国債があります。個人向け国債は発行1年経過後に中途換金可(直前2回分の利子相当額×0.79685差し引き)。市場売却する国債は価格変動により元本割れの可能性があります。
 ねくこ
ねくここうなると、財政拡大を行うための原資となる国債が思うように買われず、改革が停滞するリスクが生まれるという論理です。
金融緩和政策の副作用:円安の進行による生活コストの上昇
また、金融緩和政策は景気を押し上げる半面、円安進行といった副作用を招きます。
上述の意図せぬ金利上昇を除き、基本的には金融緩和政策を講じると、日本円は売られやすくなります。
これは為替が「金利の差」で動く部分が大きいことが理由でFX(外国為替市場)などはこの原理で動いている金融商品です。
通貨も金利が高い方が投資家としては利益を得られる
たとえば米ドルの金利が5%、日本円が0%の状況になると、投資家は「円よりドルを持っていたほうが利息が多くもらえる」と考え、ドルを買い、円を売ります。
すると円は相対的に変われないため価値(為替レート)が下がり「円安」になります。
先述のとおり、円安は輸出企業に恩恵をもたらす一方で、エネルギーや食料など輸入依存度の高い品目の価格を押し上げ、家計の購買力低下や企業のコスト増を引き起こします。
つまり、利上げを長く先送りしすぎても急激な円安や輸入インフレが進んでしまうという警戒感も示されています。
 ねくこ
ねくこ円安が進みすぎると私たちの暮らしそのものが一層苦しくなってしまいます。
財政拡大と金融緩和の副作用をバランス良く管理することが今後の政策運営の課題です。

インフレと金融政策のバランスが鍵
現在、日本の消費者物価は2%を上回る伸びが続いており、日銀は緩やかな利上げを進めたい意向を示しています。
物価上昇は企業の価格転嫁や賃金上昇につながる半面、家計の実質所得を圧迫します。
高市政権でも利上げ自体を完全に否定するわけではなく、物価や賃金動向によっては2025年末までに再び利上げが検討される可能性があります。
複数アナリストは10/6〜7時点で、「年内の利上げ観測は後退」としつつ、物価動向次第で来年以降の利上げ可能性に言及しています(特定時期の確約ではありません)。
ここまでお読みいただいた通り、政策を誤れば円安が加速し、輸入インフレや長期金利の急上昇につながってしまうため、金融政策と財政政策の協調およびバランスのとり方が重要です。
 ねくこ
ねくこ投資家は期待とともに、こうした副作用や政策運営の難しさも念頭に置き、短期的な材料だけでなく中長期的な経済指標をチェックする習慣を身に付けるべきでしょう。
終わりに|高市経済政策の行方と投資の心構え
高市新総裁誕生をきっかけに、日経平均は史上最高値圏まで急上昇し、為替市場や債券市場も大きく動きました。
背景には、
- 金融緩和と財政拡大への期待
- 円安による輸出企業の業績押し上げ
- 政策テーマ株の物色
など、複数の要因が重なっています。
本記事で紹介した割引率の仕組みや財政拡大の効果、為替チャンネルやリスクプレミアムの考え方を理解すれば、株価と政策の関係性がより立体的に見えてくるはずです。
また、政治ニュースが市場に与える影響を読み解く力は、株式投資に限らず資産運用全般に役立ちます。
今後も政策や経済指標をウォッチし、自分なりの仮説を持ってマーケットに向き合う姿勢が重要です。
 ねくこ
ねくこまた、リスクを分散するために複数の銘柄や資産クラスに投資すること、余裕資金の範囲で投資することも忘れないようにしましょう。
※投資には価格変動・金利・為替等のリスクがあり、元本・利回りは保証されません。手数料等がかかる場合があります。











