MUFGが国内初のデジタル債発行を計画|金融とブロックチェーンの未来を拓く

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、2025年11月中旬を目途に、自社名義として国内銀行で初となる可能性のあるセキュリティ・トークン債(ST債)を発行する準備に入ったと報じられています。
発行額は100億円規模とされ、MUFGグループとして自社社債へのブロックチェーン活用は初の試みとなります。

本債券は劣後債(Tier2資本性証券)に該当※し、国際的な銀行規制(バーゼルIII)上自己資本に算入される予定で、引受業務は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が担当し、個人投資家を含む国内投資家へ販売される見通しです。
※ その性質上、損失発生時には他の債務に劣後し、規制上の「実質破綻時免除特約」(元本の一部または全部が減免される損失吸収条項)が適用される可能性があります。
(※本記事は発行条件確定前の情報に基づいており、正式条件が公表され次第、内容を更新いたします。)
本記事は情報提供のみを目的としており、特定の金融商品の勧誘や推奨ではありません。投資に際しては必ず最新の公式開示資料(目論見書や有価証券届出書等)を確認し、ご自身の判断・責任で行ってください。劣後債は発行体に損失が生じた場合に元本や利息が削減されるリスク(損失吸収条項)がある点にご留意ください。
技術革新:銀行によるブロックチェーン活用の新展開
なぜ、MUFGのデジタル債発行がエポックメイキングなのか?
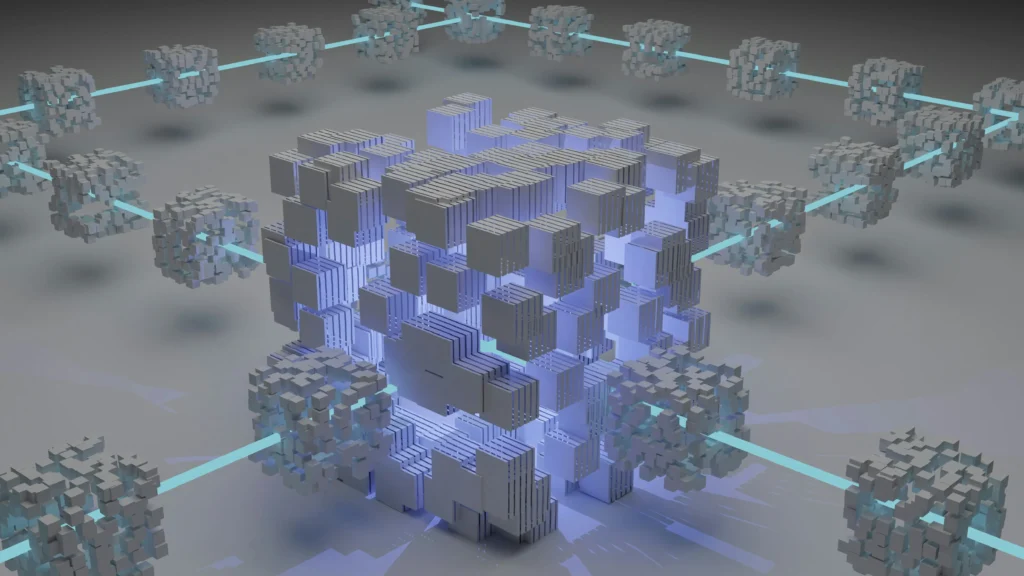
今回のMUFGによるデジタル債発行が「画期的」であると評されるのは、これまで“紙と印鑑”を中心にしてきた日本の金融の仕組みを根本からアップデートする一歩となるからです。
通常、社債を発行するには証券会社・信託銀行・決済機関など多くの関係者が関与し、それぞれが分散してデータを管理してきました。
しかし、MUFGが導入を予定している「Progmat」を使えば、発行から売買・利息支払いまでの流れをブロックチェーン上で一元管理できます。
 ねくこ
ねくこつまり、これまで紙の台帳やシステム間の照合に頼っていた手続きを、デジタル上で完結できるようにすることで、「郵送とハンコで行っていた取引を、スマホひとつで完結できるようにする」ような変化です。
債券のデジタル化による新たな資本調達手法の可能性
国内銀行が自らの社債をブロックチェーン上で発行するケースは極めて珍しく、MUFGの試みは金融機関による本格的なブロックチェーン活用の先駆けといえます。
これまで証券トークンによる資金調達は一部の証券会社やベンチャー企業で散発的に行われてきましたが、メガバンクが主体となる例はありませんでした。
 ねくこ
ねくこ今回の発行計画は技術革新の観点から大きな意義を持ち、債券のデジタル化によって金融商品の形態が多様化し、ブロックチェーンの透明性・セキュリティを備えた新たな資本調達手法が現実味を帯びてきたと言えるでしょう。
「金融×ブロックチェーン」の実装力|自社ノウハウを活かしたデジタル債発行の意義
MUFGは自社内にブロックチェーン・デジタル資産の専門チームを有し、国内外で関連技術の実証実験や関連企業への出資を積極的に行ってきました。
今回のデジタル債発行に先立ち、三菱UFJ信託銀行はProgmatを通じて不動産や社債のデジタル証券化基盤を他社に提供しており、そのノウハウを自社案件に投入する形となります。
大手金融グループ自らがブロックチェーンを用いた証券発行に踏み切る姿勢は、国内金融界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の象徴的な出来事と言えそうです。
利害関係の開示
本件発行ではMUFGグループ内の複数の関係会社が関与しています。発行体はMUFG本体、引受は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、技術基盤提供はMUFG信託銀行(Progmat関連)という構図であり、いわばグループ内取引の側面があります。一般にこのようなグループ内での証券発行に際しては、利益相反管理(情報遮断の徹底等)の枠組みを適切に適用し、公正な取引運営に努めることが求められます。
債券市場のモダナイズ:トークン化がもたらす効率化
債券をデジタル証券(セキュリティ・トークン)として発行することは、市場のモダナイズ(近代化)につながります。
先述の通り、ブロックチェーン上で権利の移転や記録を行うことで、発行から流通、決済に至るプロセスを一元化・自動化でき、従来の紙媒体や分断されたシステム間の煩雑な手続きを簡素化できます。
MUFG×NTTデータによる債券の小口化により、中小企業も資本市場アクセスが可能に
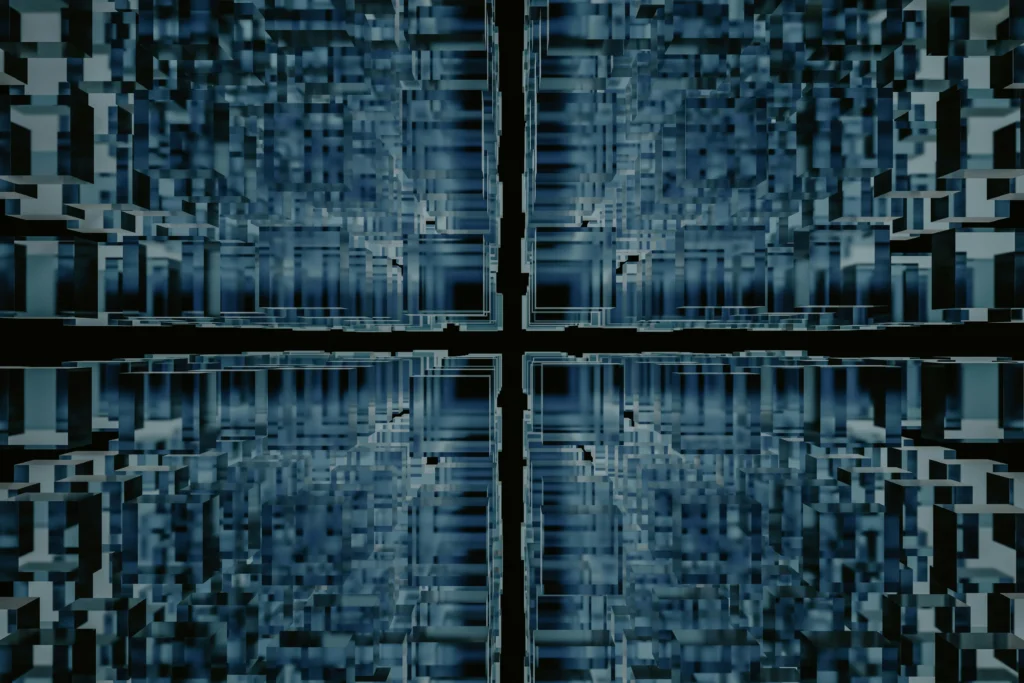
実際、MUFGはNTTデータとの共同検討の中で、ブロックチェーン活用によって債券の発行・管理コストを削減し、少額発行や小口化(投資単位の細分化)を実現できる可能性を指摘しています。
コストが下がれば従来は難しかった小規模の起債が現実的となり、より多様な企業や団体が資本市場から資金調達できるようになるでしょう。
 ねくこ
ねくこまた投資家にとっても、手頃な金額から債券を購入できるようになり、市場参加者の裾野拡大につながります。
ただし、こうした小口化のメリットを現実に生かすためには、投資家保護の徹底や十分な流動性の確保、KYC/AML(本人確認・マネロン対策)の遵守や適切な手数料体系の構築など、運用上クリアすべき前提条件が多く存在します。
これらの条件を満たして初めて、デジタル債による少額資金調達の可能性が本格的に拓けると言えるでしょう。
ブロックチェーンで債券管理を効率化|トークン化がもたらす透明性と安心感
トークン化された債券は、投資家への情報開示や権利管理の面でもメリットがあります。
ブロックチェーン上で保有者や取引履歴を追跡可能にすることで、発行体は誰が債券を保有しているかをリアルタイムで把握でき、不正な取引や二重譲渡を防ぐことができます。
またスマートコントラクトを活用すればクーポン(利息)支払いなども自動化されるため、事務処理負担が軽減されるでしょう。
 ねくこ
ねくここうした債券市場のデジタル化は、資本市場の機能拡充やユーザー体験の向上にも寄与すると期待されています。
実際、日本国内の証券トークン発行額は累計で約2,628億円(うち不動産関連が2,333億円)に達しています(2025年8月末時点)。
従来は不動産分野が大半を占めてきましたが、今後は社債分野でもデジタル発行が拡大すると見られます。
2030年には約2.5兆円規模に拡大するとの予測もあります。
規制・制度面での対応と今後の課題

デジタル債の発行にあたっては、既存の証券規制や決済制度との整合性を図ることが不可欠です。
現状、日本ではセキュリティ・トークンの発行・流通に関する法整備が進みつつあり、金融商品取引法上の「電子記録移転権利」(電子記録移転有価証券表示権利等)として位置付けられています。
MUFGも今回の発行に際し、関東財務局に必要書類を提出するなど、従来の社債発行と同様の手続きを踏んでいます。
もっとも、ブロックチェーン上での取引を念頭に置いた新たなルール整備や、デジタル証券を扱う市場インフラ(取引所・清算機関など)の構築はまだ発展途上であり、今後さらなる制度整備・標準化が求められるでしょう。
今回の大手銀行による試みを契機に、監督当局や業界団体での議論が活発化し、デジタル証券市場におけるルールメイキングが加速する可能性があります。
想定される発行条件(暫定)
| 発行体 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
|---|---|
| 通貨 | 日本円(JPY) |
| 発行額 | 約100億円(最終条件確定後に更新) |
| 償還期限 | 未定(発行登録書にて公表予定) |
| 利率(クーポン) | 未定(仮条件提示予定) |
| 利払日 | 年2回(予定) |
| 格付 | 未定(取得申請予定) |
| 任意償還条項 | あり(例:発行後5年以降に繰上償還可能予定) |
| 損失吸収条項 | あり(実質破綻時の元本減免特約付き) |
| 募集形態 | 公募(国内個人・機関投資家向け) |
| 投資家要件 | 特段の制限なし(一般投資家が購入可能) |
| 流通市場 | 店頭市場(証券会社のデジタル債取引プラットフォーム等) |
| 権利記録管理 | ブロックチェーン(Progmat基盤)上でMUFG信託銀行等が担当 |
| 決済方法 | 日本円(預金振替による決済) |
| 法的最終性 | 金融商品取引法上の有価証券(電子記録移転権利)として扱われる |
| 障害時対応 | バックアップ台帳への切替等で権利保全(予定) |
※正式条件は有価証券届出書や目論見書の公表後に更新予定。
大手銀行参入による信用力・信頼性の向上
発行主体が国内最大級のメガバンクであることは、デジタル債に対する信用力・信頼性の向上につながります。
ブロックチェーンや暗号資産に対して懐疑的な投資家層にとっても、MUFGという伝統ある金融機関が発行する債券であれば信頼感が格段に高まるでしょう。
 ねくこ
ねくこ実際、MUFGは社債発行において個人・機関投資家双方から強い需要を獲得してきた実績があり、そのブランド力や財務基盤はデジタル債においても安心材料となります。
さらに、投資家保護の観点でも、本債券が金融庁など関係当局の監督下で発行・運用される点は、デジタル債への信頼につながる重要な要素です。
主要リスク一覧(本ST債に関連する主なリスク要因)
- 信用・劣後リスク:発行体(MUFG)の信用悪化や破綻時に、劣後特約により本債券の元本・利息が削減または支払い停止となる可能性があります(他の優先債務より劣後します)。
- 金利変動リスク:市場金利の変動によって本債券の価格が上下します。特に金利上昇局面では債券価格が下落し、投資元本割れが生じる恐れがあります。
- 流動性リスク:ST社債の二次流通市場は未成熟であり、売却を希望する時に買い手が見つからない、あるいは市場価格が大きく変動する可能性があります。
- 早期償還・再投資リスク:本債券には任意償還条項(コールオプション)が付与される予定です。発行体が繰上償還を行った場合、想定より早期に償還金を受け取る一方、その時点で同程度の利回りの再投資先を確保できないリスクがあります。
- 規制変更リスク:将来的な規制変更(自己資本規制の強化やデジタル証券関連法制の改正等)によって、本債券の位置付けや市場環境に影響が及ぶ可能性があります。
- 技術リスク:ブロックチェーンやスマートコントラクトの不具合、電子ウォレットの鍵紛失・盗難、ノード障害など技術面の問題により、権利移転や利払いに支障が生じるリスクがあります。
- オペレーションリスク:新たなデジタルプラットフォームと既存の証券決済・管理システムとの接続部分で、事務処理上の不備やエラーが起こるリスクがあります。清算・決済・名義書換等のプロセスに障害が発生した場合の対応も課題です。
- サイバーセキュリティリスク:悪意あるハッキングや不正アクセスによって、ネットワークの混乱や権利記録の改ざん・不正送金が発生するリスクがあります。
- 法的最終性リスク:ブロックチェーン上の権利記録の法的な最終確定性が完全には確立されていない側面があります。万一紛争が生じた際に、どの記録が公式な権利証明と認められるか不明確な場合、法的リスクとなり得ます。
他金融機関への波及効果はどうなる?
MUFGのデジタル債発行が成功裏に完了すれば、他の銀行や金融機関にも同様の取り組みが広がる可能性があります。
大手銀行が自ら実績を示すことで、市場全体における証券トークン活用のハードルが下がり、追随する動きが出てくるでしょう。
例えば、他のメガバンクや地方銀行、さらには事業会社による社債のデジタル発行など、新たな事例が次々と登場すると予想されます。
MUFG自身も将来、提携先であるモルガン・スタンレーの海外ネットワークを通じて日本発のデジタル債を海外投資家に販売する構想を示しており、デジタル債市場が国内に留まらずグローバルにも拡大する可能性があります。
競合各社がデジタル技術を活用した資金調達の知見を共有・蓄積していくことで、市場全体の効率性が高まり、投資家にとっても選択肢が増える好循環が生まれると考えられます。
終わりに|日本のデジタル債市場が切り拓く未来
今回のMUFGによる国内メガバンク初のデジタル債発行計画は、日本のフィンテックと資本市場における歴史的な転換点となり得ます。
ブロックチェーン技術を活用した社債発行が実現することで、金融取引のデジタル化は新たな段階へと移行しつつあります。
 ねくこ
ねくこ技術革新、市場の効率化、規制対応、信用力の担保といった課題への解決策が示され始めた今、デジタル債は単なる一時的な流行ではなく、金融市場の重要な一部へと進化していくでしょう。
MUFGのこの挑戦が成功裡に完了すれば、日本の資本市場に新たな地平が拓かれることになりそうです。
参考資料
- 堀内亮「MUFGがデジタル証券に参入、1号案件は自社劣後社債-市場拡大へ」『Bloomberg』(2025年10月9日)
- 栃山直樹「三菱UFJ、デジタルアセット事業を開始──個人向けセキュリティ・トークン取引「ASTOMO」リリース」『CoinDesk Japan』(2025年10月10日)
- 臼田勤哉「三菱UFJとNTTデータ、デジタル社債の標準化インフラで提携」『Impress Watch』(2023年9月12日)
- 「セキュリティトークン(ST)社債形式での国内公募無担保劣後社債の発行について」三菱UFJ信託銀行株式会社 プレスリリース (2025年10月9日)












