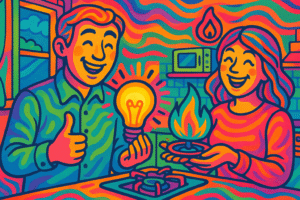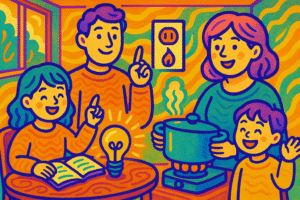生命保険は「都道府県民共済」がコスパ良いって本当?民間の生命保険との違いやについて解説

皆さんは「保険」と聞くと、どんなイメージがありますか?
お子さま向けのコープ共済や、自動車事故に備えるJA共済などを思い浮かべる方も多いかもしれませんね。
実は最近、こうした「共済」を、一般的な生命保険や医療保険の代わりに選ぶ人が増えています。
特に「県民共済」は、「少ない掛け金で幅広い保障」を掲げ、手軽さと安心感から全国的に人気が高まっています。
 ねくこ
ねくここの記事を読んでいるあなたは、もしかしたらこんな疑問をお持ちではないでしょうか?
そんな疑問にお答えするため、本記事では「県民共済」に焦点を当て、民間の生命保険との違い、メリット・デメリット、そしてどんな方に県民共済が向いているのかを分かりやすく解説します。
 ねくこ
ねくこあなたの保険選びのヒントがきっと見つかるはずです!
それでは行きましょう!
「都道府県民共済」とは? なぜ人気? その仕組みと特徴を解説

都道府県民共済(以下、県民共済)は、特定の地域に住んでいる、または勤務している人たちが加入できる非営利の保障事業です。
1973年に誕生し、今では全国47都道府県で展開されています。
「都道府県民共済」が人気の理由:驚異的な加入件数の伸び
県民共済の大きな特徴は、「小さな掛金で大きな保障」を使命としている点です。
その理念が支持され、加入件数は年々増加。
2023年3月末時点で、全国で約2,190万件もの加入実績があります。(例:都民共済だけで約215万件)
参考:全国生活協同組合連合会 加入件数(2023年度末)
- こども型:約240万人
- 総合・入院保障型:約1,082万人
- 熟年・熟年入院型:約520万人
- (その他、火災共済など含む合計):約2,190万人
なぜ、都道府県民共済は「コスパが良い」と言われるの?
県民共済は営利を目的としないため、事業運営で余ったお金(剰余金)は「割戻金」として加入者に還元されることがあります。
これが「掛け金が実質的に安くなる」と言われる理由の一つです。
 ねくこ
ねくこまた、加入者が増えるほど運営が安定し、手頃な掛け金を維持しやすい仕組みになっています。
【年代別】県民共済の主なコースと保障内容(例:都民共済)
県民共済の具体的な保障内容は、年齢によって大きく3つのコースに分かれています。
ここでは都民共済を例に、代表的なコースを見てみましょう。(※お住まいの地域の県民共済で詳細はご確認ください)
【加入年齢:0歳~17歳】こども型
- 特徴: 病気やケガの保障に加え、第三者への損害賠償責任保障や、契約者(親など)の死亡保障も含まれる、子ども特有のリスクに対応したプラン。
- 掛け金例: 月額1,000円または2,000円
- 保障内容例(月額2,000円コース):
病気入院:日額10,000円
事故(ケガ)通院:日額4,000円
第三者への損害賠償:最高200万円 - 注意点: 18歳になると自動的に次の年齢区分のコース(総合保障型など)へ移行します。自治体の「子ども医療費助成制度」も考慮してプランを選びましょう。
【加入年齢:満18歳~満64歳】総合保障型・入院保障型
- 特徴: 働き盛り世代向けの保障。医療保障と死亡保障がセットになった「総合保障型」と、入院保障に重点を置いた「入院保障型」があります。両方を組み合わせることも可能です。
- 掛け金例: 月額1,000円~4,000円
- 保障内容例(総合保障4型:月額4,000円):
病気入院:日額10,000円
病気死亡:800万円 - ポイント: 入院保障の日数が比較的長い(例:病気入院124日まで)のが特徴。
【加入年齢:満65歳~満69歳】熟年型・熟年入院型
- 特徴: シニア世代向けの保障。「熟年型」は医療・死亡保障のセット、「熟年入院型」は入院保障が中心。
- 掛け金例: 月額2,000円または4,000円
- 保障内容例(熟年4型:月額4,000円):
病気入院:日額5,000円
病気死亡:200万円 - 注意点: 総合保障型にあった「通院保障」がなくなります。また、年齢が上がるにつれて保障額が段階的に減少します(例:70歳~、80歳~)。新規加入は69歳までです。
【徹底比較】県民共済 vs 民間生命保険 どこが違う? 5つのポイント
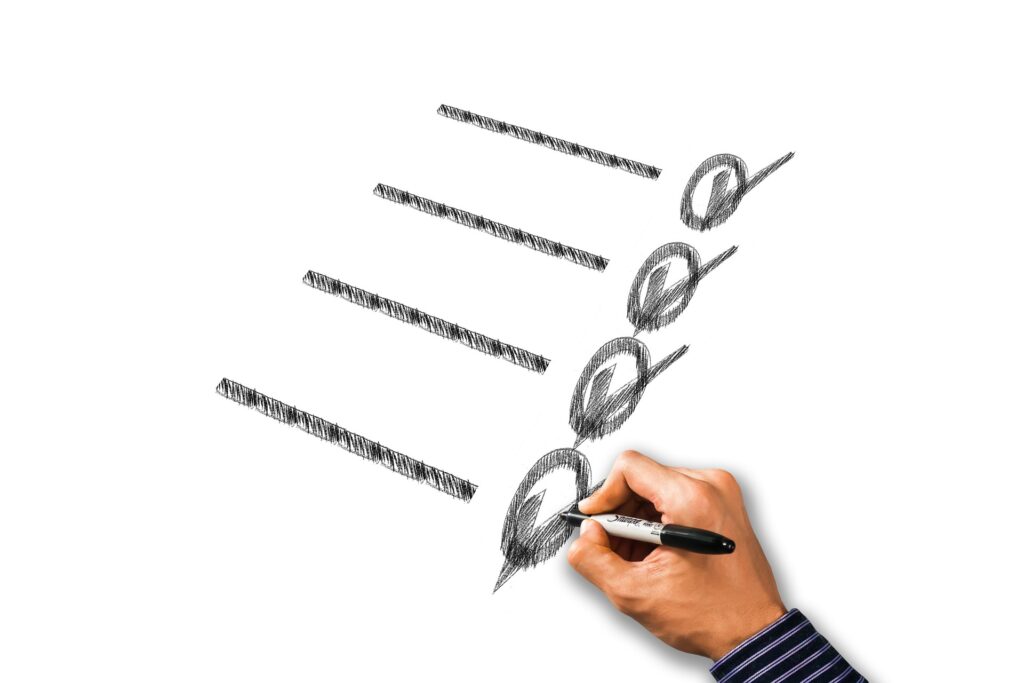
県民共済と民間の生命保険、どちらも「もしも」の時に備えるための大切な仕組みですが、その成り立ちや特徴には大きな違いがあります。
 ねくこ
ねくこ「何となく違うのは知っているけど、具体的には?」と感じている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、両者の主な違いを5つの重要なポイントに絞って、より詳しく比較・解説していきます。
運営目的:「非営利」の共済、「営利」の民間保険
まずは、「非営利」か「営利」かという点が異なります。
組織が何を目指して運営されているか、という根本的な違いが、掛け金(保険料)の設定やサービス内容、さらには加入者への還元方法にまで影響を与えています。
県民共済(非営利団体)
県民共済の最大の特徴は、「非営利」であることです。
 ねくこ
ねくここれは、特定の地域に住む人や働く人たちが、お互いに助け合う「相互扶助」の精神に基づいて運営される協同組合だからです。
県民共済の特徴
- 非営利組織:利益を最大化することを目的としない
- 相互扶助の仕組み:地域の加入者同士が支え合う
- 剰余金(決算上の余り)は「割戻金」として還元
- シンプルで分かりやすい保障内容
- 組合員全体の公平性を重視した商品設計
特に 「割戻金」 の仕組みがあることが大きなポイントです。
これは、決算の結果、事業運営に必要な経費を差し引いた後に剰余金が発生した場合、これを加入者に還元します。
そのため、支払った掛け金の一部が戻ってくる可能性があり、結果的に実質的な負担額が軽減されます。
 ねくこ
ねくここれが「県民共済はコスパが良い」と評価される理由の一つです。
商品開発においても、特定の個人のためというよりは、組合員全体の利益や公平性を重視し、シンプルで分かりやすい保障を提供することに主眼が置かれています。
民間生命保険(営利企業)
一方、私たちが普段目にする多くの生命保険会社は、株式会社などの形態をとる「営利企業」です。
営利企業であるがゆえに、多様化する顧客ニーズに応えるための激しい商品開発競争が行われ、多種多様な保険商品や特約が生まれています。
民間生命保険の特徴
- 営利企業として運営:利益を追求し、経営を維持・発展させる
- 商品開発競争が激しい:多様なニーズに応じた保険商品や特約を提供
- 利益の活用先:株主への配当、事業拡大のための投資、企業の安定運営のための内部留保
企業として、契約者の保護は最も重要な責務ですが、同時に持続的な成長と利益の確保も経営目標となります。
そのため、保険料には以下のような費用が含まれています。
- 保障の対価(保険金支払いのための費用)
- 広告宣伝費や人件費などの事業運営コスト
- 将来のリスクに備えるための準備金
- 企業としての利益
加入条件:地域や組合員資格の有無
また、居住地域による制限の有無も異なります。
具体的には、都道府県民共済の場合、どこに住んでいても加入できるわけではないという点も両者の大きな違いです。
これは、それぞれの組織の成り立ちと深く関わっています。
県民共済(制限あり)
県民共済は、その名の通り、原則としてその都道府県内に「居住している」か「勤務地がある」人でなければ加入できません。
これは、地域に根ざした組合員同士の相互扶助という理念に基づいているためです。
- 加入条件:その都道府県内に「居住している」か「勤務地がある」人
- 契約形態:共済組合の「組合員」として契約
- 出資金:初回のみ少額の出資金が必要(例:都民共済は200円)
- 引っ越し時の継続:引っ越し先の都道府県で新たに加入し直す必要あり(保障内容・掛金が変わる可能性あり)
 ねくこ
ねくここの出資金は、共済の運営基盤の一部となります。
民間生命保険(制限なし)
民間の生命保険は、日本国内に居住していれば、居住地に関係なく自由に選んで加入できます。
- 加入条件:日本国内に居住していれば、居住地に関係なく加入可能
- 契約形態:保険会社と個人の間で直接契約
- 出資金:出資金不要
- 引っ越し時の継続:全国どこへ引っ越しても手続きをすれば契約を継続可能
 ねくこ
ねくここのように、民間生命保険は加入の自由度が高いのが特徴です。
商品設計:シンプル・セット型 vs オーダーメイド・多様な選択肢
そして、商品設計、つまりどんな保障や特約にするかの自由度も異なります。
提供されている保険商品の種類や、保障内容の組み立て方にも、それぞれの特徴が色濃く反映されています。
県民共済(シンプル・セット型)
- 保障の設計:コースごとに決められた保障内容がセットになっている
- 加入コース:「こども型」「総合保障型」「熟年型」など、年齢層別にコースが分かれている
- 掛け金の設定:1,000円、2,000円、4,000円など、限られたパターンのみ
- 選びやすさ:シンプルで分かりやすく、比較的容易に選べる
- カスタマイズ性:保障内容を自由に変更することは不可
県民共済は「シンプルで分かりやすい」反面、
といった個別のニーズに合わせた細かなカスタマイズや、特定の保障だけを選んで加入することは基本的にできません。
民間生命保険(オーダーメイド・多様な選択肢)
民間生命保険の最大の魅力は、保障内容を自由に設計できる「オーダーメイド性」にあります。
- 保障の設計:主契約+特約を自由に組み合わせて設計可能
- 加入コース:年齢やライフプランに応じて、自由に保障内容を選択可能
- 掛け金の設定:保険会社やプランにより自由に設定できる
- 選びやすさ:選択肢が多く、自分に合ったプランを選ぶには知識や専門家の相談が必要
- カスタマイズ性:保障額、保障期間、特約などを細かくカスタマイズ可能
死亡保障や医療保障といった基本的な主契約に、がん、三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)、就業不能、介護、先進医療、女性疾病など、非常に多岐にわたる特約(オプション)を自由に組み合わせることができます。
 ねくこ
ねくこただし、選択肢が多い分、商品選びが複雑になりやすく、自分にとって本当に必要な保障を見極める知識や、専門家への相談が必要になる場合もあります。
保障期間:最長85歳まで vs 一生涯保障も可能

万が一の際に保障を受けられる期間がいつまで続くのか、という点は、老後の安心を考える上で非常に重要なポイントです。
県民共済(最長85歳まで)
県民共済の保障期間は、コースによって多少の違いはありますが、基本的に最長で85歳までとなっています。
つまり、85歳を迎えると保障が終了(満期)となり、それ以降に亡くなったり、病気やケガで入院・手術をしたりしても、共済金は支払われません。
平均寿命が延び、「人生100年時代」とも言われる現代において、85歳以降の公的医療保険以外の保障がなくなる点は、老後の医療費や葬儀費用などを考える上で留意すべき点です。
これは、幅広い年齢層の組合員に対して、できるだけ公平に、かつ手頃な掛け金で保障を提供するための制度設計上の制約と考えられます。
民間生命保険(一生涯保障も可能)
民間生命保険には、
といった商品が数多くラインナップされています。
これらの終身タイプを選べば、契約が有効である限り、何歳で亡くなっても死亡保険金が支払われたり、何歳になっても病気やケガによる入院・手術の保障が続いたりします(保障内容や支払限度日数は契約による)。
 ねくこ
ねくこもちろん、一定期間だけ保障を手厚くしたい場合に適した「定期保険」タイプもありますが、一生涯の安心を確保できる選択肢があることは、民間保険の大きなメリットと言えます。
加入審査:告知の基準と手続きの違い
保険に加入する際には、現在の健康状態や過去の病歴などを保険を提供する側に伝える「告知」という手続きが必要です。
 ねくこ
ねくここの告知の内容や、それに基づく加入可否の判断基準(審査)にも違いがあります。
県民共済(比較的緩やか)
県民共済の大きな特徴は、告知項目が少なく、加入しやすい点にあります。
加入時の健康告知は、定型的な質問に「はい」または「いいえ」で回答する簡易な形式です(例:「過去5年以内に入院や手術をしたことがありますか?」など)。
- 健康告知:定型質問に答える形式で、医師の診査や診断書は原則不要
- 告知項目:民間保険と比べて比較的少ない
- 審査基準:保障内容の選択肢は限定的だが、健康状態による制約が比較的少なく、加入しやすさに重点を置いた設計
- 加入条件:持病や通院歴があっても、条件を満たせば加入可能
これは、相互扶助を目的とした非営利組織である県民共済の方針が反映されたもので、より多くの組合員を受け入れる姿勢に基づいています。
 ねくこ
ねくこそのため、保険の選びやすさと加入のハードルの低さを重視する方に適しています。
民間生命保険(詳細な告知・診査)
民間生命保険では、加入時に詳細な告知と必要に応じた診査を通じて、個々のリスクを精密に評価します。
これにより、保険制度の公平性と健全性を保つことが目的とされています。
- 健康告知:現在の健康状態や既往歴など、多項目の申告が必要
- 医師による診査や診断書の提出:告知内容により追加の審査が実施されることも
- 引受条件:病歴によっては加入制限や割増保険料が適用される場合もある
加入時には、現在の健康状態、過去の病歴(病名、治療期間、経過など)、服薬の有無、職業、身長・体重、喫煙習慣など、詳細な情報を告知する必要があります。
この告知内容に基づいて、保険会社はリスクを評価し、加入の可否や保険料、保障内容を決定します。
また、健康状態に応じて、「加入不可」「特定の病気や部位が保障対象外(部位不担保)」「割増保険料が適用される」といった条件が付されることがあります。
 ねくこ
ねくここれらは保険会社のリスク評価基準に基づくものであり、事前に明示されます。
近年では、持病がある方向けの「引受基準緩和型」や、健康状態に関する告知を必要としない「無選択型(無告知型)」といった保険商品も登場しています。
これにより、従来の保険に加入が難しかった方々にも、一定の保障を提供する選択肢が広がっています。
県民共済の良い点や悪い点を解説!あなたには合っている?

県民共済を選ぶメリット:コスパだけじゃない!3つの魅力
県民共済が選ばれる理由は、掛け金の安さだけではありません。主なメリットを見ていきましょう。
掛け金が割安で家計に優しい
最大の魅力は、やはり月々の掛け金が手頃なこと。
同じコース内であれば、年齢や性別によって掛け金が変わることはありません。
 ねくこ
ねくこ更新時に保険料が上がる心配がないのは嬉しいポイントです。
さらに、決算で剰余金が出れば「割戻金」としてお金が戻ってくる可能性があり、実質的な負担がさらに軽くなることも。
支払った掛け金は、民間の保険と同様に「生命保険料控除」の対象となり、税金の負担を軽減できます。

医療と死亡の保障バランスが良く、シンプルで分かりやすい
県民共済の多くのコースは、病気やケガによる入院・手術などの「医療保障」と、万が一の際の「死亡保障」がセットになっています。
一つの契約で基本的なリスクにまとめて備えられるため、手軽で分かりやすい点が特徴です。
また、年齢層に応じたコースが用意されており、保障内容があらかじめ決まっているため、保険選びに迷いにくい仕組みになっています。
 ねくこ
ねくこ「保険は複雑でよくわからない…」と感じる方でも選びやすい点が魅力です。
持病や入院歴があっても加入しやすい
加入時の告知が比較的簡単なため、健康状態に少し不安がある方や、過去に入院・手術歴がある方でも加入できる可能性があります。
 ねくこ
ねくこ民間の保険加入を諦めていた方も、一度検討してみる価値があります。
県民共済のデメリット:加入前に知っておきたい3つの注意点
手軽で魅力的な県民共済ですが、注意すべき点もあります。
 ねくこ
ねくこデメリットもしっかり理解しておきましょう。
保障内容を自由に設計できない
コースや保障内容があらかじめ決まっているため、
といった、個別のニーズに合わせた細かなカスタマイズは困難です。
死亡保障は手厚くない
掛け金が安い分、万が一の際の死亡保障額は民間の生命保険に比べて低めです。
遺された家族の生活費や子どもの教育費などを十分にカバーするには不足する可能性があります。
 ねくこ
ねくこ万が一のときに家族の生活を守るには、保障額が十分かどうか慎重に見極めることが大切です。
県民共済の保障は高齢になると減少し、最長85歳まで
県民共済の保障は一生涯続くものではなく、最長でも85歳で終了します。
平均寿命が延びる中、「人生100年時代」の備えとしては、終身保障がない点に注意が必要です。
また、多くのコースでは60歳や65歳を境に、入院給付金や死亡保障額が段階的に減少します。
 ねくこ
ねくこ病気やケガのリスクが高まる年代で保障が手薄になる可能性があるため、加入前にしっかりと確認しておくことが重要です。
結局どっち? 県民共済と民間生命保険、あなたに合うのは?
それぞれにメリット・デメリットがある県民共済と民間生命保険。
 ねくこ
ねくこどちらを選ぶべきかは、あなたの状況や考え方によって異なります。
【県民共済がおすすめな人】
- とにかく毎月の保険料を安く抑えたい
- 複雑なプランは苦手、シンプルで分かりやすいものが良い
- 最低限の医療保障と死亡保障があれば十分
- 持病や入院歴があり、民間の保険加入が難しいと感じている
- 保険の手続きを簡単に済ませたい
【民間生命保険がおすすめな人】
- 万が一の際に、家族のために手厚い死亡保障を備えたい
- がん、三大疾病、介護など、特定の保障を充実させたい
- 一生涯続く保障(終身保障)が欲しい
- 自分のライフプランに合わせて、保障内容を細かく設計したい
- 保険のプロに相談しながら、最適なプランを選びたい
民間保険と県民共済は、保障を提供するという意味で競合関係にはありますが、それぞれの提供価値が異なるため補完的な関係になることもあります。
 ねくこ
ねくこたとえば、基本的な保障を県民共済で確保しつつ、足りない部分を民間保険で補う。
逆に、民間保険をメインにして県民共済をサブ的に活用するといった併用する方法も一つです。
【Q&A】都道府県民共済の疑問に答える

そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
県民共済って、本当にコスパが良いの?
はい。
非営利運営により保険料が安く、剰余金は割戻金として加入者に還元されるため、実質の負担が軽くなります。
民間の生命保険と県民共済の違いは?
県民共済は「非営利・地域限定・シンプル保障・最長85歳」
民間保険は「営利・全国対象・カスタマイズ可能・終身保障あり」
という違いがあります。
保障内容は県民共済の方が少ないの?
はい。
県民共済は選択肢が限られており、保障の自由度が低い一方、民間保険はオーダーメイド設計が可能です。
県民共済の保障は一生涯続く?
いいえ、保障は基本的に85歳までで終了します。
老後も保障が必要な人は終身保険の検討が必要です。
加入しやすさはどう違う?
県民共済は告知が緩やかで加入しやすいです。
民間保険は健康状態による審査があり、加入制限がかかる場合があります。
引越ししたら県民共済はどうなる?
引越し先の都道府県民共済に切り替える手続きが必要です。
同じ保障内容にならない可能性もあります。
県民共済は持病があっても入れるの?
はい、告知項目が少なく比較的加入しやすいため、持病や入院歴があっても条件次第で加入可能です。
県民共済と民間保険は併用できる?
はい、併用可能です。
県民共済で基本的な保障を確保し、不足分を民間保険で補う方法も有効です。
加入できるのは誰?条件はある?
居住地または勤務先が該当の都道府県にある人が対象で、初回に少額の出資金が必要です。
県民共済の共済金は課税される?
「入院・通院共済金」や「後遺障害共済金」などは非課税となります。
死亡共済金については掛金の負担者と共済金の受取人の関係により課税対象となります。
夫婦の場合を例に見てみます。
| 実際の掛金負担者 | 被共済者 | 共済金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻(相続人) | 相続税 |
| 妻以外(相続人以外) | |||
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税・住民税 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
海外転勤の場合はどうなる?
一時的な引っ越しの場合、契約を継続できる可能性があります。加入している県民共済に確認が必要です。
ただし永住する場合は保障対象外になります。
居住地と勤務地が異なる場合は2つの県民共済に加入できますか?
加入することはできません。
共済は一人ひとつの都道府県民共済への加入が認められており、都道府県をまたいでの加入はできません。
まとめ:「都道府県民共済」はコスパだけで決めない!「自分に必要な保障」を見つける第一歩

都道府県民共済は、割安な掛け金で医療と死亡の基本的な保障をバランス良く備えられる、非常にコストパフォーマンスに優れた選択肢です。
保険選びで最も大切なのは、「安さ」だけではありません。
「今の自分や家族にとって、本当に必要な保障は何か?」
を考えることです。
万が一の病気やケガ、あるいは死亡といった事態に直面したとき、経済的な不安なく治療に専念したり、遺された家族が安心して生活を続けられたりするために、保険は大きな支えとなります。
 ねくこ
ねくこ県民共済と民間生命保険、それぞれの特徴をよく理解し、ご自身のニーズやライフプランに照らし合わせて、最適な保険を選びましょう。
この記事が、あなたの保険選びの一助となれば幸いです。