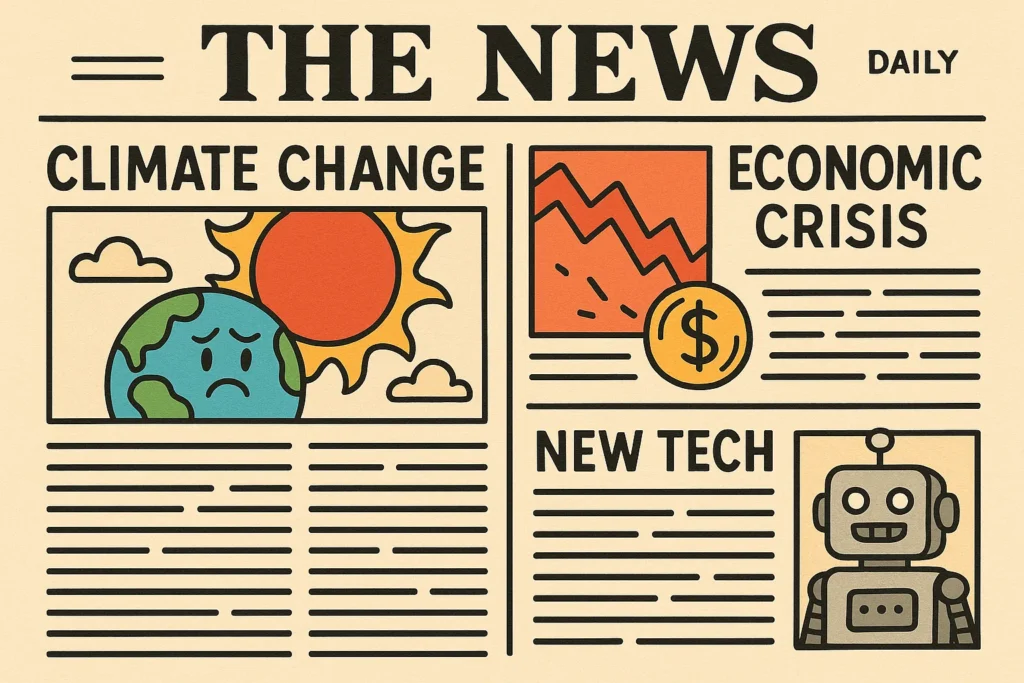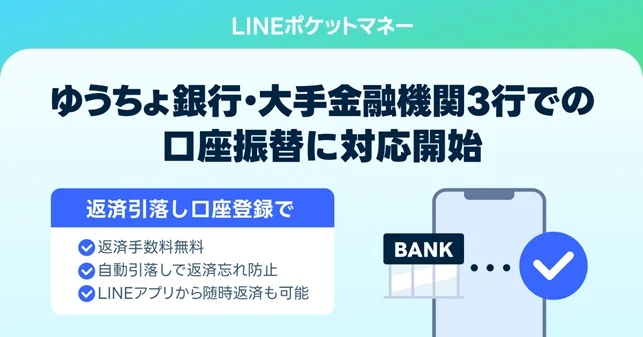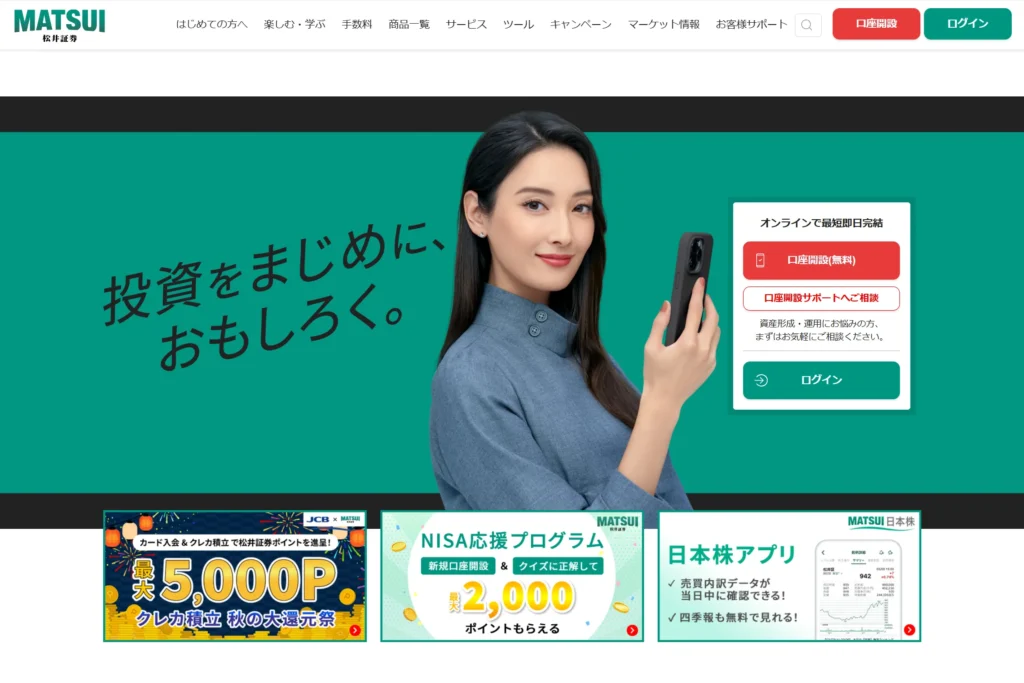次の確定申告時には見逃したくない「医療費控除」とは?制度の基本を簡単におさらい

医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税が軽減される制度です。
支払った医療費の合計−保険金などで補填される金額−『10万円』
または
『その年の合計所得金額等の5%』のいずれか少ない方
で計算し、上限は「200万円」です。
合計所得金額等が200万円未満の人は、基準額が『10万円』ではなく『所得の5%』になります。

30代主婦が税金2万円を取り戻した具体例
30代主婦が税金2万円を取り戻した具体例を順を追ってみていきましょう。
例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
※本文の数値例はわかりやすさのための概算です。実際の税率(5%~45%)・所得控除の有無・ふるさと納税等により結果は変動します。
- 出産に伴う入院費用:53万円
- 子どもの病院通院・薬代:5万円
- 夫の歯科治療費:5万円
- 年間の医療費合計:63万円
この63万円のうち、健康保険から出産一時金として支給された50万円を差し引くと、
63万円 − 50万円 = 13万円が自己負担額となります。
自己負担額13万円から、基準となる10万円を引き、控除対象額が決まります。
13万円 − 10万円 = 3万円(医療費控除額)
この3万円が医療費控除として所得から差し引かれるため、その分だけ税金が戻ります。

※差し引く保険等には出産育児一時金に限らず、高額療養費、民間の医療保険金、共済金など“医療費を補填する全ての給付”が含まれます。
医療費控除の申告で具体的にどれくらい税金が戻るのか?
※本文の数値例はわかりやすさのための概算です。実際の税率(5%~45%)・所得控除の有無・ふるさと納税等により結果は変動します。
所得税率が10%のケース(一般的な給与所得の範囲内)で計算すると、
- 所得税の軽減額:3万円 × 10% = 3,000円
- 住民税の軽減額:3万円 × 10% = 3,000円
ここまでで約6,000円の税金が戻ります。
しかし、実際の医療費控除申告では、出産一時金を超えて実際に支払った医療費がもっと大きい場合もあり、さらに家族分の医療費や交通費も含めることができるため、戻ってくる金額がさらに大きくなることがあります。
仮に出産費用以外にも家族で歯科治療や通院、薬代、さらに通院交通費などで合計20万円以上の医療費がかかっていた場合、
医療費20万円 − 基準額10万円 = 10万円(控除対象額)
10万円の医療費控除が認められたとすると、
- 所得税(10%):1万円
- 住民税(10%):1万円
合計約2万円の税金が戻る計算になります。
計算式は以下です。
- 所得税の軽減額=医療費控除額×各人の所得税率
- 住民税の軽減額=医療費控除額×原則10%(一部自治体で若干異なる)
住民税分は“翌年度の住民税が減る”のが基本で、所得税のように還付されない場合があります。
同一生計の配偶者・親族の医療費は合算可能です(所得金額にかかわらず“同一生計”が条件)。誰が申告してもよいが、最も税率の高い人が申告すると有利になりやすいでしょう。
医療費控除の対象となるもの・ならないもの
医療費控除を正しく申告するためには、「対象になるもの」「ならないもの」の区別を把握することが重要です。
医療費控除の対象になる主なもの
- 病院での診察・治療費(歯科治療も含む)
- 処方された薬代
- 入院時の部屋代(差額ベッド代などは対象外、入院基本料(部屋代含む)は対象。)
- 治療を目的としたマッサージや鍼灸の費用(医師の指示が必要)※1
- 通院にかかる交通費(公共交通機関の利用が原則)※2
- 出産に関わる費用(定期健診、分娩費用など)
※1 治療目的のあん摩マッサージ指圧・はり・きゅう等は対象。『医師の指示があるとより確実』だが、国家資格者による治療であることが前提。
※2 通院交通費は原則公共交通機関だが、深夜・急病・公共交通が使えない等のやむを得ない事情がある場合はタクシー代も対象。
医療費控除の対象にならない主なもの
- 健康維持のためのサプリメントや栄養ドリンク
- 美容整形などの美容目的の費用
- 通院時のマイカー利用のガソリン代、駐車場代(公共交通機関が使えない場合を除く)
- 自己都合による差額ベッド代など、治療とは関係ないサービス費用
これらを間違えると、後で税務署から指摘されることがありますので注意しましょう。
医療費控除を申告する具体的な手順
医療費控除の申告は、以下のような流れで簡単にできます。
① 医療費の明細をまとめる
病院や薬局から受け取った領収書やレシートを集め、「医療費控除の明細書」に医療機関名、治療費、交通費などを記入します。この明細書は、国税庁のウェブサイトから簡単にダウンロードできます。
② 確定申告書を作成する
「確定申告書」は国税庁の『確定申告書作成コーナー』というウェブサイトで簡単に作成できます。案内に沿って必要事項を入力し、作成完了後に印刷して提出します。
領収書は提出不要(5年間の保存義務あり)。医療費通知(医療費のお知らせ)があれば、明細書の一部記入を省略可能です。
③ 税務署に提出する
印刷した確定申告書と医療費控除の明細書を住所地の税務署に持参または郵送します。最近ではオンライン(e-Tax)を使って申告することも可能です。
提出が完了すると、通常は1~2ヶ月以内に指定口座に還付金が振り込まれます。
所得税の還付は1~2か月程度が目安となります。住民税分は翌年度の税額が減る形で反映されます(振込還付ではない)。
実際にいくら税金が戻るのか、簡単シミュレーション
※本文の数値例はわかりやすさのための概算です。実際の税率(5%~45%)・所得控除の有無・ふるさと納税等により結果は変動します。
実際にどれくらい税金が戻るか、簡単なシミュレーション例をもう一度挙げてみましょう。
例えば、年間の医療費総額が以下の場合:
- 家族の医療費合計:25万円
- 出産育児一時金や保険金などで補填された金額:0円(全額自己負担と仮定)
- 所得税率:10%の場合(一般的な給与所得者)
医療費控除額の計算は、
25万円(年間医療費)−10万円(基準額)=15万円(控除対象)
税金の還付額は、
- 所得税:15万円 × 10% = 1万5,000円
- 住民税:15万円 × 10% = 1万5,000円
合計で約3万円の税金が戻ることになります。
【Q&A】医療費控除の疑問に答える
そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
医療費控除とは?
1年間にかかった医療費が一定額を超えると、所得税や住民税が軽減される制度です。
一般的には年間10万円を超えた分が対象になります。

医療費控除でどのくらい税金が戻るの?
所得税・住民税率が各10%の場合、10万円の控除で約2万円が還付されます。
医療費が多いほど戻る額も増えます。
医療費控除の対象になるものは?
- 診察代
- 処方薬
- 入院費
- 公共交通での通院費
- 出産費用
などが対象です。
歯科や治療目的の鍼灸も含まれます。
医療費控除の対象外になるものは?
- 美容整形
- サプリメント
- ガソリン代や駐車場代
- 差額ベッド代
など、治療と無関係な費用は対象外です。
医療費控除を申請する方法は?
①領収書などから明細を作成
②確定申告書を国税庁サイトなどで作成
③税務署へ提出(郵送・e-Tax可)
の3ステップです。
同一年に医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できる?
同一年に『医療費控除』と『セルフメディケーション税制』は併用不可です。
どちらが有利かは『控除額(医療費控除額 or 特定OTC購入額のうち上限12万円)×各人の税率』で比較しましょう。
医療費控除は難しくない!積極的に利用しよう
医療費控除は「手続きが難しそう」と思われがちですが、実際には簡単な手続きで税金の還付を受けられます。特に出産や歯科治療、家族が病気で頻繁に病院へ通った年などは、還付される金額が大きくなる可能性があります。
「医療費控除の申告」はお金が戻るチャンス。ぜひ今年から医療費の領収書やレシートを保管し、医療費控除の申告をしてみてはいかがでしょうか。

本記事は一般的な制度解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。最新の法令・自治体運用や個別事情により取扱いが異なる場合があります。