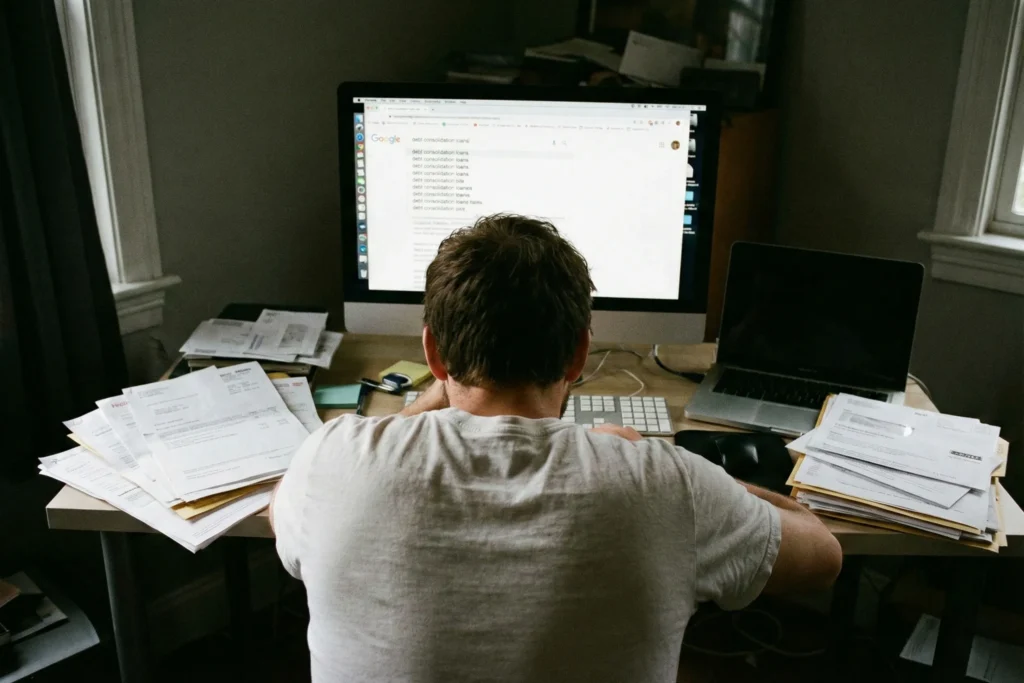【2025年深刻分析】東京の地価上昇は”異次元”へ?最新ランキング・要因・賃金格差まで徹底解説!

2025年春、最新の公示地価が発表され、そんな悲鳴にも似た声が聞こえてきそうです。
家賃は上がり続け、マイホームの価格は天文学的に上昇を続ける今。
私たちの給料は、この東京のコスト上昇に追いついているのでしょうか?
この記事では、国土交通省発表の「2025年公示地価」データを基に、単なるランキング紹介に留まらず、
- 2025年東京地価の「全体像」と加速する二極化
- 地価”急上昇”エリアTOP10、その「深い理由」とは?
- 最大の問題提起:賃金上昇は追いつくのか?私たちは住み続けられるのか?
という視点から、東京の不動産市場の”今”と”未来”を、可能な限り詳細に、そして皆さんの実感に寄り添いながら分析します。
 MIYABI
MIYABIこれは、あなたの生活設計に直結する、見過ごせないレポートです。

2025年・東京地価の全体像:加速する上昇と選別の時代
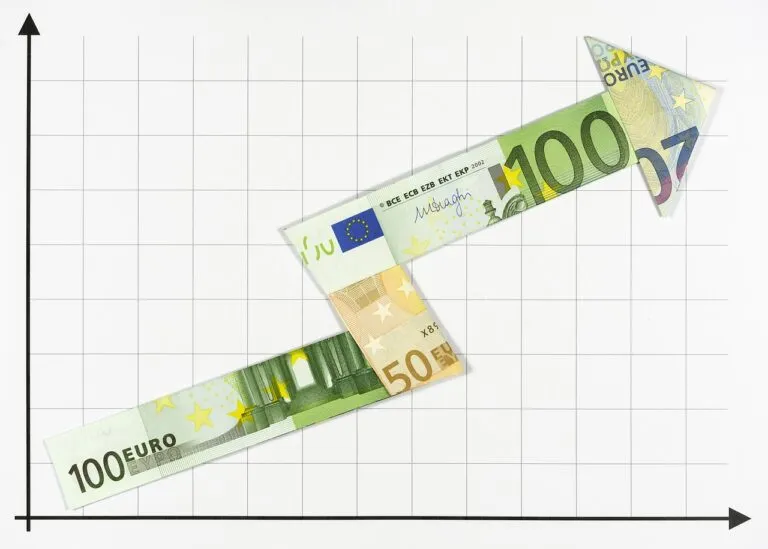
まず、今年発表されたデータの全体像を把握しましょう。
「2025年公示地価」データは、2025年1月1日時点の土地の価格を記載されたもので、前年(2024年1月1日)と比べてどのくらいの地価が上昇しているのかというデータなどが分かります。
【令和七年】東京都の地価上昇ペースはさらに加速している
「2025年公示地価」データによると、東京都全体の住宅地平均変動率は前年比+5.6%という結果になりました。
前年(+4.6%)からさらに上昇幅が拡大し、これで9年連続の上昇です。
 MIYABI
MIYABI特に23区平均は+6.6%と、都区内が全体を力強く牽引しています。
23区の土地の価格はますます上昇する結果となっています。
衰えぬ需要が価格を押し上げている
日銀のマイナス金利解除(2024年3月)※3があったものの、今回の地価算定基準日(2025年1月1日)時点では、まだ低金利環境の恩恵が残っていました。
- 共働き世帯(パワーカップル含む)の旺盛な住宅取得意欲
- 企業のオフィス需要回復
- 円安を背景とした海外投資マネーの流入
などが、価格を押し上げる要因となっています。

※3 日銀のマイナス金利解除(2024年3月19日)については、当面の低金利継続スタンスも示されたが、今後の金利動向は要注視
進む二極化・選別
また、東京都全体では平均で+5.6%、そして23区内では平均で+6.6%という結果となっており、全体としては上昇していますが、その中身を見ると「上がるエリア」と「そうでないエリア」の差がより鮮明になっています。
交通利便性、再開発の有無、エリアブランドやブランドに生活レベルが合わない人が、異なる地域に求める需要などが、地価の明暗を分ける様々な角度からの「選別の時代」に入ったと言えるでしょう。
※本記事の地価は『公示地価(標準地)』であり、実際の個別取引価格とは乖離する場合があります。売買可否や価格交渉は個別要因で大きく変動します。(参考)
【上昇率編】勢いが止まらない!2025年 地価”急上昇”エリア 詳細分析

では、特に「伸び」が著しいTOP10エリアについて、その背景をさらに深く掘り下げます。
まず、2025年1月1日までの、東京都内でも特に地価の上昇率(居住地)が高かったエリアをランキング形式で発表すると、
【東京都】上昇率TOP10 ランキング表
| 順位 | 地点 | 区・所在地例 | 上昇率 | 価格(円/㎡) | 最寄り駅目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 豊島-8 | 豊島区高松1丁目 | +10.9% | 963,000 | 要町駅、池袋駅 |
| 2位 | 荒川-10 | 荒川区東日暮里5丁目 | +10.4% | 905,000 | 日暮里駅、三河島駅 |
| 3位 | 台東-11 | 台東区根岸4丁目 | +10.2% | 867,000 | 鶯谷駅、入谷駅 |
| 4位 | 豊島-5 | 豊島区南大塚3丁目 | +10.1% | 1,100,000 | 大塚駅、向原停留場 |
| 5位 | 中央-17 | 中央区月島3丁目 | +9.7% | 1,700,000 | 勝どき駅、月島駅 |
| 6位 | 文京-11 | 文京区本駒込1丁目 | +9.3% | 1,170,000 | 本駒込駅、白山駅 |
| 7位 | 品川-31 | 品川区東五反田3丁目 | +9.2% | 1,190,000 | 五反田駅、高輪台駅 |
| 8位 | 北-11 | 北区王子1丁目 | +9.2% | 775,000 | 王子駅、王子駅前停留場 |
| 9位 | 文京-18 | 文京区大塚3丁目 | +9.1% | 1,080,000 | 茗荷谷駅、新大塚駅 |
| 10位 | 台東-16 | 台東区三ノ輪1丁目 | +9.1% | 780,000 | 三ノ輪駅、三ノ輪橋停留場 |
となりました。
以下に(すべてではないですが)、これらの地域における価格が上昇している要因を解説しました。
豊島区(池袋・大塚エリア):文化と利便性の融合
池袋エリアは山手線に加え、副都心線・有楽町線などが使えて交通アクセスが抜群でしたが、池袋では「Hareza池袋」などの大規模再開発が街のイメージを一新し、文化的な魅力を高めています。
また、大塚駅も駅ビルリニューアル等で利便性が向上したことも、地価上昇の要因となっています。
職住近接を望む層からの強い支持が集まっており、アクセス性を重視する層から需要が集中していることで、地下が上昇しています。
荒川区・台東区(日暮里・根岸・三ノ輪エリア):利便性と価格の好バランス
また、城北エリアの地価が上昇したことも、2025年の傾向です。
日暮里は成田空港へのアクセスも良く、JR・京成など複数路線が使える交通の要衝。また、鶯谷や三ノ輪も都心へのアクセスが良い割に、山手線西側や都心3区(港区・千代田区・中央区)と比較すると、手が届きやすい水準です。
下町情緒と新しい開発が混在する点も魅力で、この「利便性 vs 価格」のバランスが、賢い住まい探し層に評価されています。
中央区(月島エリア):都心隣接のウォーターフロント

ここは都心3区の元々の地価に加え、タワーマンション建設ラッシュがさらに地価を押し上げています。
銀座や丸の内へも徒歩圏内という圧倒的な都心近接性に加え、運河沿いの開放的な景観や、昔ながらの商店街(もんじゃストリートなど)が共存するユニークなライフスタイルを提供する地域です。
医師、経営者、丸の内勤務のパワーカップル、また中国の準富裕層なども惹きつけています。
文京区(本駒込・茗荷谷エリア):揺るがぬ教育ブランドと希少性
「文京区に住みたい」理由は、名門校が集まる教育環境への期待、が大きいでしょう。
加えて、厳しい建築規制により高層建築が少なく、閑静な住環境が保たれています。
これが住宅供給の少なさに繋がり、根強い需要と相まって高い資産価値と上昇率を生んでいます。
品川区(東五反田エリア):ビジネスと生活のクロスポイント
品川区の五反田エリアは、「五反田駅」や「大崎駅」などの山手線他複数路線が利用でき、品川や新橋といったビジネスエリアへのアクセスが抜群。
スタートアップ企業なども集積し、活気があります。
隣接する品川駅周辺の開発の影響も受け、こちらも池袋同様に職住近接ニーズに応えるエリアとして評価が高まっています。
北区(王子エリア):再開発期待で”伸びしろ”大
北区はJR・地下鉄・都電が集まる交通のハブでありながら、価格はまだ抑えめ。
しかし、駅周辺の再開発計画が具体化しつつあり、将来的な利便性向上や街の発展への期待感が先行して地価を押し上げています。
まさに「これからの街」としてのポテンシャルが評価され、今のうちにという層から人気が集まった結果、既に地価上昇へと昇華されている格好です。
この中では、湾岸(月島)エリアだけは元々地価が高く、過去数年で非常に値上がりしている地域であるものの、2024年1月1日~2025年1月1日の一年間に地価上昇したエリアは、いわゆる城北の下町エリアが中心となっています。
これは、都内ではそこまで地価が高くない地域かつ、都心への一定の利便性が認められる地域に焦点が当たり、需要が高まっていると考えられます。
 MIYABI
MIYABIもっとも、これらのエリアが注目される背景は、他の競合・類似となる地域の地価が既に上昇済みであり、相対的にこれらの地域に注目が集まっているとも読み取れます。
【価格編】揺るがぬ価値!2025年 東京”最高額”エリアの理由

次に、純粋な「価格(円/㎡)」が高い順のランキングです。
 MIYABI
MIYABIこちらは、もはや説明不要とも言える、東京を代表する超一等地が名を連ねます。
【東京都】価格TOP10 ランキング表
| 順位 | 地点 | 区・所在地例 | 価格(円/㎡) | 最寄り駅目安 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 港-7 | 港区赤坂1丁目 | 5,350,000 | 溜池山王駅、六本木一丁目駅 |
| 2位 | 千代田5-8 | 千代田区六番町 | 4,950,000 | 四ツ谷駅、市ケ谷駅 |
| 3位 | 港-11 | 港区南麻布4丁目 | 4,210,000 | 広尾駅 |
| 4位 | 渋谷5-14 | 渋谷区松濤1丁目 | 3,560,000 | 神泉駅、渋谷駅 |
| 5位 | 千代田5-6 | 千代田区三番町 | 3,550,000 | 半蔵門駅 |
| 6位 | 港-10 | 港区元麻布2丁目 | 3,490,000 | 広尾駅、麻布十番駅 |
| 7位 | 千代田5-7 | 千代田区四番町 | 3,410,000 | 市ケ谷駅、麹町駅 |
| 8位 | 新宿5-10 | 新宿区市谷砂土原町3丁目 | 3,010,000 | 市ケ谷駅、牛込神楽坂駅 |
| 9位 | 渋谷5-8 | 渋谷区広尾4丁目 | 2,940,000 | 広尾駅 |
| 10位 | 港区5-15 | 港区白金台5丁目 | 2,930,000 | 白金台駅 |
ご覧の通り、こちらは圧巻の価格帯です。
港区、千代田区、渋谷区といった都心中の都心が独占状態。
赤坂の地点では、1平方メートルあたり535万円という、まさに桁違いの価格がついています。
 MIYABI
MIYABI歴史、ブランド、利便性、ステータス。
すべてを兼ね備えたエリアが、依然として東京の地価の頂点に君臨していることがわかります。
港区(赤坂・麻布・白金台):国際性とステータス
港区(赤坂・麻布・白金台)などは大使館や外資系企業が多く国際色豊か。高級ホテル、レストラン、商業施設が集積し、洗練された街並みを形成しています。
六本木ヒルズや麻布台ヒルズ(虎ノ門・麻布台プロジェクト)のようなランドマーク開発も価値を高め、今後も開発が予定されているためますますの上昇が考えられます。
国内外の富裕層や経営者層からの絶大な支持が、価格を支えています。
千代田区(番町エリア):歴史と知性、絶対的な中心
番町は皇居に隣接し、江戸時代からの武家屋敷地としての歴史と格調を持つ特別なエリア。
国会議事堂や官庁街、有名私立学校にも近く、知的な雰囲気が漂います。
厳しい建築規制が閑静で緑豊かな環境を守り、他の都心エリアとは一線を画す「静かなる中心」としての地位を確立しています。
渋谷区(松濤・広尾):ブランドと洗練された住環境
松濤は都内有数の低層高級住宅街。広い敷地にゆったりと邸宅が建ち並び、プライバシーと静寂が保たれています。
渋谷の喧騒から一歩入った別世界です。
広尾もインターナショナルな雰囲気で、お洒落なショップやカフェが多く洗練されたライフスタイルを求める層に人気です。
新宿区(市谷砂土原町):利便性と高台の邸宅地
市ケ谷駅の交通利便性を享受しつつ、高台に位置する落ち着いた邸宅地。
千代田区番町エリアにも隣接し、こちらもステータス性の高いエリアとして認識されています。
これらのエリアは、単なる利便性だけでなく、
歴史、文化、ステータス、国際性、独自の住環境
といった、お金では簡単に買えない価値が複合的に評価され、圧倒的な価格を形成しているのです。
地価上昇の影:私たちは東京に住み続けられるのか?

さて、ここまで華々しい上昇や高価格の話をしてきましたが、最も重要な問いに触れなければなりません。
という問いに対する答えは、残念ながら多くの人にとって「No」でしょう。
日本の実質賃金は長らく低迷しており、近年の物価高騰でさらに目減りしている上に、
- そういった価格上昇を不動産価格に昇華する動き
- 日本では外国人の不動産購入に主たる規制がない※2
- 長らく続く円安傾向(=相対的に低い金額で購入できる)
が、地価上昇に拍車をかけています。
東京の地価・不動産価格は、この記事で見てきたように、世界的なマネーの流れや一部の富裕層の需要にも支えられ、平均的な勤労者の感覚とはかけ離れた水準で上昇を続けています。
 MIYABI
MIYABIこの「住居費 vs 賃金」のギャップ拡大は、深刻な問題を引き起こします。
※2 日本は『原則自由』だが、国安上の観点から『重要土地等調査法』で“特別注視区域”では一定規模以上の売買前に『事前届出』が必要な場合あり
家賃負担の増大
特に都心部や人気エリアでは、家賃更新のたびに負担が増し、生活を圧迫します。
更新を機に、より郊外へ移転せざるを得ないケースも増えています。
マイホーム取得の困難化
価格高騰&金利上昇により、ローン審査が厳しくなったり、組めたとしても返済負担が過重になったりします。
特に若い世代や子育て世帯にとっては、東京での住宅購入は「高嶺の花」となりつつあります。
通勤時間の長時間化
都心に住めない人々が郊外へ移り住むことで、満員電車での長時間通勤を強いられ、時間的・精神的な負担が増大します。
都市の活力低下の懸念
本来都市の活力を支える若い世代や多様な層が都心から流出し、住む人が偏る(=富裕層や高齢者中心になる)ことで、中長期的に都市のダイナミズムや文化が失われるリスクも指摘されています。
 MIYABI
MIYABI現状のまま地価・不動産価格の上昇が続けば、「一部の富裕層しか快適に住めない都市」へと東京が変貌していく可能性は否定できません。
もっと言えば、既にそう言った状況になっている、というのが本音です。
じゃあ、私たちはどうすれば良いのか?
ここまで読んで
と感じられた方も多いかもしれません。
正直に申し上げて、この状況を劇的に変える個人の特効薬はありません。
厳しい現実にため息が出るのも当然ですが、思考停止せずに、私たち一人ひとりができることや考えるべきこともあります。
 MIYABI
MIYABI状況を正しく理解し、現実的な選択肢を探るための視点をいくつかご紹介します。
徹底的な情報収集と現実的な資金計画
まず基本となるのは、「知ること」と「自分の足元を見つめること」です。
市場動向を追い続ける
公示地価だけでなく、
- 実際の売買価格(成約価格)
- 賃料相場、金利動向(特に日銀の政策変更後の長期金利など)
- 税制(住宅ローン控除など)
- 補助金制度(子育て支援や省エネ住宅関連など)
といった情報を、信頼できるソースから継続的に収集しましょう。
 MIYABI
MIYABIご自身の関心エリア、例えば、品川区であれば、
・大井町や大崎周辺の再開発
・リニア中央新幹線の計画
・羽田空港アクセス線の影響など
の、具体的なニュースにもアンテナを張ることが重要です。
「賃貸派」の場合、契約には注意する
賃貸物件を探す際には、契約形態の違いを理解しておくことも必須です。
『普通借家契約』と『定期借家契約』の違いを把握しましょう。
普通借家契約
正当な理由がない限り貸主からの更新拒絶が難しく、長期的な居住安定性が高いのが一般的
周辺相場と比べて著しく安いなどの状況でなければ、貸主と借主、双方の合意がなければ賃料を一方的に上げることは難しいです。
定期借家契約
契約期間満了で原則として契約が終了するため、住み続けたい場合は再契約が必要(貸主の合意が必要)
その分、相場より家賃が低めに設定されているケースもあるが、再契約時には借主側にとって賃料の交渉が難しい。人気エリアなどでは流動性を高める(数年単位で確実に家賃を上げる)ために定期借家契約が増えている。
 MIYABI
MIYABIどちらが良いかはライフプランによりますが、契約前に必ず確認し、その特性を理解しておくことがトラブル回避に繋がります。
上述の通り、地価上昇が著しいエリアの賃貸は、定期借家契約になるところが増える傾向にあります。
物件の良し悪しだけでなく、契約タイプにも必ず目を通しましょう。
ちなみに、筆者の知人が住むマンション(ファミリータイプの2LDK)では、2023年の入居時と比べて同じ間取りの部屋がわずか1年半で家賃+10万円で出ているそうです。
管理会社は更新時に、必ずその相場上昇に合わせて打診してきますが、
のに対し、
地価上昇エリアにおいて、契約形態は非常に重要なのです。

※1 「『普通借家契約』でも、市場や経済事情の変化等で『賃料増減請求(借地借家法32条)』が可能です。合意に至らない場合は調停・裁判で相当額が決まることがあるため、『必ず断れる』とは限りません。
「分譲派」の場合“目一杯借りる”ことはおすすめしない
「借りられる額」ではなく「返せる額」で考える
不動産広告や金融機関のシミュレーションは、しばしば「借りられる上限額」を示しますが、重要なのは「将来にわたって、無理なく安定して返済し続けられる額」です。
収入、支出、将来のライフイベント(転職、出産、子の進学など)を考慮した、極めて現実的な資金計画を立てましょう。
 MIYABI
MIYABIFP(ファイナンシャルプランナー)など専門家への相談も有効ですが、最終的な判断はご自身で行う覚悟が必要です。
\住宅ローンおすすめ金融機関はこちら/

貯蓄と資産形成の意識
頭金の準備はもちろん、将来の金利上昇や修繕費、固定資産税なども見越した貯蓄・資産形成(NISAの活用など)の意識を持つことが、これまで以上に重要になっています。
\新NISAをはじめるならここ/

「場所」と「住まい方」の選択肢を広げる
「都心・駅近・新築」だけが選択肢ではありません。
 MIYABI
MIYABIもちろん、多くの方の理想形であることは間違いありませんが、固定観念を外して視野を広げてみましょう。
エリアの再検討
「絶対にこの区(駅)が良い」というこだわりを少し緩め、隣接する区や市、あるいは通勤可能な範囲で少し離れたエリアも検討対象に入れてみましょう。
例えば品川区にお住まいなら、隣接する大田区の一部や、川崎市なども視野に入れる、といった具合です。
同じ沿線でも、急行停車駅の隣駅や、知名度は低いけれど実はアクセスが良い駅などを探すことで、掘り出し物が見つかる可能性もあります。
「通勤時間」「住環境(子育て、買い物など)」「価格」のバランス点を、ご自身の優先順位に照らして見つける作業です。
働き方と居住地の選択
働き方自体を見直す視点も有効です。
テレワーク(リモートワーク)が可能な職種や企業を選ぶことで、通勤の制約から解放され、都心から離れたより家賃や価格が手頃なエリアを居住地の選択肢に入れることが可能になります。
週数回の出社であれば、多少距離があっても実現可能な範囲は広がるでしょう。
 MIYABI
MIYABI日本の場合、東京都などの都心は地価上昇を続けますが、一方で地方は地価が下がる、格安(や場合によってはタダ同然)で家に住めるということは、留意すべきことでしょう。

新築から中古、そしてリノベーションへ
新築物件は価格が高騰していますが、「中古マンション」「中古戸建て」に目を向ければ、選択肢は大きく広がります。
特に築年数が経過した物件は、価格が手頃な場合があります。
購入後に自分のライフスタイルに合わせてリノベーション(リフォーム)するという考え方は、賢い選択肢の一つとして定着しつつあります。
 MIYABI
MIYABIもちろん、本当に相場が上昇しているエリアにおいては、新築時よりも中古の分譲マンションの方が価格が高いといったこともザラです。
あくまで一般的な傾向と捉えていただければと思います。
住まいのダウンサイジング
本当に必要な広さや部屋数を見直すことも有効です。
リモートワークの普及などで必要なスペースは変化しています。
将来的な家族構成の変化も見据え、身の丈に合ったサイズを選ぶことが、コスト削減に繋がります。
賃貸という選択肢の再評価
無理なローンを組んで購入するよりも、
あるいは
という選択も、状況によっては合理的です。
ただし、賃貸も分譲も持ち家も、周辺相場によって価格が決定することは留意しましょう。
例えば、一見賃貸派には関係がないと思われる住宅ローンの金利に関しても、
金利が上がる
➡ローンの返済額が増える
➡不動産投資や売却・賃貸に出す場合などは家賃や売却価格を上げざるを得ない
➡周辺相場で賃料は決定されるため、賃貸においても家賃が上昇する
といった動きをします。
 MIYABI
MIYABI実は、短期的には思わぬ掘り出し物があることは事実ですが、長期的に見れば周辺相場に合わせて動くため、賃貸も分譲もあまり差が生まれるものではありません。
中長期的な視点とライフプランの見直し
目先の価格変動に一喜一憂せず、長い目で住まいと人生を考える視点も大切です。
キャリアと収入
残酷な現実ですが、住居費負担能力は収入に大きく左右されます。
自身のキャリアを見つめ直し、スキルアップや収入増に向けた努力をすることも、間接的に住まいの選択肢を広げることに繋がります。

ライフプランとの整合性
「東京に住むこと」が、あなたの人生全体の目標(家族との時間、趣味、自己実現など)とどう結びついているのか、改めて考えてみましょう。
東京は平均所得が全国No.1の都道府県であることは言を俟たないですが、可処分所得そのものは下から数えた方が早いというデータも出ています。
重要なのは収入ではなくお金の自由度です。もしかしたら、住む場所を変えることで、より豊かになる人生もあるかもしれません。
住まいは目的ではなく、幸せな人生を送るための「手段」の一つです。
市場サイクルを意識する(過信は禁物)
不動産市場にも波はありますが、底値や天井を正確に予測することは誰にもできません。
「いつか下がるはず」と待ち続ける戦略にはリスクも伴います。
ただし、現在の市場が過熱気味であるという認識を持ち、焦って高値掴みをしない冷静さは必要でしょう。
社会的な課題としての認識も
最後に、この問題は、個人の努力だけで解決できる範囲を超えている側面も認識しておく必要があります。
構造的な問題
住宅価格の高騰と賃金の伸び悩みは、
- 日本の経済構造
- 都市計画
- 税制
- 金融政策
など、様々な要因が絡み合った社会的な課題です。
声を上げ、関心を持つ
すぐに状況が変わるわけではありませんが、私たち一人ひとりがこの問題に関心を持ち、あるべき都市の姿や、持続可能な社会について考え、必要であれば声を上げていくことが、未来を変える力に繋がるかもしれません。
関連する政策のニュースなどに注意を払うだけでも意味があります。
 MIYABI
MIYABI私たちも日々の時事ニュースをお伝えしているのでぜひチェックしてください!
しかし、情報を集め、現実を見据え、選択肢を広げ、長期的な視点を持つことで、厳しい状況の中でも、ご自身にとってより良い判断を下すための一歩を踏み出すことは可能です。
【Q&A】東京の地価上昇の疑問に答える
そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
2025年の東京の地価はどのくらい上昇したの?
東京都の住宅地平均は前年比+5.6%、23区平均では+6.6%と9年連続で上昇しています。
特に都市再開発や交通利便性が高いエリアで上昇が顕著です。
地価が急上昇した具体的なエリアはどこ?
豊島区、荒川区、台東区、文京区など城北エリアが上位にランクイン。
再開発や交通の便の良さが地価上昇の要因です。
なぜ地価はここまで上がっているの?
低金利の継続、共働き世帯の住宅購入意欲、円安による海外マネーの流入などが主因です。
供給が限定的なエリアで特に価格が上がっています。
地価上昇に賃金は追いついているの?
実質賃金は2025年5月時点で前年同月比『–2.9%』(速報値)。名目は伸びても物価上昇に追いつかない局面が続いています。
生活費や家賃負担が増し、住みにくくなっています。
今から東京に家を買うのは危険?
高値づかみのリスクがあります。
「借りられる金額」ではなく「返せる金額」を重視した現実的な資金計画が必須です。
賃貸契約の形態で注意すべきことは?
地価上昇エリアでは「定期借家契約」が増えています。
家賃更新交渉が難しくなるため、契約前に内容を確認しましょう。

地価が高騰する中で、どう住まいを選ぶべき?
「都心・新築」にこだわらず、隣接エリアや中古・リノベ物件も視野に入れた柔軟な選択が重要です。
東京に住み続ける必要が本当にあるの?
必ずしもありません。
テレワークの活用や地方移住など、働き方と住まい方の再検討も有効な選択肢です。
将来のために何をすべき?
継続的な情報収集と中長期のライフプラン設計が鍵です。
収入増や貯蓄・資産形成の意識も大切になります。
\新NISAをはじめるならここ/

まとめ:厳しい現実と向き合い、未来への視座を持つ

2025年の公示地価は、東京の不動産市場の力強さを示すと同時に、多くの都民・国民が直面する「住まいの問題」の深刻さを浮き彫りにしました。
- 地価上昇は加速し、エリアによる二極化が進行。
- 上昇の背景には再開発や交通利便性への期待。
- しかし、多くの人の賃金上昇や生活水準はこのペースに追いついていない。
この現実は、個人のライフプランだけでなく、社会全体で考えるべき課題です。
私たちはこの状況をどう捉え、どう行動すべきでしょうか?
すぐに答えが出る問題ではありませんが、まずは最新の動向を正確に把握し、自分や社会への影響を考えることが第一歩となるはずです。
もし、是が非でも東京に居続ける、自分の住むエリアから妥協できないというのであれば、
- 相場上昇フェーズ前に、お気に入りの分譲を購入してしまう
- 今は少し身の丈に合っていなかったとしても、ライフステージの変化などに対応できる『普通借家契約(これも絶対に断れるわけではないですが)』の賃貸に住む
のどちらかが考えられます。
ただし、個人的には
「本当に東京に住み続ける必要があるのか」
「リモートワークなども含めて自身のキャリアアップやキャリアチェンジも考えられないか」
という選択肢も検討すべきと思います。
 MIYABI
MIYABIこの記事が、そのための情報提供となれば幸いです。

\無料相談はこちら!/
本情報は一般的解説であり、特定商品の勧誘ではありません。最終判断はご自身の責任で。手数料・リスク・税制は最新の公的資料をご確認ください。