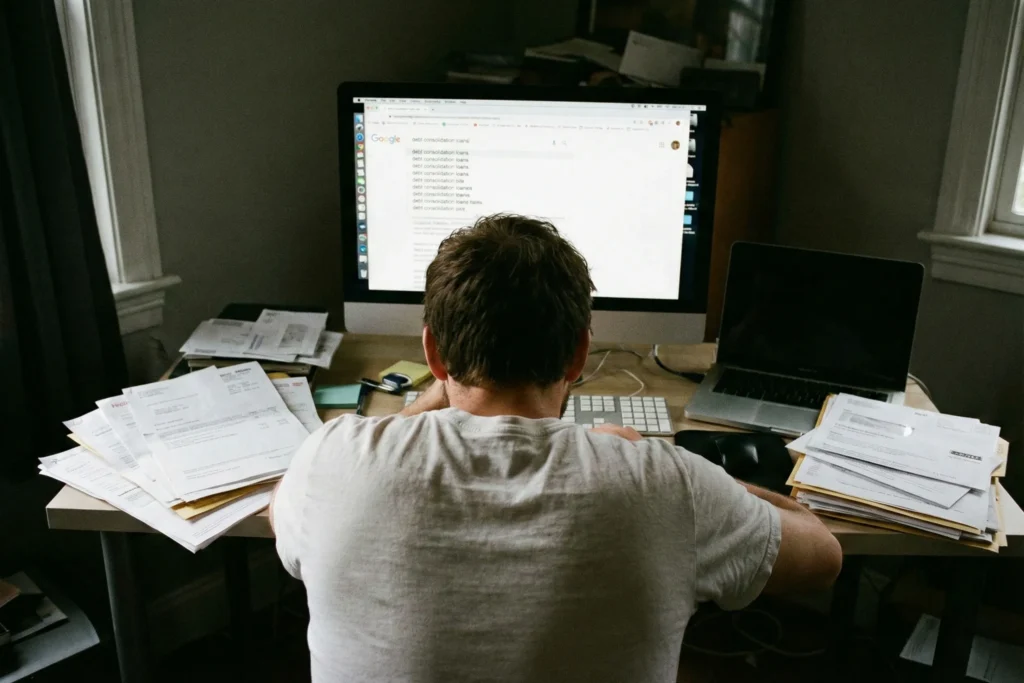【2025年11月25日】の経済・時事ニュースまとめ
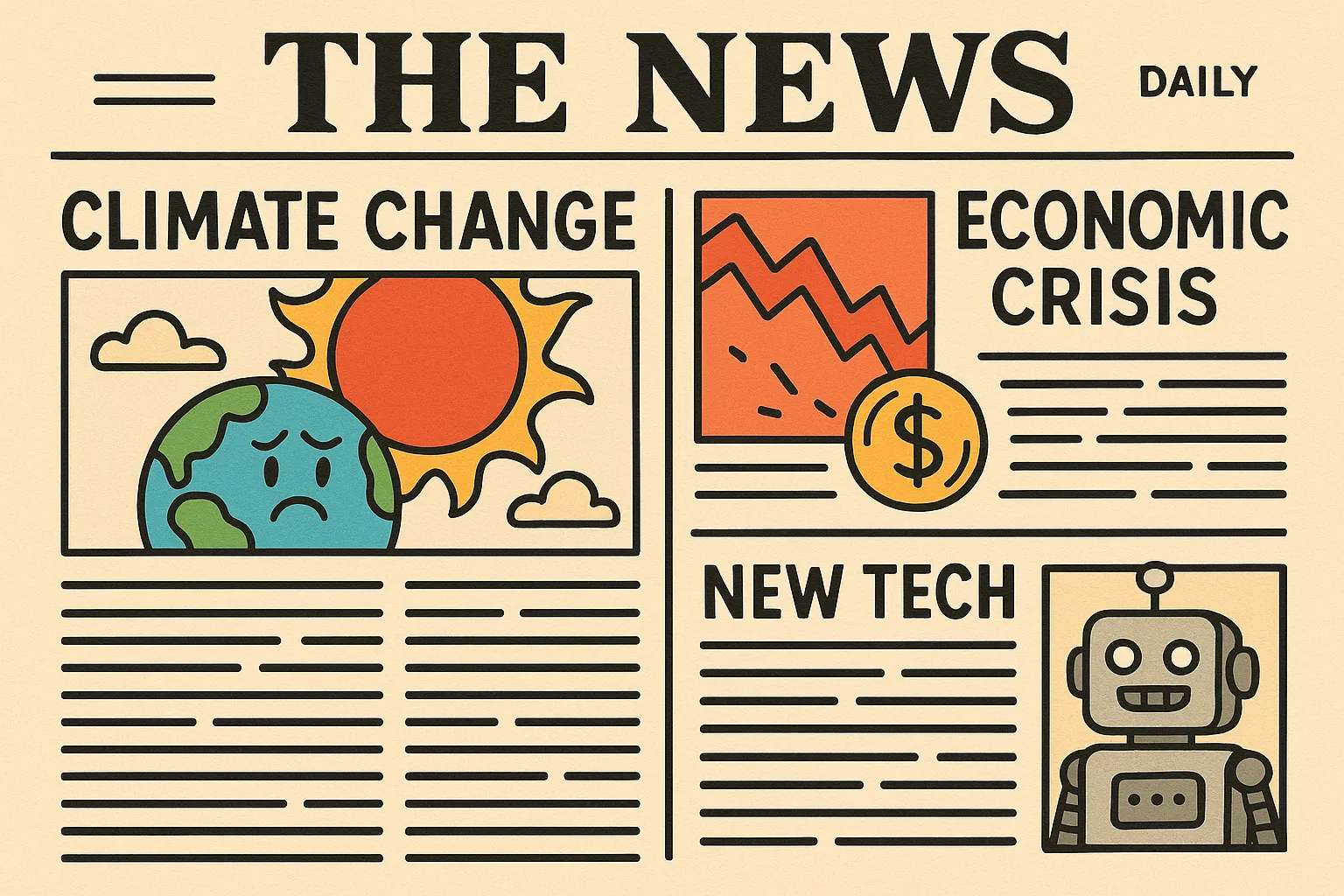
2025年11月25日は、米国の利下げ観測とAI関連株の上昇を背景に世界的に株高と円安が進んだ1日となりました。
東京市場では連休明けの日経平均株価が反発し、日本政府の21.3兆円規模の総合経済対策や円安の行方に国内外の投資家の視線が集まっています。
海外では米国株式市場の続伸に加え、イスラエル中銀の約2年ぶりの利下げやブラジル中銀の慎重なスタンス表明など、各国の金融政策の転換点をうかがわせる動きも出ています。
 ねくこ
ねくここの記事では、主要株価指数と為替の動き、資産運用のポイント、国内外の注目ニュース、そして私たちの生活への影響を整理してお伝えします。
主要株価指数・為替レート(2025年11月25日10時時点)
| 指標 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 48,960.81円 | +334.93(0.69%)円 |
| NYダウ | 46,448.27ドル | +202.86(+0.44%)ドル |
| S&P500 | 6,705.12ポイント | +102.13(+1.55%)ポイント |
| ドル円為替(ドル/円) | 156.68円前後 | -0.27円 |
ここでは2025年11月25日10時時点を基準に、東京・ニューヨークの主要株価指数とドル円レートの概況をまとめます。
 ねくこ
ねくこ日経平均は小幅高で進む一方、米国株はAI関連を中心に大きく上昇し、ドル/円は156円台後半の円安水準が続くなど、株高と円安が同時進行する相場環境となっています。
日経平均は連休明けに反発、ハイテク中心に買い戻し
25日の日経平均株価は10時時点で48,960.81円と前週末比+334.93(0.69%)円となっており、連休前の大幅安からやや持ち直しのスタート。
前日の米国株市場でハイテク株中心に主要指数が上昇した流れを引き継ぎ、東京市場でも半導体やAI関連など成長株を中心に買い戻しが広がりました。
一方で、日本の大型経済対策や財政拡張路線が長期金利上昇と円安を同時に招いたとの見方もあり、海外投資家は日本株の上昇の「持続力」を慎重に見極めようとしています。
 ねくこ
ねくこ短期的な株価の上下は経済対策や為替ニュースで振れやすいため、値動きの大きさだけで慌てて売買判断をしないことが重要です。
米国株はAI関連と利下げ期待で大幅高、S&P500は再び高値圏
24日の米株式市場では、ダウ工業株30種平均が4万6448.27ドルと前日比202.86ドル高、S&P500が6705.12ポイントと102.13ポイント高となり、いずれも堅調な動きを見せました。
米連邦準備制度理事会(FRB)の理事が12月の利下げを支持する発言を行ったことで追加利下げ観測が強まり、将来の金利低下が成長株の割高感を和らげるとの期待からハイテク株に資金が集まりました。
 ねくこ
ねくこAI関連銘柄への期待が高い局面ほど、企業の業績や投資計画が将来の利益で本当に説明できるかを冷静に確認する姿勢が欠かせません。
ドル高・円安は財政拡張と利下げ観測の綱引きに
24日のニューヨーク外国為替市場でドル/円は1ドル=156円86~96銭と前週末比でおよそ0.5円の円安ドル高となり、25日朝時点でも156円台後半での推移が続いています。
背景には、21.3兆円規模の経済対策による財政悪化懸念から日本の長期金利と円安が同時に進み、「日本版トラスショック」とも評される市場不安が意識されていることがあります。
一方で、米国では年内の追加利下げ観測が再び強まっており、今後金利差が縮小するとの見方が優勢になれば、ドル高・円安の流れが一服する可能性も指摘されています。
 ねくこ
ねくこ為替レートは短期間で大きく動くことがあるため、外貨建て資産や海外旅行の予定がある人は、複数回に分けるなどタイミングを分散する工夫がリスクを抑える助けになります。
資産運用をしている人がこの局面で心掛けるべきこと
急な株高でも「長期・分散・積立」の方針は崩さない
株式市場が大きく反発すると短期間で利益を狙いたくなりますが、値動きの勢いだけに合わせて投資方針を変えると、高値づかみや売り急ぎにつながりやすくなります。
また、株式だけでなく、投資信託や債券、預貯金など複数の資産に分散しておくと、どれか1つの値動きが大きくなっても家計全体のダメージを抑えやすくなります。
 ねくこ
ねくこ短期の成績よりも、5年から10年といった少し長い期間で資産がどう増減しているかを時々確認するくらいの距離感で市場と付き合うことが一つの考え方です。
円安局面での外貨資産との付き合い方
円安が進むと外貨建て資産の評価額は増えますが、今から新たに外貨を買う場合には急激な反転(円高)による為替差損のリスクも大きくなります。
為替証拠金取引などレバレッジをかける取引(いわゆるFX)は、小さな値動きでも損失が大きくなりやすいため、仕組みやリスクを十分理解してから必要性を慎重に検討することが欠かせません。

外貨建て投資信託や外貨預金なども、為替だけでなく手数料や金利水準を比較し、自分のリスク許容度や将来使う予定の通貨を整理してから選ぶことが大切です。
 ねくこ
ねくこ外貨資産の比率が増えすぎていると感じる場合は、新たな積み立て分を一時的に円資産中心の商品に回すなど、全体のバランスを整える視点も役立ちます。
新しいNISAやiDeCoをどう活用するか
新しいNISAは投資で得た利益に税金がかからない範囲が広がった制度で、長期の資産形成を考える人にとって重要な選択肢になっています。

特に毎月一定額を積み立てる「つみたて投資枠」と個別株などにも投資できる「成長投資枠」をどう組み合わせるかは、年齢や収入の安定度、値動きへの強さといった自分のリスク許容度によって変わります。

老後資金づくりを重視したい人は、掛金が所得控除の対象になる年金制度のiDeCo(個人型確定拠出年金)も含めて、手取り収入と将来の受け取り方のバランスを比較することがポイントです。

 ねくこ
ねくこ税制優遇を活かす制度はどれもメリットと制約があるため、焦って一気に枠を埋めるのではなく、家計の貯蓄ペースを確認しながら段階的に活用するイメージを持つと安心です。
国内ニュース
大型経済対策21.3兆円をめぐり、市場は「積極財政」を警戒
政府は21.3兆円規模の総合経済対策を決定し、物価高対策や子育て世帯への給付、エネルギー補助、成長投資、防衛力強化などに多額の財政支出を投じる方針です。
この規模の平時の補正予算は過去最大級であり、日本の財政悪化懸念が強まった結果、国債利回り上昇と円安が同時に進む「市場の警戒シグナル」が海外メディアでも指摘されています。

一方で高市政権は、物価高から家計を守りつつ成長力を高めるための積極財政だと説明しており、成長率押し上げや物価の抑制効果については今後数年かけて検証されることになります。
 ねくこ
ねくこ大きな経済対策は家計支援の安心感を高める一方で将来世代の負担や金利上昇リスクにもつながるため、恩恵だけでなくコストの側面にも目を向けておく意識が重要です。
観光業は人手不足が最大の課題、インバウンド回復の裏側
日本の観光業界を対象にした調査では、宿泊や飲食、小売などの現場で働く人材の不足が業界共通の最大の課題として挙げられています。
訪日客数がコロナ禍前の水準に近づきつつある一方で、地方の観光地では求人を出しても応募が少なく、サービス提供の質や営業時間を維持することが難しくなっているケースも増えています。
人手不足を補うため、企業は賃上げや待遇改善に加え、ITやAIを活用したチェックイン機の導入や予約の自動化など省力化投資を進めており、そのコストが宿泊料金やサービス価格の上昇につながる可能性もあります。
 ねくこ
ねくこ旅行先での混雑やサービス低下の背景には人手不足がある場合も多いため、予約時期や移動時間に余裕を持つなど、利用者側の工夫も求められそうです。
沖縄本島で最大37万世帯に断水の恐れ、水道インフラの老朽化が表面化
沖縄県大宜味村で水源と浄水場を結ぶ導水管が24日未明に破裂し、本島中南部の17市町村で最大約37万世帯が断水の恐れに直面しました。
県企業局は老朽化が原因とみて復旧工事を急ぐ一方、節水要請や給水車の配備を行い、25日明け方以降に順次送水を再開する見通しを示しており、観光地を含む広い地域の生活や事業活動への影響が懸念されています。
今回の事例は、水道管の更新が全国的に遅れている中でインフラ老朽化が一気に表面化したケースとされ、今後、地方自治体の投資計画や国の支援策のあり方が議論される可能性があります。
 ねくこ
ねくこ自宅地域で同じような断水が起きた場合に備えて、2リットルの飲料水を数本ストックしておくなど、日頃からの備蓄を見直すきっかけにもなりそうです。
海外ニュース
米国株高の背景は「利下げ期待」と「AIブーム」の二重の追い風
24日の米株式市場ではS&P500が前日比1.55%高、ナスダック総合が2.7%高となり、5月以来となる2日連続の大幅高を記録しました。
背景には、FRBが12月にも追加利下げに踏み切るとの観測が強まり、将来の金利低下が成長株のバリュエーションを正当化しやすくなるとの期待があると指摘されています。

 ねくこ
ねくこ強気の予測は将来の可能性を示した「シナリオの一つ」に過ぎず、必ず当たるものではないため、数字だけを切り取って過度な期待や不安を抱かないことが大切です。
イスラエル中銀が2年ぶり利下げ、インフレ鈍化で慎重に舵を切る
イスラエル中央銀行は24日、政策金利を0.25ポイント引き下げ4.25%とし、およそ2年ぶりとなる利下げに踏み切りました。
中銀はインフレ率が10月に2.5%まで低下し目標レンジ(1〜3%)に収まったことを理由に挙げつつ、戦時下の地政学リスクや賃金上昇への警戒も維持しています。
利下げは段階的に続くとの見方がある一方で、「世界全体がゼロ金利に戻ることはない」との認識も示されており、高金利環境が新たな常態になりつつあることがうかがえます。
 ねくこ
ねくこ海外の金利動向は為替レートや海外債券・リートへの投資成果にも影響するため、ニュースの見出しだけでなく金利水準やインフレ率の数字にも目を向けておくと流れがつかみやすくなります。
ブラジル中銀はインフレ目標達成に「満足していない」と強調
ブラジル中央銀行のガリポロ総裁は24日、インフレを目標の3%に戻す進展状況に「依然として満足していない」と述べ、金融政策は経済データ次第で必要な措置を取り続けると強調しました。
ブラジルでは政策金利が過去約20年で最高水準となる15%に据え置かれており、高い金利を長期間維持することで物価を抑え込む方針が示されています。
新興国では金利や通貨が大きく振れやすいため、日本から投資する場合も短期の高い利回りだけでなく、インフレ率や政治リスクを総合的に見る必要があることを改めて示すニュースと言えます。
 ねくこ
ねくこ高金利通貨や高配当商品は魅力的に見えますが、「なぜ金利が高いのか」「その水準を維持できるのか」を考える癖をつけておくと、より冷静な判断につながります。
アマゾンが米政府向けAIインフラに最大500億ドル投資
米アマゾン・ドット・コムは、米連邦政府のAI関連処理を支援するため、米国内のデータセンターに最大500億ドル(約7.8兆円)を投資すると発表しました。
政府機関向けの専用クラウド基盤を整備し、大規模なAIモデルの学習や安全な運用に必要な計算資源を提供することで、行政サービスのデジタル化や安全保障分野の高度化を支える狙いがあります。
巨額のインフラ投資は地元の雇用創出や電力需要の増加にもつながる一方で、環境負荷や地域の電力網への影響をどう抑えるかも今後の重要な論点になりそうです。
 ねくこ
ねくこ生成AIの普及は私たちの日常生活にも便利さとリスクの両方をもたらすため、データの扱い方やプライバシー保護についてもニュースを通じて少しずつ理解を深めておきたいところです。
私たちの生活に起こること
物価と金利、円安が家計にもたらす影響
全国の物価はすでに前年比3%前後の上昇が続いており、円安による輸入物価の押し上げも加わることで、食料品やエネルギー価格の高止まりが長引く可能性があります。
一方で賃金の伸びやボーナスの増加は業種や企業規模によって差があり、実質賃金はマイナスが続いているとの統計も出ているため、生活のゆとりが増えている世帯と苦しくなっている世帯の二極化が進みやすい局面です。
今後金利が徐々に上がれば住宅ローンの金利負担が増える一方、預貯金や個人向け国債などの金利が高くなるというプラス面もあるため、借金と金融資産の両方を家計全体で見渡す視点が重要になります。
 ねくこ
ねくこ家計簿アプリなどを使って毎月の支出と貯蓄額をざっくり把握しておくと、物価や金利の変化が自分の生活にどれくらい影響しているかを早めにキャッチしやすくなります。
賃金・雇用と観光・サービス業の変化
観光や外食、イベント関連の需要は回復していますが、人手不足や長時間労働の問題も残っており、労働条件の改善に向けた賃上げや働き方改革が進むかどうかが今後の焦点です。
賃上げが進めば若い世代や地方で働く人の収入アップにつながる一方、サービス価格の上昇という形で私たちの支出増にも跳ね返る可能性があり、家計管理の重要性はさらに高まります。
沖縄の断水のようなインフラトラブルは観光地のホテルや飲食店の営業にも影響し得るため、水道や電力などの設備更新に向けた公共投資が、雇用や地域経済にもたらす効果にも今後注目が集まりそうです。
 ねくこ
ねくこ求人票を見るときは給与水準だけでなく、休日や残業時間、福利厚生なども含めて総合的に比較する癖をつけておくと、景気の波に左右されにくい働き方を選びやすくなります。
今からできる具体的な備えと見直しポイント
物価や金利、為替が大きく動く局面では、まず家計の固定費を見直し、ムダな契約や使っていないサービスがないかをチェックすることが最初の一歩になります。




高額な買い物や住宅ローンの借り換えなどは、金利や為替の動きだけで決めるのではなく、将来の収入見通しやライフプランも含めて複数のシナリオを考えながら時間をかけて判断することが大切です。
投資については「短期で儲ける」よりも「大きく損をしない」ことを優先し、必要なら金融機関や公的な相談窓口で手数料やリスクの説明をよく聞いてから判断するよう心掛けましょう。
 ねくこ
ねくこニュースを日々追うこと自体が、金利や物価、為替などお金に関わる感覚を鍛えるトレーニングにもなるので、自分なりのペースで情報との付き合い方を見つけていきたいところです。
投資に関するご注意(免責事項)
本記事は2025年11月25日時点で公表された情報をもとに一般的な経済・市場動向を解説したものであり、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
将来の金利・為替・株価・物価などの動きは不確実であり、本文で触れた見通しやシナリオが実際の結果を保証するものではない点にご注意ください。
投資や家計の判断は、最新の情報やご自身の資産状況・リスク許容度を踏まえ、最終的にはご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いいたします。