退職金がある企業ってどのくらいあるの?支給額は減っている?不安な人はiDeCoをやるべき?

終身雇用&経済成長が当たり前の時代とは異なり、現在は定年退職時にまとまった退職金を受け取るのが、当たり前ではなくなりつつあります。
バブル期のように高額な退職金を得ることは難しくなり、企業が退職金制度を縮小・廃止したり、確定拠出年金(DC)へ移行するケースも増えているためです。
実際、大手企業ではまだ退職金が比較的多いものの、特に中小企業では「退職金がない」「制度はあっても金額がわずか」という例が多く、退職金に頼った老後資金計画はリスクが高いと言えます。
勤務先に企業型DCや退職金(DB/一時金)があるか・規約や拠出額・マッチング拠出の可否』を就業規則で確認したうえで、『iDeCoの掛金上限(2027年1月以降引き上げ)』や『加入年齢の上限(2027年1月以降70歳未満へ拡大)』も踏まえて最適な組合せを検討しましょう。
「5年ルール」が「10年ルール」に変わる可能性も取り沙汰されていますが、このルールに関しては、そもそも退職金がない人の場合、課税上の影響は小さく済む可能性が高いです。
 ねくこ
ねくこ本記事では、FPの資格を持つ私「ねくこ」が、退職金の現状や金額推移を概観しながら、自助努力による老後資金づくりの重要性をお話します。
退職金がある会社の割合
厚生労働省の調査データ
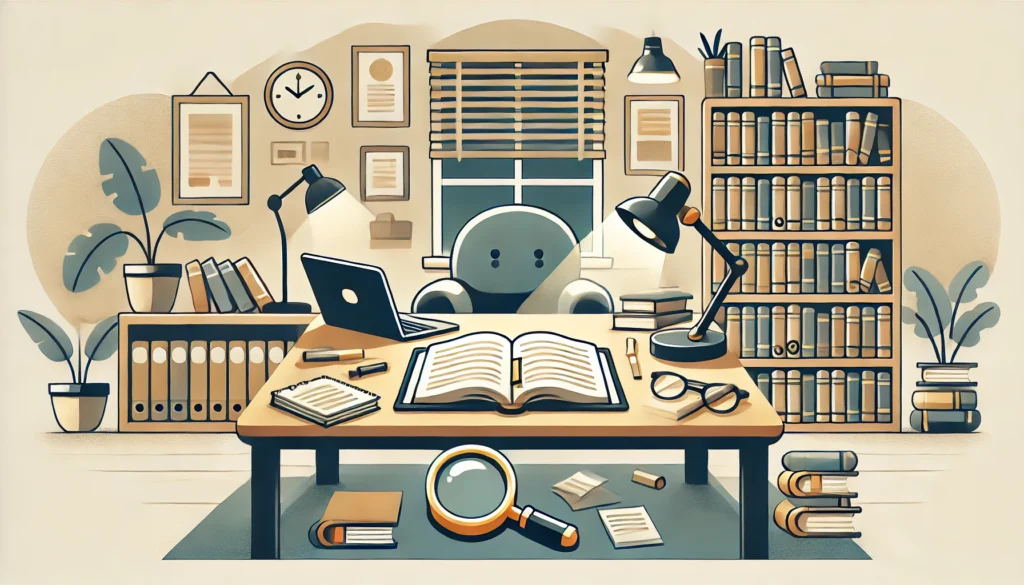
退職金制度が存在する企業の割合を把握する際によく参照されるのが、厚生労働省の「就労条件総合調査」です。
全体の退職給付(一時金・年金)制度の導入割合は『74.9%』で、『1,000人以上:90.1%/300~999人:88.8%/100~299人:84.7%/30~99人:70.1%』とされています(令和5年就労条件総合調査、2023年10月31日公表)。
ただし、これは企業規模(従業員数)による大きな違いがある点に注意が必要です。
 ねくこ
ねくこ大企業の多くは制度を設けていますが、中小企業になるほど導入率が下がる傾向にあります。
具体的には、たとえば従業員1,000人以上の企業であれば9割以上が退職金制度を有している一方、従業員が数十名以下の小規模事業所では退職金制度がないケースも珍しくありません。
このため「全体で8割」と聞いても実感と乖離が生じやすく、特に中小企業で働く人にとっては、実際には退職金を支給してもらえる可能性がかなり低いことも多いのです。
経団連など民間団体の調査
経団連(日本経済団体連合会)が定期的に公表する「退職金・年金に関する実態調査」も、退職金制度の現状を把握するうえで参考になります。
こちらでは、企業規模別の導入率や平均支給額、確定拠出年金(DC)との併用状況など、かなり詳細なデータがまとめられています。
 ねくこ
ねくここの調査でも、大企業が中心とはいえ、大企業の中でも「従来型の退職金制度」と「確定拠出年金型」に移行する企業の割合が増えており、従来の一時金としての高額な退職金を期待しづらくなっている傾向がうかがえます。

企業規模で大きく変わる“退職金のある・なし”
こうした統計から分かるのは、
という二極化が進んでいることです。
特に中小企業の場合、「退職金制度を設けている」と回答していても、実際に定年退職時に受け取る金額が少なく、思ったほど役立たないケースがあるため要注意です。
また、転職や早期退職などで勤続年数が十分に積み上げられず、結果として期待ほど退職金を受け取れないことも多くなっています。
さらに、企業の業績や雇用制度の変更によっては、退職金の受給要件や計算方法が変わるリスクも否定できません。
 ねくこ
ねくここうした現状を踏まえると、「自分の会社は退職金制度があるから大丈夫」と楽観視するのは危険です。
次章では、実際の支給金額がどの程度推移しているのかを見ていきましょう。
支払われる退職金の金額推移
出典:厚生労働省「就労条件総合調査」などを参考に作成(概算値を含む)
過去数十年を振り返ると、バブル期前後の1980年代後半~1990年代初頭は、大企業を中心に退職金の水準が極めて高かったといわれています。
しかし、その後の不況や経営環境の変化、年功序列制度の見直しなどによって、企業全体として退職金制度が徐々に変化してきました。
厚生労働省の「就労条件総合調査」や民間調査機関のレポートなどを見ると、平均退職金額は1990年代後半から減少傾向という結果が示されています。
 ねくこ
ねくこそして、この「平均値」というものは、退職金を支給している大企業の高額支給実績が含まれるため、実態よりも高く見えている可能性があります。
一方、近年は確定拠出年金(DC)など、従来の一時金とは異なる形で退職時の給付を受け取る制度が増え、従来型の「退職金としての一時金」を比較しづらくなっています。
企業規模・業種によるばらつきもある
| 業種 | 高校卒の退職金 |
|---|---|
| 建設業 | 1133万4000円 |
| 製造業 | 999万6000円 |
| 情報通信業 | 941万8000円 |
| 運輸業、郵便業 | 1142万8000円 |
| 卸売業、小売業 | 1036万7000円 |
| 金融業、保険業 | 1073万6000円 |
| 不動産、物品賃貸業 | 513万6000円 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 1026万1000円 |
| 宿泊業、飲食サービス業 生活関連サービス業、娯楽業 | 716万9000円 |
| 教育、学習支援業 | ー |
| 医療、福祉 | 332万3000円 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 995万8000円 |
東京都産業労働局 「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」を基に作成
また、退職金の金額を語るうえで見逃せないのが、企業規模や業種による大きな差です。
一般的に、製造業・金融業などの大企業では依然として高水準の退職金が維持されている一方、中小企業やサービス業の一部では長らく低水準のままで推移しています。
加えて、同じ会社でも勤続年数や役職、業績連動型制度の採用状況などによって、個人ごとの受給額に差が生じています。
 ねくこ
ねくこまれに「退職金規定はあるけれど、結局は業績不振で上積みがほとんどない」というケースもあるため、単純な平均値だけでは自分の会社の実態を判断しづらいのが現状です。
確定拠出年金(DC)化と退職金減少の傾向

最近の動きとして注目されるのが、従来の退職金制度から確定拠出年金(DC)に移行する企業が増えていることです。
DCでは、企業が拠出する掛金を従業員が自己運用し、将来的に運用成果に応じて受給額が変わる仕組みになっています。
この仕組みは企業側から見ると負担が読みやすいメリットがある一方、従業員側にとっては「運用リスクが自己責任になる」というデメリットがあります。
 ねくこ
ねくこ結果として、運用次第では従来型の退職金よりも受給額が少なくなる可能性がありますし、企業によっては拠出額自体が少なく、実質的に退職金の目減りに近い形となってしまう場合もあります。
こうした状況から、過去と比べて「退職金は減っているのか?」と問われれば、
というのが実態でしょう。
特に中小企業はそもそも金額設定が低いうえに、不況時の企業業績悪化でさらなる制度改定が行われるリスクも存在します。
iDeCoは退職金がない/少ないサラリーマンや個人事業主に最適!

というわけで、企業にも依ることは確かなものの、退職金に関して社会全体の流れとしては、
- 退職金は総じて減少傾向にある
- 企業・業種によってはなかったり、額に期待ができない
- 企業型DCも運用リスク自体は自分にある
と言えます。
 ねくこ
ねくこやはり、iDeCoをやっておき、退職所得や老後の備えとして準備しておくことが望ましいです。
退職金に恵まれないかもしれない/十分な額ではないサラリーマンはもちろん、厚生年金に加入できない個人事業主もiDeCoは検討した方が良いですよ。
iDeCoは原則60歳まで引き出せない・運用次第で元本割れの可能性がある・手数料がかかるという前提を理解したうえで、『退職金が少ない人ほど控除枠を活用しやすい』利点を検討しましょう。
受給開始は加入年数に応じて60〜65歳以降(上限75歳)です。
iDeCoの基本メリット

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、「掛金が全額所得控除」「運用益は非課税」「受取時にも税制優遇」という三段構えの優遇があるため、老後資金づくりに非常に有利な制度です。
特に、退職金がもともとない企業や、あっても少額しかもらえない方にとっては、iDeCoによる積み立てが実質的に「第二の退職金」になります。
 ねくこ
ねくこたとえば会社員の場合、iDeCoの掛金は拠出するたびにその全額が所得控除に算入できるため、税率が高いほど節税メリットが大きいです。
個人事業主であれば、国民年金しかない状態をカバーする強力な私的年金の仕組みとして役立つでしょう。
退職金が少ない/ない人だからこそ有利な理由

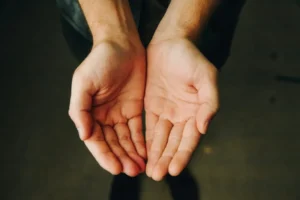
従来、iDeCoの受取時には「退職所得控除(または公的年金等控除)」を最大限に活かすため、退職金との受取タイミングを調整する手法が有名でした。
しかし、そもそも退職金制度がなかったり、支給額が少ない場合、受取時の控除枠をほぼiDeCoだけで占有できるため、課税されるリスクが低くなります。
 ねくこ
ねくこ一方、大企業や高額の退職金を想定している人は「退職所得控除をどれだけ使い切るか」「iDeCoとの合算で課税が増えないようにするか」など、タイミング調整が難しくなるケースがあります。
しかし、退職金が少ない人はそもそも「退職所得控除」の大部分を余してしまう傾向があり、そのぶんiDeCoの一時金受取でより多くの控除メリットを受けられるわけです。
公的年金等控除を活かす「年金受取」もあり
また、iDeCoの受取り方法は、一時金だけではありません。
分割(年金方式)を選択すれば、公的年金等控除の枠内に収まるように受取り額を調整することで、さらに税負担を少なく抑えられる場合があります。
 ねくこ
ねくこ特に退職金が期待できない方にとっては、iDeCoを年金形式で受け取ることで、毎月あるいは年数回の安定した現金収入を得られる点がメリットです。
\編集部おすすめの金融機関はコチラ!/
| iDeCo商品取扱本数 | おすすめな人 | おすすめポイント | 公式サイト | |
 | 38本 | 大手かつ人気があるところで始めたい人 | ・加入者数がトップクラス ・商品ラインナップが豊富 ・人気のeMAXIS Slimシリーズなど低コストファンドが充実 | 詳細を見る |
 | 37本 | 楽天ユーザー | ・楽天ポイントが貯まる ・証券資産と年金資産を1つのIDで管理できる ・サポート体制が厚い | 詳細を見る |
 | 34本 | ゆっくりと相談してじっくり決めたい人 | ・事前予約で店舗相談可能 初心者向けの商品が多め ・コールセンター対応時間が長い | 詳細を見る |
| 27本 | AppleやAmazonなど米国株式投資をしたい人 | ・「NASDAQ100指数」に連動するiDeCo商品が買える ・eMAXIS Slimシリーズなど低コストファンドも選べる ・サポート体制が厚い | 詳細を見る | |
 | 40本 | 迷ったらまずはここ | ・業界最多準のラインナップ ・eMAXIS Slimシリーズなど人気の低コストファンドが豊富 ・ポイントサービス対象 | 詳細を見る |
 | 27本 | auユーザー | ・対象投資信託の保有でPontaポイントがもらえる ・サポート体制が厚い | 詳細を見る |
【Q&A】退職金とiDeCoの疑問に答える
そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
退職金がある企業ってどのくらいあるの?
約8割の企業に退職金制度がありますが、中小企業では制度がない、またはあっても少額なケースが多いです。
企業規模が小さいほど、退職金に期待できない傾向があります。
退職金の支給額は減っているの?
一律に右肩下がりではなく、区分により増減が分かれます。
たとえば定年退職(勤続20年以上・45歳以上)の平均は「大学・大学院卒(管理・事務・技術): 1,983万円→1,896万円(2018→2023)」と低下する一方、「高校卒(管理・事務・技術): 1,618万円→1,682万円」「高校卒(現業): 1,159万円→1,183万円」のように上がった区分もあります。(参考)
確定拠出年金(DC)への移行が進んでいるって本当?
企業型DCの加入者数は 830万人(2024/3末)→ 862万人(2025/3末速報)へ増加』するなど、導入の裾野拡大が確認できます。(制度数も増加傾向)(参考)
退職金がない・少ない人はどうすればいいの?
自助努力での老後資金準備が必要です。
特にiDeCoは
- 「掛金全額所得控除」
- 「運用益非課税」
- 「受取時の税制優遇」
があり、退職金が期待できない人にとって有効な手段です。

退職金が少ない人ほどiDeCoが有利って本当?
はい、控除枠をiDeCoでフル活用しやすいため、税制メリットを最大限に受けられます。
退職所得控除をほぼiDeCoだけで使える点が有利です。
iDeCoの受取方法はどれが得?
- 一時金として受け取れば「退職所得控除」
- 年金形式なら「公的年金等控除」
が適用されます。
退職金がない人はどちらも控除が使いやすく、非課税枠を活かしやすいです。
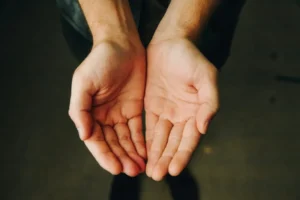
iDeCoは何歳から始めるのがベスト?
早ければ早いほど有利です。
長期の運用で非課税メリットを最大化できるため、30代・40代からのスタートが理想です。
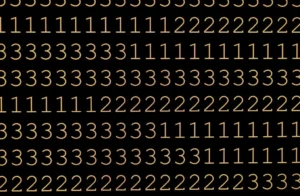
どの金融機関でiDeCoを始めればいい?
- 手数料の安さ
- 商品数
- サポート体制
で選びましょう。
初心者にはeMAXIS Slimシリーズの多いネット証券系が人気です。

今後iDeCoの制度改正があるかも?大丈夫?
制度改正があっても、長期的に見ればiDeCoの税制優遇は依然として魅力的です。
控除ルールが変わっても基本的なメリットは残ると考えられます。
5年ルールはどう変わる?
2026年1月1日以後に支払われる退職手当等から、“10年以内”に重なる退職手当等・DC老齢一時金の勤続期間重複分は控除が調整されます(いわゆる“10年ルール”)。
“5年以上あければOK”という従来の整理は通用しないため、受取時期の計画が重要です。
将来設計のために早めの準備を
今回は以上です。
退職金制度に依存できない場合こそ、早い段階から自助努力による老後資金づくりが不可欠です。
iDeCoならば拠出時点で節税になるうえ、積立が長期にわたるほど運用益が非課税で積み上がりやすくなるメリットがあります。
自営業やフリーランスの方はもちろん、サラリーマンでも
と思う人は、なるべく早期にiDeCoの導入を検討してみることをおすすめします。
 ねくこ
ねくこ今後、制度改正があったとしても、長期的に見ればiDeCoの税制優遇効果は大きな武器です。
「iDeCoの口座をどこで開設するか(金融機関など)」の比較や、受取時シミュレーションを行いながら、自分の働き方・ライフプランに合った形で活用していきましょう!

本記事の数値は厚生労働省『令和5年就労条件総合調査』(2023/10/31公表)を中心に作成しています。企業規模・業種・就業形態により大きく異なる点に留意してください。
本記事は一般的な情報提供であり、特定商品の推奨・投資助言ではありません。制度・税制は改正される可能性があり、最新の公式情報(国民年金基金連合会・厚生労働省・財務省/国税庁・金融庁)をご確認のうえ、必要に応じて税理士等へご相談ください。











