え、NISAの利確で扶養から外れてしまう?配偶者の収入で運用する際の贈与税リスクと社保扶養から外れる可能性

2024年から始まった「新NISA(少額投資非課税制度)」は、専業主婦(夫)の方にとっても魅力的な資産運用手段です。
中には、配偶者の収入の一部を使ってNISAで投資を始めようと考える方もいらっしゃると思います。


しかし、「NISAで利益を出すと扶養から外れてしまうの?」「夫のお金で妻名義のNISAを運用すると贈与税がかかるって本当?」と不安に感じていませんか。
結論、NISA口座内で非課税となる配当・譲渡益は合計所得金額に算入されないため、原則、配偶者控除等の判定に影響しません(※配当は「株式数比例配分方式」での受取が非課税要件)
一方、社会保険の被扶養者認定においては「今後1年間の見込み年収」で判断され、NISAなど利子・配当など非課税のものも“収入”に含むのが一般的運用※です(税法上の「所得」とは概念が異なる)
※ 健康保険の被扶養者判定では“向こう1年の見込み年収”で判断し、利子・配当なども収入に含む運用例が多いとされています(保険者基準により判断)
さらに、夫婦間で資金移動してNISA投資を行う場合、贈与税のリスクにも注意が必要です。
本記事では、NISAで運用益が出た場合の税法上の扶養への影響と社会保険上の扶養条件の違いを詳しく解説し、専業主婦(夫)が安心してNISAを活用するためのポイントを紹介します。
また、配偶者の資金で妻がNISA運用をする際の贈与税リスクについても触れ、扶養内で賢く資産運用する方法や代替の選択肢について考えてみましょう。
 ねくこ
ねくこ扶養とNISA運用に関しての知識を身につけ、資産形成を進める参考にしてください。
重要な留意事項
本記事の解説は一般的な取扱い(原則)を示したもので、加入している健康保険組合・協会けんぽ等や個別事情により例外や異なる判断となる場合があります。具体的な適用可否や手続の要否は、加入健保および所轄税務署・税務相談窓口で最新基準を必ずご確認ください。
また、NISAの非課税適用は口座内での配当・譲渡益等に限られ、配当の受取方法(例:株式数比例配分方式)などの要件を満たさない場合は結果が異なることがあります。
投資には価格変動リスクがあり、元本は保証されません。手数料・税制・制度は今後変更される可能性があります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
税法上の扶養控除とNISA利益|配偶者控除への影響は?
まず、税法上の「扶養」について整理しましょう。
税法上の扶養とは、所得税や住民税における「配偶者控除」や「扶養控除」の対象になるかどうかという意味です。
配偶者控除を受けるには、配偶者の合計所得金額が58万円以下であることが必要です(給与所得のみの場合、これは年収123万円以下に相当します)。

NISAの運用で得た利益は非課税扱い※となるため、この合計所得金額には含まれません。
※ただし、配当受取が銀行振込等の場合は課税となり、還付不可の取扱い例があります。受取方法は権利確定日前に株式数比例配分方式へ設定ください。
そのため、受け取りを株式数比例配分方式へ設定しているNISAでどれだけ利益を出しても、原則としてその利益が原因で配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまうことはありません。
実際、国税庁も「配偶者や親族の合計所得金額にNISAによる譲渡益や配当金は含めないため、配偶者控除や扶養控除の判定に影響しない」と明言しています(出典)。
例えば、専業主婦のAさんが新NISAで年間50万円の利益を得たとしても、その50万円は非課税所得でありAさんの合計所得金額には算入されませんし、もちろん、たとえ年間500万円の利益があっても同様です。
したがって、Aさん自身に他の課税所得がなければ、ご主人は引き続き配偶者控除を受けることができます。
 ねくこ
ねくこ税法上の扶養の範囲内でNISA運用益がどれだけあっても株式数比例配分方式へ設定していれば、原則として非課税という点は、まず押さえておきましょう。
社会保険上の扶養とNISA収入|130万円の壁※に注意

次に、社会保険上の「扶養」について見ていきます。
こちらは健康保険や厚生年金における扶養家族の認定基準の話です。
一般的に被保険者(ご主人など)の扶養に入るには、妻の年間収入が130万円未満※であること(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)が基準となります。
※2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の扶養家族については、扶養から外れる年収要件が130万円から150万円に引き上げられました。
また、勤務先の社会保険適用拡大・106万円超えの労働条件などによって、130万円未満であっても扶養から外れる可能性が生じる場合があります。
ここでは便宜上「130万円の壁」として記載しています。
注意したいのは、この「年間収入」には課税・非課税を問わず広く含まれるという点です。
 ねくこ
ねくこつまり、NISAで得た運用益も、社会保険の扶養判定では収入として考慮される可能性が高いのです。
あくまで「扶養に入れる/入れない」可能性は利確した際の問題
NISAの「含み益」(未実現利益)だけでは、社会保険上の収入にはカウントされないため随時心配する必要はありません。
つまり、利確(=売却して実際に利益が確定)した時点、または配当金を受け取った時点で初めて「収入」として扱われる可能性が生じます。
利子・配当収入は収入に含む※
※ 売却益は“継続的に利確”して定常的に生じるなら収入とみなされやすい、一方で単発の売却益は“一時的収入”として除外されうる。最終判断は各保険者の基準で確認。
社会保険の扶養判定では、「収入」という言葉が税法上の「所得」と異なり、給与や事業収入はもちろん、利息や配当などの非課税収入も含めた総収入額で判断されます。
さらにポイントとなるのが収入の継続性です。
 ねくこ
ねくこ例えば、一度きりの臨時ボーナスや退職金、一度限りの資産売却益などは「一時的な収入」として扱われ、扶養判定から除外される場合があります。
継続的な収入とみなされやすいもの
| 区分 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 株式・投資信託の配当金・分配金 | 年複数回の配当・分配を継続して受け取っている場合 | 毎年定期的に入金があるため「恒常的収入」と判断されやすい。非課税でも「実際の収入」として扱う健保が多い。 |
| 株式・投信の売却益(定期的に利確) | 毎年または定期的に利益確定している | 投資活動が継続して行われているとみなされ、「継続性あり」と判断されやすい。 |
| 不動産収入・駐車場収入 | 定期的に入金がある | 契約に基づく継続的収入のため、ほぼ確実に対象。 |
| 事業収入・副業報酬 | 定期的に依頼・報酬がある | 継続性が明確なため、扶養判定では収入扱い。 |
| 利息収入(定期預金など) | 金額が少額でも毎年発生 | 少額でも恒常的収入と判断される場合がある。 |
一時的収入とみなされやすいもの
| 区分 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 一度きりの株式・投信の売却益 | 相続株・記念株などを一度だけ売却 | 継続性がないため「一時的収入」として除外されることが多い。 |
| 退職金・賞与・慰労金 | 退職時・一時的支給のみ | 一時的収入として除外される。 |
| 相続・贈与による財産取得 | 遺産・贈与金など | 「収入」ではなく「財産移転」であり、原則扶養判定の対象外。 |
| 宝くじ・懸賞金・臨時の保険金 | 偶発的収入 | 継続性がなく「収入」に含めない。 |
| 特定の資産を売却して終わり | 不動産や車の単発売却など | 一度限りのため除外されやすい。 |
NISAは「継続的な投資による利益」として継続性が認定されるケースが多い※
しかし、株式の配当金や継続的な投資による利益は「継続性のある収入」と見なされるケースがあるため※注意が必要です。
※ 配当や定期的な利確などは“継続的収入”と判断される例がある一方、単発の売却益は“一時的”として除外される場合もあります。最終判断は保険者の基準をご確認ください。
実際、ある健康保険組合では収入の考え方として「利子・投資収入(預貯金利子、有価証券利子、株式配当金等)は継続性のある収入」に分類されていました。
また、株式の売買益についても、年間で複数回売却して利益を得ている場合や継続的に保有して運用している場合は恒常的収入と判断されるケースが多いようです。
 ねくこ
ねくここのように、何をもって“一時的”とするかは各保険者の基準によりますので、自身の加入している健康保険の取扱いを確認することが大切です。
NISA運用益で扶養から外れる可能性と判断タイミング

では、具体的にNISAの運用益で扶養から外れるケースはどのような場合でしょうか。
先述のとおり、多くの健保組合では年間の継続的収入が130万円以上※になる(今後1年の見込みが基準額以上になる)と、翌年はもちろん超えた年の途中でも非該当(扶養解除)となる取扱いが一般的です。
※2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の扶養家族については、扶養から外れる年収要件が130万円から150万円に引き上げられました。
また、勤務先の社会保険適用拡大・106万円超えの労働条件などによって、130万円未満であっても扶養から外れる可能性が生じる場合があります。
ここでは便宜上「130万円の壁」として記載しています。
例えば、専業主婦のBさん(ご主人が会社員で社会保険の加入者)が株式運用(NISA含む)で今年合計140万円の利益や配当収入を得た場合、Bさんは来年1月以降、ご主人の健康保険の扶養資格を失う可能性が高いです。
その場合、Bさん自身が国民健康保険へ加入し直し、国民年金保険料も自分で支払う必要が生じます(健康保険料・年金保険料の自己負担が年間で数十万円発生するイメージです)。
一時的なら扶養継続が当面認められるケースはあるが、投資収入は原則対象外
最近の制度改正で「年収の壁問題」緩和策も一部導入されており、一時的な収入変動に係る事業主の証明により、当面の対応として扶養継続が認められる運用があります。
しかし、このケースは投資収入は原則対象外となっており、雇用による一時的増収が対象です。
例えば、短時間労働者が一時的に年収130万円を超えても、事業主の証明があれば連続2年まで扶養継続を認める特例が2023年10月から施行されています。
もちろん“恒常的に基準超え”は対象外で、“3年連続超過”が確認されれば解除の運用も示されています。
 ねくこ
ねくこどの道、専業主婦(夫)である場合は「雇用主による証明」という形が取れないため、基本的には自身の収入見込みベースで判定される点に注意しましょう。
扶養内で運用を続けたい場合、年間の収入見込みを130万円未満に
結局のところ、扶養内で運用を続けたい場合、年間の収入見込みが130万円未満に収まるよう調整することが求められます。
具体的には、
- 毎年の利益確定(利確)は少額にとどめ、大きな売却益は複数年に分散する
- 高配当株より長期的な値上がり益狙いの投資信託を中心にして年間の配当収入を抑える
- そもそも長期運用で利確は一度きり
といった戦略や工夫も有効でしょう。
 ねくこ
ねくこ疑問があれば加入している健康保険組合等にNISAの利益の取り扱いについて事前に相談することをおすすめします。
健保によっては「NISA口座の利益については収入認定しない」など独自の判断を示している場合もある※ため、必ず個別のケースで確認することが安心です。
※ 取扱いは保険者ごとに細部が異なるため、加入健保の被扶養者認定基準で必ずご確認ください。
夫の資金で妻のNISA運用|贈与税と名義預金リスクに注意
専業主婦(夫)がNISAを利用する際、実際の投資原資(元手)は誰のものかという点にも目を向けましょう。
もし、本人が独身時代からの貯金など自分の資金でNISA投資を行うなら何も問題ありません。
しかし「生活費をやり繰りして捻出したお金」や「配偶者からもらったお金」で本人名義のNISA口座に投資する場合、贈与税の問題が潜んでいます。

生活費・教育費は“その都度・直接充当”なら非課税/預金・株式購入に回すと課税対象

税法では、夫婦間であっても金銭を無償で渡せば原則として贈与税の課税対象になります。
扶養義務者間(配偶者や親子など)でも、通常必要と認められる生活費や教育費としてその都度渡す範囲であれば贈与税はかかりません。
しかし、「生活費の援助だよ」とまとめて渡したお金や、生活費として受け取ったお金を使い切らずに預金や投資に回してしまった場合は話が別※です。
国税庁も「生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産の購入資金に充てた場合には贈与税がかかる」とはっきり示しています(出典)。
※ 生活費・教育費は“都度・直接充当”のみ非課税。預金・投資に回すと贈与税課税(基礎控除の範囲外なら申告要)。

 ねくこ
ねくこつまり、夫が妻に「将来のために」と100万円を渡し、それを妻がNISA口座で株購入に使った場合、その100万円は贈与税の非課税範囲を超えれば課税対象となり得るのです。
贈与税の基礎控除は年間110万円まで
贈与税にはご存じのとおり年間110万円までの基礎控除(非課税枠)があります。
一暦年(1月~12月)で受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず申告も不要ですが、逆に言えば、夫から妻への資金提供が年間110万円を超える場合は贈与税の申告が必要になります。
例えば、専業主婦のCさんが毎月ご主人から生活費とは別にNISA投資用資金5万円を受け取っていたとします。
この場合、年間で60万円となり贈与税の範囲内です。
ただし、ご主人以外からの贈与も合わせて年110万円を超えると課税対象になる点には注意が必要です(一般的には夫からの支援だけでしょうが、念のため)。
一方、NISA枠が拡充されたからと夫が一度に300万円を妻の口座に入金して投資させたようなケースでは、その年は110万円を大きく超える贈与となり、所定の贈与税申告と納税が必要になります。
「夫婦のお金は共有財産なのだから、やり取りしても贈与にならないのでは?」と思うかもしれません。
しかし法律上、夫婦であっても資産の名義人が変われば贈与とみなされます。
 ねくこ
ねくこ特に専業主婦名義の預金は、税務調査で夫からの名義預金と判断されるリスクも指摘されています。
たとえ夫婦間でも計画的な資産移転には税務上の配慮が必要だということを覚えておいてください。
名義預金とは口座名義人と実際のお金の所有者が異なる預金のことで、生前に適法な贈与が行われていない場合、亡くなった時に実質的に被相続人(夫)の財産とみなされ相続税の課税対象になる可能性※があります。
※ 資金拠出者が夫等で管理実態がある“名義財産”は被相続人の財産と認定され、相続税申告対象(国税庁の誤りやすい事例参照)。
夫婦間の資金移動でトラブルを避けるには、「毎年110万円以内の範囲にとどめる」「どうしても大きな額を渡す場合は贈与契約書を交わす」などの対策が有効でしょう。
専業主婦が新NISAを活用するコツと代替手段
以上の点を踏まえると、専業主婦の方でもルールに注意しながらNISAを活用すれば大きな問題は避けられることが分かります。
 ねくこ
ねくこ扶養内でNISAを賢く運用するためのポイントや、併せて検討したい資産運用の代替手段について整理してみましょう。
扶養範囲内の収益に抑える運用計画を立てる

社会保険の扶養条件(年収130万円未満)を維持するには、毎年の利益確定タイミングや配当収入を調整することが重要です。
例えば新NISAでは年間最大360万円まで投資可能ですが、一度に大きな売却益を出すとその年の収入が跳ね上がります。
長期投資を心がけ、大きな利益確定は複数年に分散する、もしくは受取を60歳以降(年収180万円未満に拡大される)まで先送りするなど工夫しましょう。
また、高配当株で毎年数十万円の配当を得るよりも、無配当の成長株や再投資型の投資信託で値上がり益を狙えば、年間のキャッシュ収入を抑えることができます。
 ねくこ
ねくこいずれにせよ、「今後このくらいの運用益が継続しそうだ」と判断されれば扶養認定に響くため、収入見込みが基準内に収まるラインで運用することが大切です。
「株式数比例配分方式」を選ばないと、NISA保有株の配当でも課税になる
NISA口座で株式の配当金を受け取る際は、必ず「株式数比例配分方式」を選択しておきましょう。
この方式に設定すれば、NISAで保有する株やETFの配当金が証券口座経由で非課税扱いで支払われます。
逆に「配当金領収証方式」や「銀行口座振込(登録配当金受取口座)方式」のままだとNISA口座の株であっても税金が源泉徴収されてしまい、せっかくの非課税メリットを受けられません。
「株式数比例配分方式」を選ばないと、NISA保有株の配当でも課税になります(後から還付不可の取扱いが一般的)。
 ねくこ
ねくこ権利確定日までの設定変更が必要で、配当受取方法の変更は証券会社で手続きが可能です。
忘れずに証券会社へ確認をしてください。
夫婦でNISA枠をフル活用する
本人が扶養内で投資額や利益をセーブしなければならない場合、配偶者側のNISA枠を最大限活用することも検討しましょう。
NISAは一人一口座までですが、夫婦でそれぞれ口座を持てば非課税投資枠は2倍になります。
もし妻がご主人からの資金提供に制限があるなら、代わりにご主人自身の収入でご主人名義のNISA枠を使ってもらう手があります。
こうすれば贈与税の問題も回避できますし、世帯全体としての非課税運用枠をしっかり使うことができます。
 ねくこ
ねくこ配偶者の年収が高い場合でもNISAの運用益自体は非課税なので、税金面で不利になることはありません(むしろ世帯合算では夫婦2人分の非課税枠を活かせるメリットがあります)。
iDeCoなど他の制度も活用検討
専業主婦(夫)(第3号被保険者)の方はiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入することも可能です。
毎月の掛金上限は専業主婦の場合月2.3万円まで(年27.6万円)で130万円の収入枠には影響しませんから、老後資金作りとして余裕資金があればNISAと併用するのも一案です。

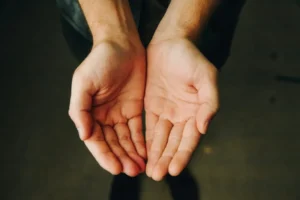
【Q&A】新NISAと扶養・贈与税の疑問に答える
そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
NISAで利益を出すと扶養から外れてしまうの?
税法上の扶養には原則影響しませんが、社会保険上は影響する可能性があります。
税法上はNISA口座内の配当・譲渡益は合計所得金額に算入されず配偶者控除などの判定に影響しません。
一方、社会保険の被扶養者認定は「今後1年の見込み年収」で判断し、非課税の利子・配当等も“収入”に含める運用が一般的です。
NISAの利益は配偶者控除(税法上の扶養)に影響する?
影響しません。
NISA口座内の配当・譲渡益は非課税で合計所得金額に含めないため、配偶者控除・扶養控除の判定から除外されます(配当は「株式数比例配分方式」での受取が非課税条件)。
社会保険の扶養判定ではNISAの利益は収入に含まれるの?
含まれる運用が多いです。
健康保険の被扶養者認定は非課税か否かを問わず“収入”で見るため、利子・配当等は収入に含める運用例が一般的です。
売却益も継続的に利確していれば収入扱いされやすくなります。
いつの時点で“収入”とみなされるの?(含み益は?)
利確や配当の受取時点です。
含み益(未実現利益)は収入に含まれません。
売却して利益が確定した時や配当を受け取った時に初めて収入として扱われる可能性が生じます。
どれが“継続的収入”で、どれが“一時的収入”?
配当や定期的な利確は“継続的”、単発の売却益などは“一時的”になりやすいです。
年複数回の配当・分配や毎年の利確は恒常的収入と判断されがち。
一度限りの売却益や退職金・懸賞金などは一時的収入として除外されうるかは保険者基準で判断されます。
NISA運用益で扶養から外れるのはどんな場合?
継続的収入の見込みが基準額(多くは年130万円、条件により180万円等)を超えると外れる可能性が高いです。
今後1年間の見込み年収で判定され、基準超えが見込まれれば年途中でも扶養解除となる取扱いが一般的です。
年収の壁の緩和策は投資収入にも使えるの?
原則使えません。
一時的増収の特例は雇用による賃金増を想定しており、投資収入は対象外とされています。
専業主婦(夫)は基本的に自身の収入見込みで判定されます。
扶養内でNISA運用を続けるにはどう調整すればいい?
年間の収入見込みが基準未満に収まるよう、利確や配当を抑える運用にします。
大きな利確は複数年に分散し、高配当中心よりも値上がり重視の商品でキャッシュ収入を抑える等が有効です。
基準や判断は加入健保の取扱いを必ず確認しましょう。
NISAの配当はどの受取方法なら非課税になる?
「株式数比例配分方式」です。
この方式に設定すればNISA保有分の配当が証券口座経由で非課税に。
銀行振込や配当金領収証方式のままだと源泉徴収され、原則後からの還付はできません。権利確定日前に証券会社で設定を。
口座開設の手順と必要書類は?
オンライン申込→本人確認→審査→ログイン・入金の流れです。
マイナンバー関連+本人確認書類(運転免許証等)を提出し、審査完了後に入金して取引開始、並行してデモ活用が有効です。
夫のお金で妻名義のNISAを運用すると贈与税がかかるって本当?
基礎控除(年110万円)を超える資金移動は贈与税の対象になり得ます。
生活費・教育費は“その都度・直接充当”なら非課税ですが、預金や投資に回すと贈与課税の対象。
夫婦間でも名義が変わる資金移転は贈与とみなされます。
専業主婦(夫)はiDeCoも使える?NISAと併用できる?
使えますし、併用も可能です。
第3号被保険者はiDeCoに加入でき、掛金は収入扱いではありません(運用益は非課税、受取時は課税方式あり)。
60歳まで引き出せない点に留意しつつ、NISAと併用して老後資金づくりに活用できます。
終わりに|扶養とNISAのルールを正しく理解して安心運用を
NISAの利確で扶養から外れるかどうかという疑問について、税法上は原則、配偶者控除等の判定に影響しません(※配当は「株式数比例配分方式」での受取が非課税要件)が、社会保険上は注意が必要という結論になりました。
健康保険など社会保険上の扶養認定ではNISAを含む収入も年収に含めて判断される場合があるため、継続的な投資収入が年間130万円の基準を超えると扶養から外れる可能性があります。
また、夫婦間で資金を融通して投資する場合は贈与税の基礎控除(110万円)を意識し、場合によっては適切な手続きや対策を取る必要があります。
とはいえ、これらのポイントさえ押さえておけば、専業主婦の方でも怖がることなくNISAを活用できるでしょう。
扶養内であっても賢く制度を利用し、ご夫婦で協力して資産形成を進めていくことは十分可能です。
「非課税枠」というNISAのメリットを最大限に享受しつつ、扶養の範囲も意識した計画的な運用を心がければ、将来に向けた大切な資産づくりを安心して継続できます。
 ねくこ
ねくこぜひ本記事の内容を参考に、扶養とNISAのルールを正しく理解した上で、ご家庭に合ったベストな運用スタイルを見つけてください。

















