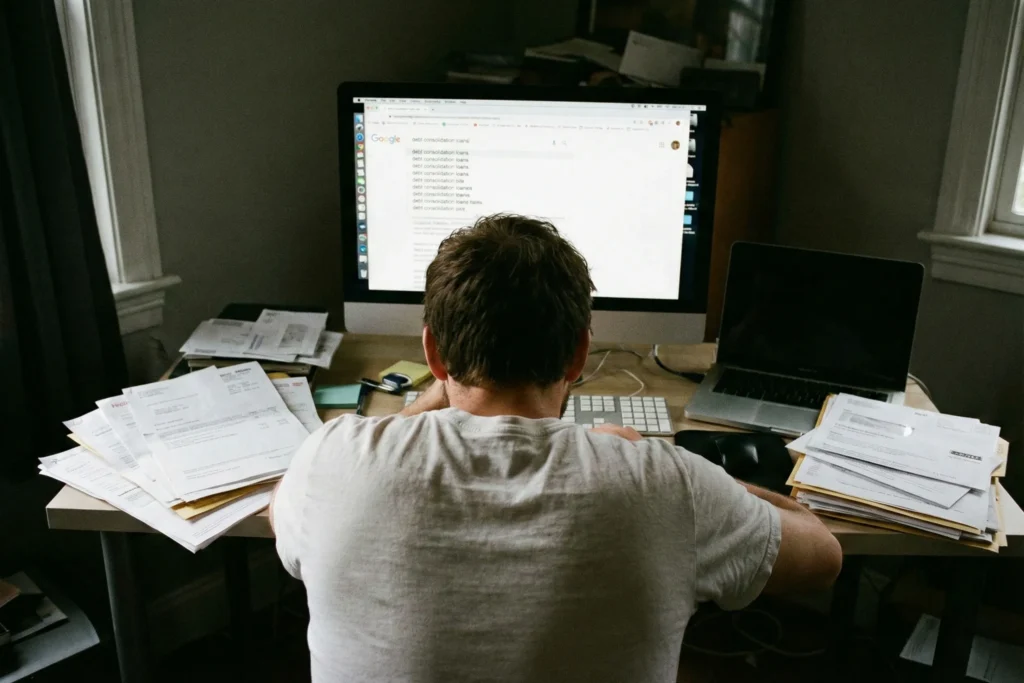【2025年8月5日】の経済・時事ニュースまとめ

8月に入って初めての火曜日となる8月5日、国内外の金融市場は先週末の乱高下を経て持ち直しの動きを見せています。
日本では最低賃金の大幅引き上げ目安が提示され、日銀議事要旨からは通商問題の行方次第で利上げ再開の可能性も示唆されました。
一方、海外では米株3指数が急反発し、英国やEUでも金融・規制面の動きが活発です。
 ねくこ
ねくこここでは午前10時時点の主要指標と、過去24時間に報じられた注目ニュースを分かりやすく整理します。
主要株価指数・為替レート(8月5日 午前10時時点)
| 指数 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 40,505.92円 | +215.22 (0.53%)円 |
| NYダウ | 44,173.64ドル | +585.06 (1.34%)ドル |
| S&P500 | 6,329.94ポイント | +91.93 (1.47%)ポイント |
| ドル円 | 147.08 円 | +0.28円 |
日経平均株価と為替の動向
午前の東京市場は米国株の急反発を好感し、日経平均が3日ぶりに反発してスタートしました。
輸出企業の採算改善余地がやや縮小するものの、株価には米国主導のリスクオンが追い風となっています。
 ねくこ
ねくこFRBの早期利下げ観測が再燃したことで米金利上昇が一服し、リスク資産が買い戻されています。
日本時間今晩発表される米JOLTS求人件数や、週後半に控える米CPIの結果によっては、円高進行が再拡大する可能性があります。
米国株式市場の背景
ダウ平均は585ドル高と金曜日の下げをほぼ帳消しにしました。
半導体セクターの好決算に加え、弱い雇用統計による利下げ期待が相場を押し上げました。金曜日比でS&P500は+1.5%としっかり反発し、テクノロジー株中心のナスダックも2%高と先導役を果たしました。
木曜日の対中追加関税発動期限を巡る報道次第では再びボラティリティが高まる余地があります。
為替市場の焦点
ドル円は昨日の円高傾向から円安方向へ推移。
昨日は日銀議事要旨で一部委員が利上げ再開に含みを残したことが円買い材料となっていましたが、下げ渋りが起こり147円台に持ち直しています。
今の市場局面で資産運用者が心掛けるべきこと
8月は海外勢の休暇入りで流動性が細りやすく、米国株・日本株ともに値動きがぶれやすい時期とされています。
楽観が続くときほど突然の調整に備える姿勢が重要です。
TOPIXなど広範指数は昨夏の急落を経てファンダメンタルズ主導の上昇基調を維持していますが、短期過熱感には注意が必要です。
長期・分散・積立の徹底
価格変動が大きい局面でも、NISAの年間投資枠を活用した積立投資を止めないことで平均取得単価を平準化できます。

つみたて投資枠の有効活用
円高時は外貨建て資産を多く含む投信を継続購入することで、円ベースの取得コスト低減が狙えます。
成長投資枠とリスク許容度
一括投資を検討する場合でも、資金を数回に分ける時間分散で突発的な下落への耐性を高めましょう。

為替ヘッジとFXの位置付け
FXで短期売買を行う場合は、円高方向へのボラティリティが高まる夏場こそロットを抑え、損切り水準を明確に設定してください。

国内外株式
円ベースで海外ETFが割安になるケースがあり、ドルコスト平均法での追加購入が有効です。
金利上昇局面でも安定配当を続ける銘柄は、インカムゲインの土台として機能します。
債券と預金
債券と預金はインフレ率連動部分があるため、実質価値を守りやすい点がメリットです。
円高で輸入物価が落ち着く間は現金比率を高め、次の投資機会に備える余地を残しましょう。
オルタナティブ・分散投資
米利下げ観測が再燃すると金は相対的に買われやすく、ポートフォリオの緩衝材になります。
インフレ下でも実物資産の収益配分が期待でき、キャッシュフロー安定化に寄与します。

固定費を点検し変動費とのメリハリを
家計管理アプリ「マネーフォワードME」が8月5日から月額料金を値上げするように、サブスク費用は意識しないうちに膨らみがちです。


生活費6か月分程度を安全資産で確保し、残りをリスク資産に振り向ける比率を再確認しましょう。
急落時に備えて段階的に買い下がる買付余力を残すことが心理的ゆとりにつながります。
まとめ
マーケットの不確実性が高まるほど、投資の成功要因は「継続できる仕組み」にあります。
制度を活用しつつリスクを抑え、生活基盤を整えたうえで長期視点の資産形成を進めましょう。
国内ニュース
最低賃金引き上げ目安を提示
厚生労働省の中央最低賃金審議会は、全国加重平均63円引き上げ(+6.0%)の目安を示しました。
引き上げ後の平均は1,118円となり、制度開始以来最大幅の上昇見込みです。
物価高対応と賃上げの流れを地方へ波及させることが目的で、石破内閣は「実質賃金の底上げ」を掲げます。
人件費増によるコスト転嫁が難しい中小・小規模企業では、価格改定や業務効率化が急務となりそうです。
日銀議事要旨:再利上げの含み
6月会合の議事要旨によると、複数の政策委員が「通商摩擦が緩和すれば年内にも利上げ再開が検討可能」と発言しました。
物価と賃金の上昇が想定を上回る一方、米中摩擦が実体経済を下押しするリスクが残るため、政策柔軟性を確保した形です。
長期金利は0.5%前後で安定しているものの、先物市場では来春の追加利上げ織り込みがじわり進んでいます。

トヨタ、4–6月期32%減益見通し
トヨタ自動車は7日発表予定の決算で営業利益が前年同期比32%減となるとの見方が浮上しました。
円高進行と原材料コスト増が要因です。円高による採算悪化は他の輸出型メーカーにも波及する恐れがあります。
同社株は年初来−13.4%と日経平均を大きく下回り、決算への警戒感が高まっています。
海外ニュース
英国:利下げ検討もインフレ高止まり
英中銀は政策金利を4.25%から4.00%へ引き下げる可能性を探る一方、コアインフレ3.6%と高止まりが続き判断が難しくなっています。
経済減速を防ぐための利下げが、賃金インフレを助長する危険性を中央銀行は警戒しています。
住宅ローン金利や光熱費が依然高水準にあり、消費マインドが冷え込むリスクが指摘されています。
中国製造業:ASEANシフト見直し
米国の新関税(最大40%)を受け、中国企業は東南アジアへの生産移管戦略を再考しています。コストや不確実性の高さから中国回帰の動きもみられます。
電子部品や繊維など、従来ASEAN展開が進んでいた分野で再調整が進行中です。
関税長期化の場合、ベトナム・タイなどの輸出拡大期待が後退し、域内景気の下振れ要因となる可能性があります。
EU AI Act、罰則適用開始
EUではAI Actの監督体制が今月始動し、違反企業には最大€35Mまたは売上高7%の罰金が科されます。
安全・透明性の確保と域内スタートアップ保護の両立を図るのが目的です。
EU向けサービスを提供する企業は、モデル開示やリスクアセスメント対応が急務となります。
私たちの生活に起こること
最低賃金の大幅アップはパート・アルバイト世帯の所得押し上げ効果が期待される一方、零細企業では価格転嫁が難しく雇用調整につながる懸念もあります。
為替が円高方向に振れれば輸入品・海外旅行費用は抑えられますが、輸出関連企業の賃上げ余力を削ぐ恐れがあります。
 ねくこ
ねくこ個人としては、生活費の固定化を避け変動費を意識的に抑えつつ、分散投資や時間分散を基本とする長期的な資産運用を続ける姿勢が重要です。
高金利通貨やテーマ株など値動きの大きい商品に偏りすぎないよう、あらためてリスク許容度を点検しましょう。