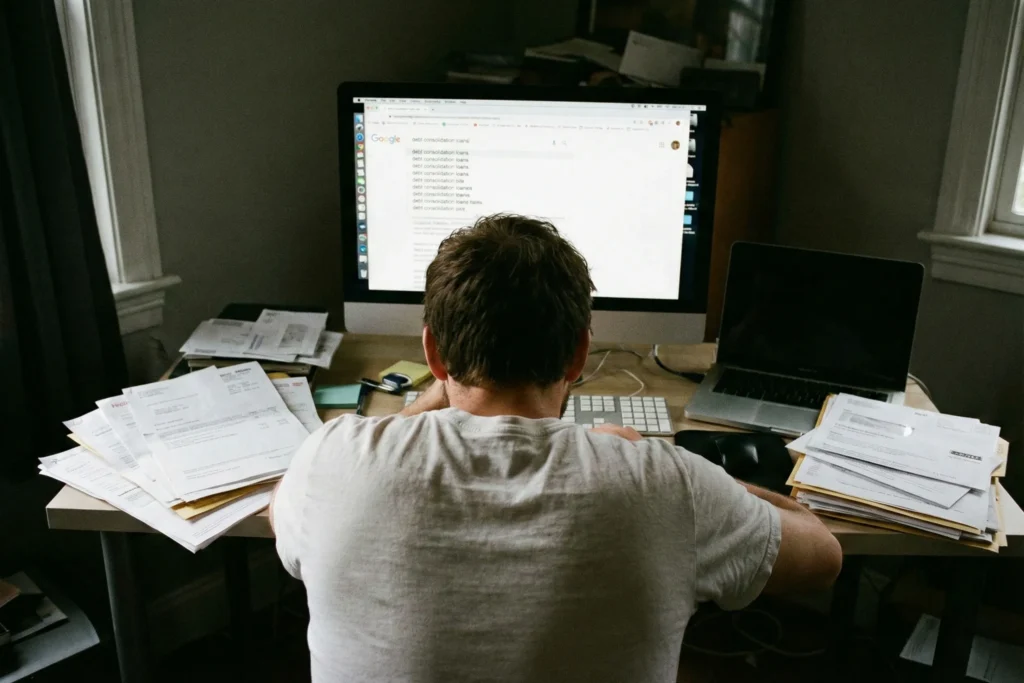2025年10月からどう変わる?改正育児・介護休業法のポイント

2025年10月1日から、働くパパ・ママに嬉しい育児・介護休業法の改正が施行されます。
この改正では、小さな子どもを育てながらでも無理なく働き続けられるよう、企業に柔軟な働き方の制度整備が義務付けられました。
また、従業員一人ひとりの状況に合わせて希望を聞き取る仕組みも強化され、会社側から個別に制度の案内や意向確認を行うことが義務化されます。
この記事では、この改正内容について、特に「時短勤務にしようかな?」「テレワークができたら助かる」といった思いや検討をしている本人や配偶者の方に関係するポイントをわかりやすく解説します。
 ねくこ
ねくこ改正で導入される柔軟な働き方の選択肢や対象者、企業と従業員の対応、制度ごとの特徴や活用シーン、さらに会社からの周知や申請のタイミングなど、読めば自分に合った働き方のヒントが見つかるはずです。
柔軟な働き方を実現する、改正育児・介護休業法5つの制度とは

2025年10月改正の目玉となるのが、「柔軟な働き方を実現するための措置」(選択制措置)です。
これは企業が従業員の仕事と育児の両立を支援するために導入すべき制度で、法律上あらかじめ5種類提示されています。
企業はこの5つの中から少なくとも2つ以上を選んで就業規則などで制度化する義務があります。
対象となるのは3歳以上~小学校就学前の子どもを育てる全ての従業員で、企業規模の大小に関わらず適用されます。
従業員は、会社が用意した2つ以上の選択肢の中から自分に合った制度を1つ選んで利用できるようになります。
 ねくこ
ねくこでは、その5つの制度とは具体的にどのような内容なのでしょうか。
それぞれの概要を見てみましょう。
① 始業・終業時刻の変更(時差出勤・フレックスタイム制)
始業・終業時刻の変更は、1日の総労働時間を変えずに働く時間帯を調整できる制度です。
例えば、時差出勤では通常より早め・遅めの始業や終業を選べますし、フレックスタイム制ならコアタイム以外で自由に始業・終業時刻を決めて働くことが可能です。
これにより、「保育園への送り迎えに合わせて出社時間を遅らせたい」「子どもを寝かしつけてから残りの仕事をしたい」といったニーズに応えられます。
 ねくこ
ねくこ勤務時間帯をずらすことで育児と仕事の両立を図りたい方に適した柔軟勤務の選択肢です。
② テレワークの導入(月10日以上利用可)

テレワーク等は、在宅勤務など会社以外の場所で働ける制度です。
改正法では、1か月に10日以上の在宅勤務等ができる体制を整えることが求められており、かつ時間単位での利用も可能にする必要があります。
通勤時間を短縮できるため、朝夕の送迎や家事の時間を確保しやすくなるメリットがあります。
職種や業務内容によってテレワークが許される場合、育児中の従業員にとっては非常に有効な制度と言えるでしょう。
 ねくこ
ねくこ「子どもが小さいうちは週数日は在宅勤務にしたい」「子どもが病気の日は自宅で仕事ができると助かる」という方に向いています。
③ 保育施設の設置・運営等(ベビーシッター費用補助など含む)
保育施設の設置運営等は、企業が従業員のために保育サービスを提供または支援する制度です。
具体例として、社内に託児所を設けたり、提携する保育施設を用意したり、あるいはベビーシッターの手配や費用補助を行うことなどが挙げられます。
保育園の送迎時間に縛られず職場で安心して子どもを預けられれば、長時間の勤務や急な残業にも対応しやすくなります。
また、待機児童問題で保育園が見つからない場合でも会社の支援で保育サービスを確保できれば、育児と仕事を両立しやすくなるでしょう。
 ねくこ
ねくこ特に「身近に預け先がなく働きづらい」「保育料の負担が大きい」と悩む家庭にメリットの大きい制度です。
④ 養育両立支援休暇の付与(年10日以上、時間単位取得可)
養育両立支援休暇は、子育て中の従業員が取得できる特別な有給・無給休暇制度です。
年次有給休暇とは別枠で年間10日以上取得できる休暇を会社が与えるもので、時間単位での取得も認められます。
これは育児のための休みを取りやすくするための新設制度で、子どもの学校行事や予防接種、急な発熱対応など幅広い用途に使えることが想定されています。
「子の看護休暇」(子どもが病気の際に取る休み)は従来からありますが、養育両立支援休暇は病気に限らず育児全般に利用できる柔軟な休暇です。
 ねくこ
ねくこ例えば「入園式に出席したい」「夏休みに子どもと過ごす日を作りたい」といった希望も、この休暇を活用して叶えやすくなるでしょう。
年にまとまった休暇取得が難しい場合でも、時間単位で細切れに取得できるため、勤務の合間に学校行事へ参加することも可能です。
⑤ 短時間勤務制度(1日6時間勤務など)

短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を短縮して働ける制度です。
一般的には1日あたり6時間程度に勤務時間を減らすケースが多く、いわゆる「時短勤務」として広く知られています。
従来、育児・介護休業法では3歳未満の子を養育する労働者に短時間勤務の権利が保障されていましたが、今回の改正で企業はこの短時間制度を選択肢の一つとして小学校就学前まで拡大提供することも可能になります。
時短勤務を利用すれば勤務時間が短くなる分、保育園や幼稚園のお迎えに間に合いやすくなったり、子どもと過ごす時間を増やしたりできます。
 ねくこ
ねくこフルタイム勤務が難しいご家庭や、「しばらくは収入より育児時間を優先したい」と考える方に適した制度と言えるでしょう。
企業は以上5つの内、2つを導入しなければならない
| 制度の種類 | 主な内容 | 活用が向いているケース |
|---|---|---|
| 始業・終業時刻の変更 (時差出勤・フレックス) | 1日の労働時間は変えず、勤務開始・終了時刻をずらせる。 | 出退勤時間を調整して育児したい(例:送り迎えに合わせて遅め出社)。 |
| テレワーク(月10日以上) | 在宅勤務など会社以外で働ける。時間単位の利用も可。 | 自宅で働ける環境があり、通勤時間を育児に充てたい。 |
| 保育施設の設置・補助 | 社内託児所やベビーシッター費用補助など、会社が保育サービス提供・支援。 | 保育園が見つからない、または費用・送迎負担を軽減したい。 |
| 養育両立支援休暇 (年10日以上) | 育児のため年10日以上の特別休暇を付与。時間単位取得も可。 | 子の行事参加や急な対応で、有給休暇だけでは足りない。 |
| 短時間勤務制度 (時短勤務) | 1日6時間程度に勤務時間を短縮。 | 育児時間をより確保したい、フルタイム勤務が難しい。 |
上記5つの制度のうち、企業ごとに2つ以上が整備されます。
例えばある会社では「フレックスタイム制とテレワーク」を導入し、別の会社では「短時間勤務と特別休暇」を用意するといった具合です。
従業員はその会社の2つ以上の制度の中から自分の希望に合う制度を1つ選んで利用できます。
 ねくこ
ねくここの選択は労働者の自由であり、会社側が一方的に制度を指定することは想定されていません。
自分と家族の状況に照らし合わせて、「これなら仕事を続けられそうだ」という制度を選びましょう。
なお、法律上は従業員が制度を利用する際に、勤続1年未満の方や週2日以下の勤務形態の方などは労使協定で対象外とすることも可能です。
そのため、入社して間もない場合や非常に短い週日数で働いている場合は、会社の就業規則を確認して適用条件をチェックしてください。
企業側の義務と労働者の選択肢
企業は個別に「制度の案内」と「利用希望の有無」を確認しなければならない

改正法では、上記の柔軟な働き方制度を企業が整備するだけでなく、労働者への働きかけについても新たな義務が設けられています。
企業は対象となる従業員に対し、個別に制度の案内を行い、利用希望の有無を確認しなければなりません。
たとえば、お子さんがいる社員に対して「当社ではテレワークと時短勤務の制度がありますが利用しますか?」といった周知と意向確認を行うイメージです。
これは単に形式的に尋ねるだけでなく、従業員が制度を利用しやすいよう配慮することまで求められます。
企業はヒアリングを設け、可能な範囲で調整に努める義務がある
また、希望を伝えるチャンスが設けられているので、「本当はテレワークしたいけど言い出しづらい…」と悩んでいる場合でも、会社はヒアリングの場を設けなくてはならず、遠慮なく相談できます。
会社は従業員の希望する働き方について耳を傾け、可能な範囲で勤務条件の調整などに努める義務があります。
つまり「そもそも案内しないこと」や「なんとなくの空気間で“仕向ける”」といった行為は義務違反となります。
会社には制度の利用を妨げるような言動をしてはならないことも明記されており、働く側が正当な権利としてこれら制度を選択できる環境整備が図られています。
万一、従業員から聞き取った希望に沿う対応が難しい場合でも、単に拒否するのではなく「なぜ難しいのか」を説明するなど丁寧に対応することが重視されています。
 ねくこ
ねくこ要するに、企業は制度を「用意して終わり」ではなく、従業員一人ひとりに寄り添った対応が求められるようになりました。
例えば子どもの年齢や保育環境、家族の働き方などによって適した制度は異なりますが、会社がきちんと情報提供と相談対応を行うことで、従業員は自分に合う選択肢を選びやすくなります。
これからは、働くパパ・ママが制度を知らずに埋もれてしまうことなく、会社と相談しながら柔軟な働き方を実現できる時代と言えるでしょう。
制度利用の流れ:周知・意向確認はいつ行われる?
では、このような会社からの個別周知・意向確認は具体的にいつ行われるのでしょうか。
改正法では、主に以下のタイミングで実施することが義務付けられています。
妊娠・出産を申し出たとき

労働者本人が妊娠した場合や配偶者の出産を会社に報告した場合、その時点でまず会社は個別ヒアリングを行う必要があります。
これまでも育休制度の案内等は義務化されていましたが、2025年10月からはそれに加えて「今後どんな働き方を希望するか」まで含めて意向を聴くことが義務化されました。
 ねくこ
ねくこ妊娠中・出産直後の働き方や育児休業の取得予定、復職後に利用したい制度(時短勤務やテレワークの希望など)について、この段階で会社と話し合うことになります。
お子さんが3歳になる前(誕生日の1カ月以上前まで)

3歳未満の子を育てている従業員に対しては、お子さんが2歳頃(1歳11か月を過ぎてから2歳11か月になるまで)の適切な時期に、会社が個別周知と意向確認を行う義務があります。
具体的には、会社が選択した柔軟な働き方の制度(前述の対象措置)について詳しく説明し、
といった希望の確認を行います。
会社側から従業員側への情報提供について
現在育休中で復職を控えている場合なども、このタイミングで話し合いが持たれます。
上記のように、妊娠時と子が2歳代のタイミングで会社から個別面談や連絡が来ることになります。
企業側の周知方法は、対面での面談のほか、書面配布やメール送信などでも構いません(オンライン面談や希望者へのメール送付もOK)。
いずれの場合も、会社側は従業員に確実に情報が届くように配慮しなければなりません。
これらの個別周知の場では、会社から以下のような情報提供が行われます。
- 会社が選択して整備した柔軟な働き方の制度の詳細(例:フレックス勤務の制度内容やテレワーク利用可能日数など)
- 各制度を利用したい場合の申出先(例:人事部への申請手続き方法)
- 育児中の従業員が利用できるその他の制度(※時間外労働の制限や残業免除、深夜勤務制限の制度なども含む)
このような関連制度も含め、企業は抜け漏れなく個別に周知し、「制度を利用したい」という従業員の意向を確認する義務があります。
 ねくこ
ねくこもし会社から上記のような案内がなかなか来ない場合は、育児中の方は遠慮せず自分から人事担当者に尋ねてみましょう。
「改正育児休業法で何か利用できる制度はありますか?」と声を上げることで、会社側も対応に気づく場合があります。
上手に活用するには:申請のタイミングと具体的な行動

実際にこれら制度を利用したいと思ったとき、従業員はどのように動けばよいでしょうか。
基本的な流れとしては、会社への申し出(申請)が必要です。
法律上、柔軟な働き方措置を利用する申し出期限について特に細かな規定はありません。
そのため、各企業が就業規則などで「利用したい場合は○週間前までに申請」といったルールを定めているケースがあります。
まずは自社の制度資料や就業規則を確認し、申請期限や手続き方法を把握しましょう。
早めの相談・申請が鍵
一般的には、早めの相談・申請が鍵です。
例えば「子どもが3歳になるタイミングで時短勤務に切り替えたい」と考えているなら、少なくとも希望開始日の1〜2か月前には上司や人事に意向を伝え、社内手続きを進めるのが望ましいでしょう。
会社側も代替要員の手配や業務体制の調整が必要になるため、余裕を持って伝えることでスムーズに話が進みます。
人事部や総務部の案内に従い、必要事項を記入して提出
申請にあたっては、会社指定の申請書や届出フォームの提出が求められる場合があります。
人事部や総務部の案内に従い、必要事項を記入して提出しましょう。
この機会に家庭内での役割分担を整理
また、家族内での役割分担についても、この機会に話し合っておくことをおすすめします。
特に共働き家庭では、夫婦どちらがどの制度を利用するかで家庭内のサポート体制も変わります。
 ねくこ
ねくこ今回の法改正で、男性社員も含め誰もが制度を利用しやすくなりました。
配偶者と相談しながら、お互いの勤務スタイルを調整するとよいでしょう。
制度利用開始後も、状況に応じて働き方を見直す
制度利用開始後も、状況に応じて働き方を見直すことができます。
法律の指針では、育児休業から復帰したタイミングや短時間勤務・テレワーク利用中のタイミングで、定期的に上司との面談を行い現在の制度が適切か確認することが望ましいとされています。
お子さんの成長や保育環境の変化に合わせて「やはりもう少し勤務時間を増やしたい」「テレワークより出社メインに戻したい」と感じることもあるでしょう。
その際は会社と相談の上、必要に応じて制度の変更や他の措置への切り替えを検討してみてください。
 ねくこ
ねくこ柔軟な働き方の制度は一度選んだら固定ではなく、あくまで従業員のニーズに合わせて柔軟に運用されるべきものです。
遠慮なくキャリアと家庭のバランスについて相談し、最適な働き方を追求しましょう。
終わりに|新制度を活用して無理なく両立を

2025年10月施行の改正育児・介護休業法によって、仕事と育児を両立するための環境は大きく前進します。
企業には柔軟な働き方を支える制度整備ときめ細かなサポートが求められ、働く私たちも安心して利用できる権利が保障されました。
子育てと仕事の両立は決して簡単なことではありませんが、制度を上手に活用すれば「キャリアを諦めずに家庭も大事にする」ことが可能になります。
大切なのは、自分の状況に合った選択肢を知り、主体的に活用することです。
まずは自社でどの制度が利用できるのかを確認し、利用したい場合は早めに意思表示しましょう。
会社からの案内やヒアリングの機会も積極的に活かして、「こういう働き方ができれば続けられます」と遠慮なく伝えることが重要です。
 ねくこ
ねくこ法律によって守られた権利ですので、周囲に気兼ねする必要はありません。
むしろ制度利用者の声が増えることで社内の理解も深化し、今後ますます仕事と家庭の両立がしやすい職場環境へとつながっていくはずです。
改正法施行の日は目前です。
ぜひこの機会に、あなた自身の働き方プランを見直してみてください。
柔軟な制度をフル活用しながら、無理のないペースでキャリアと子育てを充実させていきましょう。