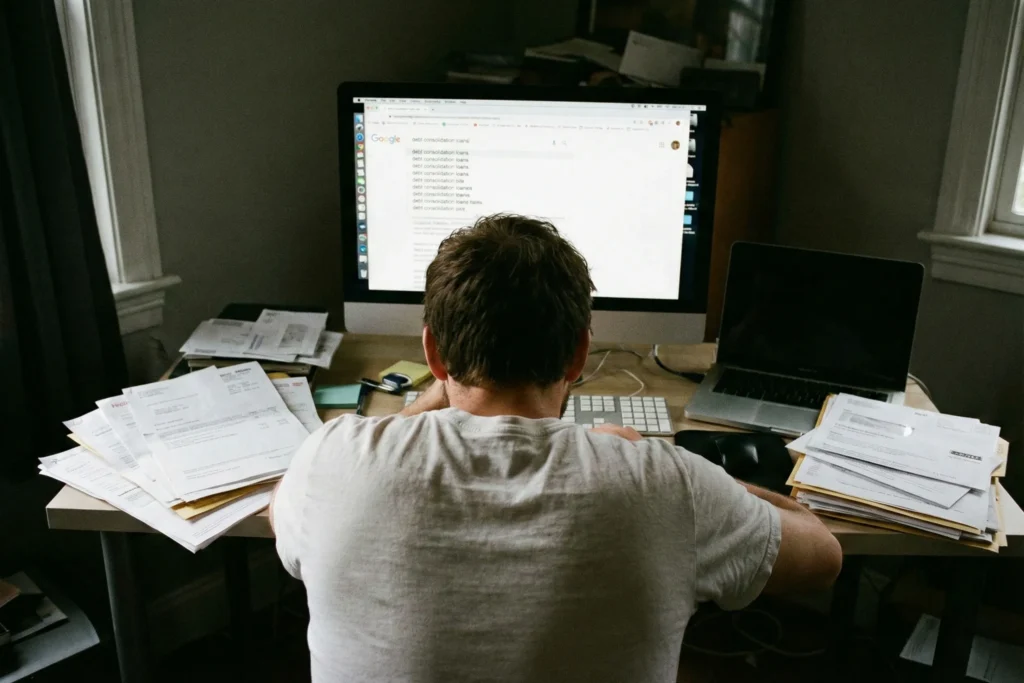MUFGの「不動産ファンド新設」が示す、日本市場の転機と暮らしへの波及

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)が2025年9月、新たに約1,000億円規模の国内不動産投資ファンドを立ち上げると報じられました。
超低金利が長く続いた日本で、昨今の金利上昇を背景に投資家の資金運用ニーズが変化していることが背景にあります。
「金利ある世界」の到来により、投資家はより高い利回りを求めるようになっており、MUFGはこうした需要を取り込むべく、不動産運用事業を強化しているのです。
 MIYABI
MIYABI本記事では、この動きを軸に現在の不動産市場動向や金利環境、セクター別の需給状況、そして私たち生活者や投資家への影響について、やさしく丁寧に解説します。

「小口で不動産投資にアクセス!」
野村證券の不動産セキュリティ・トークンは、野村證券株式会社が提供する不動産投資商品です。
ブロックチェーン技術を活用し、小口化することで受益権をデジタル証券化したサービスです。
- 直物はまだ重いけど、中身は見て選びたい
- 値動きより“設計どおりの運用”を見たい
- ポートフォリオに“リアル資産のピース”を足したい
といった方に向いており、オンライン手続きは口座開設→ログイン→購入の3STEP。
大型不動産への分散投資を検討したい個人をサポートします。
※ 予想分配金利回りは市場環境や物件収益等により変動し、利回りを保証するものではありません。最低投資単位は100万円/1口〜で変更の可能性があります。ブロックチェーンやプラットフォーム運営の不確実性に伴う遅延、流動性の制約・譲渡制限等のリスクがあります。検討の際は必ず目論見書等の最新の公式情報をご確認ください。
\ 小口化で大型不動産にアクセス /
三菱UFJの「1000億円不動産ファンド」新設の背景

MUFGの新ファンドは、空室や老朽化といった課題を抱える不動産を購入し、改修やテナント誘致(リーシング)、運営改善によって収益力と資産価値を高める「バリューアッド型」の投資商品です。
バリューアッド型ファンドで3大都市圏のオフィスやレジデンス、ホテルに投資
同社がこうしたバリューアッド型ファンドを手掛けるのは初めてで、内田直克社長は「金利ある世界で、投資家のリターン目線が高まっている」と述べ、高利回り志向に応える商品であることを強調しています。
ファンドは国内機関投資家から約300億円の出資(エクイティ)を募り、借入も合わせて総額1,000億円規模の投資を行う計画です。
投資対象は東京・関西・名古屋を中心とした中規模のオフィスビル、賃貸マンション(レジデンス)、ホテルで、まさに日本国内の主要な不動産セクターを広くカバーしています。
「金利正常化」の流れで高利率運用を目指して設立
このファンド設立の背景には、不動産市場への投資需要拡大があります。
長らくゼロ金利状態だった日本ですが、最近では日銀が約17年ぶりに政策金利を引き上げるなど(金利0.5%程度への誘導)金利環境に変化が見られます。
2025年には長期金利(10年国債利回り)が一時1.5%を超え、2009年以来の高水準となる場面もありました。
この「金利正常化」の流れにより、安全資産である国債の利回りが上昇すると、不動産などリスク資産にもそれ相応のリターンが求められるようになります。
 MIYABI
MIYABI不動産運用で投資家に魅力的な成果を提供するためには、従来以上に収益性の高い運用が必要となり、MUFGの新ファンドはまさにそのニーズに応えるものです。
グループの信用力で有望案件の発掘や資金調達で優位性を確保
一方で、日本の金利は欧米に比べ依然低水準であるため、国内外の機関投資家から見ると日本不動産は利回り面で相対的に魅力的な投資先でもあります。
実際、海外マネーの流入もあり不動産取得競争が激化しているとされ、MUFGは自社グループの信用力やネットワークを活かして有望案件の発掘や資金調達で優位性を確保しようとしています。
 MIYABI
MIYABI新ファンドはグループ各社連携で市場外案件(オフマーケット案件)の開拓にも取り組むとのことです。
不動産関連で運用資産残高1兆円を目指す計画
また、MUFGは2024年4月に信託銀行の不動産ファンド運用機能を統合するなど不動産アセットマネジメント事業を強化しており、新生MUREAM(エムユーリアム)として運用資産残高1兆円を目指す計画です。
将来的には上場REIT(不動産投資信託)事業への参入も視野に入れており、必要があればREITの買収も検討したいとしています。
不動産市場の全体動向:金利環境と需給の現状
金利環境の変化が不動産市場に与える影響について整理してみましょう。
戦後最低水準の金利は脱しているフェーズ
日本銀行の金融緩和修正により、住宅ローン金利などもじわり上昇傾向にあります。

例えば長期固定型の【フラット35】金利は2023年から上昇に転じ、2025年時点で約1.9%前後と、数年前の最低水準と比べ上昇しています。
 MIYABI
MIYABI変動金利型も将来的な追加利上げ次第では上振れしうるものの、現状ではなお低水準を維持しています。
インフレ基調から不動産投資においても採算や資金繰りに要注意
企業向け融資も含め、市場全体で「お金の値段」が少しずつ上がり始めており、その分不動産投資の採算計算や資金繰りに繊細な注意が必要なフェーズに入っています。
一方で緩やかな金利上昇は、日本経済のインフレ率の高まりを反映したものでもあります。
景気が底堅く推移し企業収益が上向けば、不動産需要にもプラスに働きます。

不動産オーナーにとっては借入金利コスト上昇という課題はあるものの、テナント企業の業績改善によって賃料負担力が増すことが期待でき、結果的に賃料水準が上昇する可能性もあります。
とはいえ、現在も堅調な需要に支えられ地価上昇を続けている
こうした中、最新の統計データを見ると、日本の不動産市場はセクターごとに明暗が分かれつつも、全体としては堅調な需要に支えられています。
土地価格は全国平均で上昇基調が続いており、国税庁発表の2025年路線価(相続税評価の基準となる地価)は全国標準宅地の平均が前年比+2.7%と2年連続で過去最大の伸び率を記録しました。
 MIYABI
MIYABIインバウンド(訪日外国人)の増加や都市近郊で進む再開発の活発さが地価上昇の背景にあると分析されています。
2024年時点で全国の住宅地は前年比+0.9%、商業地は+2.4%といずれも3年連続で上昇し、上昇幅も前年より拡大しました。
三大都市圏では住宅地+3.0%、商業地+6.2%と全国平均を上回る伸びを示しています。
【2025年9月最新】不動産種別ごとの市場動向

以下では、オフィス、住宅、ホテルそれぞれの市場動向を詳しく見ていきましょう。
オフィス市場:オフィス需要の回復と新たな課題
国内のオフィス需要は、コロナ禍からの経済活動正常化とともに持ち直しています。
東京主要5区(千代田・中央・港・新宿・渋谷区)では2020~2022年にかけて空室率が上昇しましたが、そのピークでも5%台後半と欧米に比べ低い水準にとどまりました。
その後は大規模供給が相次いだ影響で改善ペースは緩やかでしたが、2023年以降オフィス回帰の動きが進み、2025年中頃には主要ビジネス地区の空室率は概ね3%前後まで低下しています。
都心主要五区の空室率は下落傾向
実際、東京主要5区の潜在空室率(募集中フロア全体の空室率)は2025年7月時点で2.74%と、4年9か月ぶりに3%を下回りました(出典)。
超都心部のグレードAオフィスビルに限れば空室率は1~2%台と逼迫しており、優良オフィスへのテナント需要が根強いことを示しています。
日本企業では出社回帰が比較的顕著

テレワークが定着した米国などと異なり、日本企業では出社回帰やオフィス拡張の動きが比較的顕著です。
実際、ある調査ではオフィス移転を検討・実施する理由の首位が「人員増・事業拡大」で、全体の2割を占めました。
業種によってはIT企業など一部でフリーアドレス化による集約もありますが、多くの企業が対面コミュニケーションの価値を再認識しているようです。
その結果、都心の新築・高性能オフィスは空室が出てもすぐに契約が決まる状況で、平均募集賃料も上昇傾向にあります。
 MIYABI
MIYABI2024年から東京で大規模な新築ビルの供給が続いていますが、新ビルへの移転ニーズが強く、古いビルから新ビルへの「玉突き移転」による需給の再編が進むでしょう。
オフィスの二極化傾向が懸念材料
一方で築年数が古く設備の見劣りするビルでは空室が長期化する例も出始めており、オフィス市場の二極化も懸念されます。
貸し手市場が続く中、貸主(ビルオーナー)が契約更新時に賃料アップを提示するケースも増えています。
実際、「契約更新が難航した(賃料条件の折り合いが付かない)」と回答するテナントが2023~24年にかけて急増しているそうです。
 MIYABI
MIYABIつまり中小企業などテナント側にとっては、オフィス賃料負担増への備えや、条件交渉力の強化が今後ますます重要になってくると言えます。
住宅市場:価格高騰と賃貸ニーズの変化

住宅不動産市場では、都市部を中心に価格高騰が際立っています。
2023年には東京23区のマンション平均価格が1億円を突破

特に新築分譲マンションの価格上昇が顕著で、東京都心部では富裕層向けの超高額物件が相次ぎ、2023年には東京23区の新築マンション平均価格が初めて1億円の大台を突破しました。
その勢いは留まるところを知らず、2025年前半時点で東京23区平均はさらに約1億4,000万円規模に達し前年より36%も上昇しています。
投資家需要により都心三区は平均坪単価1,000円超えに
この背景には建設コストの上昇や用地取得難もありますが、最大の要因は富裕層や投資家による旺盛な需要です。
 MIYABI
MIYABI一方で価格高騰の反動として、一般の実需層(自ら住む目的の購入希望者)にとって新築マンション取得は一段と厳しくなっています。
富裕層戦略により新築供給は減少傾向
ディベロッパー各社も販売対象を富裕層に絞り込み傾向が強まり、首都圏全体の新規供給戸数は減少傾向です。
その結果、「都心で新築」は限られた層のものとなり、多くの家族は都心以外の郊外エリアでの住宅購入や、中古マンション・リノベーション物件の検討にシフトしつつあります。
賃貸はファミリータイプの家賃上昇が顕著
賃貸住宅市場にも変化が現れています。
東京都心の賃料はじわじわと上昇を続け、東京カンテイの調査によれば2024年6月の東京23区ファミリー向け分譲マンション平均賃料は1㎡あたり4,336円と、調査開始以来の史上最高値を更新しました(出典)。
東京23区の賃料を世帯別に見ると、単身向け平均約8万9千円(前年比+1.2%)、カップル向け約13万9千円(+3.8%)、ファミリー向け約21万2千円(+8.9%)と軒並み上昇しており、広い住戸ほど上昇率が高いのが特徴です。
需要に応じた二極化する相場

物価全体の上昇や所得環境の改善を背景に、オーナー側が強気の賃料設定を行っている側面もあります。
もっとも、郊外や地方都市では需要に見合わない高値設定は敬遠されるため、エリアごとの需給バランスで二極化も進んでいます。
今後、金利上昇で住宅ローン負担が増せば持ち家志向が弱まり、一定の層が賃貸に留まることで賃貸需要が底堅く推移する可能性もあります。
 MIYABI
MIYABI生活者にとっては、購入でも賃貸でも住居費負担増が続く懸念があるため、家計管理の中で住宅コストの計画を慎重に見直す時期と言えるでしょう。
ホテル市場:観光需要の回復と投資の活発化
ホテル・宿泊業界はコロナ禍から力強い回復を遂げています。
円安による環境産業の拡大
円安も追い風となり主要観光地のにぎわいが戻っています。
観光庁のデータでも国内ホテルの客室稼働率は2023年後半に大都市圏・地方ともおおむね80%前後まで上昇し、一部高級ホテルでは満室が続出する状況です。
こうした需要増に対応し、全国で新規ホテル開業が相次いでいます。
東京や大阪、京都といった人気エリアでは外資系ホテルチェーンの進出や、日本発の高級旅館ブランドの都市型ホテル転換など、多彩なプロジェクトが進行中です。
ホテル不動産への投資が活性化
ホテル不動産への投資マネーも再び活発になっています。
コロナ禍で経営不振に陥った地方の旅館やビジネスホテルが投資ファンドに買収され、リブランド(ブランド刷新)して再出発する事例が増えています。
またJ-REIT市場でもホテル特化型REITの物件稼働率改善が評価され、投資口価格が上昇傾向にあります。
人材不足と価格、サービスのバランスが鍵
もっとも、宿泊業界には人手不足という課題も横たわっています。
慢性的な人材難に対応するため、客室清掃やフロント業務へのIT・省人化投資が進むなど、ソフト面の改革も求められています。
生活者の視点では、旅行者としては宿泊料金が全般に上がり以前より割高感を感じる局面もありますが、その分サービスや衛生面の向上につながっているケースもあります。
地方の観光地ではインバウンド効果で地域経済が潤う恩恵があり、中小の旅館業者にとってはチャンスと課題が混在する状況と言えるでしょう。
不動産投資信託(REIT)市場の動向と投資マネーの動き
J-REIT(上場不動産投資信託)の市場もここ数年で浮き沈みがありましたが、2023年後半から2025年にかけては堅調さを取り戻しつつあります。
コロナ禍ではオフィスや商業施設系REITが売られ指数が低迷しましたが、経済再開とともに稼働率や収益が改善し、投資家心理も上向いてきました。
 MIYABI
MIYABI2025年7月末の東証REIT指数は1,780ポイント近辺まで回復し、これは2022年春以来の高水準です。
セクター別ではオフィス・商業・住宅いずれも上昇傾向

セクター別ではオフィス系・商業系・住宅系いずれも上昇傾向にあり、特にホテル系REITはインバウンド回復を追い風に大きく値上がりしました。
予想分配金利回り(配当利回り)は平均で約4.9%前後と依然として高水準にあり、長期国債利回り(約1.4%)との差(イールド・スプレッド)は3%以上確保されています。
このスプレッドの大きさは、投資家にとってREITが相対的に魅力的な利回り商品であることを意味します。
もっとも将来的な金利上昇が急激に進めばREIT価格に下押し圧力となる可能性はあるため、その点は注意が必要です。
4年ぶり上場で市場の活性化に期待
市場トピックスとしては、2025年には実に4年ぶりとなる新規J-REITの上場案件が発表され、マーケット活性化への期待が高まっています。
これは投資対象資産の多様化(データセンターや物流特化など)を狙った動きで、成熟してきたJ-REIT市場に新風を吹き込むものです。
また前述のMUFGの内田社長が「上場REITの取得も検討したい」と語ったように、金融機関系の運用会社がREIT事業に参入を模索するケースも出ています。
これは裏を返せば、J-REIT市場が依然として成長余地のある魅力的な領域と見なされている証と言えるでしょう。
引き続き国内外から資金が流入している
投資マネー全体で見れば、日本の不動産には引き続き国内外から幅広い資金が流入しています。
年金基金や保険会社などの機関投資家は安定運用の一環で不動産投資を拡大しており、個人投資家もNISA拡充などを追い風にREITや私募ファンドを活用した不動産投資に関心を寄せています。
重要なのは、投資家それぞれが金利動向や不動産市況を注視しつつ、無理のない範囲で分散投資を行うことです。

生活者にとって「つまりどうなる?」
不動産市場の変化は、私たち一般生活者の日々の暮らしにもじわり影響を及ぼします。
「都心×新築マイホーム」のハードルは高くなる一方
まず住宅面では、都心の新築価格高騰によって「マイホーム購入」のハードルが上がっています。
これから住宅購入を考える場合、希望エリアで予算内に収まらず計画を練り直すケースが増えるかもしれません。
 MIYABI
MIYABI実際にSNS上では「東京はもはや住む場所じゃない」といった声も囁かれるほど、都心部の価格高騰は一般層にとって深刻です。
地方移住や郊外での物件選びも選択肢に

しかし選択肢はあります。
郊外や地方であれば手の届く物件も多く、リモートワーク普及のおかげで以前より通勤距離を気にせず郊外移住を検討する人も増えました。
また中古マンションや中古戸建てをリノベーションして自分好みに再生する動きも盛んです。
 MIYABI
MIYABI不動産市場が活況な今だからこそ、逆に「新築にこだわらない」「エリアを広げる」など柔軟に発想することで、より現実的なマイホーム取得計画を立てることができるでしょう。
賃貸派は「二極化する地域」どのように折り合いをつけるか
賃貸派の方にとっては、家賃動向が気になるところです。
足元では物価上昇と連動する形で都市部を中心に家賃が上がっています。
引っ越しの際に「以前より同じ家賃で狭い部屋しか借りられない」と感じることがあるかもしれません。
ただ、賃貸市場は需給バランスによって地域差が大きいのも事実です。
人口減少が進むエリアや新築供給が多い郊外では空室が埋まらず、むしろ条件の良い物件が借りやすくなるケースもあります。
 MIYABI
MIYABIもし現在の家賃負担が重いようであれば、思い切ってエリアを変えてみる、あるいは少し築年数の経った物件を狙うなどの工夫で、家計負担を抑える余地もあるでしょう。
住宅ローンを組む“最後のチャンス”の可能性
さらに、2025年現在は住宅ローン金利がやや上昇しているとはいえ依然低水準(大手行の変動金利は約0.7%、フラット35は約1.9%)です。
持ち家か賃貸か迷っている方にとって、金利が本格的に上がりきる前の今はローンを組む一つのタイミングとも考えられます(もちろん将来の金利上昇リスクも踏まえつつ慎重な判断が必要です)。

 MIYABI
MIYABIこのように、不動産市場の動向を“自分ごと”として捉え、情報収集しながら柔軟にライフプランを考えることが、これからの時代には求められていると言えそうです。
終わりに|この変化を“自分ごと”にするために
日本の不動産市場は、金利環境の転換期を迎える中で、新たなステージに入ろうとしています。
MUFGの大型ファンド設立というニュースはその象徴的な出来事であり、マクロ経済の変化が不動産分野にどのような影響を及ぼすかを考えるきっかけとなりました。
不動産は私たちの暮らしやビジネスに密接に関わるものです。
だからこそ、今回のような市場の変化を「自分ごと」として捉え、一人ひとりが賢く適応していくことが大切です。
生活者の皆さんにとっては、住まい選びや家計管理の面で、不動産価格や金利動向を知っておくことが安心・納得の暮らしにつながります。
投資に関心のある方にとっては、市場のデータやプロの動向からヒントを得て、無理のない範囲で資産形成を検討する好機と言えるでしょう。
 MIYABI
MIYABI変化の激しい時代ですが、「知らなかった」で終わらせず、「だから自分はこう動こう」と考える。
そんな前向きな姿勢で、不動産を含む経済環境の変化と付き合っていきましょう。