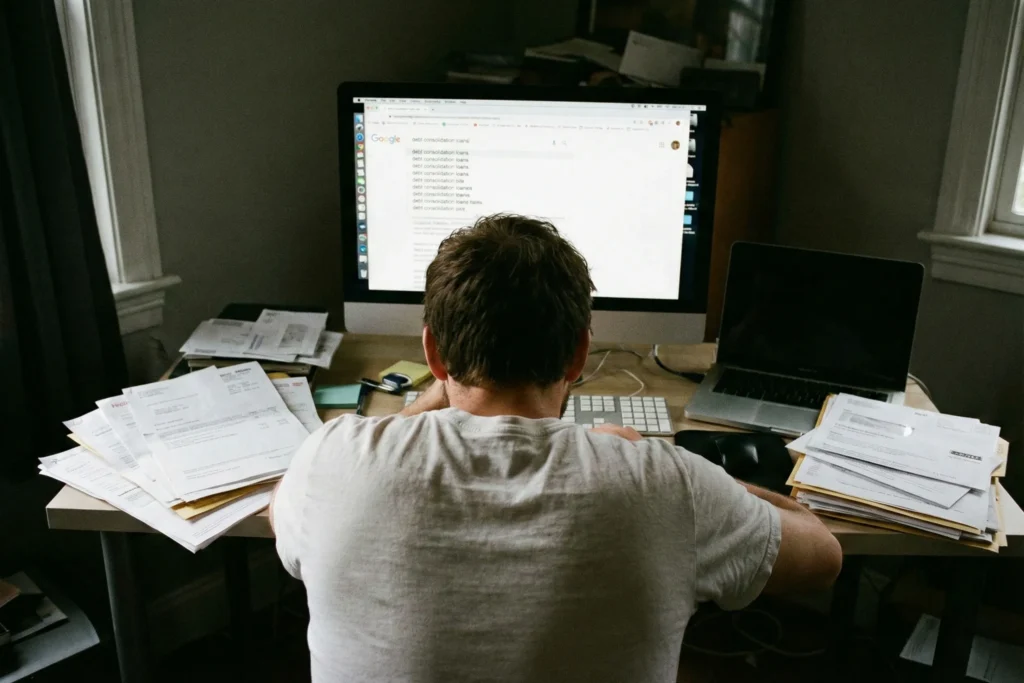金融庁の仮想通貨保有・取引ガイドライン見直しで銀行が仮想通貨を扱えるように!?業界やメガバンクの反応は?

最近、「銀行がビットコインなどの仮想通貨を扱えるようになるかもしれない」というニュースが注目を集めています。
2025年10月21日付の報道によれば、金融庁(FSA)は銀行グループの証券子会社などによる暗号資産交換業への参入や銀行本体によるビットコインなど暗号資産の投資目的保有の解禁を検討段階に入れたとされています。
これまで銀行が仮想通貨に手を出すことはほとんどなく、リスクの高さから厳しく制限されてきました。
それだけに、この動きは「今までと何が違うのか?」「仮想通貨を銀行が導入すると何が良いのか?」といった疑問がわいてきますよね。
本記事では、マネーリテラシーを高めたい初心者の方にも分かるように、今回のガイドライン見直しの背景や狙い、そして主要メガバンクの反応について丁寧に解説します。
 ねくこ
ねくこ仮想通貨を巡る金融の世界で今何が起きているのか、一緒に「なるほど!」と納得できるポイントを探ってみましょう。
金融庁が仮想通貨規制を見直しへ:何が検討されている?

まず今回報じられたニュースの概要からです。
2025年10月21日、金融庁が銀行グループによる仮想通貨の保有・取引を可能にするよう監督規制を見直す検討に入ったと報じられました。
具体的には、
- 銀行が自社の資金でビットコインなどの暗号資産を投資目的で取得・保有できるようにする制度改正案
- 銀行グループの会社(例:証券子会社)が暗号資産交換業者として登録し仮想通貨の売買サービスを提供できるようにする案
といった議論されています。
この動きは、日本の金融当局が仮想通貨に対して従来の慎重姿勢から一歩踏み出し、新たなルール作りに乗り出したことを意味します。
暗号資産市場のグローバルな成長と国内での取引拡大
背景には、暗号資産市場のグローバルな成長と国内での取引拡大があります。
海外では大手金融機関が暗号資産関連サービスに参入し始めており、国際的な銀行規制の枠組み(バーゼル銀行監督委員会の基準など)でも、一定の自己資本を条件に暗号資産保有を認める方向性が示されています。
 ねくこ
ねくこつまり、日本もこの潮流に合わせて取り残されないよう規制をアップデートしようとしている面があります。
また、日本国内でも既に証券会社系の企業(例:楽天ウォレットやSBI VCトレードなど)が暗号資産取引サービスを展開しており、銀行だけが参入できないのは競争上不利との指摘もあります。
こうした状況を踏まえ、銀行にも参入の道を開くことで市場へのアクセス拡大と競争条件の公平化を図る狙いがあるとされています。
従来の規制では銀行の仮想通貨保有は「事実上NG」だった
「今までと何が違うのか?」を理解するため、従来のルールをおさらいしましょう。
実は現行の監督指針(2020年改定)では、暗号資産価格の激しい変動が銀行財務に与えるリスクを考慮し、銀行グループが投資目的で暗号資産を取得・保有することは事実上禁止されてきました。
「経営リスク」から金融庁が事実上の禁止をしている
銀行は預金者のお金を預かる存在でもあり、その健全性が損なわれれば金融システム全体に波及しかねません。
例えば、銀行が自社で大量のビットコインを持ち、大暴落して損失を出したら、最悪の場合銀行経営に響く恐れもあります。
こうしたリスク管理の観点から、現在のルールでは銀行による仮想通貨投資は封じられていたのです(ただし2025年10月現在、金融審議会のワーキンググループでこの指針見直し案が正式に議題化されています)。
グループの会社が暗号資産交換業を営むこともできない
また、銀行グループの会社がみずから暗号資産交換業(取引所サービス)を営むことも現行制度ではできませんでした。
銀行法の制約で、銀行グループの子会社が金融庁に暗号資産交換業者として登録することが認められていなかったのです。
その結果、日本の暗号資産マーケットは主に証券会社グループ傘下の業者(例:楽天ウォレット〈楽天証券系〉やSBI VCトレード〈SBIホールディングス系〉など)や独立系の取引所が担い、銀行は間接的に関連サービスを提供するに留まっていました。
 ねくこ
ねくこ今回の検討は、この「銀行だけ参入不可」という構図を改めようというものなのです。
規制見直しの背景:なぜ今、銀行の仮想通貨参入なのか
ではなぜ、ここにきて規制見直しが検討されているのでしょうか。
 ねくこ
ねくこ背景には大きく分けて国内外の環境変化があります。
グローバルな潮流

世界的にデジタル資産の法整備が進みつつあります。
米国や欧州でも銀行が暗号資産関連サービスを提供する動きが出ており、国際的な銀行規制の基準でも暗号資産保有を一定条件下で認める方向性が示されています。
例えばバーゼル銀行監督委員会は2025年までの実施を目標に、価格変動の大きい暗号資産について銀行が保有できる上限をTier1自己資本の約1%(最大2%)程度とする規制基準を策定済みです。
 ねくこ
ねくこ日本もこの潮流に乗り遅れないよう、国際基準に沿った対応を模索していると考えられます。
既存金融とデジタル資産の融合
日本国内でも、従来の金融インフラと暗号資産との境界が少しずつ薄れてきました。
大手証券会社の野村HDや大和証券は暗号資産関連サービスに参入し始めています。
例えば野村ホールディングスは海外で機関投資家向けの仮想通貨取引事業への準備を進め、大和証券はグループ会社を通じてビットコインを担保に円を融資するサービスを紹介開始しました(※融資自体はグループ会社のFintertech社が実施)。
 ねくこ
ねくここうした中で「銀行だけが参入できない」のは競争上不利との指摘があります。
銀行業界としても、証券系ばかりが先行する状況に歯がゆさがあったと言えるでしょう。
暗号資産市場の拡大と需要
ビットコインをはじめ暗号資産の保有口座数は国内で約1,213万口座(2025年1月末時点)に達し、いまや国民の10人に1人が取引に関わる規模とも言われます。
これだけ広がった市場を無視することは難しく、利用者保護の観点からも銀行が関与して透明性や安全性を高めた方が良いという考えもあります。
金融イノベーション政策
政府はフィンテックやデジタル通貨の推進にも意欲を見せています。
たとえばデジタル円の実証実験や、ブロックチェーン技術の産業活用などが進む中で、銀行が暗号資産に関与できるようにすることは日本の金融イノベーションを後押しするとの期待もあります。
「銀行×ブロックチェーン」の取り組みとして、三菱UFJ銀行は独自のデジタル通貨(コイン)の実証実験を以前から進めていますし、みずほ銀行もデジタル債券への取り組みを表明しています。
銀行が仮想通貨や関連技術にもっと深く関われるようになれば、新しい金融サービス創出につながるとの見方があります。

 ねくこ
ねくこ以上のような理由から、「銀行も仮想通貨を扱えるようにしよう」という議論が具体化してきたわけです。
金融庁としては、市場拡大や公正な競争環境の整備といったメリットを追求しつつ、後述するようなリスク管理策とセットで制度設計を進めようとしています。
銀行が仮想通貨を扱えるようになると何が変わる?
では、もし本当に銀行が仮想通貨を扱えるようになったら、私たち利用者にとって何が変わるのでしょうか。
 ねくこ
ねくこ「今までと違うポイント」と「仮想通貨導入のメリット」を中心に考えてみましょう。
個人ユーザーにとってのメリット:便利で安心?
銀行による仮想通貨取り扱い解禁の最大の変化は、個人が仮想通貨をより身近に感じられるようになることです。
これまでビットコインなどを買おうと思ったら、専用の仮想通貨取引所に口座を開設し、お金を振り込んで取引・・・という手順が必要でした。
しかし銀行がそのままサービスを提供できれば、自分の銀行口座から直接ビットコイン等を売買できたり、銀行のスマホアプリで預金残高と一緒に暗号資産の残高を確認できたりするかもしれません。
わざわざ別の取引所に登録する手間が省け、ワンストップで資産管理できる便利さが期待できます。
※ 現時点(2025年10月24日)では制度設計は検討段階であり、こうしたサービス提供が実現するかどうか、その範囲は今後の法令改正や監督指針の内容に左右されます。
大手銀行が参入することによる「安心感」
また、大手銀行が参入することで「安心感」が増すという声もあります。
仮想通貨の世界ではこれまで、取引所のハッキング被害や経営破綻による資産消失といったトラブルも報じられてきました。
その点、銀行であれば厳格な法規制と内部管理体制の下で運営されるため、資産保全やセキュリティ面で信頼しやすいでしょう。
暗号資産(ビットコイン等)は預金保険の対象ではありません。
銀行で扱う場合でも預金と同様の保護は現状ありません(※一方で金融庁の整理によれば、銀行が顧客預金を裏付けとして発行する「預金扱いのステーブルコイン」は預金保険の対象になり得ます)。
 ねくこ
ねくこだからこそ初心者にとって、信頼できる窓口から仮想通貨に触れられる意義は大きいと言えます。
サービス面での新展開への期待
さらに、サービス面での新展開も考えられます。
例えば銀行が価値が安定したステーブルコイン(法定通貨と連動する暗号資産)を発行し、24時間365日リアルタイム送金を実現するといったことも技術的には可能です。
三井住友フィナンシャルグループ(SMBC)は2025年4月にブロックチェーン企業のAva Labsやデジタル資産カストディ企業Fireblocksなどと提携し、独自ステーブルコインの実用化プロジェクトを開始しました。
日本では同年施行の改正資金決済法で「電子決済手段」としてのステーブルコイン発行が解禁されており、銀行が発行主体となることも可能になっています。
ただし、発行主体や仲介業者には厳格なマネーロンダリング対策(トラベルルール対応など)や資産保全義務が課されるため、実現には体制整備が必要です。
 ねくこ
ねくこそれでも将来的に銀行経由で安全なデジタル通貨による送金や決済ができれば、海外送金のコストが大幅に下がったり、電子マネー感覚で円建てのデジタルマネーを使えたりと、私たちの生活にも便利さが広がる可能性があります。
金融業界全体へのインパクト:競争とイノベーションの加速

銀行の仮想通貨参入は、金融業界の構図も変えるポテンシャルがあります。
現在、日本の暗号資産ビジネスは前述のように証券会社グループ傘下の企業(楽天、SBIなど)や独立系の取引所がリードしています。
ここにメガバンクが本格参入してくれば、新旧プレイヤー入り混じった競争が活発化するでしょう。
競争によってサービス向上やイノベーションの可能性
競争が進めばサービスの質が向上し、手数料の引き下げや商品の多様化といったユーザー恩恵も期待できます。
また、従来はフィンテック企業やベンチャーが先行していたブロックチェーン技術の活用分野に、潤沢な資金と顧客基盤を持つ銀行が加わることで、金融サービスのイノベーションが加速する可能性があります。
例えば、デジタル証券(セキュリティトークン)の発行や管理、スマートコントラクトを使った融資・保険商品など、「伝統金融×暗号資産」の新サービスが生まれるかもしれません。
銀行業界にとっては先行投資も必須
一方で、銀行業界にとっては新たな収益機会が広がる反面、これまで馴染みの薄かった分野への対応力が問われます。
暗号資産に詳しい人材の育成やシステム投資など、内部的なチャレンジも必要になるでしょう。
古くからの大企業が新興分野に挑むことで、組織文化の変革やリスク管理手法のアップデートといった課題にも向き合うことになります。
 ねくこ
ねくここうした変化への対応を迫られる点も含めて、銀行の仮想通貨解禁は業界全体の変革ドライブとなり得るのです。
主なリスク・課題は?

価格変動リスク
ビットコインなどは価格の乱高下が激しく、銀行が保有することで資産価値の急減に晒される危険があります。
これを放置すると銀行経営に影響が出るため、自己資本規制の強化や保有上限の設定など対応策が不可欠です。
(国際的には2025年開始のバーゼル規制で「ボラティリティの高い暗号資産は銀行自己資本の1%以内(上限2%)まで」といった基準が定められています)
サイバーセキュリティリスク
暗号資産を扱う以上、ハッキングや不正流出のリスクと常に背中合わせです。
大手銀行といえども専用の高度なセキュリティ対策と専門チームが必要になります。
システム投資や人的リソース確保は大きな課題です。
マネーロンダリング等の不正
暗号資産は匿名性が高く、不正資金の洗浄や犯罪利用に使われる懸念があります。
銀行が関与する場合、現行以上に厳密な顧客確認(KYC)や取引モニタリングが求められます。
 ねくこ
ねくこ規制当局もこの点を特に重視しており、違反があれば厳しい処分対象となるでしょう。
顧客保護・情報開示
初心者にとって、仮想通貨のリスクを正しく理解するのは簡単ではありません。
銀行が販売や仲介をする際には、リスクを十分説明し誤解を与えないようにする義務が伴います。
場合によっては金融商品並みの詳細な開示資料や相談窓口の整備も必要になるでしょう。
規制・監督の課題
新たな枠組みを作る金融庁側にも課題があります。
これまでになかったタイプのビジネスをどう監督するか、他分野の法律(金融商品取引法や資金決済法など)との兼ね合いをどうするかなど、適切なルール設定と柔軟な監督体制が求められます。
 ねくこ
ねくここのように光と影の両面がありますが、重要なのはメリットを伸ばしリスクを抑えるための工夫です。
銀行側も当局も、そのバランスを取るべく詳細な制度設計をこれから詰めていくことになるでしょう。
終わりに|日本の金融と仮想通貨のこれから
金融庁による銀行の仮想通貨保有・取引解禁の検討は、日本の金融史において一つの転換点になるかもしれません。
もちろん、実現には慎重な議論と準備が必要です。
主要銀行は新たなビジネスチャンスとして期待を寄せつつも、「リスク管理を徹底した上で」という条件付きの歓迎です。
当局も解禁と同時に厳格なルールでガードを固める姿勢で、まさに「解禁ムード」と「慎重論」が並走しています。
初心者の皆さんにとって大事なのは、こうした動きをきっかけに金融とテクノロジーの融合が進んでいる事実を知ることです。
銀行が仮想通貨を扱うようになれば、将来は私たちの資産運用や送金の常識が変わる可能性があります。
 ねくこ
ねくこ日本の金融当局と業界が慎重かつ着実に歩もうとしているこの方向性は、デジタル時代のお金との付き合い方に大きな影響を及ぼすでしょう。
今後の動向に注目しつつ、私たちもマネーリテラシーを高めて新しい波に備えていきたいですね。
ご注意
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の暗号資産や金融商品の勧誘・推奨または投資助言を行うものではありません。投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。また、本記事の内容は法的助言を目的とするものでもありません。暗号資産は価格変動が大きく、元本や利益が保証されるものではありません。暗号資産は預金保険の対象外であり、たとえ銀行経由で取扱いが開始されても預金と同様の保護が受けられるわけではありません。制度・数値・手数料等の情報は将来変更される可能性があります。最新の公式情報もあわせてご確認ください。
引用・参考文献
- Reuters「日本、銀行グループの暗号資産取引サービス参入を検討(日経報道)」2025年10月21日公開[最終確認日:2025年10月24日]
URL: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-mulls-letting-banking-groups-offer-crypto-trading-services-nikkei-reports-2025-10-21/ - 金融庁 金融審議会 資料「暗号資産制度に関するワーキンググループ 事務局説明資料」2025年10月22日公表[最終確認日:2025年10月24日]
URL: https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/angoshisanseido_wg/gijishidai/20251022/04.pdf - CoinDesk Japan「金融庁、銀行の暗号資産投資解禁と交換業参入を検討へ」2025年10月19日掲載[最終確認日:2025年10月24日]
URL: https://www.coindeskjapan.com/319764/ - CoinDesk Japan「暗号資産口座1200万突破、預託金5兆円超え:JVCEA統計」2025年3月6日掲載[最終確認日:2025年10月24日]
URL: https://www.coindeskjapan.com/279853/ - 三井住友フィナンシャルグループ プレスリリース「デジタルアセット分野における米国企業との協業開始について」2025年4月2日[最終確認日:2025年10月24日]
URL: https://www.smfg.co.jp/news/japanese/DX20230402-1.pdf - 国際決済銀行(BIS)「Prudential treatment of cryptoasset exposures (最終規定)」2022年12月発表[最終確認日:2025年10月24日]
URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d545.pdf - 預金保険機構「預金保険の対象外となる預金等について」(預金保険制度の説明資料)[最終確認日:2025年10月24日]
URL: https://www.dic.go.jp/content/000030083.pdf