【2025年11月17日】の経済・時事ニュースまとめ
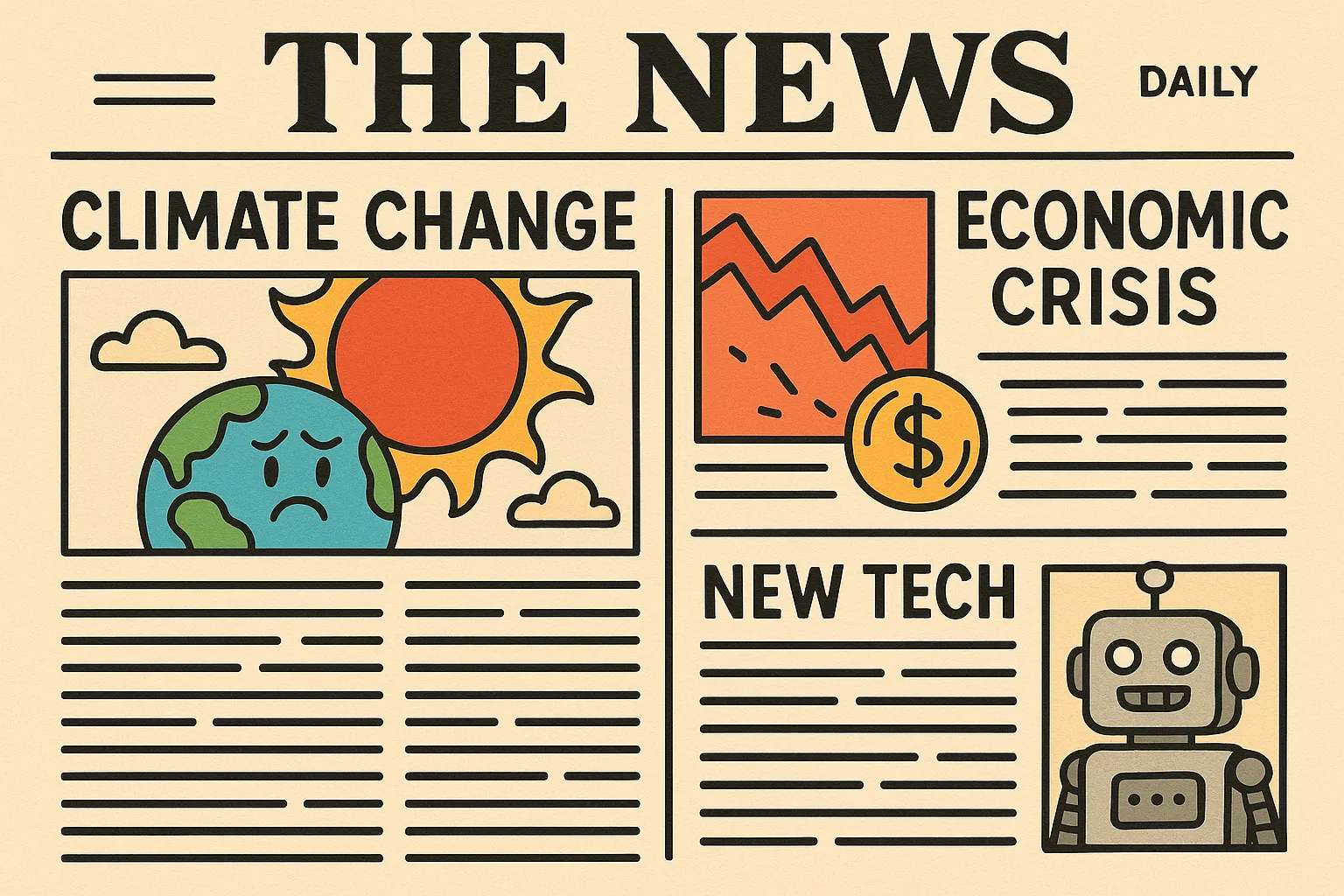
週明け11月17日の東京市場は、日経平均が前営業日終値からさらに下落してスタートし、ドル円は154円台半ばで高止まりするなど、株安・円安・リスクオフが続いています。
国内では7〜9月期GDPが年率マイナス1.8%と6四半期ぶりのマイナス成長となり、政府は電気・ガス料金の補助拡充など追加の経済対策を急いでいます。
海外では、ビットコインが10月の高値から大きく値下がりする中、日本の金融庁が暗号資産への規制・税制見直しを検討していることや、米国不在のCOP30で中国の存在感が強まっていることが注目されています。
 ねくこ
ねくここの記事では、主要株価指数と為替の動き、資産運用の考え方、国内外の主なニュース、そして私たちの生活への影響をコンパクトに整理してお伝えします。
主要株価指数・為替レート(2025年11月17日9時時点)
まず、2025年11月17日9時時点(日本時間)の主要株価指数とドル円レートを確認します。
値はいずれも公表ベースの終値または同時点の概算値であり、マーケットの状況によって日中も変動する点に注意が必要です。
| 指標 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 50,185.07 円 | −191.46(0.38%)¥ |
| NYダウ | 47,147.48ドル | -309.74(-0.65%)ドル |
| S&P500 | 6,734.11ポイント | -3.38(-0.05%)ポイント |
| ドル円為替(ドル/円) | 154.59円 | -0.03 円 |
日経平均は週明けも軟調スタート
日経平均株価は17日朝、前営業日終値からマイナス圏で始まり、9時過ぎ時点で49,900円台と5万円の大台を一時割り込む展開となりました。
背景には、米国株市場でAI関連銘柄中心にボラティリティが高まっていることや、米金利の先行き不透明感が強まっていることがあり、日本株にもリスク回避の売りが波及しているとみられます。
また、本日朝発表の日本の7〜9月期GDPが市場予想よりもマイナス成長となったことで、景気の減速懸念が意識され、景気敏感株を中心に売りが優勢になっています。
 ねくこ
ねくこ一方で、政府の追加経済対策や電気・ガス料金補助の拡充期待もあり、押し目を拾う動きも見られるなど、下値では一定の買い需要も意識されています。
米国株はAI関連の乱高下で方向感薄い
先週末14日の米国株市場では、NYダウが前日比309.74ドル安の47,147.48ドルと続落した一方、S&P500は3.38ポイント安の6,734.11と小幅安、ナスダック総合は小幅高と、主要3指数でまちまちの動きとなりました。
AI関連の主力株は、直近の高値警戒感から利益確定売りに押される場面が続いたものの、一部銘柄には押し目買いも入り、セクター内で明暗が分かれました。
また、長期化した米政府機関の一部閉鎖(シャットダウン)がようやく収束に向かうとの見方がある一方、利下げ時期を巡るFRB高官のタカ派的な発言が続き、投資家心理はまだ落ち着きを取り戻していません。
 ねくこ
ねくこ米国景気やAI投資の持続性を巡る見方が割れる中で、今週は追加の経済指標や企業決算が、相場の方向性を決めるカギとなりそうです。
ドル円は154円台半ばで高止まり
ドル円相場は17日朝時点で1ドル=154.59円前後と、先週から続く154円台半ばのレンジで推移しており、前日比ではごく小幅な円高にとどまっています。
米国の利下げ観測が後退しつつある中で、日米の金利差は依然として大きく、円を売ってドルを持つ動きが続きやすい環境が続いています。
一方で、日本側では物価と賃金の動向次第で日銀が追加利上げに踏み切る可能性も引き続き議論されており、市場では金融政策の行方を慎重に見極める姿勢が強まっています。
 ねくこ
ねくこ為替水準は企業収益や輸入物価に直接影響するため、企業の想定レートや家計の物価感覚にも影響が及ぶ点に注意が必要です。
資産運用をしている人がこの局面で心掛けるべきこと
短期の値動きよりも「長期・分散・積立」を優先する
株価指数や為替、ビットコインなどの暗号資産は、このところニュースヘッドラインに連日登場するほど値動きが激しくなっています。
しかし、長期で資産を育てていくうえでは、日々の上げ下げを追いかけて売買を繰り返すよりも、時間分散しながらコツコツ積み立てることの方が、リスクを抑えやすいと考えられます。
投資対象を国内外の株式・債券・投資信託・現金など複数に分ける「分散投資」は、どれか1つの資産が大きく下がっても、他の資産でクッションを効かせられるという基本的な考え方です。
今のようにニュースが騒がしい時期こそ、自分が決めた資産配分を見直しつつも、ルールに沿って淡々と積み立てを続ける姿勢が大切になります。
NISAやiDeCoを使う人が意識したいポイント
NISAやiDeCoなどの制度は、運用益にかかる税金を抑えながら長期・分散・積立をしやすくするための仕組みです。

新しいNISAの「つみたて投資枠」「成長投資枠」をどう配分するかは、生活資金にどれだけ余裕があるか、どのくらい値動きを許容できるかによって変わってきます。

iDeCoは、毎月の掛金を自分で拠出し、老後資金づくりを目的に長期運用する年金制度で、掛金が所得控除の対象になる点が特徴です。

 ねくこ
ねくこいずれの制度も、「非課税だからたくさんリスクを取る」という発想ではなく、あくまで自分の家計全体のバランスの中で無理のない金額・商品配分を決めることが重要です。
FXや暗号資産のレバレッジに要注意
FXやビットコインなどの暗号資産は、少ない元手でも大きな取引ができる反面、相場が逆方向に動いたときの損失も大きくなりやすいという特徴があります。

現在、ビットコインは10月のピーク約12万5,000ドルから9万ドル台まで下落しており、「上がっているから安心」という状態が長く続くとは限らないことを改めて示しています。
短期売買や高いレバレッジ取引は、値動きに慣れていない人ほど想定外の損失を抱えやすいため、「最悪どこまで損をしても生活に支障がないか」を事前にイメージしておくことが大切です。
 ねくこ
ねくこ生活費や緊急資金までリスク資産に回してしまうことは避け、まずは現金・預貯金で数か月分の生活費を確保したうえで、余裕資金で投資を行うようにしましょう。
国内ニュース
日本の7〜9月期GDPが年率マイナス1.8%、6四半期ぶりマイナス成長
内閣府が17日に発表した7〜9月期の実質GDP(速報値)は、年率換算でマイナス1.8%となり、市場予想のマイナス2.5%よりは小幅ながらも6四半期ぶりのマイナス成長となりました。
前期比ではマイナス0.4%で、輸出から輸入を差し引いた外需が成長率を0.2ポイント押し下げた一方、設備投資は1.0%増と底堅さを見せています。
背景には、米国の対日関税引き上げにより自動車などの輸出が打撃を受けたことに加え、食品価格の上昇などで実質消費が伸び悩んだことがあります。
 ねくこ
ねくこ新たに誕生した高市政権は、こうした景気の下振れに対応するため、電気・ガス料金の補助拡充などを含む大型の経済対策と補正予算の編成を進めており、日銀の利上げペースとの兼ね合いが今後の焦点となります。
電気・ガス料金の補助が来年冬に倍増へ
政府は、物価高対策の一環として、来年1〜3月の電気・ガス料金に対する補助を、標準的な家庭で月平均2,000円程度に倍増させる方向で調整していると報じられています。
今夏も電気・ガス料金の支援事業により、家庭向けの料金負担が1か月あたり数千円程度抑えられており、今回の追加策は冬場の暖房需要が高まる時期の家計負担を軽減する狙いがあります。
一方で、補助金の拡充は国の財政負担を増やす面もあり、経済対策全体の規模は17兆円を超えるとの見方も出ていることから、将来の増税や社会保障負担とのバランスも議論の対象となりそうです。
 ねくこ
ねくこ光熱費の一時的な軽減は家計にはプラスですが、長い目で見ると省エネ設備への投資や、家計の見直しも並行して進めていくことが重要だといえます。
人手不足を背景に、企業の身だしなみルール緩和が進展
東京の大手ディスカウント店ドン・キホーテなどでは、髪色やネイル、アクセサリーに関するルールを緩和し、派手な髪色やネイルアートを認める動きが広がっていると報じられています。
背景には、急速に進む少子高齢化で働き手が不足し、特に小売・サービス業を中心にアルバイトやパートの確保競争が激しくなっていることがあります。
髪色や服装の自由度を高めることで職場選びのハードルを下げ、若い世代の応募を増やしたいという企業側の思惑もあり、労働市場の需給バランスの変化が職場文化にも影響を与えていることが分かります。
 ねくこ
ねくこ今後は、働きやすさや多様性への配慮と、企業イメージや顧客対応とのバランスをどのようにとるかが、企業の人材戦略の一つのテーマになりそうです。
日韓の議員連盟が協力強化を確認、北朝鮮問題にも言及
日本と韓国の超党派の議員連盟は、ソウルでの合同総会で、政治・経済・文化など幅広い分野で両国関係を「新たな高み」に引き上げるとする共同声明を採択しました。
声明では、北朝鮮の核・ミサイル開発を非難し、朝鮮半島の完全な非核化に向けて両政府が緊密に協力する必要性が強調されています。
日韓関係は、安保・経済面での連携が日本企業のサプライチェーンや観光需要にも影響し得るため、政治対話の前進はビジネスや生活にも間接的なプラス材料となる可能性があります。
海外ニュース
ビットコイン急落と、日本の暗号資産規制見直しの動き
ビットコインは、10月に一時12万5,000ドル近辺まで上昇したあと、現在は9万3,000ドル前後まで下落し、ここ数か月で24%程度時価総額が減少したと報じられています。
リスク資産全体に売りが広がる中で、米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ観測が後退したことが、暗号資産市場にも重しとなっているとの見方が強まっています。
こうした中、日本の金融庁は、暗号資産をインサイダー取引規制の対象となる「金融商品」として位置づけ、課税率を現在の最大55%から株式と同じ20%程度に引き下げる案などを検討していると伝えられています。
 ねくこ
ねくこ暗号資産に対するルール整備が進めば、投資家保護が強化される一方で、値動きの激しさ自体が小さくなるわけではないため、利用者側のリスク理解がますます重要になってきます。
COP30で米国不在、中国が気候外交で主導権を強める
ブラジル・ベレンで開かれている国連気候変動会議(COP30)では、30年ぶりに米国が首脳級の代表団を送らず、代わりに中国が会場の中心的な存在感を示していると報じられています。
中国は再生可能エネルギーや電気自動車で世界的な存在感を高めており、その技術力と投資力を背景に、気候外交の場でも各国との関係を深めようとしています。
一方、トランプ米大統領は再びパリ協定からの離脱方針を打ち出し、温暖化対策よりも自国の雇用やエネルギー安全保障を優先する姿勢を示しており、世界の気候ガバナンスは多極化が進みつつあります。
 ねくこ
ねくこ日本企業にとっては、中国や欧州などが先行する脱炭素トレンドの中で、どの地域にどのように投資するか、サプライチェーンの組み方を含めた戦略の再検討が求められます。
関税と資源を巡る米欧中の新たな駆け引き
スイス政府は、米国との間で新たな関税枠組みに合意したことを明らかにしました。
具体的には、米国側の輸入関税が従来の39%から15%へと大幅に引き下げられる見通しである一方、スイス企業は今後数年間で2,000億ドル規模の対米投資を行うと報じられています。
また、米国は中国との間でレアアース(ハイテク機器に不可欠な希土類)の供給確保に向けた暫定合意を進めており、感謝祭(11月27日)までの最終合意を目指して交渉を続けているとされています。
中国はレアアースの採掘・精製で世界的なシェアを持つ一方、欧州ではオランダと中国の対立を背景に、半導体企業ネクスペリアを巡る供給懸念から「中国依存」を減らそうとする動きも強まっています。
 ねくこ
ねくこ日本にとっても、レアアースや半導体など重要物資の調達リスクは自動車や電機など輸出産業の競争力に直結するため、サプライチェーンの多元化や在庫戦略が一段と重要なテーマとなりそうです。
私たちの生活に起こること
物価高と景気減速が家計に与える影響
7〜9月期GDPのマイナス成長は、輸出減速の影響が大きいものの、食品などの価格上昇で実質消費の伸びが鈍っていることも示しており、家計の「節約モード」が続いていることがうかがえます。
冬の電気・ガス料金補助は、当面の光熱費負担を和らげてくれますが、補助が終了した後に一気に負担が戻る可能性もあるため「一時的な追い風」としてとらえ、日頃から家計全体のバランスを整えておくことが重要です。
企業側では人手不足を背景に、働きやすさを重視した職場環境づくりが進みつつあり、中長期的には賃金や働き方の柔軟性が改善していく余地もありますが、そのスピードは業種や企業規模によって大きく異なると考えられます。
家計防衛の基本は「見える化」と余裕資金の確保
景気や物価、為替が大きく動く局面では、投資以前に毎月の収入と支出のバランスを把握し、生活費と投資用の余裕資金を分けて管理することが家計防衛の土台になります。
とくに、家賃や通信費、保険料などの固定費を見直すことで、無理なく毎月の貯蓄・投資に回せる金額を増やせる場合も少なくありません。




一度にすべてを変えようとするのではなく、「通信費を見直す」「保険の内容を確認する」「家計簿アプリで支出を記録する」など、小さな行動を積み重ねることで、将来の不安を少しずつ減らしていくことができます。
投資との付き合い方を定期的に振り返る
ビットコインや株式相場の急変、為替の大きな動きなど、ニュースが増える時期は、「自分はなぜ投資をしているのか」「どのくらいのリスクまでなら許容できるのか」を改めて振り返る良いタイミングです。
将来の教育資金や老後資金づくりが目的であれば、10年・20年のスパンで物事を考えましょう。
 ねくこ
ねくこ短期的な値動きに過度に振り回されないよう、あらかじめ「損失許容ライン」や「リバランスの基準」を決めておくと冷静さを保ちやすくなります。
本記事は、特定の金融商品や投資手法を推奨するものではなく、一般的な情報提供を目的としたものです。
過去の実績や本記事で触れた見通しは、将来の市場環境や投資成果を保証するものではありません。
実際の投資判断は、ご自身の資産状況やリスク許容度を踏まえ、必要に応じて専門家にも相談しながら、最終的にはご自身の判断と責任で行ってください。











