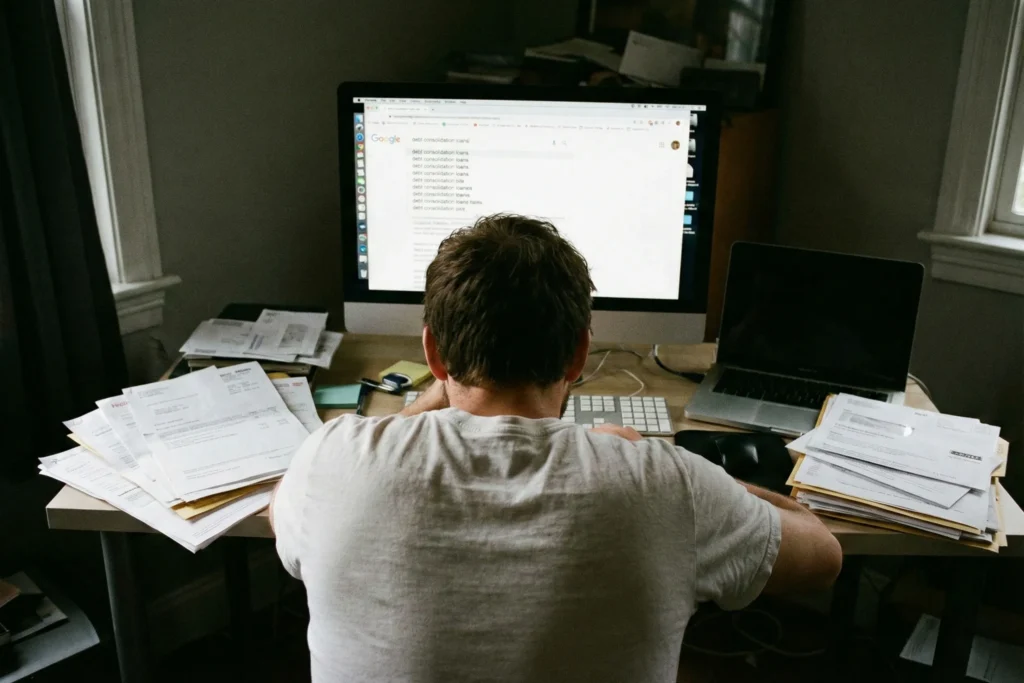【2025年11月18日】の経済・時事ニュースまとめ
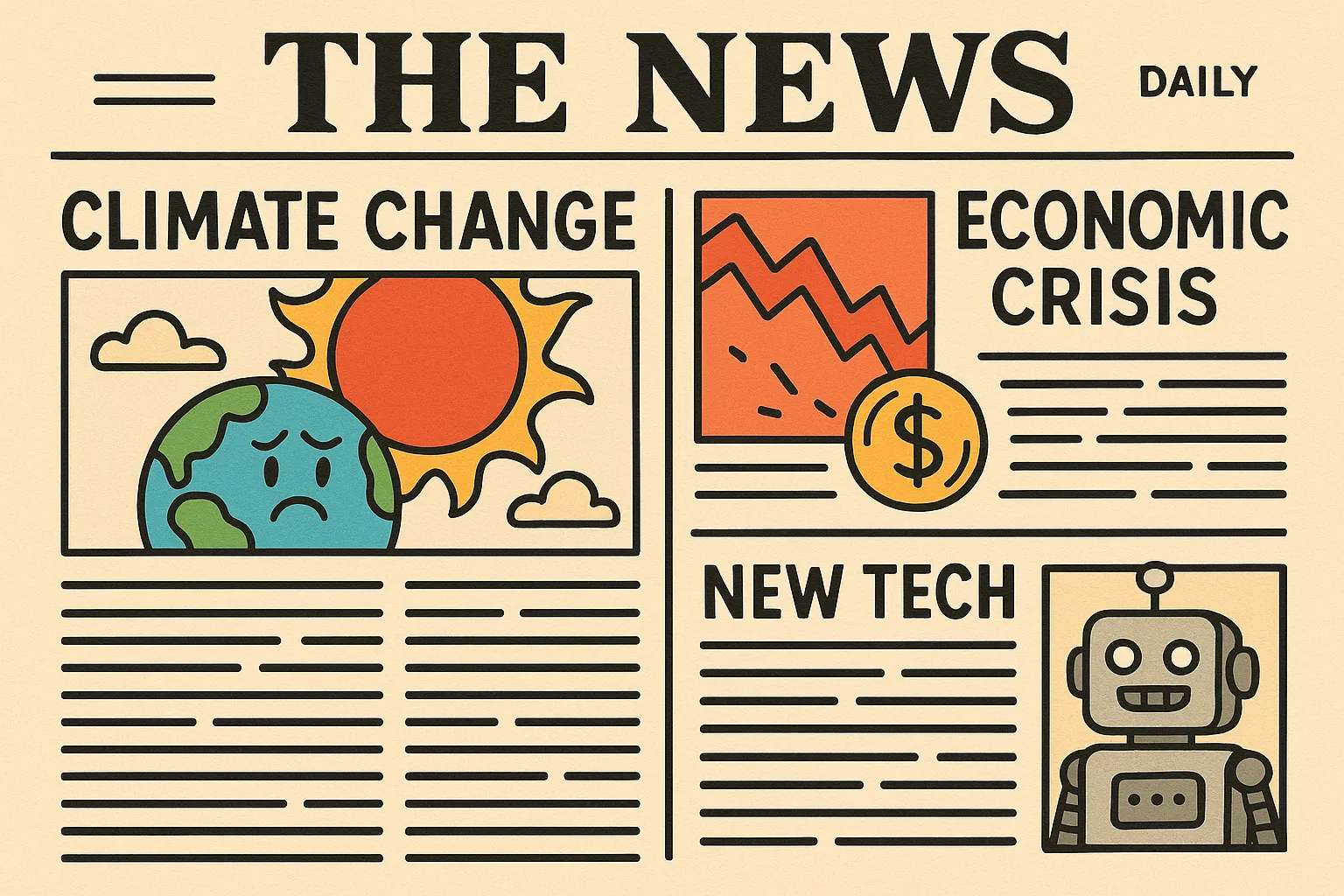
11月18日の金融市場は、日経平均株価が一時1000円超の急落となるなど、世界的な株安と円安が同時に進む不安定な1日になっています。
米国株式市場でもダウ平均やS&P500が下落基調を強めており、利下げ期待の後退や半導体大手の決算を前に投資家心理が慎重になっています。
国内では日本のGDPが6四半期ぶりのマイナス成長となったことや、新政権による経済対策と政治改革の行方が注目されています。
 ねくこ
ねくここの記事では、主要な株価指数と為替の動き、資産運用で意識したいポイント、国内外の重要ニュース、そして私たちの生活への影響を整理してお伝えします。
主要株価指数・為替レート(2025年11月18日11時時点)
| 指標 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 49,355.00円 | -968.91(-1.93%)円 |
| NYダウ | 46,590.24ドル | -557.24(-1.18%)ドル |
| S&P500 | 6,672.41ポイント | -61.70(-0.92%)ポイント |
| ドル円為替(ドル/円) | 155.18円前後 | -0.08円 |
東京市場では日経平均株価が大幅安となり、前日の終値からおよそ2%近い下落と報じられています
米国株は前夜の取引でダウ平均とS&P500がそろって下落し、為替市場ではドル円が155円台前半で推移しています。
日経平均は一時1000円超安、AI関連中心に大きく調整
18日午前の東京株式市場で日経平均株価は一時下げ幅が1000円を超え、4万9000円台前半まで急落する場面がありました。
前日まで上昇が目立っていた半導体や生成AI関連など成長期待の高い銘柄に利益確定売りが広がり、指数全体を押し下げた形です。
背景には、米国株の下落や米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げペースが市場の想定より鈍くなるのではないかという見方があり、世界的にリスク資産を減らす動きが強まっています。
日本独自の要因としては、最新のGDP速報値でマイナス成長が示されたことから、輸出や設備投資の弱さを懸念する声も出ています。
 ねくこ
ねくこ急落は不安になりますが、指数ベースではここ数カ月で急ピッチに上昇していた分の「利益確定と持ち高調整」が一度に出た側面もあり、値動きの大きさに目を奪われすぎないことも大切です。
米国株は利下げ期待の後退と決算警戒で続落
17日の米国市場ではダウ平均が前日比約557ドル安の46,590.24ドル、S&P500も約0.9%下落するなど主要指数がそろって下落しました。
投資家の間では、これまで期待されていた2026年にかけての利下げペースが緩やかになるとの観測が広がり、金利敏感なハイテク株を中心に売りが優勢となりました。
さらに半導体大手エヌビディアの決算発表を控え、AI関連銘柄の成長が本当に続くのかどうかを見極めたいとの思惑から、いったんリスクを落とす動きも強まっています。
 ねくこ
ねくこ米国株の調整は、ここ数年で高値圏にあった銘柄のバリュエーション(株価水準と利益のバランス)を見直すきっかけにもなっており、短期的な値動きは荒くなりやすい局面です。
ドル円は155円台前半、金利差とリスク回避で円売り優勢
為替市場ではドル円が一時155円30銭前後まで上昇し、今年の円安水準に再び近づいています。
米国ではインフレや雇用の先行きに不透明感があるものの、FRB高官が「利下げは慎重に進めるべきだ」と発言したことで、米金利が相対的に高い状態が続くとの見方が意識されています。
また、世界的な株安で安全資産とされる米ドルを持とうとする動きもあり、円が売られやすくなっていることもドル高・円安を後押ししています。
 ねくこ
ねくこ輸入品や海外旅行にはマイナス要因ですが、輸出企業や海外で売上を上げる企業にとっては円安が業績を支える追い風となる面もあり、日本経済への影響はプラスとマイナスが混在しています。
資産運用をしている人がこの局面で心掛けるべきこと
短期の値動きに振り回されず、最初に決めた方針を確認する
株価が急落すると、含み損が気になって「とにかく今すぐ売らないと」と焦りやすくなります。
しかし、資産運用では最初に決めた投資期間やリスク許容度、毎月の積立額などの方針を見直すことなく、感情だけで判断してしまうと後悔につながりやすいです。
NISAで長期の資産形成をしている人は、「何年先のお金を運用しているのか」「一時的な値下がりをどこまで許容すると決めていたか」を改めて確認することが大切です。

 ねくこ
ねくこ一度ルールを紙に書き出して冷蔵庫など目につく場所に貼っておくと、ニュースに不安をかき立てられたときも、感情ではなく自分のルールに従って行動しやすくなります。
積立と分散を続けることで、価格変動リスクをならす
価格が大きく下がったタイミングでは、毎月一定額を投資し続ける積立投資は、結果的に安い価格で多くの口数を買うことにつながりやすくなります。
株式だけでなく、債券や現金、場合によっては不動産投資信託(REIT)などに分散しておくことで、特定の資産クラスが大きく下がったときのダメージを抑えられます。
今のポートフォリオで株式の比率が想定より高くなりすぎていないか、リスクの取り方が自分の収入や家計の状況に見合っているかを点検する良い機会です。
 ねくこ
ねくこ一度に大きな金額を動かすのではなく、「毎月・毎年同じタイミングで機械的に積立やリバランスを行う」と決めておくと、相場観に頼らない運用になりやすいです。
レバレッジ商品やFX取引のリスクを改めて意識する
相場が急に動く局面では、先物やCFD、信用取引、FXなどレバレッジ(てこの仕組み)を使った取引は短時間で損失が膨らみやすくなります。

特に為替は24時間動き続ける市場のため、寝ている間や仕事中にレートが急変して証拠金不足になり、強制ロスカットが発生するリスクもあります。
レバレッジ取引をしている人は、ポジションの大きさや証拠金余力を見直し、「一度に資金の何%までなら失っても生活に影響が出ないか」の基準を具体的な数字で決めておくことが重要です。
 ねくこ
ねくこ「見ていない時間帯に相場が大きく動いても耐えられる量だけに抑える」というシンプルなルールを設けるだけでも、過度なリスクを避ける助けになります。
老後資金づくりはiDeCoなど長期前提の制度も選択肢に
将来の年金だけでは不安という声が多い中、老後資金づくりは10年〜20年単位の長期で考える必要があります。
iDeCoは掛金が所得控除の対象になるなど税制優遇が大きい一方で、原則60歳まで引き出せないという制約があるため、生活費の予備資金とは分けて考えることが大切です。

また、NISAとiDeCoのどちらを優先するかは、年齢や収入、退職までの年数、やむを得ない出費が発生したときに取り崩す可能性の有無など、家計全体の状況で判断する必要があります。
 ねくこ
ねくこ老後資金の準備は「今の生活を極端に我慢してまで増やす」のではなく、「家計の中で無理なく回せる範囲でコツコツ続ける」ことを基本に、制度の特徴を組み合わせる発想が有効です。
国内ニュース
日本のGDPが6四半期ぶりマイナス、輸出と消費の弱さが浮き彫りに
内閣府が発表した2025年7〜9月期の実質GDP速報値は、年率換算でマイナス成長となり、6四半期ぶりのマイナスに転じました。
トランプ前大統領による対日関税の影響などで輸出が伸び悩んだことに加え、物価上昇に賃金の伸びが追いつかず、個人消費も力強さを欠いていると指摘されています。
エコノミストからは、生産性向上や人手不足解消につながる投資を促す政策とあわせて、財政運営の信認をどう維持するかが今後の大きな課題になるとの見方が出ています。
 ねくこ
ねくこ数字の悪化だけを見ると不安になりますが、一部には設備投資の底堅さなど明るい材料もあり、「どの項目が弱いのか」を分解して見ることが今後のニュースを理解するうえで役立ちます。
高市首相と維新・藤田氏が初のランチ会談、定数削減と経済対策を協議
高市早苗首相は17日、日本維新の会の藤田文武共同代表と首相官邸で昼食を交えた会談を行い、連立政権発足後初のランチ会談となりました。
会談では衆議院議員の定数削減について「両党の約束を果たしていこう」と確認したほか、政府が取りまとめる経済対策への維新からの要望についても意見交換が行われました。
連立与党内で政治改革と経済政策を同時に進める姿勢をアピールする狙いがあるとみられ、今後の具体的な法案づくりや予算編成の議論が注目されます。
 ねくこ
ねくこ定数削減は選挙制度や地域代表のあり方にも関わるテーマであり、短期的な景気対策だけでなく「政治のコストをどうするか」という長期的な視点も合わせて議論されることが重要です。
台湾有事発言を巡り、中国の日本人学校などに文科省が安全確保を要請
台湾有事に関する高市首相の発言を巡って中国側の反発が高まる中、文部科学省は中国にある日本人学校や日本人留学生に対し、安全確保に一層努めるよう注意喚起を行う方針を示しました。
松本教育相は会見で、中国・深センで日本人学校に通う児童が刺され死亡した事件に言及し、児童や生徒、その家族や教職員の安全を守るため、現地の学校と連携して情報収集と対策を進める考えを示しています。
中国には11の日本人学校があり、約3300人が通っているとされることから、現地在住の日本人家庭にとっても通学路や送迎方法の見直しなど、身近なレベルでの対応が求められそうです。
 ねくこ
ねくこ海外在住者にとって安全確保は最優先のテーマであり、情勢に変化があったときは政府や学校からの連絡だけでなく、現地メディアや周辺住民からの情報も複数のルートで確認することが重要です。
海外ニュース
米国株安の背景にFRBの利下げペース巡る不透明感
米株式市場では、ダウ平均やS&P500、ナスダック総合指数がそろって下落し、AI関連など成長期待の高い銘柄を中心に調整が続いています。
FRBのウォーラー理事がロンドンで行った講演で、インフレ抑制のためには利下げを急ぎ過ぎるべきではないとの考えを示したこともあり、市場は「高金利が想定より長く続くのではないか」と警戒を強めています。
一方で、米政府機関の統計遅延などから重要な経済指標の発表が滞っており、投資家は限られた情報の中で先行きを判断せざるを得ない状況が続いているとの指摘もあります。
 ねくこ
ねくここのように「材料が少ないのに値動きだけ大きい」局面では、噂や見出しだけに反応するのではなく、FRBや政府高官の公式発言といった一次情報を確認する姿勢がいっそう重要になります。
世界の中央銀行はインフレとの闘いを続けつつ、一部で利下げも検討
欧州中央銀行(ECB)は、ユーロ圏のインフレ率が2%目標に近づきつつあるとしながらも、成長の弱さや地政学リスクを理由に慎重な姿勢を崩していません。
一方、アフリカなど新興国では物価上昇が落ち着いてきたことから、年内最後の会合で利下げに踏み切る中央銀行も出てくるとの見方が報じられています
世界的には、主要国の政策金利が高止まりする中で、一部の国が景気悪化に対応して利下げを始める「金融政策の二極化」が進む可能性があり、為替や資本の流れに影響を与えるとみられます。
 ねくこ
ねくこニュースで「利下げ」と聞くと景気にプラスの印象がありますが、背景に「景気の弱さ」や「財政不安」があるケースも多く、金利だけでなく物価や雇用の動きとセットで見ることが大切です。
米国で「ギリギリの生活」が増加、物価高と賃金伸び悩みが影響
米国では、全世帯の約4分の1が給料日まで「ぎりぎりの生活」を送っているとの分析が米銀の調査機関から公表されました。
インフレ率はピーク時よりは低下したものの、足元では年率3%前後とFRBの2%目標を上回る水準が続いており、賃金の伸びが追いつかないことが家計の圧迫要因になっています。
 ねくこ
ねくここのような「K字型」の格差拡大は日本でも無縁ではなく、物価上昇局面では家計の防衛策として、支出の優先順位付けや緊急時の備えを日頃から考えておく必要があります。
私たちの生活に起こること
物価と金利の高止まりが家計に与える影響
円安と海外の高金利が続くと、輸入原材料や燃料コストが押し上げられ、電気代やガソリン代、食品価格など身近な支出にじわじわと影響が出やすくなります。
日本国内の金利は依然として低いものの、世界的な金利水準が高止まりすると、企業の資金調達コストや国の利払い負担が増え、中長期的に税や社会保障負担の形で家計に跳ね返る可能性があります。
こうした環境では、家賃や通信費、保険料など毎月必ず発生する固定費を見直すことが、物価上昇に対応する最初の一歩になります。




 ねくこ
ねくこ一度にすべてを変えようとするのではなく、「スマホ料金」「サブスク」「保険」のようにテーマを決めて月ごとに見直していくと、負担感を抑えつつ家計の体質改善につなげやすくなります。
収入がすぐ増えない前提での防衛策を考える
物価が上がっても給料がすぐには増えにくい環境では、「今より収入が増えたら考える」のではなく、「増えなくても耐えられる家計」をつくる発想が重要になります。
具体的には、手取り収入の6か月分などを当面の生活防衛資金として確保するなど、値上がりや予期せぬ出費があっても生活を維持できるように準備しておくことが挙げられます。
同時に、資格取得やスキルアップ、副業など将来の収入の柱を増やす取り組みも、短期的な成果を焦らず「数年単位のプロジェクト」として考えると取り組みやすくなります。
 ねくこ
ねくこ不安なニュースが多いときほど、「今日できる小さな一歩」を決めて実行することで、先行きへの漠然とした不安を具体的な行動に変えていくことが大切です。
長期の資産形成で意識したい3つの視点
株価急落や円安といった大きなニュースが続いても、長期の資産形成では「長期・分散・積立」という基本を守れるかどうかが最終的な成果を左右しやすくなります。
そのうえで、家計の貯蓄と投資のバランス、国内外や資産クラスの分散状況、老後や教育費など目的ごとの時間軸が妥当かどうかを、年に1回程度は点検することが望ましいです。
また、SNSなどで目立つ「短期間で大きく稼いだ事例」は、相応のリスクを取った結果の一部だけが切り取られている場合も多く、自分のリスク許容度や生活の安定を犠牲にしてまで真似する必要はありません。
 ねくこ
ねくこ今日のように相場が大きく動く日は、「ニュースを追い続ける時間の一部を、自分の家計や運用方針を見直す時間にあてる」ことが、長い目で見ると一番のリスク管理になるかもしれません。
この記事で取り上げた内容は、将来の投資成果を保証するものではなく、特定の金融商品や投資手法を推奨する目的のものでもありません。
実際の投資判断は、それぞれの読者の方の資産状況やリスク許容度、投資経験などを踏まえ、ご自身の判断と責任で行っていただく必要があります。
必要に応じて、金融機関や専門家などのアドバイスも参考にしながら、無理のない範囲で資産形成に取り組んでいただければと思います。