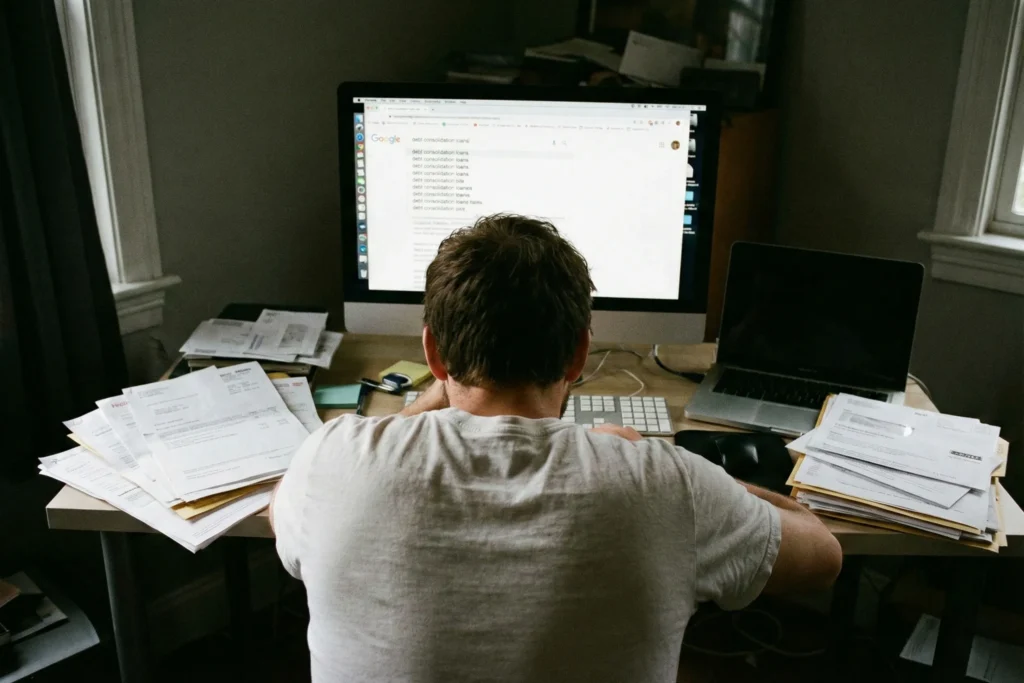【2025年11月21日】の経済・時事ニュースまとめ
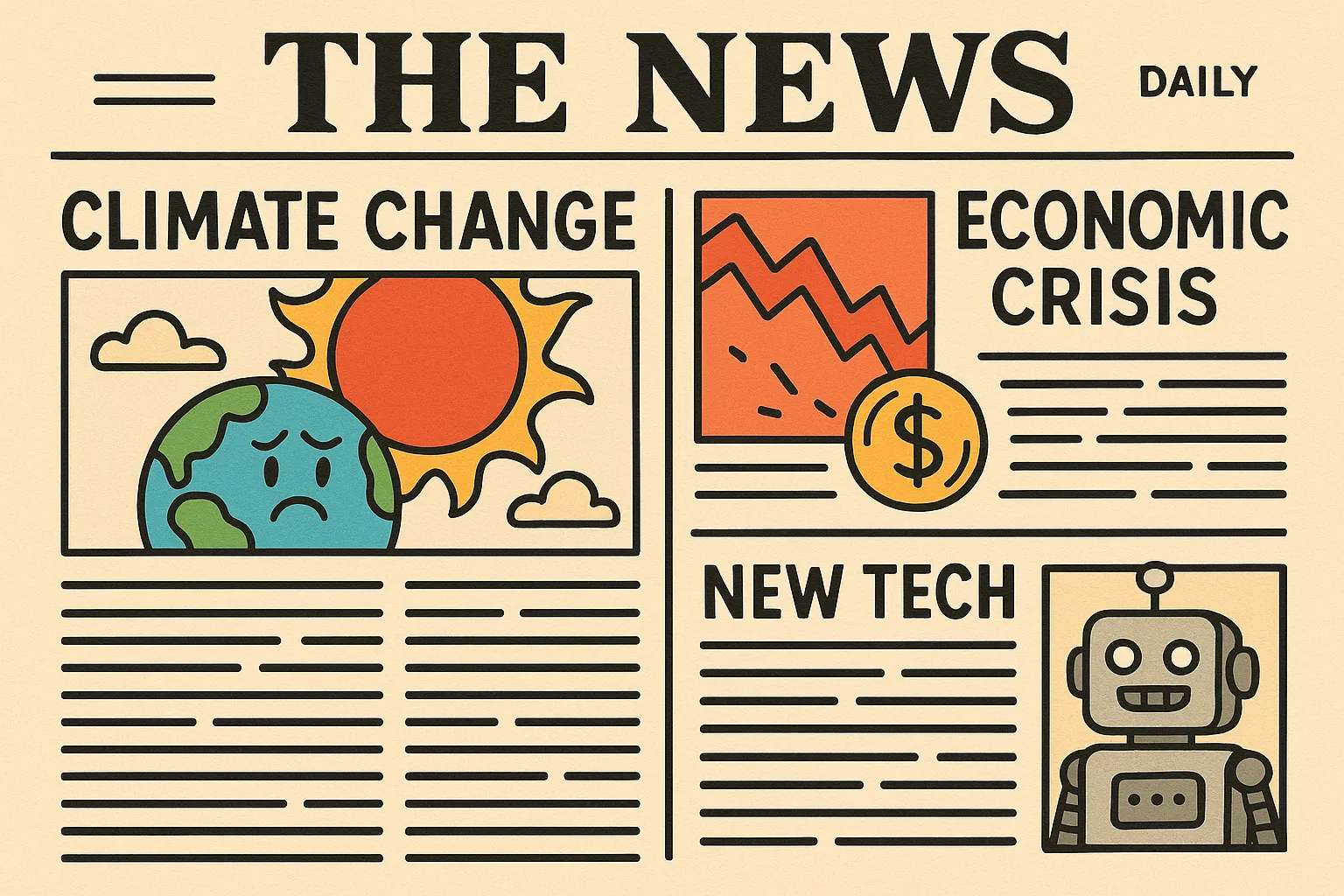
2025年11月21日は、東京市場で日経平均株価が前日比で2%を超える下落となる一方、ドル円は157円台の円安水準が続き、物価や金利、財政政策を巡る不透明感が意識される1日となっています。
米国ではNVIDIAなどハイテク株の乱高下を受けて主要株価指数がマイナス圏で取引を終え、FRB(米連邦準備制度)の要人からは利下げペースに慎重な発言が相次いでいます。
日本では10月の消費者物価指数が日銀の2%目標を上回る伸びを続けるなか、新政権が21.3兆円規模の大型経済対策を詰めの段階に入っており、市場は金利と財政の両面で今後の政策運営を注視しています。
 ねくこ
ねくここの記事では、主要株価指数と為替の動き、資産運用で気を付けたい点、国内外の主なニュース、そして私たちの生活への影響をコンパクトに整理してお伝えします。
主要株価指数・為替レート(2025年11月21日10時時点)
| 指標 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 48,802.40円 | -1,021.54(-2.05%)円 |
| NYダウ | 45,752.26ドル | -386.51(-0.84%)ドル |
| S&P500 | 6,538.97ポイント | -103.19(-1.55%)ポイント |
| ドル円為替(ドル/円) | 157.39円 | +0.01円 |
まず、日本時間11月21日10時時点での主要株価指数とドル円レートのおおよその水準を確認します。
 ねくこ
ねくこ日経平均株価とドル円は取引時間中の値を、NYダウとS&P500は20日(現地時間)の終値ベースの数値を用いています。
上記の株価指数および為替レートは、2025年11月21日10時時点または直近営業日の終値など、記事執筆時点の参考値です。その後の市場動向により数値は大きく変動している可能性があるため、実際の投資判断にあたっては、証券取引所や為替レート提供会社などが公表する最新データをご確認ください。
日経平均は大幅安、財政拡大と金利上昇懸念で売り優勢
日経平均株価は4万8,800円台と前日比で約1,000円安となり、下落率は2%を超える水準になっています。
新政権が21.3兆円規模の大型経済対策を進めるなかで国債増発や金利上昇への警戒感が強まり、長期金利の上昇とともに株式市場に売りが出やすい地合いになっています。

輸送用機器や金融、ハイテクなど金利や景気に敏感な銘柄に売りが広がる一方、円安の追い風を受ける一部輸出関連には押し目買いも入り、銘柄ごとの強弱が分かれています。
 ねくこ
ねくこ日経平均が短期的に大きく振れる局面では、指数だけでなく、自分が保有する資産の価格変動幅やリスク許容度を具体的な金額で確認しておくことが大切です。
インデックス投資をしている場合も、急落局面で慌てて売買する前に、投資の目的や期間が当初の想定と変わっていないかを落ち着いて振り返るようにしたいところです。
米国株はハイテク株の反落で主要指数が続落
20日の米国株式市場では、ダウ平均が0.8%安、S&P500が1.6%安、ナスダック総合指数が2.2%安とそろって下落して取引を終えました。
人工知能関連の象徴であるNVIDIAの好決算を受けて序盤は上昇したものの、その後は利益確定売りと高バリュエーションへの警戒が強まり、終盤にかけてハイテク株中心に売りが広がりました。
ボラティリティ指数VIXも4月以来の高水準に上昇しており、世界的にリスク資産に対して神経質なムードが強まっていることがうかがえます。
 ねくこ
ねくこ米国株の短期的な値動きは、日本の投資信託や指数連動型ETFの基準価額にも数日のタイムラグを伴って影響することが多い点を知っておくと、日々の値動きに振り回されにくくなります。
ドル円は157円台、円安と利上げ観測が綱引き
ドル円は21日午前の時点で1ドル=157円台前半から半ばで推移しており、24時間前と比べると小幅な値動きにとどまっています。
日本では大型経済対策への懸念から長期金利が上昇する一方、FRBは利下げペースに慎重姿勢を示しており、日米の金利差や日本の財政・金融政策への不安が複雑に絡み合いながら円安基調を支えています。
日銀政策委員や政府要人からは市場を「強い危機感」を持って注視するとの発言が相次いでおり、市場では1ドル=160円に接近するような場合には為替介入や追加の利上げが意識されるとの見方も出ています。
 ねくこ
ねくこ為替レートは短期間で大きく動くことがあるため、外貨建て資産を持つ場合には円ベースの評価額がどの程度変動し得るかを、シミュレーションしておくと安心です。
特にレバレッジをかける取引では、想定外の円高や円安が一度に家計へ大きな負担を与える可能性があるため、仕組みやリスクを十分に理解してから小さく始める姿勢が重要になります。
資産運用をしている人がこの局面で心掛けるべきこと
短期の値動きより家計全体のバランスを確認する
株価や為替が大きく動く局面ほど、日々の値動きに合わせて頻繁に売買するのではなく、自分の家計全体のバランスシートを点検することが重要になります。
具体的には、現金や預貯金、債券、株式、投資信託、不動産などにどれくらい配分しているかを整理し、想定しているリスク許容度と比べて過度にリスク資産に偏っていないかを確認します。
近い将来に使う予定の資金まで株式やリスクの高い商品で運用している場合は、相場急変時に取り崩しを迫られる可能性があるため、運用期間と資金の目的をもう一度紐づけて考え直すことが大切です。
 ねくこ
ねくこ目安の一例として、数年以内に使う予定のお金は値動きの小さい預貯金や安全性の高い資産を中心に、10年以上先の資金は値動きを前提にした長期投資と整理すると判断しやすくなります※。
※ ただし、適切な配分は収入の安定性や家族構成などによって大きく異なります。
NISAやiDeCoを活用する人が意識したいポイント
NISAやiDeCoの制度内容・税制優遇措置は2025年11月21日時点の法令等に基づいています。将来の税制改正や制度変更により、非課税の条件や控除額などが変わる可能性があります。利用の際は、金融庁やiDeCo公式サイトなどが公表する最新情報や、各金融機関の資料もあわせて確認してください。
NISAなどの税制優遇制度を利用している場合でも、非課税だからといって短期売買を繰り返すと、想定以上にリスクを取ってしまうことがあります。
NISA口座であっても投資対象によっては元本割れの可能性があることや、税制・制度の内容は将来変更される場合がある点にも注意が必要です。

つみたて投資枠や成長投資枠では長期・分散・積立を前提に、毎月一定額を淡々と積み立てることで、いわゆる「ドルコスト平均法」と呼ばれる考え方の効果を期待しやすくなるとされています※。
※ 元本が保証されるものではなく、相場環境によっては損失が生じる可能性もあります。

iDeCoは原則60歳まで引き出せない代わりに掛金が所得控除の対象となるため、老後資金づくりと節税を両立させる仕組みとして活用できます。
運用商品によっては元本割れの可能性があるほか、税制や制度の内容は将来変更される場合があります。
自分の退職時期や必要な生活費、リスク許容度を踏まえて掛金額や商品を決めることが大切です。

 ねくこ
ねくこ制度の違いが分かりにくいときは、商品選びより先に「何年後に・何のために・毎月いくら投資したいか」を紙に書き出し、その目的に合う制度だけを絞り込んで検討すると整理しやすくなります。
為替や金利を意識した外貨資産・FX取引のリスク管理
外貨建て投資信託や外貨預金、債券などを保有している場合は、円安が進むと評価額が増える一方で、将来円高に振れたときの下落幅も大きくなることをあらかじめ想定しておく必要があります。
特にFXのようにレバレッジをかけて為替差益を狙う取引では、相場が急変した場合に短期間で大きな損失が発生し、預けた資金を大きく割り込むおそれもあります。
証拠金の余裕度やロスカット水準を厳しく管理するとともに、金融商品取引業の登録を受けた業者かどうかを事前に確認し、自分にとって必要性やリスクが高すぎないか慎重に検討することが欠かせません。

外貨建て資産を長期保有する場合には、為替ヘッジ付きの商品を一部組み合わせる、外貨と円の比率を決めておき一定範囲を超えたらリバランスするなど、自分なりのルールを事前に決めておくと感情に流されにくくなります。]
 ねくこ
ねくこ為替や金利の見通しを完全に当てることはプロでも難しいため、「当てる」よりも「外れても家計が致命傷にならないように設計する」という発想に切り替えることが、長く資産運用を続けるうえでの土台になります。
FX取引(外国為替証拠金取引)は、レバレッジの利用により短期間で大きな損失が生じる可能性があり、預けた証拠金を超える損失が発生する場合もあります。また、金融商品取引業の登録を受けていない無登録業者との取引を行うと、トラブル発生時の対応が極めて困難になります。取引前に必ず登録業者かどうかを確認し、仕組みとリスクを十分理解したうえで検討してください。
国内ニュース
10月のコアCPIは前年比3.0%、日銀の利上げ観測が高まる
総務省が発表した10月の消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)は前年同月比3.0%上昇となり、日銀の物価目標である2%を3年以上上回る状況が続いています。
エネルギーと生鮮食品も除いた指数は3.1%上昇と9月の3.0%から伸びがやや加速しており、サービス価格や人件費の上昇がじわじわと物価に波及していることがうかがえます。
日銀は12月の金融政策決定会合でこれらの指標を詳しく点検するとしており、市場では来年にかけての利上げや国債買い入れ縮小のタイミングを巡る思惑が強まっています。
 ねくこ
ねくこ物価指標は難しく聞こえますが、「どの費目がどれだけ上がっているか」を家計の支出項目と照らし合わせてみると、自分の生活にとって何が負担になりやすいのかが見えやすくなります。
新政権が21.3兆円規模の大型経済対策を最終調整
政府は21.3兆円規模の経済対策を最終調整しており、家計への給付金や減税に加えて、危機管理や経済安全保障関連の支出を含む内容になると報じられています。
一方で税収上振れだけでは賄いきれず追加国債の発行が必要になる見通しから、国債市場では長期金利の上昇と債券価格の下落が続き、円安や株価の変動要因にもなっています。
物価高に苦しむ家計を支える効果が期待される一方で、持続可能な財政運営との両立や将来世代への負担をどう抑えるかが今後の大きな政策課題となりそうです。
 ねくこ
ねくこ給付金や減税は家計にとって一時的な追い風になりますが、将来の税負担や社会保険料の引き上げにつながる可能性もあるため、臨時収入があっても生活水準を急に引き上げすぎないことが大切です。
製造業PMIが5カ月連続で縮小、景気の足踏みがにじむ
民間調査会社の11月製造業PMI速報値は5カ月連続で景況判断の分かれ目となる50を下回り、輸出や生産活動の弱さが続いていることが示されました。
原材料価格や人件費の上昇で仕入れコストは6カ月ぶりの高い伸びとなる一方、販売価格の上昇ペースはやや鈍っており、企業が利益率を守るための価格設定に苦心している様子もうかがえます。
とはいえ将来の生産に対する企業の期待感は今年1月以来の高水準に回復し、雇用指数も6月以降で最も強い伸びを示すなど、中長期的な設備投資や人員確保への前向きな動きも見られます。
 ねくこ
ねくこ景気指標が弱いからといってすぐに不況入りというわけではなく、輸出や製造業が厳しい局面でも、内需やサービス業が底堅ければ雇用や賃金は比較的安定しやすい側面があります。
ニュースで見る景気判断と、自分の勤め先や地域の仕事量・求人動向などを見比べることで、数字と実感のギャップを小さくしながら冷静に状況を捉えることができそうです。
海外ニュース
米FRBでは利下げに慎重な発言が相次ぎ、市場は先行き不透明
米シカゴ連銀のグールズビー総裁は、インフレが2%目標に向けて十分に減速していないとして、利下げを前倒しすることに「不安」を感じていると改めて述べました。
クリーブランド連銀のハマック総裁も、これ以上の利下げは金融システムの安定を損ないかねないと警鐘を鳴らし、直近の利下げ決定に反対票を投じたと明らかにしています。
FRB副議長のバー氏など他の高官からも慎重な発言が相次いでおり、米国の利下げペースを巡って政策委員会内の見解の違いが表面化しているとの見方が広がっています。
 ねくこ
ねくこ米国の政策金利の行方は世界の株式や債券、為替市場に大きな影響を与えるため、日本の個人投資家にとっても「アメリカの利上げ・利下げの方向感」は押さえておきたい重要なポイントです。
ただし今回のようにFRB内部でも見解が割れている局面では、市場参加者の予測も外れやすくなるため、シナリオを一つに決めつけず複数パターンを想定しておく姿勢が役に立ちます。
米国株はハイテク株主導で急反落、世界のリスク資産に波及
前述の通り20日の米国株式市場ではダウ平均やS&P500、ナスダック総合がいずれもマイナスで引け、特にナスダックは9月以来の安値圏に沈みました。
人工知能ブームをけん引してきたNVIDIA株は一時大幅高となった後にマイナス圏へ急反落し、好決算を発表したウォルマートなど個別材料の明暗も相まって、投資家心理の振れ幅の大きさが浮き彫りになっています。
欧州株やアジア株の先物市場でも、米国株のボラティリティ上昇を受けて短期筋のポジション調整が進んでいるとみられ、世界的にリスク資産への慎重姿勢が広がっています。
 ねくこ
ねくこ世界全体の株価が同じ方向に動きやすい局面では、地域分散だけではリスク低減効果が限定的になることがあり、債券や現金など異なる値動きをする資産を組み合わせる意義が高まります。
一時的な下落局面で積立投資を止めてしまうと、価格が安いときに買える「おいしいタイミング」を逃すこともあるため、無理のない金額の範囲で積立を継続できるかどうかをあらかじめ検討しておきたいところです。
トランプ政権がブラジル産牛肉・コーヒーへの関税撤廃を決定
米トランプ政権はブラジルから輸入される牛肉やコーヒー、ココアなど一部農産品に対して課していた40%の追加関税を撤廃する大統領令に署名しました。
関税は今年7月に同国のボルソナロ前大統領の訴追を巡る対立を理由に導入されていましたが、ブラジルが米国向けコーヒー輸出の約3分の1を担うほか主要な牛肉供給国でもあることから、価格高騰や物価高を懸念する声が強まっていました。
同じタイミングで発表された国際NGOの調査では、米国や日本を含む先進国が開発途上国への支援を縮小しているとの結果も示されており、貿易や援助を通じたグローバルな連帯の在り方が改めて問われています。
 ねくこ
ねくこ食料やエネルギーの国際価格は日本の食料品価格や光熱費にも波及するため、遠い国の出来事のように見えても、数カ月から数年の時間差を伴って家計に影響が出ることがあります。
私たちの生活に起こること
物価と金利の動きが家計に与える影響を整理する
日本の物価上昇率が3%前後で推移し金利もじわじわと上昇している状況では、現金だけを保有していると実質的な購買力が少しずつ目減りしていく一方、ローン金利や借入コストは今後上がる可能性があります。
本文中の物価・金利水準は2025年10月時点の統計や報道に基づくものであり、今後の物価や金利の動きを保証するものではありません。日本銀行は消費者物価上昇率2%を物価安定の目標としていますが、将来の金融政策や市場金利は国内外の経済情勢によって変動します。
住宅ローンなど変動金利型の借入が多い世帯では、金利上昇局面で返済額が増えるリスクを意識しつつ、繰り上げ返済や固定金利への借り換えなどの選択肢を含めて中長期の返済計画を検討することが重要です。
その際には、金融機関ごとの手数料や金利条件、団体信用生命保険の取り扱いなどを必ず確認し、総支払額ベースで比較するようにしましょう。

一方で預貯金金利が上昇してきた場合には、安全資産であっても得られる利息が増える可能性があるため、金利の動きを踏まえて普通預金と定期預金の比率を見直す余地も出てきます。
 ねくこ
ねくこ金利や物価のニュースを見たときは、「自分の家計にとってはプラスかマイナスか」「いつ頃から影響が出そうか」という二つの軸で考えると、単なる不安ではなく具体的な行動につなげやすくなります。
物価高と円安のなかで家計防衛のためにできること
物価高や円安で食料品や光熱費がじわじわと上がる局面では、いきなり収入を増やすことが難しい分、毎月の固定費や生活習慣を見直すことが家計防衛の第一歩になります。




通信費や保険料、サブスクリプションサービス、使っていない口座の手数料などは、見直すことで毎月数千円から1万円程度の節約につながるケースも多く、物価上昇分をカバーする余地になり得ます。

また家計簿アプリやクレジットカードの利用明細を活用して支出を見える化し、1〜2カ月だけでも細かく記録することで、自分にとって優先度の低い支出を見つけやすくなります。
 ねくこ
ねくこ節約と聞くと我慢をイメージしがちですが、まずは「払っていることすら忘れている支出」を減らすだけでも効果が出やすく、生活の満足度を大きく落とさずに家計を軽くすることができます。
同時に健康やスキルアップなど将来への投資につながる支出はむやみに削りすぎず、メリハリを付ける意識も忘れないようにしたいところです。
長期の資産形成は「時間」と「分散」を味方につける
相場変動が激しいときほど、長期の資産形成では時間と分散を味方につけることで、一時的な値下がりの影響をある程度ならしながら将来の資産形成を目指す発想が重要になります。
ただし、長期投資であっても元本が保証されるわけではなく、運用成果は市場環境によって変動します。
NISAやiDeCoを活用した積立投資では、毎月一定額を機械的に投資することで高いときにも安いときにも同じ金額で購入し、結果として平均購入単価を平準化しやすくなるとされています※。
※ 将来の運用成果や元本の保証を意味するものではありません。
国内株だけでなく、海外株式や債券、REIT(不動産投資信託)など複数の資産クラスに分散することで、特定の国や業種の不調に家計全体が引きずられにくくなります。
 ねくこ
ねくこ長期投資の成否は「いつ買ったか」よりも「どれだけの期間続けられたか」に左右されるといわれることが多く、無理のない金額設定と生活防衛資金の確保が、途中でやめずに続けるための土台の一つになります。
免責事項
本記事は2025年11月21日時点で入手可能な情報に基づき編集部が一般的な解説を行ったものであり、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
将来の市場環境や価格、金利、為替レートなどは予測と異なる可能性があり、本記事の内容はその結果を保証するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的な判断は、必ずご自身の責任と判断により行い、必要に応じて金融機関や専門家への相談もご検討ください。
また、税制や各種制度、金融商品の手数料・金利・為替レート等は将来変更される可能性があります。本記事で取り上げたNISA・iDeCoその他の制度や商品については、必ず最新の公式情報や目論見書・契約書類等をご確認ください。