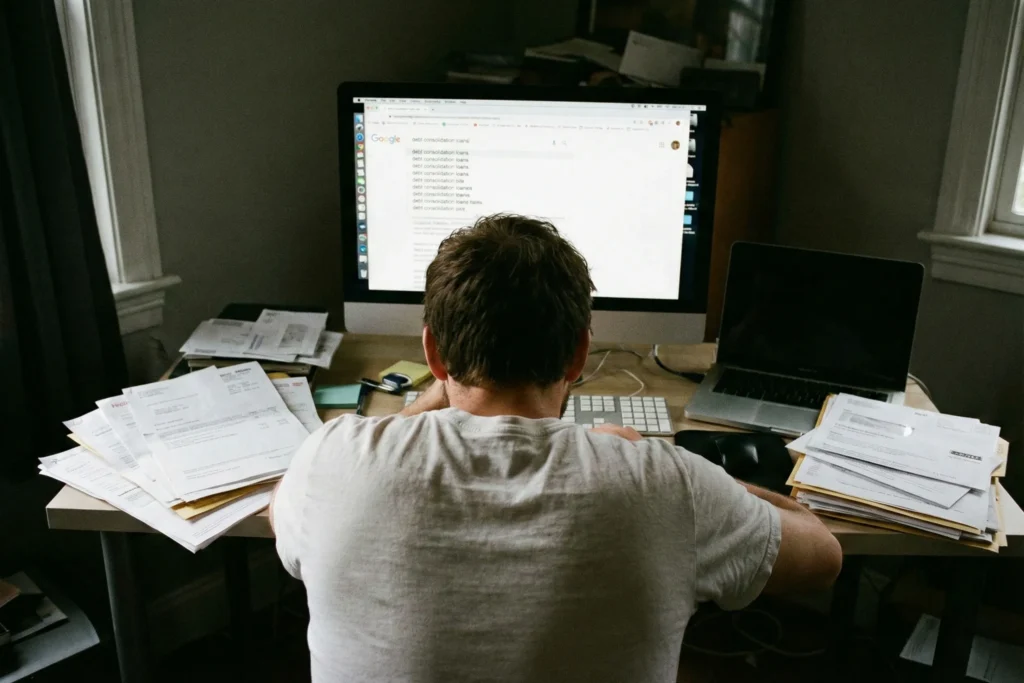【2025年11月26日】の経済・時事ニュースまとめ
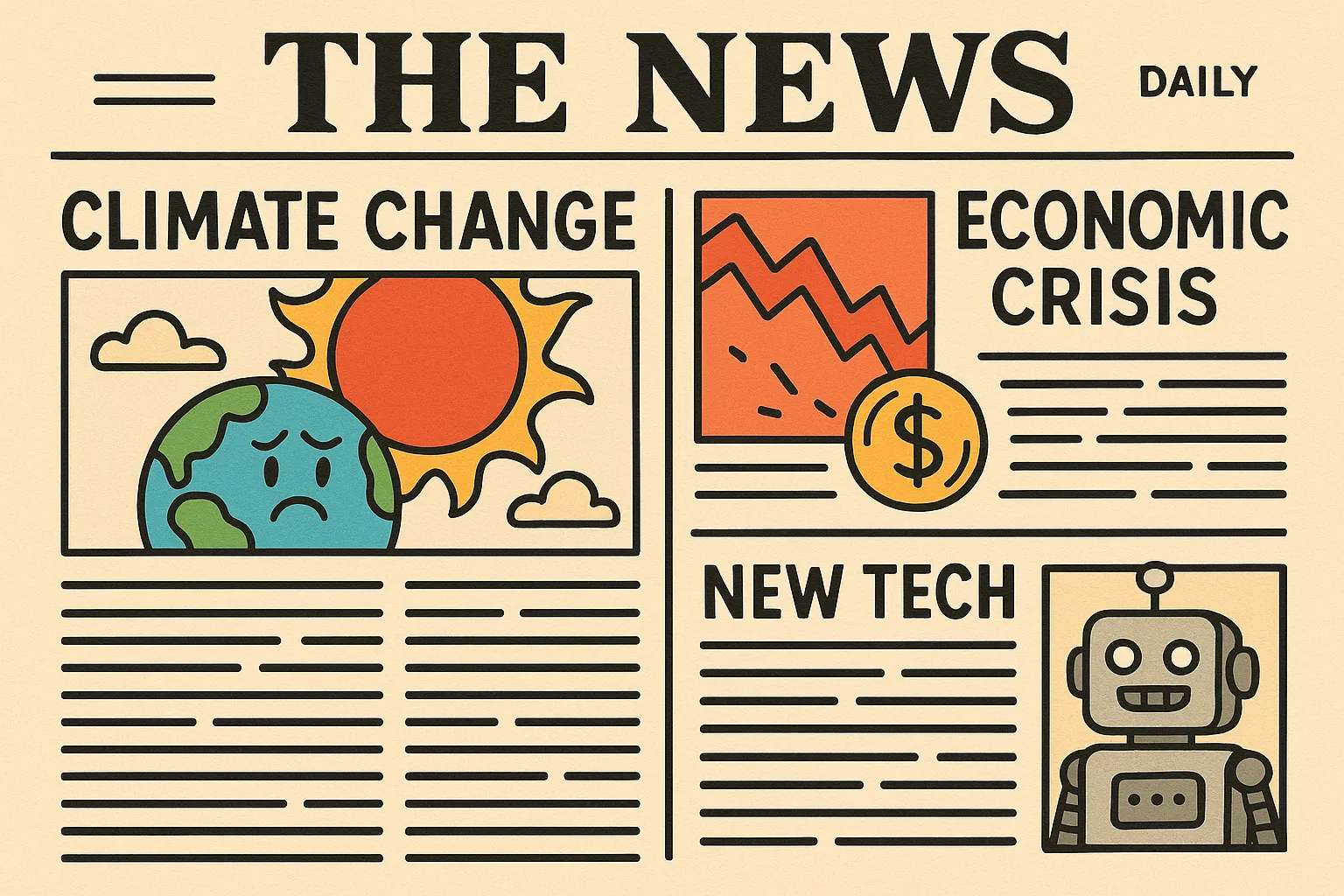
2025年11月26日の金融市場は、米利下げ期待を背景に米株が大幅高となり、その流れを受けて日経平均も4万9000円台を回復するなど、株高・ドル安が同時に進む1日となっています。
国内では、高市政権初の政労使会議で「物価に負けない賃上げ」が呼びかけられたほか、20兆円超規模の総合経済対策を支える2025年度補正予算案のスケジュールも具体化しつつあります。
海外では、ウクライナ和平案を巡る交渉の前進や豪州の物価指標の上振れ、日中間のフライト減便報道、アメリカウナギの国際規制議論など、地政学とインフレが絡み合うニュースが相次いでいます。
 ねくこ
ねくここの記事では、最新24時間以内のニュースをもとに、主要株価指数と為替の動き、資産運用で意識したいポイント、国内外の注目トピックス、そして私たちの生活への影響を整理してお伝えします。
主要株価指数・為替レート(2025年11月26日10時時点)
| 指標 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 49,388.64円 | +729.12(+1.49%)円 |
| NYダウ | 47,112.45ドル | +664.18(+1.43%)ドル |
| S&P500 | 6,765.88ポイント | +60.76(+0.91%)ポイント |
| ドル円為替(ドル/円) | 155.95円 | -0.29円 |
ここでは、日本時間2025年11月26日10時時点で把握できる主要株価指数の最新終値と、ドル円レートの午前の水準を一覧にしています。
日経平均は米利下げ期待で4万9000円台を回復
26日午前の東京株式市場では、日経平均株価が前日比でおよそ1.5%高の49,388.64円前後まで上昇し、4万9000円台をしっかり回復する展開となっています。
背景には、前日の米国株市場でダウ平均が664ドル高、S&P500も0.9%上昇するなど主要3指数がそろって続伸し、年内追加利下げ観測が強まったことがあります。
東京市場でも、米金利低下と株高を受けて輸出関連株やハイテク株に買いが入り、日経平均の寄り付きは前日比352円高の4万9012円と買い優勢のスタートとなりました。
一方で、値がさ株やAI関連銘柄には前日までの調整の流れが残っており、寄り付き後は4万9000円台を挟んで一進一退となる場面もみられています。
 ねくこ
ねくこ足元では、日経平均が5万円台を明確に回復できるかどうかが投資家心理の節目とされており、米利下げのタイミングと円安進行が企業業績の押し上げ材料になるかが注目されています。
米国株は利下げ期待で3日続伸、景気減速との綱引き
25日の米国株式市場では、ダウ工業株30種平均が前日比664.18ドル高の4万7112.45ドルと3日続伸し、S&P500も60.76ポイント高の6765.88と史上高値圏に迫る水準まで上昇しました。
9月の小売売上高や卸売物価指数(PPI)が市場予想を下回り、米景気の減速を示唆したことで、12月のFOMCで追加利下げが行われるとの観測が一段と強まりました。

CMEのFedWatchによれば、12月会合で0.25%の利下げが行われる確率は先週の約50%から8割前後へと高まり、これを受けて米長期金利が低下し株式市場を支えています。
もっとも、半導体大手など一部のAI関連銘柄には利益確定売りも出ており、指数全体は上昇しつつも銘柄ごとに値動きの差が大きくなる「選別相場」の様相も強まっています。
 ねくこ
ねくこ利下げ期待による株高はプラス材料ですが、データ次第では「景気減速が深刻だから利下げする」という見方に転じる可能性もあり、今後の指標やFRB要人発言に市場の注目が集まっています。
ドル円は156円前後まで軟化、米利下げ観測でドル安優勢
25日のニューヨーク外国為替市場では、ドル円が一時155円80銭付近まで下落した後、終値は156円03銭前後と、前日終値の156円89銭付近からおよそ80銭のドル安・円高で引けました。
弱めの米小売売上高やPPI、消費者信頼感指数などが相次いで発表され、米景気の減速懸念と12月利下げ観測の高まりを受けて、ドル売り・円買いが優勢となったためです。
東京時間26日午前のドル円は156円台前後でもみ合い、9時ごろの気配値は155.95円前後、前日17時時点から30銭弱のドル安・円高水準にあります。
為替ニュース各社は、米利下げ期待の一方で日本は依然として大規模金融緩和を維持していることから、基本的な円安基調は続きつつも、155円台前半には厚い買い注文が控えて下値を支えていると指摘しています。
 ねくこ
ねくこ為替水準そのものを短期的に当てようとするよりも、自分の資産全体でどの程度の外貨比率を許容するか、円高・円安の両方のシナリオで家計にどのような影響が出るかを考えておくことが重要です。
資産運用をしている人がこの局面で心掛けるべきこと
「長期・分散・積立」の基本を崩さない
株式市場や為替が大きく動く局面ではニュースを見るたびに売買したくなりますが、長期の資産形成を目指すなら一時的な値動きに振り回されないことが大切です。
特にNISAを使っている人は、非課税のメリットを生かすためにも数年から10年以上の時間軸でコツコツ積み立てる前提でプランを見直すとよいでしょう。

新しい制度では「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を組み合わせることで、値動きの大きい株式と比較的安定した投資信託をバランスよく持つことができます。

一気に投資額を増やすよりも、毎月一定額を自動で積み立てることで価格が高いときも安いときも平均的なコストで買える「ドルコスト平均法」が働きやすくなります。
 ねくこ
ねくこ長期で資産を増やすには、相場が好調なときほど「今は買い過ぎていないか」と自分を冷静にチェックする習慣をつけておくと安心です。
円安局面での外貨建て資産と為替リスクの整理
ドル円が156円前後と歴史的な円安水準にあるなか、外貨建ての投資信託や米国株を持っている人は円ベースでは評価額が増えやすい一方で今後円高に振れた場合の逆風も大きくなります。
iDeCoや企業型DCのように老後資金を長期で積み立てる仕組みでは、為替だけでなく株価も長い時間をかけて上下することを前提に資産配分を決めることが重要です。

短期の値動きだけを狙ってレバレッジをかけたFX取引に踏み出すと、想定外の方向に相場が動いたときに元本以上の損失を抱えるおそれがあり初心者にはリスクが高い商品です。

外貨資産を増やしたい場合は、投資信託や為替ヘッジ付きの商品なども含めて家計全体の金融資産のうち何割を外貨建てにするかという視点で無理のない範囲にとどめることが現実的です。
 ねくこ
ねくこ具体的な為替水準を予想してポジションを取るのではなく「今の円安が続いても、ある程度円高に戻っても生活が破綻しないか」というシナリオでシミュレーションしておくと安心です。
家計のクッションと固定費の見直しを意識する
金利や物価が大きく動くときほど生活費の6か月分程度の現金を手元に残しつつ残りを投資に回すという「クッション」を意識することが大切です。
毎月の固定費が膨らんだままだと物価や金利が上がったときに貯蓄に回せるお金が減り、せっかくの投資計画が続かなくなるリスクがあります。




家賃や通信費、保険料、ローン金利などはすぐに削りにくいイメージがありますが、契約の見直しや借り換え、不要なオプションの解約などで中長期的に支出を軽くできる可能性があります。
 ねくこ
ねくこ投資の利回りばかり気にするのではなく、電気代やスマホ代を見直して月数千円節約できれば、それをそのまま積立額の上乗せに回すという発想もインフレに備える一つの方法です。
国内ニュース
高市政権初の政労使会議で「物価に負けない賃上げ」を要請
政府は25日、高市政権として初めて経済界と労働団体の代表者を集めた政労使会議を開き、高市首相は2026年春闘で「物価上昇に負けないベースアップ」の実現に協力を求めました。
会議では、中小企業の賃上げを後押しする1兆円規模の支援策や、全国で地方版政労使会議を開催する方針が説明され、政府の総合経済対策との連携が強調されました。
連合は既に2026年春闘で3年連続となる5%以上の賃上げを目指す方針を打ち出しており、非正規労働者では7%を目安とするなど、物価3%台の環境下で実質賃金の底上げを狙う動きが続いています。
 ねくこ
ねくこ賃上げの議論は、来年の給与やボーナス、地域ごとの最低賃金だけでなく、政府の補助金や税制優遇の方向性ともつながるため、自分の働く業界や雇用形態にどのような影響が出そうかを意識してニュースを追うことがポイントです。
2025年度補正予算案、11月28日に閣議決定へ
26日の報道によると、政府は総合経済対策の財源となる2025年度補正予算案を11月28日(金)に閣議決定し、12月の臨時国会に提出するスケジュールを想定しています。
補正予算は20兆円超規模の経済対策を裏付けるもので、地方の物価高対策や中小企業の賃上げ支援、子育て支援などに重点が置かれる見通しです。
年末までには与党税制改正大綱や2026年度当初予算の編成も同時に進むため、税負担や社会保障制度の見直しがどの程度盛り込まれるかが家計にとっても重要な論点になります。
 ねくこ
ねくこ補正予算や税制改正の内容は、給付金やポイント還元だけでなく、住民税や社会保険料を通じた負担にも影響するため、自分の自治体や勤め先がどのような支援策の対象となるのかを一度確認しておくとよいでしょう。
私立大学などで非常勤講師が一斉スト、賃上げを要求
26日付の報道では、日本大学や専修大学、日大三島中学・高校など複数の私立大学・付属校で、非常勤講師の労働組合が15%の賃上げや正規教職員の10%賃上げなどを求めて一斉ストライキを実施したことが伝えられました。
25日には、日大文理学部の正門前でスト集会が開かれ、正規教員がストを支援したり学生が手を振って応援するなど、教職員と学生が連帯する様子も報じられています。
大学側が賃上げ要求を理事会に伝えていないと労組側が批判するなど、非正規教員の待遇改善と大学財政の制約の間で、今後の交渉の行方に注目が集まっています。
 ねくこ
ねくこ教育現場での賃上げ要求は授業料や学校運営費にも影響し得るテーマであり、保護者や学生にとっても無関係ではない問題として、大学側の説明や交渉の透明性が一層求められます。
中国政府が日本行きフライトの減便を要請、日中往来に影響懸念
26日の報道によると、中国政府が自国の航空会社に対し、2026年3月末まで日本行きのフライトを減便するよう「当面の措置」として求めていたことが、米メディア報道を通じて明らかになりました。
減便する路線や本数は各社の判断に委ねられるものの、春節シーズンを含め日中間の移動需要に影響が出る可能性が指摘されており、観光業や航空業界では先行きへの警戒感が高まっています。
背景には、高市首相の台湾有事に関する国会答弁に中国側が反発していることがあるとされ、外交・安全保障を巡る発言が航空路線や観光需要にも直結し得ることが改めて浮き彫りになりました。
 ねくこ
ねくこ海外旅行や出張を予定している人は、円相場だけでなく、直行便と乗り継ぎ便の運航状況やキャンセルポリシーも含めて早めに確認しておくと、急な減便や運休のリスクに備えやすくなります。
海外ニュース
米利下げ期待とドル安で世界の株式・債券市場が反発
25日の世界の金融市場では、米金利の低下と利下げ期待に支えられ、欧米株がそろって上昇し、米国株は主要3指数が3日続伸するなど「リスクオン」の流れが強まりました。
ロイターによれば、CME FedWatchが示す12月会合での0.25%利下げの織り込みは先週の約50%から8割超へ高まり、米10年債利回りも低下するなど、金利と為替の同時調整が進んでいます。
ドル安が進む一方で、景気減速への懸念も残っており、今後の指標次第では「利下げ=景気悪化のサイン」と受け止められて相場のボラティリティが高まる可能性も指摘されています。
 ねくこ
ねくこ海外株式や外貨建て債券に投資している場合は、利下げ局面で値上がりが期待できる面だけでなく、企業収益や財政の持続性も合わせてチェックすることで、過度なリスク取りを避けやすくなります。
ウクライナ和平案を巡る交渉が前進も、条件面ではなお溝
26日の報道では、トランプ米大統領がロシアとウクライナの和平協議が前進しており、ロシアがいくつかの譲歩に応じたと述べた一方で、合意に期限は設けない考えを示したと伝えられています。
一方、日本の報道によれば、ウクライナが領土をどこまで放棄するかや軍の規模、NATO加盟を断念するかどうかなど、少なくとも3つの重要な論点で米ウクライナ側と米政権との間に見解の相違が残っているとされています。
ウクライナ国家安全保障会議の幹部は、ゼレンスキー大統領が数日以内に訪米し、戦争終結に向けた合意を最終決定する可能性があるとしながらも「ウクライナが受け入れられる案はまだ存在しない」と慎重な姿勢も示しました。
 ねくこ
ねくこ仮に停戦合意に至ったとしても、制裁解除や復興資金の負担、エネルギー供給ルートの再構築など経済面の調整には長い時間がかかると見込まれます。
日本企業の投資計画やエネルギー価格にも中長期的な影響が及ぶ可能性があります。
豪州の物価指標が予想を上回り、利下げペースに注目
26日に発表されたオーストラリアの10月消費者物価指数(CPI)は前年同月比3.8%上昇と、市場予想の3.6%を上回り、インフレ圧力の根強さが意識されました。
四半期ベースでは今年7〜9月期のCPIが前期比1.3%上昇しており、電気料金や住宅関連費用、外食などの価格上昇が全体の押し上げ要因となっています。
インフレ率が豪準備銀行(RBA)の目標レンジ上限付近にとどまっていることから、利下げ開始のタイミングが後ずれする可能性もあり、指標発表後の豪ドルは底堅い値動きとなりました。
 ねくこ
ねくこ高金利通貨として豪ドル建て資産を保有している場合、金利差だけでなく現地の物価動向や経済成長率もあわせてチェックすることで、長期保有のリスクとリターンをより正確に把握しやすくなります。
アメリカウナギの国際規制議論が本格化、日本のうなぎ価格にも影響懸念
27日からのワシントン条約締約国会議では、ウナギの取引規制を巡る本格的な議論が始まる予定で、日本で安く販売されているアメリカウナギも規制強化の対象候補となっています。
アメリカやカリブ海で捕れたアメリカウナギの稚魚は主に中国へ輸出されて養殖・加工された後、日本に輸入されてスーパーなどで比較的安価なうなぎとして販売されているのが現状です。
規制が強化され輸出が減った場合、日本への供給量が細り、うなぎ価格の上昇や品薄につながる可能性があるとして、地元漁業者や関係者からは懸念の声が上がっています。
 ねくこ
ねくこうなぎはすでに高級食材となりつつありますが、国際的な資源管理の流れは今後も続くとみられます。
土用の丑の日などの食文化も含め、価格と供給の変化にどう向き合うかが家計の小さなテーマになりそうです。
私たちの生活に起こること
賃上げと物価の「追いかけっこ」は当面続く可能性
日本の10月の消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)は前年比3.0%上昇と2か月連続で伸び率が拡大し、電気代や食料品、とりわけ年末食材を中心に物価高が続いています。
一方で、連合は2026年春闘で3年連続となる5%以上の賃上げを目指す方針を掲げており、中小では6%以上、非正規では7%を目安とするなど、実質賃金をプラスに転じさせることを重視しています。
ただし、賃上げが実際の手取り収入として増えるまでには時間差があるうえ、社会保険料や税負担も変化するため「給料は上がったのに生活はあまり楽にならない」という状況が当面続く可能性があります。
 ねくこ
ねくこ給与明細を確認するときは、基本給だけでなく残業代や各種手当、社会保険料の増減も合わせてチェックし、家計簿アプリなどで実質的な可処分所得がどう変わっているかを把握しておくとよいでしょう。
円安とドル安の揺り戻しが物価と旅行費用に与える影響
足元のドル円は昨年より円安水準ながら、米利下げ観測の高まりで一時155円台までドル安・円高方向に振れる場面もあり、円安トレンドの中で小さな揺り戻しが続いている状態です。
円安が続けば輸入食品やエネルギー価格を押し上げる一方、今回のようにドル安が進む局面ではドル建ての海外旅行費用や米国株投資の為替コストがやや軽くなる可能性もあります。
さらに、中国政府が日本行きフライトの減便を航空各社に求めているとの報道もあり、為替だけでなく路線数や燃油サーチャージといった要因も海外旅行の費用や選択肢に影響を与えます。
 ねくこ
ねくこ海外旅行を計画する際は、早めの予約で運賃を抑えるか、直前まで様子を見るかだけでなく、為替の両替タイミングやキャンセル条件も含めて「総額」で比較することが、円安下での賢い選び方につながります。
家計が今からできる3つの具体的な準備
物価と賃金、為替のニュースが相次ぐ今だからこそ、まずは家計全体の資産と負債を一覧にし「現金・預金」「投資」「ローンなどの借金」のバランスを見える化しておくことが大切です。
次に、今後1〜2年の大きな出費(教育費、車検、住宅の修繕、旅行など)を洗い出し、それぞれにどの通貨でどの金融商品を使って準備するかをざっくり決めておくと、相場変動に慌てにくくなります。
あわせて、ガソリン代や電気代、食費など主要項目について「価格が10%上がると年間いくら負担が増えるか」を一度計算しておくと、ニュースで聞く数字が自分の生活にどう響くかを具体的にイメージしやすくなります。
 ねくこ
ねくこ今日のように市場や政治のニュースが多い日は、すべてを追いかけるのではなく、自分の勤務先や居住地域、ライフプランに関係が深いニュースに絞って情報収集するだけでも十分です。
免責事項
本記事は2025年11月26日時点で公表されている情報に基づき作成したものであり、将来の市場動向や経済情勢を保証するものではありません。
記載された内容は一般的な情報提供および教育的な解説を目的としたものであり、特定の株式、投資信託、為替取引、保険商品などの購入や売却を推奨するものではありません。
実際の投資やライフプランに関する最終的な判断は、必要に応じて金融機関や専門家の説明も参考にしつつ、必ずご自身の責任と判断で行ってください。