住宅ローンはみんないくら払ってる?目安となる平均額や、収入に合わせた借入額、返済額目安など決め方を紹介

マイホーム購入を考え始めると、
など、住宅ローンについて様々な疑問が浮かぶのではないでしょうか。
特に30代の共働き夫婦で世帯収入がある程度ある場合でも、本当に無理なく返済できる金額はどのくらいなのか悩むものです。
住宅ローンは長期にわたる大きな支出になるため、平均的な返済額や借入可能額の目安を知り、自分たちに合った計画を立てることが大切です。
この記事でわかること:
- 最新データから見た住宅ローンの平均返済額(物件の種類ごとの年間・月額平均)
- 家計やライフプランから逆算して考える無理のない返済額の決め方(生活費・教育費・貯蓄など具体例)
- 返済額に大きく影響する借入期間の考え方(平均的な借入期間と長期返済のメリット・デメリット)
- 共働き夫婦における住宅ローンの組み方の選択肢(ペアローンと収入合算の違い、メリット・注意点)
 MIYABI
MIYABI宅建資格保持者&住宅ローンアドバイザーの筆者が解説していきます!
では、順番に見ていきましょう。

みんな住宅ローンを月々いくら払っている?最新データで見る平均返済額

まずは世間一般の住宅ローン返済額がどの程度なのか、最新のデータから押さえておきましょう。
物件の種類ごとの年間平均返済額はこちら
国土交通省「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」の調査によると、住宅ローンを利用している世帯の年間返済額(1年間に返済している元利合計)は、物件の種類によって次のようになっています。
 MIYABI
MIYABIかっこ内は月額に換算した平均です。
| 物件種別 | 年間返済額(平均) | 月額換算(平均) |
|---|---|---|
| 注文住宅(新築) | 約174万円 | 約14.5万円/月 |
| 分譲戸建住宅(新築) | 約127万円 | 約10.6万円/月 |
| 分譲マンション(新築) | 約148万円 | 約12.3万円/月 |
| 中古戸建住宅 | 約107万円 | 約8.9万円/月 |
| 中古マンション | 約101万円 | 約8.4万円/月 |
新築注文住宅とは土地から購入して建築したケース、分譲戸建は建売住宅、分譲マンションは新築マンションの購入ケースを指します。
見ると、注文住宅(新築一戸建て)の月々返済額が平均約14.5万円と最も高く、中古マンションが約8.4万円と最も低くなっています。
 MIYABI
MIYABI注文住宅は新築なので購入費用が高額になりやすい一方、中古物件は購入価格が抑えられる傾向にあるためです。

新築と中古では、購入&ローン借入額に大きな差が伺える
実際、同調査によると新築・中古の戸建て住宅における購入&ローン借入額は、
新築注文住宅・・・平均購入額5,436万円/平均借入額3,772万円
であるのに対し、
中古戸建住宅・・・平均購入額3,340万円/平均借入額1,908万円
と、大きな差があります。
借入額が大きければ毎月の返済も増えるため、物件種別による返済額の差は購入価格・借入額の差を反映していると言えるでしょう。
 MIYABI
MIYABIなお、注文住宅(新築)の年間返済額が約174万円ということは、ボーナス併用払いがなければ月々約14.5万円の返済に相当します。
多くの人は返済期間を30~35年程度に設定している
また多くの人が返済期間を30~35年程度に設定しています。
先の国交省調査でも、住宅ローンの平均借入期間は
- 注文住宅で約33年
- 分譲戸建て約33年
- マンション約29~30年
- 中古住宅で約28~29年
と報告されています。
 MIYABI
MIYABIつまり「住宅ローン=約30年かけて返済していく」のが一般的という前提で、上記の平均返済額が成り立っている点も押さえておきましょう。
世帯年収1000万円だと住宅ローンはいくら借りられる?毎月の返済額モデルケース

平均は参考になりますが、
は、借りる人や世帯の収入によって変わります。
ここでは仮に、共働きなどで世帯年収が1000万円あるケースをモデルに、毎月どのくらいの返済額・借入額になるか考えてみましょう。
 MIYABI
MIYABIその際、ポイントとなるのが「返済負担率」という考え方です。
住宅ローンの「返済負担率」とは?
返済負担率とは、年収に占める年間返済額の割合のことです。
計算式で表すと、以下のようになります。
返済負担率(%)=年間の住宅ローン返済額 ÷ 年収 × 100
金融機関の住宅ローン審査では、この返済負担率が重要な指標になります。
一般的な銀行やフラット35による融資の場合、年収に対して返済負担率が高すぎると審査に通りにくいのが通常です。
例えばフラット35ではすべての借入れ※に関して、年収に占める年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が次表の基準を満たす方(収入を合算できる場合があります。)という基準があります。
| 年収 | 400万円未満 | 400万円以上 |
| 基準 | 30%以下 | 35%以下 |
民間銀行でも多くは返済負担率35%前後を上限基準にしています。
※【フラット35】のほか、【フラット35】以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含みます。)などをいいます(収入合算者の分を含みます。)。また、賃貸予定または賃貸中の住宅に係る借入金を含みます(当該借入金が賃貸用のアパート向けのローン(ローンの対象が1棟の共同住宅または寄宿舎)である場合は、借入金には含めません。)。参考:フラット35
 MIYABI
MIYABIただし、これはあくまで「銀行が貸せると判断する上限」であって、借りる側にとって無理のない負担かどうかとは別問題です。
実際は「手取り収入の20~25%」が理想と言われる
いくら上述の返済負担率の基準内に収まっているといっても、実際は金融機関の基準ギリギリまで借りてしまうと、家計に余裕がなくなる恐れがあります。
そのため、
という考え方が広く用いられます。
手取り収入とは、税金や社会保険料を差し引いた後の実際に使える収入(可処分所得)のことです。
 MIYABI
MIYABI額面年収(税引き前)ではなく、手取りベースで考えましょう。
そうすることで、生活費なども考慮した現実的な負担率を把握できます。
年収1000万円のケースで毎月いくらまで返済に充てられる?

これらの前提から、仮に世帯年収1000万円の場合、具体的に毎月いくらぐらいの住宅ローン返済が「無理のない範囲」なのでしょうか。
 MIYABI
MIYABI前述のとおり、理想は手取り収入の20%前後、上限でも25%程度に収めることです。
年収1000万円(額面)だと手取りは家族構成にもよりますが、
ざっくり年740万円前後、つまり÷12した、月あたり62万円前後が可処分所得になるケースが多いでしょう。
この「手取り月収に対して20~25%」ということは、
が目安となり、年間では148.8~186万円程度が目安となります。
 MIYABI
MIYABI実際、ファイナンシャルプランナーからも「住宅ローンの返済は手取り年収の20~25%以内に抑えるのが安心」とよく言われています。
世帯年収800万円なら手取り640万円前後、年収500万円なら手取り400万円程度なので、これらの20~25%を目安にしましょう。
低金利の変動型ローンであれば5,000~6,000万円程度が目安
年収1000万円の個人や家庭の場合、仮に、金利1%前後の変動金利型ローンを利用できれば、5,000~6,000万円前後の借入も返済負担率25%以内で可能となる計算です。
実際、住宅ローンの目安として「ざっくり額面年収の5倍~6倍程度まで」と言われることがありますが、
と言えるでしょう。
 MIYABI
MIYABI年収800万円なら4,000~4,800万円、年収500万円なら2,500~3,000万円ですね。
簡易シミュレーション:年収1,000万円のケース
前提:金利1.0%、元利均等返済、返済期間35年、ボーナス返済なし、返済比率25%目安
- 5,000万円→月約14.1万円
- 6,000万円→月約16.9万円
 MIYABI
MIYABI可処分所得が月62万円前後なら、6,000万円は25%をやや超える可能性があるため“5,000万円台が現実的目安となります。
一方、フラット35などの固定金利型ローンは、金利が固定され返済計画が立てやすい反面、変動金利型に比べて金利が高めに設定される傾向があります。
フラット35(全期間固定金利)・金利2.45%・返済期間35年のローンシミュレーションを行うと、年収1,000万円の個人/家庭の借入可能額は約4,400万円となり、上記の変動金利のケースと比べると借入可能額が減ることが分かります。。

重要なのは無理なく返せること
しかし、重要なのは「いくら借りられるか」より
です。
たとえ年収的に6000万円以上借りられる余地があっても、毎月の返済が手取りの3割にも達するようでは家計に余裕がなくなり、想定外の出費に対応できなくなる可能性があります。
先ほど例に挙げた、月15万円前後の返済額であれば、返済負担率が25%のため「子どもが2人いても家計に多少の余裕がある額」といった試算結果もあります。
 MIYABI
MIYABIつまり、年収1,000万円だとしても手取りの3割を超える月20万円を超えるような返済は、かなり収入にゆとりがない限り避けた方が無難でしょう。
もちろん、日々の出費や子どもの人数などに左右される事情ではありますが、あれもこれもという方が住宅ローンも目一杯というのはおすすめできません。
家計とライフプランから逆算!無理のない住宅ローン返済額の決め方

ローン返済とは別に、固定資産税・都市計画税、火災/地震保険、(マンションなら)管理費・修繕積立金、駐車場代など“居住コストの固定費”を月換算で別枠計上してください。これらは金利や家族構成に関わらず発生します。
住宅ローンの「無理のない返済額」は、それぞれの家計状況やライフプランによって異なります。
 MIYABI
MIYABIそこで、具体的な支出項目を洗い出し、毎月の家計から逆算して返済に充てられる金額を算出する方法を紹介します。
以下のステップで考えてみましょう。
①月々の手取り収入を把握する
まずは、世帯の手取り月収の合計を確認します。共働きの場合は夫婦それぞれの手取りを合算しましょう。
(当然ですが)仮に手取り月収が合計50万円であれば、それが家計全体で使えるお金の上限です。
 MIYABI
MIYABIボーナスは変動しやすいので、できればボーナスに頼らず月収の範囲で返済計画を立てることをおすすめします。
②毎月の生活必需コストを差し引く
次に、手取りから毎月の生活必需コストを差し引きます。
- 食費・日用品などの生活費
- 電気・ガス・水道などの光熱費
- スマホ代・インターネット代などの通信費
- 車の維持費(車を所有していればガソリン代・駐車場代・自動車保険等)
- 各種保険料(生命保険・医療保険など)
- その他、交通費や交際費、趣味娯楽費 など
これらは人によって金額が異なりますが、ざっくり毎月20~25万円程度は固定的に出ていく家庭が多いようです。
 MIYABI
MIYABI仮に生活費等の合計が20万円なら、手取り50万円の場合、残り30万円が住宅ローンや貯蓄・教育費に回せる枠となります。
③将来の教育費やライフイベント費を見積もる

お子さんがいる(または今後予定している)場合は、教育費の積立も考慮しましょう。
一般に教育費は手取りの5~10%程度が適正水準と言われます。
例えば手取り50万円なら、子どもの教育費に毎月2.5~5万円は充てたいところです。
 MIYABI
MIYABIまた、「マイカーの買い替え」「家族旅行」「冠婚葬祭」など、将来的に発生し得る大きめの支出も可能な範囲で見積もっておきます。
これら将来費用に備えて「毎月〇万円を貯蓄」と、決めて先取り貯蓄しておくと安心です。

④緊急予備資金も確保する
エアコンなど家電の買い替え、車の修理代、病気・ケガによる医療費負担など、急な出費も人生にはつきものです。
こうしたイレギュラー出費に備える予備費も毎月少しずつ貯めておくと心強いです。
 MIYABI
MIYABI家計全体の5~10%程度を目安に貯蓄や予備費にまわす家庭が多いです。
残った金額が「無理なく返済に充てられる額」
そして、①~④の支出をすべて差し引いて、まだ残っている金額が、毎月の住宅ローン返済に充てても家計が回る上限額と言えます。
例えば、手取り50万円の共働き世帯の場合
- 生活費等:25万円
- 教育費貯蓄:5万円
- 予備の貯蓄:5万円
50万円ー(25万円+5万円+5万円)=15万円
その家庭の収入や生活費を考慮すると、無理なく返済できる最大の月額返済額の目安は15万円となります。
実際にはここからさらに多少の余裕をみて、たとえば
といった保守的な設定にすると、より安心でしょう。
 MIYABI
MIYABIここは、ご家族の皆さまの価値観(何にお金を使いたいか)などで決めて行きましょう。
いずれにせよ、以上のように家計をシミュレーションすると、
という具体的な数字が見えてきますが、その金額こそが「自分たちにとって無理のない返済額」です。
 MIYABI
MIYABI例えばお子さんが小さいうちは教育費はそれほどかからなくても、中学高校と進むにつれて増加するなども加味してくださいね。

あるいは、共働きでも、将来どちらかが育児や介護で一時的に退職・収入減となる可能性も考えられます。
もちろん各家庭で事情は異なりますが、一つの参考基準として覚えておきましょう。
余裕を持たせるためのポイント
- ライフプランの変化を見据えて、多少の収入減や支出増があっても維持できる範囲に返済額を設定する
- 家計バランスの目安として、住宅ローン返済は手取り収入の20%前後、教育費は5~10%程度に抑えるのが理想
借入期間で変わる月々の返済額:長期ローンのメリット・デメリット
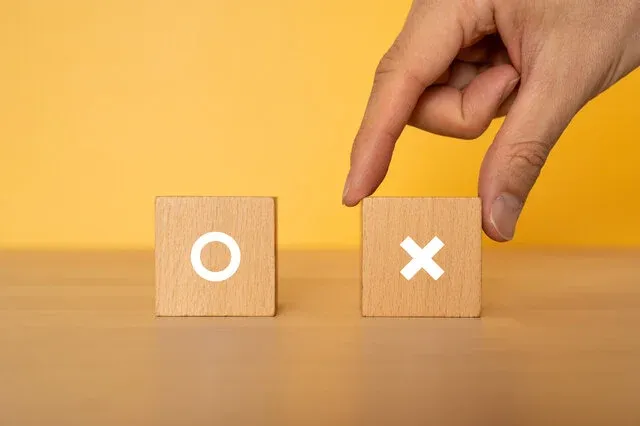
さらに、住宅ローンの毎月返済額は、借入金額だけでなく「借入期間」によっても大きく変わります。
前述のとおり、日本の住宅ローンの平均的な返済期間はおよそ30年前後、特に多くの方は35年ローンを利用します。
しかし、同じ金額を借りても、返済期間が長くなれば月々の返済負担が小さく、短くすれば総返済額が小さくなります。
 MIYABI
MIYABIここでは平均的な返済期間と、長期で借りる場合のメリット・デメリットを見てみましょう。
長期返済のメリット①:月々の負担が軽く余裕が持てる
住宅ローンを長期間(例えば35年や40年など)で組む最大のメリットは、毎月の返済額を抑えられることです。
同じ金額を借りても返済回数が多くなれば、1回あたりの支払いは少なくて済みます。
例えば、3,500万円を年利0.5%で借りた場合
- 35年返済なら月々約9万円
- 50年返済なら月々約6.6万円
と、期間を延ばすほど月々の負担は小さくなります。
 MIYABI
MIYABI月々の返済負担が軽ければ、家計にゆとりが生まれやすく、生活費や教育費との両立も図りやすいでしょう。
特に、共働きで子育て中の世帯などは、毎月のやりくりに余裕が持てる点は大きなメリットです。
長期返済のメリット②:借入可能額自体を増やせるケースも
また、返済期間を長く設定すれば、借入可能額自体を増やせる場合があります。
これは、先述の通り、金融機関の審査では月々や年の返済負担率が重視されるため、月々の返済額が低く抑えられれば、その分、高額のローンでも審査に通りやすくなるためです。
「もう少し借りないと希望の物件が買えない…」という場合、期間を延ばすことで希望額を借りられるケースもあります。
 MIYABI
MIYABIただし、借入額を増やすこと自体はリスクも伴うため、本当に必要な範囲に留めることが大前提です。
長期返済のデメリット①:総支払額が増え、完済までのリスクも高まる
一方で、返済期間を長くすると利息の総額が増え、最終的な支払い総額が大きくなるのが最大のデメリットです。
金利や借入額によりますが、期間を延ばした分だけ余分に利息を支払うことになるため、トータルでは短期返済よりも多くのお金を返すことになります。
低金利のローンであっても、長期にわたれば利息負担が積み重なり、結果的に短期で返した場合より数百万円単位で総支払額が増える可能性があります。
 MIYABI
MIYABI「月々は少ないけど、長い目で見れば大きな額を返済する」点は注意が必要です。
長期返済のデメリット②:完済期間が長ければ、それだけ予期せぬ事態が起こりうる
また、完済までの期間が長いほど予期せぬ事態が起こるリスクも高まるという側面もあります。
返済期間中の数十年の間には、
- 景気変動による金利上昇リスク(※変動金利型の場合)
- 勤務先や収入の変化
- 病気・ケガ
- 離職、離婚
など、さまざまなライフイベントが起こり得ます。
期間が短ければそうしたリスクの露呈期間も短いですが、長期になるほどリスクに晒される期間が長くなるわけです。
例えば夫婦どちらかが働けなくなった場合、長期ローンだとまだ多額の残債が残っている可能性が高く、家計への影響も大きくなります。
さらに、長期間だと元本がなかなか減らないため、途中で繰上返済しようと思った時にも残高が多く、利息も多めに支払っている状態になりがちです。
例えば、3,500万円を年利0.5%で借りてから金利上昇した場合
- 0.5%なら月々約9万円
- 1.5%なら月々約11万円
- 3.0%なら月々約13.5万円
と、金利上昇で総支払額が増えていきます。
未払い利息が生じ得るケースもあるので注意が必要です。
 MIYABI
MIYABI心理的にも「いつまでも借金が減らない…」という重荷を感じる人もいるでしょう。
メリットデメリットと価値観で、どんなバランスを取るか決めよう
以上をまとめると、
長期ローンは月々の負担軽減というメリットと引き換えに、総返済額増加やリスク期間の長期化というデメリットを伴う
と言えます。
そのため、
のか、
かの、どちらの価値観に近いかを考えて返済期間を設定しましょう。
最近では一部金融機関で最長40年~50年ローンの商品も登場しています。
ただし金利が上乗せされたり、結局総支払額が大きく増えたりするため、慎重な判断が必要です。
 MIYABI
MIYABI一般的には、定年までに無理なく完済できる範囲で期間設定するのが無難でしょう。
共働き夫婦の住宅ローンの組み方:ペアローンと収入合算の違い

共働き夫婦が住宅ローンを組む際には、大きく分けて「収入合算」と「ペアローン」という2つの方法があります。
それぞれ仕組みやメリット・デメリットが異なるため、自分たちに合った組み方を選ぶことが大切です。
 MIYABI
MIYABIここでは収入合算とペアローンの違いと、共働きならではの注意点を解説します。
収入合算とは(連帯保証型・連帯債務型)
収入合算とは
住宅ローンの審査や借入において夫婦など複数の収入を合算して借り入れる方法。
一般的には主たる債務者(契約者)を夫、配偶者を連帯保証人または連帯債務者としてその収入を合計し、借入可能額を増やす形になります。
 MIYABI
MIYABI簡単に言えば「1本のローンを夫婦で協力して返していく」イメージです。
収入合算には2種類あり、連帯保証型と連帯債務型があります。
連帯保証型:配偶者が主債務者の返済を保証するだけで実際の債務者は1人
連帯債務型:夫婦が共同で債務を負う形で、どちらも主債務者としてローンを返済
連帯債務型の場合、銀行によってはお互いを連帯保証人に立てるペアローンとほぼ同じ扱いになるケースもありますが(夫婦双方が債務者)、一般的な「ペアローン」は(後述のように)契約自体が2本存在する点が異なります。
収入合算のメリット
- 1本のローンにまとめるため諸費用(事務手数料・保証料・登記費用等)がペアローンより割安
- 夫婦どちらか単独では希望額を借りられない場合でも、収入を合算することで借入可能額を増やせる
 MIYABI
MIYABI「ペアローンほど手間や費用をかけずに、でも収入を合算して借入額を増やしたい」というケースでは収入合算が有効でしょう。
収入合算のデメリット・注意点
- 収入合算者(主債務者ではない方の配偶者)は住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)※2を受けられない
住宅ローン控除は住宅ローン残高の1%を所得税から控除できる制度ですが、基本的にローン契約者しか利用できません。
連帯保証人として収入合算した場合、保証人側は契約者ではないため控除対象外になります。
また連帯債務型であっても、金融機関によっては配偶者側が住宅ローン控除を受けられないケースがあります(連帯債務者も持分割合に応じて控除可能な場合もありますが、取扱金融機関は限られます)。
※2 住宅ローン控除の適用は“入居年・住宅の区分・床面積・持分・契約形態(連帯債務/ペアローン等)”で異なります。最新の控除率・上限・期間は国税庁の解説をご参照ください。
団体信用生命保険(団信)の保障範囲にも注意

さらに団体信用生命保険(団信)の保障範囲にも注意しましょう。
通常、住宅ローン契約者が加入する団信は、契約者本人が亡くなった場合などに残債がゼロになる保険です。
原則として収入合算者は原則として団信に加入できないため、主債務者以外の収入合算者が死亡・高度障害になった場合でも団信による残債保障はありません。
夫が契約者・妻が収入合算者の場合、夫に万一のことがあればローン残高は団信でカバーされますが、妻に万一のことがあってもローンはそのまま残ります。
夫婦のどちらの収入に依存しているかにもよりますが、このリスクヘッジが不十分なのが収入合算の弱点です。

 MIYABI
MIYABIたとえばpaypay銀行などは、夫婦双方を保障する連生団信という特約商品もあります。
取り扱っている金融機関が少ないですが、収入合算を検討したい方にとっては有力な金融機関になるでしょう。
ペアローンとは
ペアローンとは
夫婦それぞれが別々の住宅ローン契約を組む方法。
同じ物件に対して2本のローンを組み、夫も妻もそれぞれ主債務者となります(お互いのローンの連帯保証人になるのが一般的です)。
 MIYABI
MIYABI例えば5,000万円の借入が必要なら、夫婦で2,500万円ずつローンを契約するといった形になります。
ペアローンのメリット
- 夫婦双方が住宅ローン控除を受けられる
ペアローンなら夫婦それぞれがローン契約者なので、それぞれ年末残高に応じた控除を受けることができる - 夫婦両方が団信に加入でき、それぞれ保障を受けられる
もしものことがあっても、もう一方のローンだけ返せば良くなるため、家計へのダメージが半分で済む - 夫婦それぞれで別々の契約内容を選べる
金利タイプの選択や、返済期間・繰上返済のタイミングなどを別個に設定できる
 MIYABI
MIYABI収入合算で契約者以外は保障がないケースに比べ、ペアローンなら夫婦双方に万が一の備えがあると言えます。
また、夫婦の収入や年齢差に応じて柔軟にローン条件を組めるのはペアローンならではです。
ペアローンのデメリット・注意点
- ローンを2本組むため、事務手数料や保証料、登記の司法書士報酬などの諸費用が2倍かかる
「控除で戻る額」と「余計にかかる諸費用」を比較してどちらが得か検討する必要がある - ローンが2本あるため毎月2つの返済を管理しなければならず複雑になりやすい
- もし夫婦関係が解消しても、ローンの契約関係は簡単には解消されない
将来的に離婚や収入減があった場合の対処も簡単ではなく、離婚後も双方に返済義務が残る
 MIYABI
MIYABI極端な話、離婚して別々に暮らしていても、相手がローンを滞納すれば自分が肩代わりしなければならないのです。

借入額がそれなりに大きく両者が控除枠をフルに使えるならメリットが上回るケースも多いですが、借入額次第では諸費用増のデメリットの方が痛い場合もあるので注意しましょう。
家を売却するにも名義が夫婦共有の場合、双方の同意が必要でスムーズにいかないケースがあります。
契約者それぞれが団信に加入する必要がある
さらに、ペアローンでは契約者それぞれが団信に加入する必要があるため、健康状態によっては一方が審査に通らない可能性もあります(夫婦どちらかが持病で団信に入れない場合、ペアローン自体組めないことがあります)。
 MIYABI
MIYABIその場合は収入合算で片方のみ契約者にする、といった選択肢に切り替える必要があります。
つまり、まとめると
ペアローンがおすすめ
- 「共働きで収入がある程度あり、借入可能額を最大化しつつ控除もフルに受けたい」場合
→費用負担やリスク管理も踏まえて検討することが大切 - 夫婦2人の収入がないと希望額に届かないが、それでいてローン残高も大きい」という場合
→ペアローンにして双方の控除を受けた方が有利
収入合算がおすすめ
- 借入額をそこまで増やさなくても足りる場合
- 費用を抑えてシンプルに借りたい場合
 MIYABI
MIYABIたとえば「夫の収入だけで希望額の7割は借りられるが、少し不足する分を妻の収入合算で補いたい」程度であれば、収入合算(連帯保証型)で事足りることが多いです。
どちらにせよ、夫婦でよく話し合い将来のプランも共有した上で決めることが肝心です。
住宅ローンは長丁場ですから、共働きで協力して返済していくにしても、お互いの役割分担や万一の際の対処(生命保険の加入や貯蓄計画など)についても話し合っておくと安心です。
【Q&A】住宅ローンの疑問に答える
そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
住宅ローンの年間平均返済額は?
国土交通省の調査によると新築注文住宅の月々返済額は平均約14.5万円、中古マンションは約8.4万円です。
物件種別や購入額によって返済額は大きく異なります。
どのくらいの金額を借りられますか?
金融機関は年収に対する返済負担率(年収の35%前後が上限)という指標があります。
無理のない返済のためには手取り収入の20~25%程度に抑えるのが理想的です。
無理のない住宅ローンの返済額の決め方は?
月々の手取り収入から
- 生活必需コスト
- 将来の教育費
- ライフイベント費
- 緊急予備資金
を差し引いた残りの金額が、無理なく返済に充てられる額の目安となります。
住宅ローンの借入期間が長い場合のメリットとデメリットは何ですか?
長期返済のメリットは月々の負担が軽く、借入可能額を増やせることです。
デメリットは利息の総支払額が増え、完済までの間に予期せぬ事態が起こるリスクが高まる点です。
共働き夫婦の住宅ローンにはどのような組み方がありますか?
大きく分けて、夫婦の収入を合算して1本のローンを組む「収入合算」と、夫婦それぞれが別々にローン契約を結ぶ「ペアローン」の2種類があります。
収入合算の住宅ローンのメリットと注意点は何ですか?
収入合算のメリットは諸費用が割安で借入可能額を増やせることです。
しかし、収入合算者は住宅ローン控除を受けられず、団信の保障範囲にも注意が必要です。

ペアローンの住宅ローンのメリットと注意点は何ですか?
ペアローンは夫婦双方が住宅ローン控除と団信の保障を受けられ、個別の契約内容を選べます。
しかし、諸費用が2倍かかるほか、ローン管理が複雑で離婚時の解消が難しい点が注意点です。

住宅ローンを考える上で最も大切なことは何ですか?
平均や他人のケースに惑わされず、「自分たちにとって無理のない返済額」を家計や価値観から見極めることが最も大切です。
銀行が貸してくれる上限をそのまま借りるのはリスクが高いです。

まとめ:借入上限より「自分たちにとって無理のない金額」を最重視しよう
| 変動金利 | 固定金利 (10年) | フラット35 | 返済方法 | 5年ルール 125%ルール | 審査日数 | 事務手数料 | 一部繰上げ返済手数料 | 金利変更手数料 | つなぎ融資 | オプション | 公式サイト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
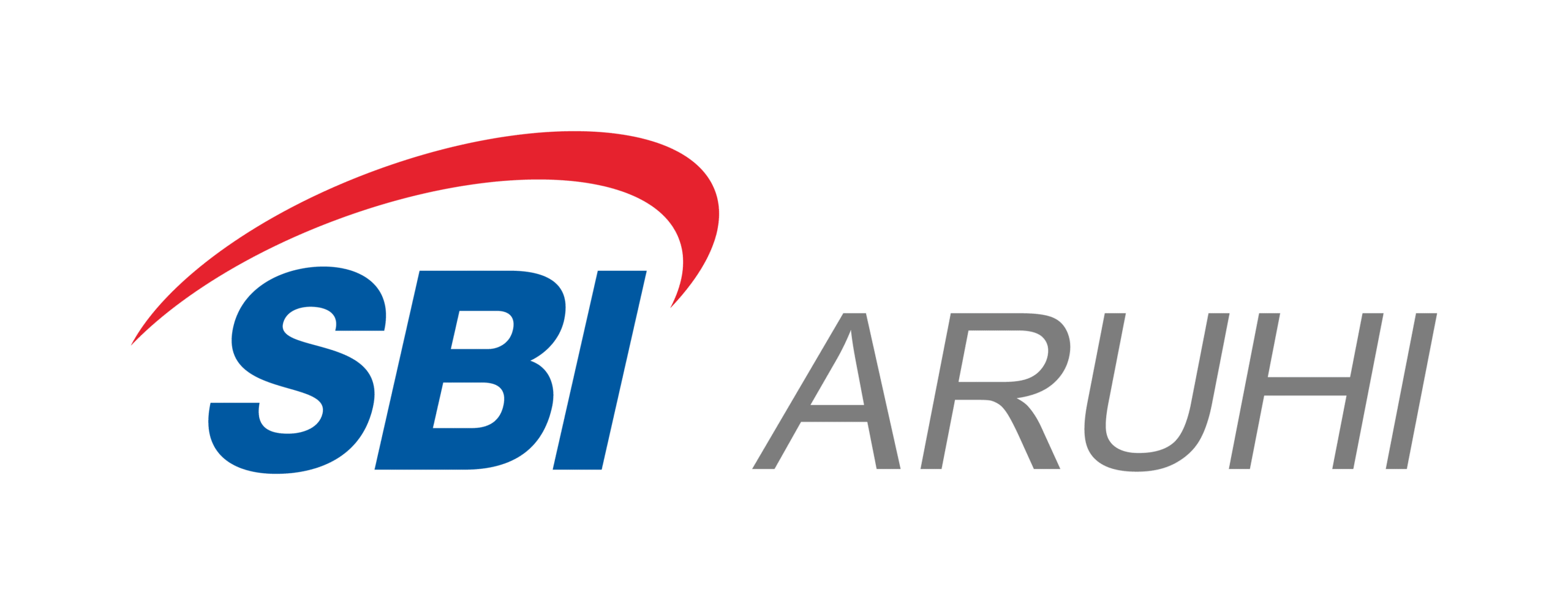 SBIアルヒ
SBIアルヒ
| 年1.364%~ (半年型) | 年3.314%~ |
スーパーフラット(例): スーパーフラット7.5:当初5年間 年1.140%/6年目以降 年2.140% (2026年2月実行金利) フラット35(機構団信加入): 年1.91%(15年~20年)/年2.26%(21年~35年) (36年~50年はフラット50等の商品・条件で異なるため要確認) | 元利均等返済/元金均等返済方式 | 記載なし | 事前審査が最短1営業日※ 本審査が最短3営業日※ |
借入金額×2.2%+消費税 ※最低事務手数料220,000円 最新の貸付条件はこちら | WEB受付は無料 電話受付は有料 | 金利固定化手数料5,500円(税込) | あり SBIアルヒフラットつなぎ | SBIアルヒ 暮らしのサービス 約40種類の優待特典 | 詳細を見る |
 PayPay銀行
PayPay銀行
|
年0.630% (新規・借換いずれも/全期間引下型) ※公式ページの表示は「2026年1月31日現在」 |
年2.080% ※公式ページの表示は「2026年1月31日現在」 | 取り扱いなし | 元利均等返済 | 要確認 | 事前審査(当日~2営業日) 本審査(書類提出から3~10営業日) | 借入金額×2.20% ※税込・要確認 | WEB受付:無料 電話受付:5,500円/1回 | 手数料無料 | 取り扱いなし | ー | 詳細を見る |
 住信SBI銀行
住信SBI銀行
|
年0.650%~ (物件価格80%以内・通期引下げプランの例/2026年2月実行金利) ※物件価格80%超は表示金利に年0.09%上乗せ |
年2.449% (固定10年・当初引下げプランの表示例/2026年2月実行金利) |
フラット35(買取型・例): 当初5年間 年1.26%/6年目以降 年2.26% (4ポイント割引、融資比率9割以下、21年~35年の例) フラット35(保証型):当初5年間 最大年▲1.0%引下げ(条件あり) | 元本均等返済/元利均等返済 | あり | 仮査定なら最短当日 本審査1週間〜10日 | 借入金額×2.2%(税込) | 無料 | 手数料無料 | 取り扱いなし 土地先行プランあり | ー | 詳細を見る |
 SBI新生銀行
SBI新生銀行
|
要確認 (2026年2月の適用金利は公式の金利一覧で確認) |
要確認 (2026年2月の適用金利は公式の金利一覧で確認) | 取り扱いなし | 元利均等返済 | 取り扱いなし | 申し込み~借入:約1ヶ月半 | 借入金額×2.2% | 無料 | 固定金利選択手数料:5,500円 | あり | ー | 詳細を見る |
 楽天銀行
楽天銀行
|
年1.257%~年1.907% (2026年2月基準金利の表示例) |
年2.928%~年3.578% (2026年2月基準金利の表示例) |
要確認 (フラット35は毎月更新のため公式金利一覧で確認) | 元本均等返済/元利均等返済 | あり | 最短26日※フラット35は最短35日程度 | 事務手数料:一律33万円 ※フラット35は融資額×1.1% | 無料 | 手数料無料 | あり | 住宅ローン会員ランク特典 等 | 詳細を見る |
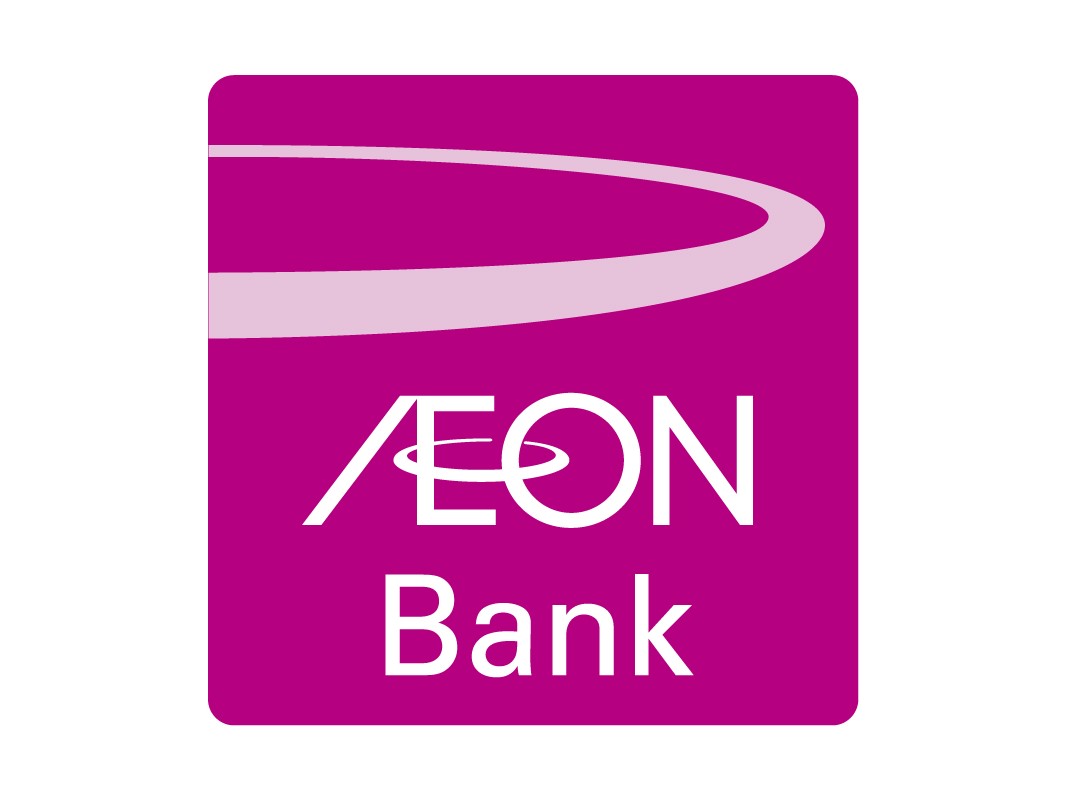 イオン銀行
イオン銀行
|
年0.78%~ (借入率80%以内) 年0.83%~ (借入率80%超) | 年2.80%~ |
イオン【フラット35】(団信あり・例): 融資率90%以下:Aタイプ 年1.91%(20年以下)/年2.26%(21年~35年) 融資率90%超100%以内:Aタイプ 年2.02%(20年以下)/年2.37%(21年~35年) Bタイプ(定額)もあり:90%以下 年2.11%/2.46%、90%超 年2.22%/2.57% | 元利均等返済 | あり | 事前審査最短翌日 正式審査1〜2週間 |
<定率型> 借入金額×2.20%(税込) 最低220,000円 <定額型> 110,000円(税込) 定率型より年0.2%高 | 無料 | 手数料無料 | あり | イオングループ特典 等 | 詳細を見る |
 auじぶん銀行
auじぶん銀行
|
「がん50%保障団信の特約付き」で 年0.834%(借入金額割合80%以下、新規) 借入金額割合80%超は表示金利に年0.045%上乗せ(例:年0.879%) |
年1.550% (当初期間引下げプラン<2月適用>、がん50%保障団信の特約付きの表示例) | 取り扱いなし | 元本均等返済/元利均等返済 | あり | 仮審査 当日~3営業日 本審査 3~10営業日 | 借入金額×2.20%(税込) | 無料 | 手数料無料 | 取り扱いなし | 住宅ローン金利優遇割 | 詳細を見る |
※ 金利は毎月見直されます。多くの民間ローンと【フラット35】は『実行時金利』が適用されます。審査結果・融資率・団信プラン・優遇適用可否により実際の金利は異なります。
※ 審査・融資までの最短日数は物件・書類・審査状況等で前後します。
※スーパーフラット5では、就業不能保険 スタンダードにご加入いただくことが条件となります。就業不能保険 スタンダードの詳細はこちら(https://www.sbiaruhi.co.jp/product/option_insurance/syugyofunou_standard/)をご確認ください。
平均的な住宅ローンの返済額や、年収から計算した理論上の借入可能額について見てきました。
しかし、住宅ローンを考える上で最も大切なのは、平均や他人のケースに惑わされず、
です。
人それぞれ収入や家族構成、将来の計画は違います。
たとえ平均より少ない額のローンでも、その人の家計にとって重ければ無理がありますし、逆に平均より多い借入でも高収入で支出が少なければ問題ないかもしれません。
つい「銀行が貸してくれる上限=自分が借りても大丈夫な額」と考えてしまいがちですが、金融機関の審査基準ギリギリまで借りるのは非常にリスキーです。
適切な借入額と返済計画で、将来にわたって安心して暮らせるマイホーム計画を立てましょう。
必要であればファイナンシャルプランナー等の専門家にも相談し、自分たちにピッタリの住宅ローンを見つけてくださいね。
 MIYABI
MIYABIよく計画を練って住宅ローンと付き合い、夢のマイホームを笑顔で手に入れましょう!
無理のない返済額の範囲内で、豊かな新居での生活をぜひ実現してください。

おうちにプロは、エアコンクリーニングをはじめとするハウスクリーニングの予約サイトです。ご希望のサービス内容・料金・エリア・口コミ等から、簡単に業者を比較、選定、予約することが可能です。
本記事は一般的情報であり、特定の金融商品を勧誘・推奨するものではありません。最終判断は各金融機関の最新条件と家計状況をご確認ください。















