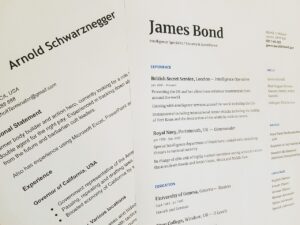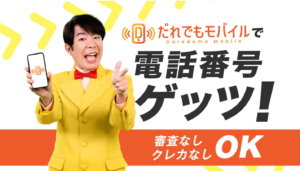生命保険は貯金代わりになるって本当?貯蓄型保険で貯金するメリット・デメリットを解説

多くの方が抱えるお金の悩みですが、将来への備えに関心が高まる中、解決策の一つとして「貯蓄型の生命保険」が注目されています。
「保障もついて貯金もできる」という点が魅力的に映るかもしれません。


しかし、生命保険を単純な「貯金」と考えるのは注意が必要です。
メリットだけでなく、デメリットやリスクも存在しますし、NISAやiDeCoといった資産形成もある今、「本当にあなたのライフプランに適した選択肢なのでしょうか?」という点を確認した方が良い事項だからです。
この記事では、貯蓄型保険の仕組みからメリット・デメリット、種類、選び方のポイントまで、あなたの疑問を解消するために徹底解説します。
 ねくこ
ねくここの記事を読めば、貯蓄型保険があなたにとって有効か、自信を持って判断できるようになるはずです。
貯蓄型保険とは? 基本の仕組みと「貯金代わり」と言われる理由

まず、生命保険の基本と貯蓄型保険の仕組みを理解しましょう。
生命保険の2大タイプ:「貯蓄型」と「掛け捨て型」
生命保険は、大きく2つのタイプに分けられます。
貯蓄型保険
貯蓄型保険は、支払った保険料の一部が積み立てられ、満期時に「満期保険金」、途中解約時に「解約返戻金」として戻ってくる可能性がある保険です。
万が一の「保障」と将来のための「貯蓄」機能を併せ持ちます。
 ねくこ
ねくこ早期解約では払込額を下回ることが多い点に注意が必要です。
掛け捨て型保険
一方、掛け捨て型保険は「保障」機能に特化し、貯蓄機能はありません。
保険料は割安ですが、満期保険金や解約返戻金は無いか、あってもごくわずかです。
 ねくこ
ねくこ「貯金代わり」と言われるのは「貯蓄型保険」の方です。
なぜ貯蓄性が生まれるのか?
では、なぜ貯蓄型保険にはお金が貯まる仕組み、つまり貯蓄性があるのでしょうか?
それは、私たちが支払う保険料の使い道に関係しています。
保険料は、大きく分けて次の2つの部分で構成されています。
- 将来の支払いに備えるお金
→ 保険金や満期保険金を支払うために積み立てられる部分 - 保険会社の運営費
→ 人件費や広告費など、保険会社が運営するために必要な費用
特に貯蓄型保険では、「将来の支払いに備えるお金」が重要です。
このお金は契約者のために積み立てられ、保険会社が株式や債券などで運用して、運用によって増えた利益と積み立てたお金が、満期保険金や解約返戻金の「もとで」になります。
これが、貯蓄型保険に貯蓄性が生まれる基本的な仕組みです。
 ねくこ
ねくこ運用による収益は、予定利率に基づいて保険料計算に反映されたり、変額保険のように運用実績に応じて受取額が変動したりします。
「貯金代わり」と言われる理由
では、なぜ貯蓄型保険が「貯金代わり」と表現されるのでしょうか。
主な理由としては3つあります。
①満期保険金や解約返戻金としてお金が戻ってくる可能性がある
まず、掛け捨て型保険とは異なり、将来、満期を迎えた時や途中で解約した際に、満期保険金や解約返戻金としてお金が戻ってくる可能性がある点が挙げられます。
 ねくこ
ねくここの「支払ったものが戻ってくる(かもしれない)」という仕組みが、貯蓄に近い感覚を与えます。
②計画的に資金を準備できる
次に、学資保険で子どもの教育資金を準備したり、個人年金保険で老後の生活資金を積み立てたりするように、特定のライフイベントに合わせて目標額と時期を設定し、計画的に資金を準備できる点も理由の一つです。
③半ば強制的に貯蓄を進められる
さらに、多くの場合、保険料は毎月口座から自動的に引き落とされるため、半ば強制的に貯蓄を進めることができる点も、「貯金代わり」と見なされる要因でしょう。
貯蓄が苦手な方にとっては、この仕組みが貯蓄習慣の形成に役立つこともあります。
このように、お金が将来戻ってくる可能性があり、計画的に、かつ半強制的に積み立てられる特徴から、貯蓄型保険は「貯金代わり」と言われることがあります。
 ねくこ
ねくこただし、後述するように、いつでも自由に出し入れできる銀行預金とは性質が大きく異なる点を理解しておくことが重要です。
知っておきたい!貯蓄型保険を「貯金代わり」にする4つのメリット

貯蓄型保険には、単なる貯金にはないメリットがあります。
【最大の魅力】万が一の保障を得ながら貯蓄できる
まずは、なんと言っても万が一の保障を得ながら貯蓄できる点。
これが貯蓄型保険の最大の特徴です。
病気や死亡といった不測の事態に備える「保障」と、将来のための「貯蓄」を一つの契約で両立できます。
例えば、
- 学資保険・・・子どもの教育資金を準備しつつ、親に万が一があれば以降の保険料が免除され、学資金は確保される安心感があります
- 終身保険 ・・・一生涯の死亡保障を確保しつつ、解約返戻金を将来の資金(老後資金など)に活用できます。予期せぬ事態が起きても貯蓄計画が中断しにくい、または家族を守れる点が大きな付加価値です。
などがあり、万一の事態にアレンジして対応してくれます。
【節税効果】生命保険料控除で税負担を軽減できる
支払った保険料に応じて、所得税や住民税が軽減される「生命保険料控除」の対象となる場合があります。
年間の払込保険料に応じて一定額が所得から控除され、課税対象額が減る仕組みです。
新制度の生命保険料控除は3区分あります。
- 一般保険料控除:生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料
- 個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料
- 介護医療保険料控除:入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料
手続きは年末調整や確定申告で行います。
 ねくこ
ねくこ節税メリットを重視する方には魅力的ですね。

【貯蓄習慣の形成】計画的に、半強制的に貯蓄できる
「ついお金を使ってしまう…」という方にとっても、貯蓄型保険は有効な手段です。
 ねくこ
ねくこ「意志の力」に頼らず貯蓄を進めやすく、貯蓄が苦手な人には大きなメリットです。
将来の目標のために確実に資金準備したいニーズに応えます。
【目標達成感】満期金や年金としてまとまったお金を受け取れる
養老保険や学資保険、個人年金保険などでは、契約時に定めた時期にまとまった満期保険金や年金を受け取れます。
長期間の積み立てを経て、目標額を手にできる達成感があります。
 ねくこ
ねくこ例えば、以下のような保険内容があります。
- 養老保険:一定期間の保険料を払い込んだ後、満期時に満期保険金を受け取れる。
- 学資保険:子どもの教育資金の準備を目的とし、進学時期に応じた給付金を受け取れる。
- 個人年金保険:老後の生活資金として、契約時に定めた年齢から年金を受け取れる。
契約前に必ず確認!貯蓄型保険の6つのデメリットと注意点

メリットだけでなく、デメリットや注意点もしっかり理解しましょう。
【最重要リスク】早期解約は元本割れのリスクが非常に高い
とにかく、早期の解約は“損をする”可能性が高い点。
これが最大のデメリットです。
貯蓄型保険は長期継続が前提。契約初期(数年~10年程度)に解約すると、支払った保険料総額より解約返戻金が大幅に少なくなる「元本割れ」の可能性が極めて高いです。
契約初期は保険会社の経費が多く引かれるため、十分な返戻金が貯まるまで時間がかかります。
契約前に、いつ頃返戻率が100%を超えるのか(または超えないのか)を必ず確認しましょう。
 ねくこ
ねくこもし保険料支払いが困難になっても、すぐに解約せず「払済保険」「延長保険」への変更や「契約者貸付制度」の利用も検討しましょう。
インフレ(物価上昇)で資産価値が目減りするリスク
多くの定額タイプは、将来受け取る金額が契約時に確定しています。
インフレが進むと、お金の価値自体が下がるため、受け取る金額の実質的な価値が目減りするリスクがあります。
例えば、30年後に300万円受け取っても、物価が上がっていれば買えるものが少なくなっている可能性があります。
このリスクに対応しにくい点はデメリットです。
 ねくこ
ねくこ対策として運用実績で受取額が変わる「変額保険」や「外貨建て保険」もありますが、これらは運用リスクや為替リスクを伴います。
銀行預金と比べて流動性が低い【すぐにお金を引き出せない】
半強制的に貯蓄できる反面、必要な時にすぐお金を引き出すことが困難です。
解約には手続きが必要で時間がかかり、元本割れリスクも伴います。
 ねくこ
ねくこ「契約者貸付制度」もありますが、利息がかかる借金であり、利用可能額も限られます。
急な出費への対応には不向きです。
掛け捨て型保険と比べて保険料が割高になる
貯蓄機能がある分、同じ保障内容なら掛け捨て型より保険料は高くなります。
将来の支払いに備えるための保険料が含まれるためです。
 ねくこ
ねくこ例えば20代では掛け捨て型でコストを抑えつつ、将来的に貯蓄型へ移行するのも一つの方法です。
予定利率が低い時期の契約は不利になる可能性
保険会社が資産を運用する際の「予定利率」(約束利率)は、契約時に固定されることが一般的です。
これは保険料にも影響を与えます。
低金利の時期に契約した保険は、予定利率が低いため、運用による資産の増加はあまり期待できません。
また、将来市場金利が上昇しても、その恩恵を受けることはできません。
 ねくこ
ねくこ特に長期間契約する場合、予定利率の影響は大きくなります。
金利の動向を見ながら、タイミングを考えるのも一つの戦略です。
保障内容が限定的、または時代に合わなくなる可能性
貯蓄性を重視するあまり、必要な保障が不足したり、医療の進歩などで保障内容が古くなったりする可能性があります。
定期的な見直しが必要ですが、貯蓄型保険は簡単に見直しにくい側面もあります。
どんな種類がある?代表的な貯蓄型保険とその特徴
 ねくこ
ねくこ代表的な貯蓄型保険の種類と特徴を見ていきましょう。
終身保険

終身保険は、その名の通り保障が一生涯続く死亡保険です。
保険料の払込期間(例えば60歳までなど)が満了した後も保障は継続し、もし途中で解約した場合には、それまでに積み立てられた解約返戻金を受け取ることができます。
メリット
この保険のメリットは、一生涯の死亡保障を確保できる点に加え、貯まった解約返戻金を老後資金や介護費用といった将来の資金ニーズに柔軟に活用できる可能性があることです。
 ねくこ
ねくこまた、受取人を指定できることから相続対策としても利用される場合があります。
デメリット
しかし、掛け捨て型の保険と比較すると保険料は高くなる傾向があり、解約返戻金の返戻率が支払った保険料の総額を上回る(100%を超える)までには、ある程度の長い期間が必要となる点には注意が必要です。
さらに、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定する代わりに月々の保険料を割安にした「低解約返戻金型終身保険」というタイプもあります。
払込期間を満了すれば返戻率が高まることが期待できるため、長期間継続する意思がある場合に検討されます。
養老保険
養老保険は、例えば「10年間」や「60歳まで」といったように保険期間が定められている貯蓄型の保険です。
満期を迎えた際には、契約時に設定した死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができます。
また、保険期間中に万が一死亡した場合には、死亡保険金が支払われます。
メリット
この保険の大きなメリットは、
生死に関わらず満期時には必ず契約した金額を受け取れるため、貯蓄目標を確実に達成できる点と、期間中の死亡保障も同時に確保できる点です。
デメリット
一方で、貯蓄性が高い分、他の貯蓄型保険と比較しても保険料はかなり割高になる傾向があります。
加えて、保険期間が終了すると保障もそこで終了してしまう点もデメリットと言えるでしょう。
養老保険は、満期というゴールが明確であるため、退職金の補填や住宅ローンの繰り上げ返済資金など、特定の時期に必要な資金を確実に準備したい場合に適した保険です。
学資保険(こども保険)

学資保険は、主にお子さまの教育資金、特に大学進学などにかかる費用を計画的に準備することを目的とした保険です。
契約時に満期(例えばお子さまが18歳になる時など)を設定し、満期時や、中学・高校の入学といった進学の節目に合わせて祝い金や満期保険金を受け取れるように設計されています。

メリット
この保険のメリットは、教育資金を計画的に準備できることに加え、多くの商品で契約者である親などに万が一のことがあった場合に、それ以降の保険料の支払いが免除される「保険料払込免除特約」が付いている点です。
 ねくこ
ねくここれにより、不測の事態が起きても教育資金を確保できるという安心感が得られます。
デメリット
受け取る金額は契約時に固定されることが多いため、インフレによって将来の教育費が想定以上になった場合に対応しにくいというデメリットがあります。
また、他の貯蓄型保険と同様に、早期に解約すると元本割れするリスクが高く、商品によっては満期まで払い込んでも返戻率が100%を下回る(支払った保険料より受け取る額が少ない)ケースもあるため、契約前の確認が不可欠です。
返戻率を少しでも高めたい場合は、
- 進学時の祝い金をなくす
- 保険料の払込期間を短く設定
- 月払いではなく年払い
といった工夫が考えられます。
 ねくこ
ねくこまた、新NISAのつみたて投資枠など、他の教育資金準備方法と比較検討することも重要です。

個人年金保険
個人年金保険は、公的年金だけでは不安だという方が、老後の生活資金を自助努力で上乗せして準備するための保険です。
契約時に定めた年齢(例えば60歳や65歳)まで保険料を払い込み、その後、一定期間または一生涯にわたって年金形式でお金を受け取ることができます。
メリット
計画的に老後資金を準備できる点が主なメリットです。
さらに、税制上の優遇措置として、一定の要件を満たす契約(税制適格特約が付加されたもの)であれば「個人年金保険料控除」の対象となります。
 ねくこ
ねくこ所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。
デメリット
ただし、定額タイプの個人年金保険はインフレに弱いというデメリットがあります。
また、運用実績によって年金額が変わる「変額個人年金保険」や外貨で運用する「外貨建て個人年金保険」もありますが、これらは運用リスクや為替リスクを伴います。
さらに、長期間にわたって資金が拘束されるため、流動性が低い点にも注意が必要です。
老後資金準備の手段としては、iDeCo(個人型確定拠出年金)も有力な選択肢であり、税制優遇の面ではiDeCoの方が大きいことが多いですが、原則60歳まで引き出せないなどの制約もあります。
 ねくこ
ねくこそれぞれの特徴を理解し、比較検討することが大切です。

【診断】あなたはどっち?貯蓄型保険での貯金が向いている人・向いていない人
そして、保険を検討する際には
で悩むと思います。
そこで、貯蓄型保険が自分に合っているか、チェックしてみましょう。
 ねくこ
ねくこ下記のどちらの価値観により当てはまるかをふまえて、ベストな選択肢を検討するといいですよ。
<貯蓄型保険がフィットしやすい人>

- 貯金が苦手で、半強制的に貯めたい人
- 保障と貯蓄を一つの契約でシンプルに管理したい人
- 教育資金や老後資金など、目標のために計画的に準備したい人
- リスクを抑えて比較的安全に貯蓄したい人(元本割れリスクは理解の上)
- 生命保険料控除の節税メリットを活かしたい人
- 長期的にコツコツ継続できる人
 ねくこ
ねくこ特定の目的がある場合には貯蓄型を選びましょう。
老後の生活費には「個人年金保険」、子どもの学費には「学資保険」、保障に貯蓄をプラスしたい人は「終身保険」「養老保険」がおすすめです。
<貯蓄型保険以外の選択肢を検討した方が良い人>
- 近い将来にお金が必要になる可能性がある人(流動性重視)
- 保険料を抑えて大きな保障を確保したい人(掛け捨て+別途貯蓄/投資)
- インフレリスクに備えたい、より高い収益を目指したい人(NISA、iDeCo等)
- 貯蓄と保障は明確に分けて管理したい人
- 手元資金の自由度を重視する人
- すでに十分な貯蓄がある人
 ねくこ
ねくこまた、少ない保険料で大きな保障を求めるなら、掛け捨て保険と別途貯蓄・投資を組み合わせる方が合理的な場合もあります。
【Q&A】貯蓄型保険に関するよくある疑問
最後に、貯蓄型保険に関するよくある疑問についてお答えします。
Q1. 途中で保険料が払えなくなったら?
すぐ解約せず、「払済保険」「延長保険」への変更、保障額の「減額」、「契約者貸付」などを検討しましょう。
まずは一度、保険会社に相談するといいですよ。
Q2. 保険会社が破綻したら?
「生命保険契約者保護機構」により、責任準備金の90%まで補償されますが、保険金額等が削減される可能性はあります。
破綻してしまったからと言ってすぐに解約をしてしまうと、早期解約控除といったペナルティ(最大20%)が差し引かれる可能性があります。
 ねくこ
ねくこ損が重なってしまうので、慌てずにFPや保険会社に相談しましょう。
Q3. 貯蓄型保険と銀行預金、投資信託(NISAなど)、iDeCo、どれがいいの?
結局、どの資産形成手段が良いかは目的やリスク許容度で異なります。
以下の表を参考に、組み合わせるのが理想的です。
| 特徴 | 貯蓄型保険(定額) | 銀行預金 | 投資信託(NISA等) | iDeCo |
|---|---|---|---|---|
| 安全性 | △(元本保証なし、早期解約リスク) | ◎(元本保証あり※) | ×(元本保証なし) | ×(元本保証なし※※) |
| 収益性 | ×(低い) | ×(非常に低い) | △~◎(変動) | △~◎(変動) |
| 流動性 | ×(低い) | ◎(高い) | 〇(比較的高い) | ×(原則60歳まで不可) |
| 保障機能 | ◎(あり) | ×(なし) | ×(なし) | ×(なし) |
| 税制優遇 | △(生保控除) | ×(ほぼなし) | 〇(NISA等) | ◎(掛金全額控除等) |
※預金保険制度で保護。 ※※iDeCoでも元本確保型商品あり。
\新NISAの基本をおさらいしたい方はコチラ!/

\iDeCoの基本をおさらいしたい方はコチラ!/

まとめ:貯蓄型保険は「目的」と「リスク」を理解し、賢く活用するツール

貯蓄型の生命保険は、「保障」と「貯蓄」を両立できる選択肢の一つです。計画的な貯蓄が苦手な方や、保障と貯蓄をセットで考えたい方には有効でしょう。
しかし、「貯金代わり」という言葉だけで安易に選ぶのは避けましょう。
早期解約時の元本割れリスク、インフレリスク、流動性の低さといったデメリットを十分に理解することが不可欠です。
検討する際は、
- 目的、期間、目標額は明確か?
- 貯蓄型保険は最適な手段か?(他の商品と比較して)
- デメリットやリスクを許容できるか?(長期継続できるか?)
- 保険料負担は適切か?
を自問自答し、必要なら中立的な専門家(FPなど)に相談しましょう。
貯蓄型保険は、あくまで資産形成やリスク管理のツールの一つです。
 ねくこ
ねくこその特性を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて賢く活用することで、将来への安心感を高める一助となるはずです。