公務員になりたい人・辞めたい人のための転職ガイド【2025年版】

※本記事は、2025年11月時点で公表されている情報をもとに、公務員×転職に関する制度の概要を整理したものです。実際の受験資格や副業の可否、給与条件などは、省庁・自治体ごとに異なり、年度によっても変更されます。最終的な判断は、必ず各団体の最新の募集要項・規程および一次情報をご確認のうえで行ってください。
「公務員」はいつの時代も安定の象徴です。けれど近年、その公務員のあり方が変わり始めています。
副業が認められ、社会人経験者の採用枠を広げる国の機関や自治体が増えてきました。
そうした変化の中で公務員に転職する人、公務員から転職する人も目立つようになっています。
一方で、公務員の転職には独自の制度やルールがあり、民間の転職とは違う準備が必要です。
年齢制限、試験内容、併願可否、副業ルール──。
自治体や区分によって条件が異なるため、「一般論」で判断するのは危険です。
この記事では、2025年11月時点の最新制度と一次情報をもとに、公務員からの転職、公務員への転職、そして公務員から公務員へのキャリアチェンジまでのポイントを詳しく解説します。
※年齢要件・倍率・副業ルール・ボーナス水準などの詳細は、記事末の「参考・出典」一覧(※1〜※5)もあわせてご確認ください。
公務員×転職の全体像

公務員から転職するのか、それとも民間企業から公務員を目指すのか。
「どこから、どこへ向かうか」で手順は大きく変わります。
まずは公務員と転職に関する全体の構造を知り、整理しましょう。
なぜ公務員×転職が注目されているのか
背景には、社会構造と働き方の変化があります。
少子高齢化による人材確保の難しさから、自治体や国の機関が社会人経験者採用の枠を広げる動きが続いています。
同時に、働き方改革の進展により「副業ができる」「テレワークが可能」といった柔軟な勤務形態が広がりつつあります。
一方で、公務員から民間へ転じる人も増えています。
「安定よりも挑戦を」「専門性をより広い社会で生かしたい」と考える層が動いているのです。
2025年現在、公務員は「一度就けば一生安泰」という存在ではなく、制度を理解し、自分に合った働き方を選べる職業へと移り変わりつつあるといえます。
立場で変わる——公務員に関する転職の手順
まず、民間企業から公務員への転職を目指す場合、各自治体や省庁が定める採用試験を受ける必要があります。
社会人経験者採用など、民間での実務を評価する枠も年々拡大しています。
次に公務員から民間企業への転職は、制度上の手続きが特に設けられていません。
採用は企業側の判断に委ねられ、一般の転職活動と同じ流れになります。
最後に、公務員から公務員への転職は、多くは再受験や経験者採用を通じて別の自治体や職種へ移る形です。
その際、試験科目や日程が他区分と重なるなど、制度上の制約が受験計画に影響することもあります。
公務員と民間の違い
公務員への転職を検討するなら、「安定しているかどうか」だけで判断するのは早計です。
大切なのは、自分の価値観や生活に合う働き方は何か、一度立ち止まって確認すること。
そもそも公務員と民間では、求められる姿勢やスキル、判断基準や評価の仕組みが大きく異なります。
【民間と公務員の違い】
民間:成果・スピード・競争
公務員:公共性・手続の正確さ・公平性
公務員には法令や組織体制に沿った働き方が求められ、裁量の大きさは部署によって差があります。
その一方で、福利厚生や雇用の安定性が高く保たれているという特徴もあります。
結局のところ、「働きやすさ」は自分の価値観との相性で決まるもの。同じ職場でも、安心だと感じる人もいれば、窮屈だと感じる人もいます。
・どんな環境で力を発揮しやすいか
・どのような“安定”(収入・働き方・環境)を求めているのか
この2点を考え、理解しておくことが、より良い転職を実現する手がかりとなります。
公務員に関する転職のポイント
民間→公務員、公務員→民間、公務員→公務員――。
同じ“転職”でも、自分が公務員なのか、それとも民間企業にいるのかで、必要な情報や確認すべき制度は異なります。
ここでは、上記のパターンそれぞれについて、手順や制度の違いを整理します。
まずは情報量の多い民間→公務員から、年齢・試験・倍率・流れなど、ポイント を見ていきましょう。
1. 民間から公務員へ——転職のポイント

民間から公務員を目指すなら、まずはどの区分で受験するのか、決めなければいけません。
もっとも代表的な区分は、次の2つです。
・一般枠(大学卒程度)
・社会人経験者採用(実務経験を評価する枠)
一般枠は、基礎的な知識や適性を広く問う試験で、新卒や第二新卒を主な対象にしています。
一方、社会人経験者採用は、職務経験や人物面を重視しており、面接や書類審査の比重が大きくなりやすい仕組みです。
加えて、公務員試験は自治体や省庁ごとに制度の設計が異なります。
たとえば、次のような点は団体によって大きく変わります。
・試験方式(筆記・基礎能力検査・作文 など)
・どの経験を評価するか(業務内容・年数)
・書類審査の有無や形式
・人物面をどの程度重視するか
同じ「社会人採用」という名称でも、選考の流れや評価基準は統一されていません。
さらに、試験日程や併願の可否にも違いがあります。
筆記が同日に設定されている区分は同年度に申し込めないなど、受験計画そのものに影響が出るケースもあります。
そのため、年度ごとの受験案内を確認することが欠かせません。
※年齢要件や受験区分ごとの条件は、自治体・年度による差が大きいため、「〇歳まで受けられる」といった一般論ではなく、必ず志望先の最新の受験案内を確認してください。※5
年齢要件は自治体・区分ごとに異なる
公務員試験の年齢要件は自治体・区分・年度によって異なります。
一般枠(大学卒程度)は29〜35歳を上限とする自治体が多い一方、社会人経験者採用は59歳まで応募できる例もあり、自治体ごとの差は大きくなっています。
また、年齢の判断基準には「受験日基準」「採用日基準」など複数の方式があり、同じ年齢でも受験可否が変わることがあります。過去の目安だけでは判定できないため、受験する年度の受験案内で要件を必ず確認することが重要です。
※ここでの年齢はあくまで目安であり、実際の受験資格は自治体・区分ごとに異なります。必ず志望先の最新の受験案内でご確認ください。※5
試験科目と評価方法
公務員試験の科目構成や評価方法も、自治体・省庁・年度によって大きく異なります。
その中でも社会人経験者採用では、従来の「教養試験中心」だけでなく、人物面や実務経験を重視した試験構成を採用する自治体が増えています。
主な試験方式(民間→公務員)
- 基礎能力検査(教養試験)
文章理解・数的処理・論理など、基礎的な思考力を測るもの。自治体によっては SPI 型の方式を採用する例もあります。 - 作文・小論文
行政課題や社会問題、自身の経験をどう整理し言語化できるかを見る試験。社会人採用では実務経験との接点を問われることが多い領域です。 - 書類審査(職務経歴書・自己申告書 等)
どのような経験をどのくらい積んできたかを確認する段階。自治体により提出書類の様式や評価ポイントが異なります。 - 面接(個人面接・集団面接)
人物評価の比重が高く、複数回実施する自治体もあります。課題対応力・協働姿勢・動機の妥当性などを総合的に見られます。
専門択一の有無に注意
社会人経験者採用では、専門試験を課さない自治体が多いものの、技術系・福祉系など職種によっては専門試験が設けられるケースもあります。必ず受験年度の募集要項で確認するようにしてください。
評価方法の傾向
筆記成績だけで合否が決まることは少なく、書類・面接・実務経験の総合評価で判断される流れが主流です。筆記は「足切り」的役割、面接は「最終判断」的役割をもつ例もあります。
例:社会人経験者採用の試験フロー(よくあるパターン)
- 一次試験:書類審査(職務経歴書・自己PRシート)+基礎能力検査
- 二次試験:個人面接+作文(または小論文)
- 三次試験:最終面接
このように、筆記だけでなく、職務経験の内容や動機、人物面を複数回の面接で確認する方式が一般的になりつつあります。
倍率は“高い・低い”より中身で見る
公務員試験の倍率は「一般枠より社会人枠が低い」「採用人数が多いから有利」といった単純な比較では語れません。自治体や年度、試験区分によって大きく変動します。
政令市や特別区クラスでは、一般枠の倍率は概ね3〜8倍程度になることが多く、科目が少ない(教養のみ・適性中心など)試験ほど受験者が集まり、相対的に高倍率になりやすい傾向があります。※5
つまり、「倍率の数字」だけを見るのではなく、次のようなポイントとセットで考えることが大切です。
・採用予定数
・一次合格者数・最終合格者数
・試験科目や区分の違い
 ねくこ
ねくこ直近年度の公表データから、志望先の倍率の“傾向”をつかむようにしましょう。
受験の流れと注意点
民間から公務員を目指す場合、おおまかな流れは次のとおりです。
民間→公務員 受験フロー
- 募集要項の確認・申込
- 一次試験(筆記・基礎能力検査など)
- 二次以降の試験(面接・作文/小論文 など)
- 最終合格後の採用手続き
- 区分によっては官庁訪問や説明会へ参加
試験の回数や順番、実施時期は自治体や区分ごとに異なります。
また、同じ年度でも「一次から人物重視」「一次は基礎能力+書類」といった違いがあるため、志望先の受験案内を確認して自分のスケジュールに落とし込むことが重要です。
とくに注意したいのは、試験日程の重なりと併願制限です。
筆記日が同日であったり、「同一年度は1区分のみ申込可」と定める自治体もあり、計画次第で受験できる選択肢の数が変わってきます。
在職中に受験する場合は、仕事との調整も含めて早めに年間スケジュールを組んでおきましょう。
2. 公務員から民間へ——転職のポイント
公務員から民間企業への転職は、「安定からの離脱」というより、働き方やキャリアの方向性を見直す選択肢のひとつです。
近年は、公務員としての経験を民間で生かしたいと考え、30代以降で動き始める人も少なくありません。
公務員から民間へ転じる動機としては、次のようなものがよく挙げられます。
・自分の専門分野を、より幅広いフィールドで試してみたい
・プロジェクトのスピード感や成果への手応えを重視したい
・自分の成果や頑張りが、評価や給与に分かりやすく反映される環境で働きたい
自分の強みを説明できるよう準備する
民間企業から見ると、公務員としての経験をもつ人材には、次のような強みがあります。
・住民・議会・他機関とのやり取りを通じて培った調整力・折衝力
・報告書や説明資料の作成を通じて身についた文書作成力
・法令やルールを踏まえてリスクを判断してきた経験
ただし、「○○課で△△業務を担当」といった肩書きだけでは、こうした強みは伝わりにくいものです。
担当していた仕事を、規模(件数・人数・予算)や自分の役割、工夫した点などで言語化し、民間企業の業務イメージと結びつけて説明できるよう準備しておきましょう。
公務員と民間の違いを理解する
公務員から民間への転職を希望するなら、「働き方」と「評価の基準」の違いを理解しておくべきです。
民間:売上や利益、スピード、数値目標など
公務員:手続の正確さ、公平性、継続性など
どちらが良い・悪いではなく、大事にしているものの前提が違う、と捉えておくと、自分に合う環境を選びやすくなります。
準備としては、次のような整理から始めるとスムーズです。
・関心のある業界・職種を大まかに絞る
・年収・働き方・勤務地など、譲れない条件の優先順位を決める
・自分の経験を、民間企業の課題(顧客対応・事業運営・組織運営など)とどう結びつけられるかを考える
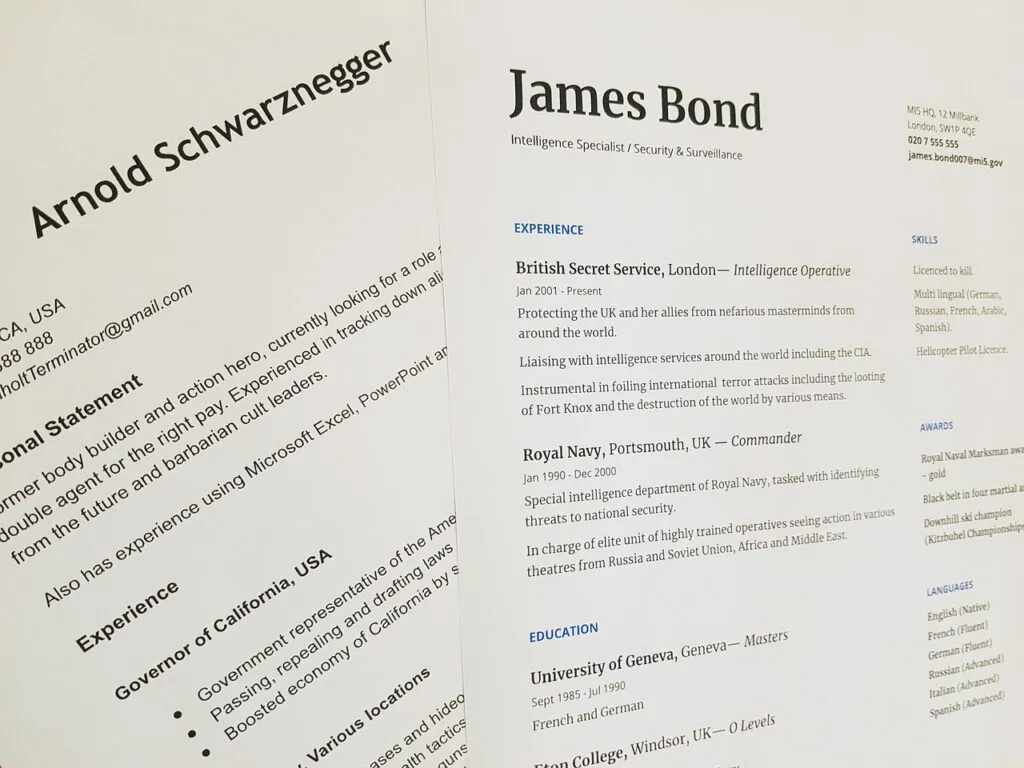
3. 公務員から公務員へ——転職のポイント

国家公務員→地方公務員、自治体→別の自治体、同じ自治体内で別職種を目指すケースなど、公務員から別の公務員へ移る場合も、多くは「異動」ではなく、あらためて採用試験を受けることになります。
ただし、採用区分・年齢要件・試験科目・経験者枠の有無は団体ごとに異なります。
現職の経験がどの枠で評価されるのかを整理しておくと、その後に確認すべきルールが見えやすくなります。
ここからは、公務員→公務員の主なパターンと、受験ルール・準備のポイントを解説します。
公務員→公務員 転職の主なパターン
公務員から公務員への転職でよく見られるパターンは次の3つです。
・国家公務員→地方公務員(例:省庁→政令市・県庁 など)
・地方公務員→別の自治体(例:市役所A→市役所B・都道府県庁 など)
・同じ団体の中で別職種を受験(例:一般行政→技術職・福祉職 など)
こうしたケースの多くは、
・公務員経験者採用として受験する
・一般枠をふたたび受験する
のどちらかを選ぶ形になります。
自分の職歴がどの枠に当てはまるかは団体ごとに異なるため、まずは志望先の募集要項で応募できる区分を確認してください。
受験ルールとスケジュールについて
公務員→公務員の転職では、次のような点を事前に確認しておきましょう。
・年齢要件や「経験〇年以上」などの条件
・「同一年度は1区分のみ申込可」などの受験制限の有無
・筆記日程が他区分と同日かどうか(併願できるか)
在職のまま受験する場合は、
・試験日程と現在の業務スケジュール
・退職時期の見通し
・勤務先への報告タイミングや引き継ぎに必要な期間
もあわせて考えておく必要があります。
公務員→公務員の転職は、現在の経験をどの団体・どの職種で生かしたいのかを先に決めることで、その後に確認すべき年齢要件・試験内容・受験ルールがクリアになります。
 ねくこ
ねくこ具体的な条件は、民間企業から公務員への転職を希望する場合と同様に、必ず受験年度の受験案内で確認してください。
公務員という働き方|安定性・待遇・副業ルール(2025年時点)

「収入や待遇が安定している」「副業はできない」といった漠然としたイメージだけでは、公務員の働き方の実態はつかみにくいものです。
ここでは、公務員への転職を検討する上で知っておきたいポイントを、次の3つに絞ってお伝えします。
・安定性を支える身分保障と分限・懲戒の仕組み
・給与・ボーナスの決まり方を左右する給与表や人事院勧告
・法律や通知にもとづいて運用される副業(兼業)ルール
ここを押さえておくと、公務員で働き続ける場合や別の道を選ぶ場合も、ぐっと判断しやすくなります。
公務員の安定性と身分保障
公務員は「安定している」と言われますが、解雇リスクはゼロではありません。
民間企業とは異なるかたちで身分が保障される一方で、法律に基づく免職や処分の仕組みもあります。
身分が保障されていることで、景気の変動や業績悪化だけを理由とした整理解雇は、民間企業と比べると起こりにくい傾向にあります。
その反面、勤務実績が著しく不良な場合や、心身の故障により職務遂行が難しい場合、重大な非違行為があった場合などには、分限処分や懲戒処分として免職に至ることも法律上想定されています。
「クビにならない仕事」というよりも、一定のルールに守られながら、そのルールに基づいて責任も問われる働き方だと捉えると、公務員の安定性について、実像に近いイメージになるでしょう。
※分限・懲戒の具体的な内容は、国家公務員法・地方公務員法および各団体の条例で定められています。※3 ※4
身分保障と免職制度
公務員の身分保障と免職に関する仕組みは、おおまかに次のように整理できます。
身分保障:法律に基づき、恣意的な解雇がされないよう身分を守る制度
分限処分:勤務実績の不良や心身の故障など、職務の継続が難しい場合にとられる処分
懲戒処分:服務規律違反や非違行為に対する処分(戒告・減給・停職・免職 など)
経営悪化による突然の整理解雇は起こりにくい一方で、職務遂行や服務に関わるルールに反した場合には、段階的な処分を経て免職に至る可能性があります。
公務員として働き続けるか、別のキャリアに踏み出すかを考える際は、この「守られている部分」と「責任を問われる部分」の両方を理解しておくことが大切です。
公務員の待遇(給与・ボーナス)の仕組み
公務員の給与は、個別の交渉ではなく「給与表」に基づいて決まります。
職種や役職ごとに級と号が設定され、経験年数や評価に応じて号が上がっていく仕組みです。
そこに扶養手当や地域手当、住居手当などが加わり、毎月の支給額が決まります。
ボーナスにあたるのが、いわゆる特別給(期末手当・勤勉手当)です。
国家公務員の場合、人事院勧告などを踏まえて毎年の支給月数が決まります。
2025年8月の人事院勧告では、特別給(期末・勤勉手当)を年間4.60月分から4.65月分へ引き上げることが示され、同年11月には政府が勧告どおりの改定案を閣議決定しています。※1
地方公務員はこの勧告を参考にしつつ、各団体が条例改正などを経て支給水準を定める形です。
ここで押さえておきたいのは、多くの民間企業と同様、ボーナスの支給月数や水準は年によって見直されることがある、という点です。
「必ずこの月数が出る」「毎年同じだけ支給される」といった固定的なイメージではなく、勧告や条例に応じて変動しうる仕組みと捉えておくと実態に近づきます。
公務員の待遇を考えるときは、次の3つに分けておくと、どの部分が土台で、どの部分が見直しの影響を受けやすいかをイメージしやすくなります。
① 基本給:給与表にもとづいて決まる金額
② 各種手当:扶養・地域・住居などの上乗せ分
③ 特別給:期末・勤勉手当として支給されるボーナスの月数
公務員の副業ルールの基本と2025年時点の流れ
公務員の副業は「一律禁止」ではありません。
国家公務員・地方公務員ともに、法律に基づく許可制・承認制が基本です。
おおまかな枠組みは次のとおり。
国家公務員:国家公務員法103条(私企業からの隔離)・104条(営利企業等の従事制限)に基づき、有償の兼業や営利企業での業務は原則として承認・許可が必要 ※3
地方公務員:地方公務員法38条に基づき、営利企業の従業員などとして働く場合は原則として任命権者の許可が必要 ※4
共通して重視されるのは、次のような観点です。
・本来の職務に支障が出ないか
・職務の公正さや中立性が損なわれないか
・所属組織の信用を傷つけるおそれがないか
・利害関係者との関係が生じないか
2025年時点では、地域貢献やスキル活用を目的とした副業を認める動きも広がりつつあります。
とくに地方公務員については、2025年6月11日に総務省から『営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する留意事項について(通知)』が発出され、営利企業での副業を含む兼業について、任命権者が許可基準を明確化することが求められました。※2
これを受けて、副業・兼業の運用方針を公表する自治体が増えつつあります。
一方で、実際に副業が認められるかどうか、どの程度の時間や内容まで許容されるかは、所属する省庁・自治体の基準に左右されます。
在職中に副業を始める際は、次のような順番で確認することが重要です。
・所属先の就業規則や副業・兼業ガイドラインを確認する
・申請が必要な場合は、事前に内容・時間・報酬などを整理して相談する
・守秘義務や情報の取り扱い、本務との時間配分をどう担保するかを考えておく
転職を前提に副業を検討する場合も、「勝手に始めて既成事実化する」のではなく、あくまで所属組織のルールに沿って進めることが、公務員としてのキャリアを守るうえでは重要です。
※副業の許可・不許可や条件の詳細は、所属先の就業規則やガイドライン、個別の事情によって判断が分かれます。本記事は一般的な情報提供であり、個別の副業が認められることを保証するものではありません。具体的な計画がある場合は、事前に所属先や専門家に相談するようにしてください。
民間から公務員を目指す人の選び方と受験プラン【今年の動き方を決める】

ここまでは、公務員×転職の全体像や、公務員という働き方を見てきました。
ここからは、民間から公務員を目指す人に焦点を絞り、どの枠を選び、どんな順番で準備を進めていくかを整理します。
まず「どの区分・どの自治体」を候補にするか決める
最初の一歩は、受けられる区分と受けたい自治体・職種をざっくり絞ることです。
ここが曖昧なままだと、情報収集や勉強の範囲が広がりすぎてしまいます。
次のような観点から候補を選んでみましょう。
・自分の年齢・経験年数から見て、一般枠(大学卒程度)/社会人経験者採用のどちらが現実的か
・志望する職種(行政職/技術職/福祉職 など)
・希望する勤務エリア(通勤可能な範囲か、転居前提か など)
・家庭・ライフイベントを踏まえて、今後数年働けそうかどうか
この段階では、第一志望+周辺の2〜3自治体くらいを候補にしておけば十分です。
「受けられるもの全部」ではなく現実的な受験数に絞る
民間から公務員を目指すときにありがちなのが、「受けられそうな試験は片っ端から」という受け方です。
ただ、実際には、
・勉強時間や仕事との両立
・試験日程の重なり(同日実施・同一年度1区分制限 など)
・試験科目の違い(教養のみ/専門あり/SPI型 など)
といった要素を考えると、現実的に受験できる試験の数には限界があります。
次のような基準を手がかりに、「本気で準備する試験」を3〜5個程度に絞っていくのがおすすめです。
・第一志望に近い自治体・職種かどうか
・自分の経験が評価されやすい区分かどうか(社会人採用か、一般枠か)
・試験科目や方式が似ていて、勉強の相性が良い組み合わせかどうか
数をこなすのではなく、「受けるものを決めて準備する」という感覚に切り替えるのがポイントです。
1年間の受験スケジュールをカレンダーに落とし込む
候補が見えてきたら、1年間のざっくりしたスケジュールに落とし込みます。
在職中に受験する場合はとくに、この部分が計画の現実性を左右します。
民間→公務員の受験では、一般的に次のようなステップをたどるケースが多いです(自治体や区分によって順番の前後やステップの増減があります)。
【民間→公務員|受験ステップの全体像(年間イメージ)】
① 募集要項の公開
② 出願(出願期間と必要書類〔職務経歴書・自己PRシートなど〕の提出)
③ 一次試験(筆記・基礎能力検査など)
④ 二次以降の試験(面接・作文/小論文など)
⑤ 合格発表
⑥ 採用・勤務開始
※ 国家公務員の場合、この途中に官庁訪問の期間が入ることがあります。
これらの時期をカレンダーに書き出してみると、
・仕事が繁忙になる時期と試験日程の重なり
・勉強時間を確保しやすい時期
・併願先との日程衝突が起こりそうなところ
などが見えてきます。在職中の人はさらに、
・年次有給休暇の残日数
・試験当日や面接日に休みを取りやすいか
・合格後、いつ退職・引き継ぎを行うのが現実的か
といった点もあわせて考えておくと、直前になってスケジュール調整で困ることは少なくなるでしょう。
第三者の視点を借りる
ここまでやっても、『自分一人では決めきれない』と感じることもあるでしょう。
その場合は、一度、第三者の視点を借りてみるのも一つのやり方です。
・公務員試験の予備校・講座の無料相談
・転職エージェントのキャリア面談(民間→公務員→民間の可能性を含めて聞いてみる)
・元公務員・現役公務員へのOB/OG訪問
など、立場の違う人と話してみることで、
「自分の経歴なら、この区分が現実的そう」「この条件だと、今年はここまでにしておいた方がいい」といった具体的なヒントが見えてくることがあります。
大切なのは、誰かの意見をそのまま採用することではありません。
ほかの人の意見を参考にしながら、「自分は何を優先したいのか」をあらためて自分の言葉で整理していくことが重要です。
まとめ|公務員×転職のポイントおさらい

この記事で解説してきたことの中から、とくに重要だと思うポイントを3つ抜粋します。
民間から公務員、公務員から民間、公務員から別の区分の公務員へ──どの方向の転職を考える方にも共通する視点として、頭の片隅に置いておいてください。
① 一般論ではなく「その年度・その自治体の一次情報」を基準にする
年齢要件、試験科目、倍率、副業ルール、ボーナスの水準。これらは自治体や区分、年度によって変わります。「〇歳までは受けられるらしい」「公務員は副業できないらしい」といった一般論ではなく、必ず受験年度の受験案内や公式資料で確認しましょう。※1 ※5
② 公務員という働き方は、制度とルールの上に成り立っている
身分保障と分限・懲戒、給与表と特別給(ボーナス)、副業の許可制など、公務員の「安定」「収入」「副業可否」は具体的な仕組みに支えられています。イメージだけで判断せず、「自分はこの仕組みをどう受け止めるか」を一度立ち止まって考えることは、公務員への転職を目指す場合はもちろん、公務員という働き方を続けるかどうか考えるときにも大切です。
③ 自分の優先順位と、現実的な動き方を決めておく
どの区分・どの自治体を候補にするか、どこまで併願するか、在職中にどこまで動けるか。収入・働き方・勤務地・家族の事情などを書き出し、「自分は何を優先して、今年どこまで取り組むか」を自分の言葉で決めておくことで、迷いに振り回されにくくなります。
どのような転職にも言えることですが、万人共通の正解ルートはありません。
だからこそ、「一次情報にもとづく判断」「制度への理解」「自分の優先順位」という3つの軸をそろえたうえで、自分なりのペースと順番で選んでいくことが、納得感のあるキャリアづくりにつながります。
FAQ|よくある質問
30代後半〜40代からでも公務員転職は現実的?
「年齢だけで完全にアウト」というわけではありません。一般枠(大学卒程度)は29〜35歳上限の例が多い一方、社会人経験者採用では59歳前後まで受験できる自治体もあります。自治体・区分・年度ごとに条件が違うため、「何歳まで大丈夫か」ではなく、志望先の受験案内で最新の年齢要件を確認することが前提です。※5
一般枠と社会人枠、複数自治体の併願はできる?
複数自治体を受けること自体は一般的です。ただし、
- 「当該年度は1人1区分のみ」のルールがある
- 一次試験日が同日で、物理的に両方受けられない
などの制限がかかることがあります。併願を考えるときは、受験案内で試験日程と受験制限を確認したうえで、優先順位をつけるイメージを持っておくと現実的です。
社会人経験者採用は、一般枠より入りやすい?
「社会人枠=簡単」「一般枠=難しい」とは言い切れません。政令市や特別区クラスではどちらも倍率が数倍になることが多く、
- 募集人数
- 試験方式(筆記重視か、人物重視か)
- 受験者層
によって受かりやすさの印象は変わります。自分の年齢や経験、強みを踏まえ、どちらが「自分に合う土俵」かで考えるのが現実的です。※5
公務員になったら副業はできない?
「一律禁止」ではなく、法律にもとづく許可制・承認制が基本です。
- 国家公務員:国家公務員法にもとづき、有償の兼業や営利企業での業務は原則として承認・許可が必要(※3参照)
- 地方公務員:地方公務員法にもとづき、営利企業で働く場合などは原則として任命権者の許可が必要※4
近年は、地域貢献やスキル活用を目的とした副業を認める自治体も増えていますが、「何がどこまでOKか」は所属先ごとの基準次第です。検討する際は、就業規則やガイドラインを確認し、必要に応じて事前に相談・申請するようにしてください。※2
公務員は「クビにならない仕事」って本当?
「民間よりは安定している」が、「クビにならない」は言い過ぎです。景気悪化だけを理由とした整理解雇は起こりにくい一方で、
- 勤務実績不良や心身の故障に関する分限処分
- 服務違反や非違行為に対する懲戒処分(免職を含む)
といった制度が法律に定められています。公務員の安定性は、「恣意的な解雇からは守られているが、ルールに基づいて責任も問われる働き方」と捉えると実態に近いイメージになります。※3 ※4
免責・注意事項(記事末)
本記事の内容は、2025年11月時点で公表されている情報をもとに、公務員×転職に関する一般的な制度の概要をまとめたものです。実際の受験資格・給与・ボーナス・副業可否・分限・懲戒等の取扱いは、各省庁・自治体・所属組織の規程や個別事情により異なり、今後の制度改正等により変更される可能性があります。
具体的な受験や転職、副業等の判断にあたっては、必ず最新の募集要項・条例・就業規則・公式資料をご確認のうえ、必要に応じて専門家(弁護士・社労士・キャリアコンサルタント等)にご相談ください。
本記事は情報提供のみを目的とするものであり、特定の選択肢の適合性や結果を保証するものではありません。
参考・出典(脚注一覧)
※1 人事院「(令和7年)国家公務員給与等に関する人事院勧告の概要」
内容:2025年(令和7年)人事院勧告における特別給(期末手当・勤勉手当)4.60月→4.65月への引上げ等に関する情報
URL:https://www.psrn.jp/topics/detail.php?id=38771
確認日:2025年11月14日
※2 総務省「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する留意事項について(令和7年6月11日付通知)」に関する解説
内容:地方公務員の営利企業従事・副業に関する許可基準の明確化を求めた2025年6月11日通知の概要
URL:https://www.morihamada.com/ja/insights/newsletters/123031
確認日:2025年11月14日
※3 国家公務員法(第103条・第104条 ほか)
内容:国家公務員の営利企業従事制限、分限・懲戒等の法的枠組み
URL:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/attach/1366607.htm
確認日:2025年11月14日
※4 地方公務員法(第28条、第29条、第38条 ほか)
内容:地方公務員の営利企業従事制限、分限・懲戒等の法的枠組み
URL:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/attach/1366609.htm
確認日:2025年11月14日
※5 公務員試験の倍率・年齢要件等に関する統計・解説(地方公務員試験全般・政令市・特別区などの例)
内容:地方上級・政令市・特別区等の倍率や、年齢要件の目安に関する解説
例:
https://studying.jp/komuin/about-more/magnification.html
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/about_Civil_service_examination/Magnification_Local_civil_service_examination.html
確認日:2025年11月14日
【公務員試験講座18社】予備校・通信講座・スクールのおすすめ比較!大学生も社会人も!費用も紹介 | オトナ-スタディ
オトナ-スタディは、株式会社テトラメディアが運営する「社会人向けの勉強メディア」です。忙しい社会人が働きながら資格取得や学習するためのお役立ち情報を発信しています。














