iDeCo(イデコ)が改悪される!? 5年ルールが10年ルールになったらどうなる?
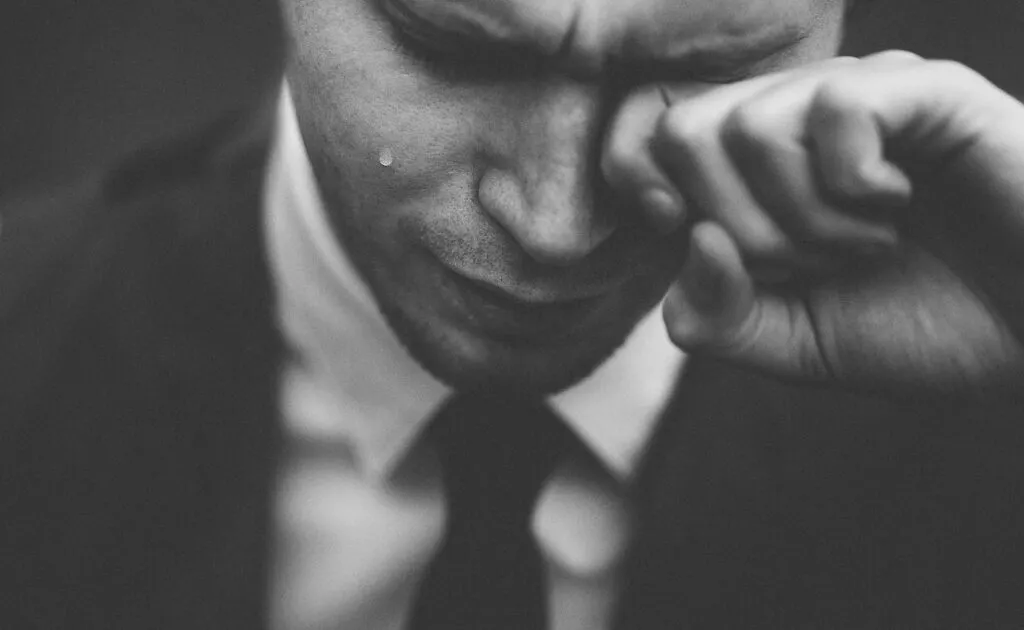
最近、
iDeCoの受取り時の所得控除が、現行の“5年ルール”から“10年ルール”に変わるのでは?
という話題がニュースなどで取り沙汰されています。
 ねくこ
ねくこ「2025年の税制改正で、DC/iDeCoの老齢一時金を先に受け、その後に退職手当等を受けるケースの調整期間は『前年以前4年内』から『前年以前9年内』へ拡大が決定しました。適用は原則2026年1月1日以後の支払に対して行われます。(参考)
『5年ルール』は俗称で、正確には“退職所得控除の計算における勤続(加入)期間の重複排除の調整対象期間”を指します。一方、『退職金→DC/iDeCo一時金』の順序は従来どおり『前年以前19年内』の調整が維持されています。
この変更が実施されると、複数回にわたって「退職所得」の非課税枠(退職所得控除)を利用してiDeCoの一時金を受け取る際のメリットが小さくなり、結果的に税負担が増えてしまう可能性が指摘されています。
今回は、「5年ルール」が「10年ルール」に代わってしまった際のインパクトおよびどうすれば良いかを、私「ねくこ」が具体的にお伝えします。

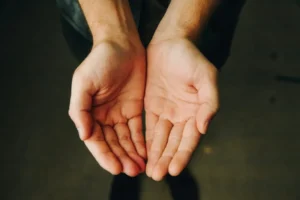
本稿の“10年ルール”は便宜的表現で、条文上は『前年以前9年内』を指します。境界年は支払年ベースで判定します(根拠:財務省『令和7年度税制改正の大綱』)。
退職所得控除の基本と「5年ルール」のおさらい
そもそも、前提の知識として覚えておきたいのが、
お勤めの企業からもらえる「退職金」や、iDeCoを「一時金」として受け取った場合は「退職所得」に区分され、給与所得などと別枠で所得計算される
と、いうことです。
そして、退職所得を計算する際には「退職所得控除」が適用されます。
 ねくこ
ねくここれが例えば、「給与所得」などと比べると税制上優遇されている場合が多いため、iDeCoの強みのひとつにもなっています。
そして、「5年ルール」とは、1回目の「退職所得」の受け取りと2回目の以降の「退職所得」受け取りの間に5年以上経過した場合、退職所得控除がリセットされ、再度控除が受けられる(=別枠扱いになる)仕組みが現行ルールです。
つまり、「退職所得」は税制上優遇されているのですが、それは「退職所得①と退職所得②の受け取りの間に5年以上、期間が開いていること」などが条件となっています。
たとえば、次のようなケースだとメリットがあるとされてきました。
- 60歳になったとき、iDeCoの一時金(退職所得)を受け取る
- 5年以上経ったあとに、会社から退職金(退職所得)を受け取る
- そうすると、会社から退職金を受け取る際、退職所得控除を“もう一度”フルに使える(逆も同様)
これがもし「5年以上あけないと」➡「10年以上あけないと」に変わった場合、5年後にiDeCoの一時金を受け取る戦略が使えず、10年後まで待たないと退職所得控除のリセットができないことになります。
『〇年ルール』は“合算課税”を意味するのではなく、後に受け取る側の退職所得控除の計算式から“重複する期間分”を差し引く(=控除が目減りする)という仕組みです。
その結果、税金が多くかかる可能性が出てくるわけです。
 ねくこ
ねくこ具体的にどのくらい金額が変わるのか、次項で解説します!
適用時期のまとめ
2026年1月1日以後にDC/iDeCoの老齢一時金の支払を受け、かつ同日以後に退職手当等の支払を受ける場合に、“前年以前9年内”の調整が適用されます。逆順(退職金→DC/iDeCo一時金)の“前年以前19年内”は従来どおりです。
退職金2,000万円が出るサラリーマンの場合のシミュレーション
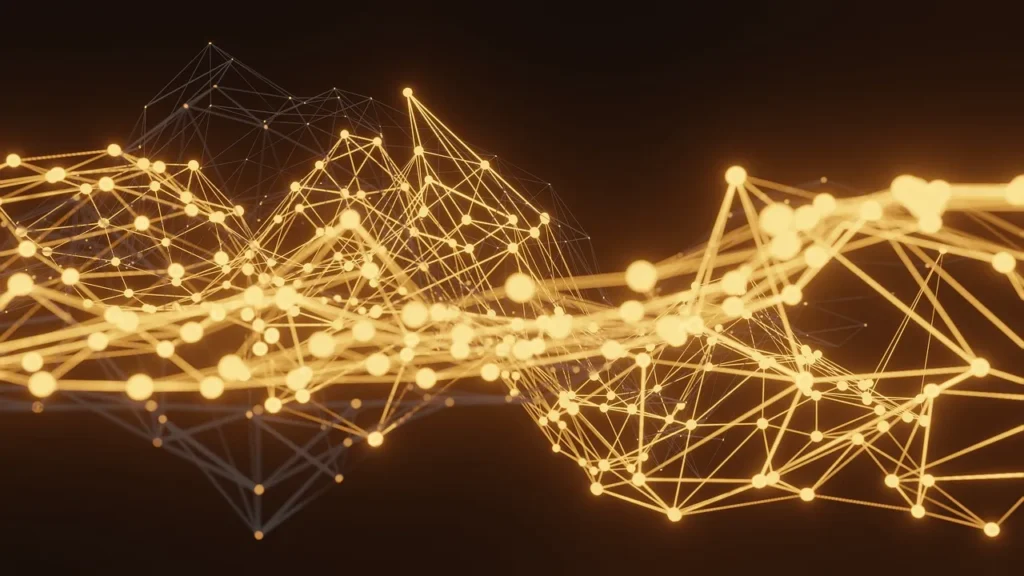
ここでは、以下の前提条件でシミュレーションしてみます。
仮に条件を、
- 会社からの退職金:2,000万円
- iDeCoの一時金:500万円(運用歴20年:40歳開始➡60歳で受け取り)
- 勤続年数:35年(65歳退職を想定)
- 現行ルール(5年後に退職金を受け取る場合)と、10年ルールが導入された場合を比較
- 課税率(概算)
- 所得税:10%(復興特別所得税等は省略)
- 住民税:10%
- 合計:20%
とします。
※以下の税額比較は“説明簡略化”のため概算20%を仮置きしています。実務は所得税の累進税率+復興特別所得税+住民税で速算表に基づき源泉徴収・年末精算されます。正確な税額は国税庁の速算表とタックスアンサーをご確認ください。(参考:国税庁)
 ねくこ
ねくこまず、退職所得控除から算出してみましょう。
退職所得控除の計算

退職所得控除は、勤続年数(iDeCoの場合は運用歴)に応じて次のように計算されます(2024年現在のルール):
- 勤続年数/iDeCoの加入年数が20年以下の場合
- 40万円 × 勤続/加入年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続年数/iDeCoの加入年数が20年超の場合
- 800万円 + 70万円 × (勤続/加入年数 – 20年)
iDeCoの運用歴は20年なので、
40万円 × 20年=800万円
です。
また、企業の退職金の場合は35年勤続なので、
800万円+70万円×(35−20)=800万円+70万円×15=800万円+1050万円=1850万円
が、それぞれ退職所得控除となります。
そして、実際に所得税&住民税がかかる退職所得の計算方法は、
です。
※特定役員退職手当等など一部例外あり。控除額は20年以下:40万円×年数(最低80万円)/20年超:800万円+70万円×(年数−20)(参考:国税庁)
 ねくこ
ねくこ×1/2されるのも、退職所得のポイントです。
上記の計算式に当てはめて、0やマイナスになった場合は課税金額が0ですよ。
パターンA:現行(5年ルール)の場合
そして、上記の条件&計算式で計算した場合、
1. iDeCo(60歳に受取、加入期間20年)
- iDeCo 一時金:500万円
- 退職所得控除(iDeCo分):800万円
計算式
(500万円−800万円)×1/2=-150万円・・・は「マイナス」になるので、課税所得は0円、よって税金はかかりません。
2. 会社の退職金(65歳に受取、勤続35年)
- iDeCo受取から5年空いている(60歳→65歳)ため、「別枠」が適用されます。
- 退職金:2,000万円
- 退職所得控除(勤続35年分):1,850万円
計算式
(2,000万円−1,850万円)×1/2=75万円
この金額にさらに、前提条件の「課税率20%」を掛けると、
が、税金として取られる計算になります。
➡ 現行の5年ルールだと、上記体の場合は退職金にかかる税金は約15万円
(iDeCoは非課税で受け取り、かつ退職金は別枠で計算できるため、税負担が小さい)
パターンB:もし「10年ルール」になった場合
現行のルールである「5年ルール」ではiDeCoと退職金、2500万円に対して15万円が税金となりました。
では、これがもし「10年ルール」になった場合はどうでしょう?
1. iDeCo(60歳に受取)
同じく「加入期間20年」による退職所得控除800万円を前提にすると、この時点だけを見れば税金は0円です。ただし、「10年ルール」になった場合「60歳(iDeCo受け取り)→65歳(退職金受取)」は5年しか空いていないので、2回目の受け取り(65歳)とは合算扱いになる可能性があります。
2. 会社の退職金(65歳に受取)
- 10年未満なので、1回目(iDeCo)と2回目(企業退職金)が合算されて計算されるイメージになります。
 ねくこ
ねくこiDeCoの一時金と、退職金をプラスした金額から一括して退職所得控除が引かれた金額に税率が掛かり、税金を納めなくてはならなくなります。
合算計算の流れ(簡略版)
改正後は『DC/iDeCo一時金→退職金』が“前年以前9年内”に該当すると、退職金側の退職所得控除額から“重複期間分(例: iDeCo加入年数と勤続期間が重なる年数×40万円等)”が差し引かれます。
そのうえで(収入金額−調整後の控除額)×1/2で退職所得を算出します(本稿のシミュレーションは理解促進のため簡略化しています)。
- iDeCo 500万円 + 退職金 2,000万円 = 合計 2,500万円
- ➡退職所得控除(35年分の1,850万円)を差し引く
※厳密には、iDeCoの加入期間分の控除800万円と、企業勤続35年の控除1,850万円をどう区分するかなど複雑な規定がありますが、ここでは代表的なケースとして「後の退職金の勤続年数をベースに計算される」想定でシミュレーションします
計算式
(2,500万円−1,850万円)×1/2=650万円×1/2=325万円
この金額にさらに、前提条件の「課税率20%」を掛けると、
が、税金として取られる計算になります。
 ねくこ
ねくこルールが変わるだけで、50万円多く納税する必要が生じました。
➡ 10年ルールになった場合、最終的にかかる税金は約65万円
もちろん、この「65万円」は「iDeCo+退職金」を合わせた全体の退職所得に対する税金ですが、結果的には65歳でもらう退職金として大部分が課税されるイメージになります。
もし「10年ルール」に改悪された場合、どう対処すればいい?

ここまで見ると、「10年ルール」になったときに、退職金・iDeCo一時金を10年未満で受け取ってしまうと、課税の面で非常にもったいないことがわかります。
では、実際にそうなった場合、どのような対策が考えられるでしょうか?
1. 退職金とiDeCoの受取りタイミングを大きくずらす
10年ルールが実際に導入された場合、iDeCoの一時金を受け取りたい時期を、退職前後「10年目以上空ける」※ことで、現行の5年ルールと同様、別枠の退職所得控除を満額近く受けられる可能性があります。
※条文上の表現は“前年以前9年内”です。“10年目以上”という言い回しは便宜的表現で、境界年の扱いは支払年ベースで判定される点を注記してください。
 ねくこ
ねくこただし、iDeCoは60歳以降に受け取れる仕組みです。
勤務延長や再雇用など人によっては、生活資金との兼ね合いも出てくるので、10年先まで待てるかどうかは注意が必要です。
2. 分割(年金)受取を検討する
iDeCoには一時金で受取る方法のほかに、年金方式(分割受取)があります。
- 一時金で受け取ると「退職所得扱い(退職所得控除)」
- 年金方式で受け取ると「雑所得扱い(公的年金等控除)」
となります。
当然ですが、年金方式で少額ずつ受け取れば、1年あたりの課税所得が少なくなるメリットがあります。
公的年金と合計した金額が控除額の範囲内であれば、結果的にほとんど税金がかからないケースもあります。(参考:国税庁)
※ただし、いわゆる年金として受け取る場合は給付事務手数料(1回の振込につき税込440円)などが掛かる点も加味してください。
 ねくこ
ねくこ10年ルールになったら、一時金で満額を受け取るメリットが下がるかもしれません。
それでも雑所得の方が損になるケースがないとは言えませんが、「分割受取り + 公的年金等控除を活用」という戦略を取るのも一つの手です。
受給年齢の制約
iDeCoの老齢給付は原則60〜75歳の間で受給開始を選択します。受取タイミング調整の際は、この上限年齢も計画に織り込んでください。
3. 退職金の受取り方法を分散できないか検討する
企業によっては、早期退職制度や退職金の分割受取り(企業年金など)を選べる場合もあります。
- 退職金の受取りを一度にまとめず、ある程度年数を空けて受け取る
- iDeCo一時金をどのタイミングで受け取るか調整する
など。
 ねくこ
ねくこ複雑になりますが、各制度の選択肢をしっかり把握したうえで、総合的なシミュレーションを行うのが重要です。
4. そのほかの資産形成手段を併用する
もしまだ資産形成を始めていない人で、「iDeCoの税制メリットが小さくなるかも・・・」と感じるのであれば、NISAと併用し、受け取り時の非課税メリットをさらに活かす方法も考えられます。
例えば
- iDeCoの拠出金は全額所得控除という強みがある
- 受け取り時に課税リスクが高まるなら、その分NISA枠を利用して出口(売却時)非課税枠を確保する
ため、併用、もしくは退職金のある企業にお勤めの場合は、NISAを始めるといった判断をしても良いでしょう。


【Q&A】iDeCoの5年ルール改正の疑問に答える
そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
iDeCoの「5年ルール」とは何?
退職所得控除を2回使うための条件です。
2回目の退職所得受取まで5年以上空けると退職所得控除がリセットされ、別枠で控除が使える仕組みです。
「5年ルール」が「10年ルール」になるとどうなる?
控除が再適用されるまでの期間が10年に延び、退職金とiDeCoの受取時期が近いと控除が1回分しか使えず、税負担が増える可能性があります。
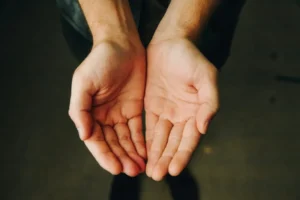
実際にどのくらい税額が変わる?
例えば、現行の5年ルールなら税額は約15万円で済むところ、10年ルールだと約65万円になる試算もあります。
「10年ルール」に備えるにはどうしたらいい?
- 受取時期を10年以上ずらす
- iDeCoを年金方式で受け取る
- 退職金を分割する
などの対策が考えられます。
一時金ではなく年金方式で受け取るとどうなる?
「雑所得」扱いになり、「公的年金等控除」が使えます。
控除枠内に収めれば非課税となる可能性もあり、税負担を抑える戦略として有効です。
退職金とiDeCoの受取タイミングを調整する意味は?
同じ年に受け取ると控除が1回分しか使えないため、タイミングをずらして控除を2回活用することで節税効果が得られます。
iDeCoとNISAはどう使い分ければいい?
iDeCoは拠出時の所得控除が強み、NISAは受け取り時非課税が特徴です。
制度の特性に応じて併用するとバランスよく資産形成ができます。

ルールが変わる前に今できることは?
制度改正に備えて、情報収集を怠らず、必要に応じて専門家に相談しましょう。
自分に合った受取戦略の設計が重要です。
まとめ
- 5年ルールが10年ルールに変わると、iDeCoの一時金を受け取るタイミングを退職金受取から5年だけ空けていた戦略が通用しなくなる
- 10年未満だと、退職所得控除を新たにフルで使えないため、課税額が大幅に増えるおそれがある
- 一時金ではなく「年金方式」で受け取り、公的年金等控除を使う方法や、退職金・iDeCo受取のタイミング調整を行うことで、税負担を抑える可能性がある
iDeCoの最大のメリットは、拠出時の「全額所得控除」や運用益の「非課税」など、長期にわたる税制優遇にあります。
ただし、受け取りのタイミング次第で思わぬ課税リスクが生じるかもしれないため、最新の制度改正情報を追いつつ、ライフプラン全体を見据えて準備することが大切です。
※この記事は、2024年12月時点の情報をもとに作成したシミュレーション例・解説です。実際の税制は年度によって変更される可能性があります。また、個々人の所得状況や家族構成などによって最適な受取方法は異なりますので、具体的には税理士やFPなど専門家へのご相談をおすすめします。
 ねくこ
ねくこまだ確定ではないため、「10年ルール」にならないように声をあげることも大切ですね!











