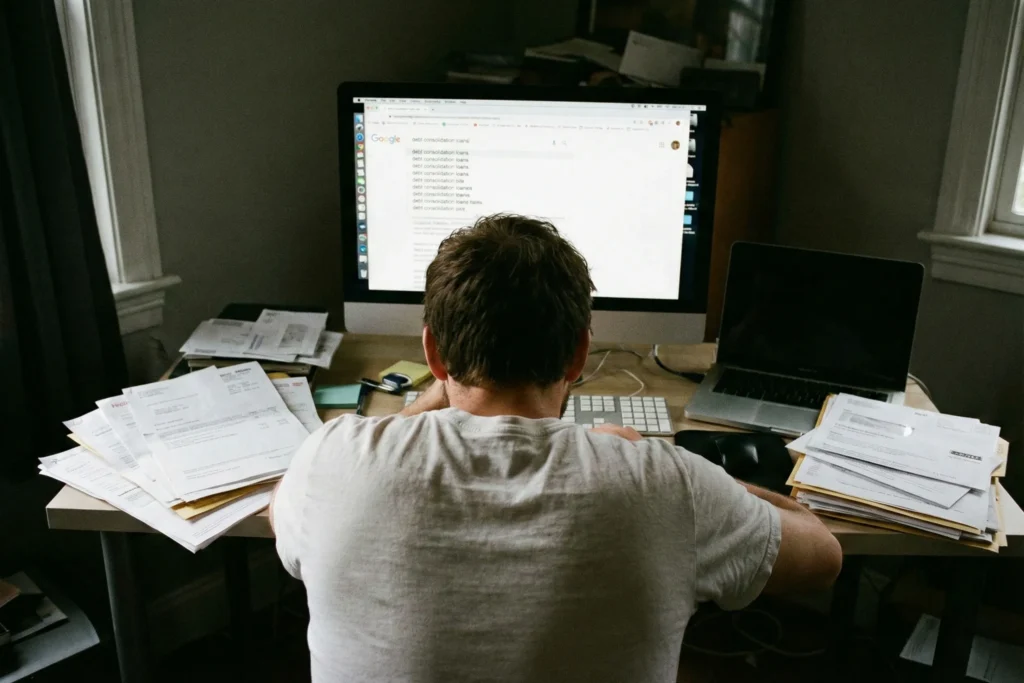【2025年7月4日】の経済・時事ニュースまとめ

7月4日朝のマーケットは、前夜の米国株高と強い米雇用統計を受けてリスク選好が優勢となり、日経平均株価は節目の4万円に迫る勢いとなりました。
国内では家計消費の回復や日銀審議委員の追加利上げ発言が注目を集め、海外ではEUのAI規制運用指針や米最高裁の判決が話題となっています。
 ねくこ
ねくここれらの動きを、主要指数の値動きとともに整理します。
主要株価指数・為替レート(7月4日 午前10時時点)
| 指数 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 39,875.39円 | +89.49 (0.22%)円 |
| NYダウ | 44,828.53ドル | +344.11 (0.77%)ドル |
| S&P500 | 6,279.35ポイント | +51.93 (0.83%)ポイント |
| ドル円為替 | 144.60円 | +0.72円 |
日経平均株価の動き
日経平均は前夜の米国株上昇を好感し、半導体や自動車株が買われました。前日の終値39,785.90からやや上昇基調で4万円に迫る勢いです。
米長期金利の落ち着きが続けば40,000円突破、一方、日銀の追加利上げ観測が強まれば上値を抑える可能性があります。

米国主要指数の動向
7月3日の米国市場は独立記念日前の短縮取引ながら、強い雇用統計を受けてNYダウが344.11ポイント、S&P500が51.93ポイント上昇して取引を終えました。
雇用の力強さは企業業績の下支え要因ですが、FRBの追加利上げシナリオが再浮上すると株価バリュエーションには逆風となるため注意が必要です。
ドル円為替の動向
午前10時のドル円は144.60円前後で推移し、前日17時比で72銭のドル高・円安となりました。
米金利高と日銀の慎重姿勢がドル買い材料となっています。米雇用統計を受けたFRBの利下げ後ずれ観測が続けば、145円台への上昇も視野に入ります。
ただし日本政府・日銀の円買い介入警戒も根強く、急騰局面では注意が必要です。
資産運用のポイント(2025年7月4日現在)
① 市場全体の流れを俯瞰する
米国株は独立記念日前の短縮取引でも主要3指数がそろって最高値を更新し、日本では家計消費の力強い回復が確認されました。
こうしたリスク選好環境はポートフォリオ全体の時価を押し上げる一方、材料出尽くし後の急な調整も招きやすい局面です。
値上がりの背景(雇用増・賃上げ・政策期待)と下押し要因(追加利上げ観測・貿易摩擦再燃)を同時に把握し、全体リスク量を調整する姿勢が欠かせません。
② 長期・分散・低コストの基本を死守する
株式やREITが好調でも、短期の値動きに合わせた頻繁な売買は取引コストと税負担を増やします。
NISAやiDeCoを活用し、世界株式インデックス型など手数料の低い商品を中心に「時間」と「地域」の分散を続けることが、複利効果を最大化する王道戦略です。
今後もグローバル株高が続く保証はないため、相場が熱気を帯びているときほど投資方針を再確認しましょう。


③ 金利上昇局面での債券・預金の見直し
日銀の高田審議委員が「利上げ再開は一時停止に過ぎない」と述べたように、国内金利の追加上昇リスクは無視できません。
超長期国債や変動金利付き社債の価格変動は大きくなりやすく、残存期間の短い債券ファンドや個人向け変動10年国債などへリバランスする選択肢があります。
また普通預金金利が上がりにくい場合は、ネット銀行の定期やMMFで受取利息を底上げする工夫も検討に値します。


④ 円安トレンドと外貨建て資産
ドル円は144円台で底堅く推移し、輸入コスト増と資産目減りリスクが続いています。
外貨建てMMFや米国株ETFを既に保有している場合、評価益を享受しつつも急な介入による逆流に備えて為替ヘッジ比率を点検しましょう。
ドルの持ち高を増やす場合でも、積み立て頻度を高めて平均取得レートを平準化する「時間分散」が有効です。
⑤ 税制優遇制度のフル活用
2024年に拡充された新NISAは年間投資枠が360万円に拡大し、非課税保有限度額も1,800万円まで伸びました。
まずは積立枠(年間120万円)で国際分散インデックスを自動購入し、余裕資金がある場合に成長投資枠(年間240万円)で個別株やアクティブファンドを追加する流れが効率的です。
iDeCoは拠出額が全額所得控除となるため、特に所得税率が高い現役層ほど節税メリットが大きくなります。


⑥ 短期取引(FX・暗号資産)の注意点
強い米雇用統計でボラティリティが上昇しやすい状況下、証拠金取引では逆方向への急変動でロスカットが発生する事例が増えています。
レバレッジを下げ、損切り水準を事前に決める「資金管理」が生命線です。
暗号資産はJ.P.Morganが市場規模見通しを下方修正したように、規制動向ひとつで需給が変わる点を念頭に置き、全体資産の数%以内に抑えるのが無難でしょう。

⑦ 生活防衛資金の確保とメンタル面
家計消費が回復しても、輸入品価格や公共料金は引き続き上昇基調にあります。
手取り月収の6か月分を流動性の高い預金で確保し、突発的な支出に備えておくことで、相場変動時に資産売却を強いられるリスクを減らせます。
またSNSやニュース速報に触れる時間を限定し、情報過多による焦りを回避することも長期投資を続けるコツです。

国内ニュース
家計消費が市場予想を大幅に上回る
総務省発表によると、5月の実質家計消費は前年同月比+4.7%と市場予想の+1.2%を大きく上回りました。
サービス支出増加が寄与しています。
消費回復を背景に、日銀が年内にも追加利上げに動くとの見方が強まり、金融株や小売株の物色が活発化しています。
日銀・高田審議委員「利上げ休止は一時的」と発言
日銀・高田創審議委員は講演で「物価目標達成が見通せれば利上げを再開すべき」と述べ、年内の政策修正を示唆しました。
発言を受けて長期金利が上昇し、銀行株が買われる一方で、不動産株や高配当株には売りが入りました。
参院選が公示 物価高対策が主要争点に
20日に行われる参院選の公示がスタートし、与野党とも生活コスト抑制策を前面に掲げています。
食品価格高騰への対策や減税案が注目されています。
選挙結果次第で来年度予算編成や社会保障制度の見直し速度が変わる可能性があり、関連銘柄の物色が続きそうです。
日本企業の賃上げ率、34年ぶりの高水準
日本最大の労働組合連合である連合は、2025年の春闘最終集計で平均賃上げ率が5.25%に達したと発表しました。
これは1991年以来の高水準で、昨年の5.10%、一昨年の3.58%を上回ります。深刻な人手不足と物価高を背景に、企業側にも「インフレを上回る賃上げ」が半ば常識として定着しつつあります。
一方で、中小企業や非製造業が賃上げを継続できるかが課題となり、コスト転嫁の動きが価格に波及するリスクも指摘されています。
「漫画終末論」が訪日観光を揺さぶる
1999年刊行の漫画『私が見た未来』の「2025年7月に大地震が起こる」という解釈がSNSで拡散し、香港発の訪日需要が前年同月比11%減少しました。
一部航空会社は秋以降の日本路線を減便・休止するなど観光業に思わぬ影響が広がっています。
インバウンド需要に依存する地域観光地や小売は、夏休み商戦の見通しを下方修正しています。政府・観光庁は正確な防災情報の発信を強化し、風評被害の抑制に乗り出しました。
海外ニュース
EU、AI法運用へ業界向けコード策定へ
EUはAI法の円滑な運用を目的に「コード・オブ・プラクティス」を2025年末までに適用すると発表しました。
企業はリスク評価と透明性確保が求められます。
EU域内で事業を行う日本企業にも規制対応コストが発生する可能性があり、IT投資計画の前倒しが検討されています。
米最高裁、移民関連でトランプ政権を支持
米最高裁は南スーダン難民の強制送還を巡り、政権側の権限を認める判決を下しました。
移民政策の強硬姿勢が続く場合、製造業の人手不足やサプライチェーン構築に影響が出るとの懸念があります。
J.P.Morgan、ステーブルコイン成長予測を下方修正
J.P.Morganはステーブルコイン市場の25年後残高を従来推計の1兆ドルから5,000億ドルに引き下げました。
暗号資産関連株には一時的な調整圧力がかかる見込みですが、規制明確化による長期安定化効果も期待されています。
フランス競争当局、Sheinに4,000万ユーロの制裁金
仏競争当局は、中国系ファストファッション大手Sheinが「値引き前価格」を意図的に引き上げるなど虚偽の割引表示を行ったとして、同社に4,000万ユーロ(約47億円)の罰金を科しました。
調査対象商品の57%が実質的な値下げになっていなかったと指摘しています。
EU域内の消費者保護規制違反に対する監視強化が鮮明となり、越境EC事業者は価格表示の透明性確保とサステナブル対応が不可欠となりそうです。
私たちの生活に起こること
7月に入り、消費回復と円安が同時進行しています。円安は輸入食品や海外旅行のコスト増につながる一方、輸出企業や国内観光地には追い風です。
家計では「値上げ前に必要品を早めに購入」「変動金利ローン利用者は返済計画の見直し」を検討する価値があります。
また、投資面では短期的な為替変動に振り回されず、長期・分散・低コストの原則を守ることが重要です。