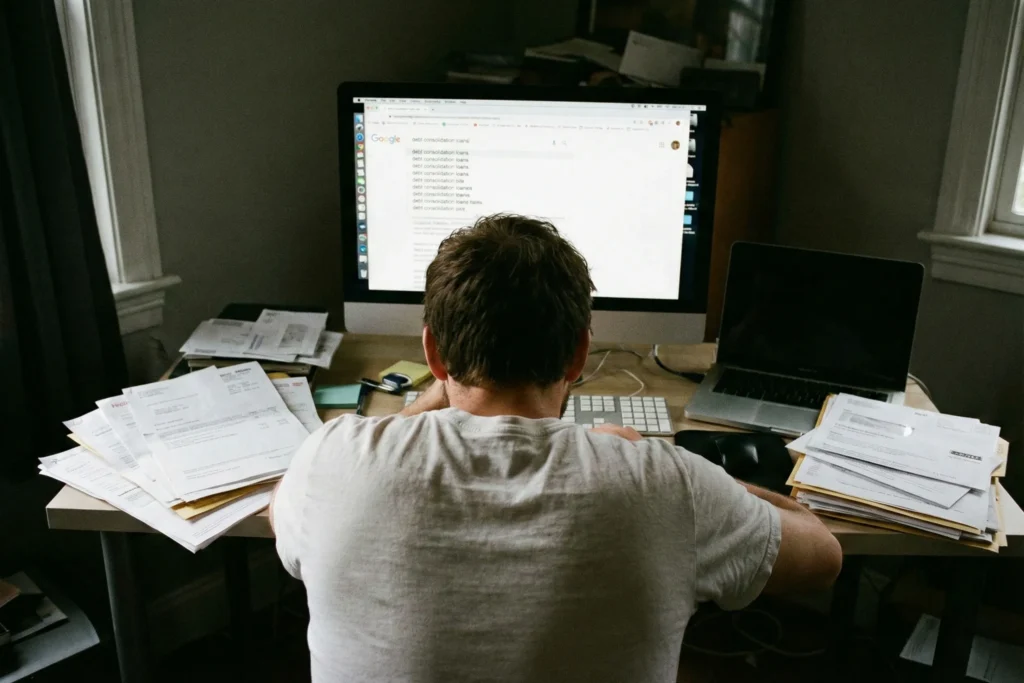【2025年7月11日】の経済・時事ニュースまとめ

7月11日午前、東京市場は豪雨に伴う交通混乱と米国株の最高値更新という対照的な材料を抱えて始まりました。
日経平均株価は小幅高で寄り付き、円は146円台前半で推移しています。
国内では首都圏の新幹線が一時運転を見合わせ、中国軍機の異常接近など安全保障面の緊張も報じられました。
海外では米国株が航空・消費関連を中心に続伸し、ネパールでは氷河湖決壊による洪水が発生するなど、経済と災害のニュースが交錯しています。
主要株価指数・為替レート(2025年7月11日 午前10時時点)
| 指数 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 39,685.93円 | +39.57 (0.100%)円 |
| NYダウ | 44,650.64ドル | +192.34 (0.43%)ドル |
| S&P500 | 6,280.46ポイント | +17.20 (0.27%)ポイント |
| ドル円為替 | 146.32円 | +0.06円 |
日経平均:ソフトバンクGや半導体関連が下支え
日経平均、朝方は米国株高を受けた買いが先行しましたが、豪雨による交通混乱で取引参加者が減少し、上値は限定的でした。
ソフトバンクグループや半導体製造装置株が円安メリットを追い風に堅調で、指数を小幅プラス圏に保っています。

米国株:航空・消費関連がリードし主要指数が再び最高値
10日(米東部時間)の米国市場は、デルタ航空の好調な見通しを受けて航空株が急伸し、ダウとS&P500がそろって過去最高値を更新しました。
インフレ鈍化観測が強まり、ハイテクや小売りにも資金が流入したことが背景です。
ドル円:FRB利上げ観測でじり高
米金利の再上昇を背景にドルが買われ、ドル円は146円台前半で推移しています。
前日のNY終値(146.26円)から小幅高となり、輸出関連株の支援材料になっています。
資産運用で心掛けること(2025年07月11日時点)
株式・ETF:高値圏でのバランス調整
米国主要指数は最高値圏にあり、日本株も円安で底堅い水準を維持しています。
こうした相場では評価益に気を取られてポートフォリオが株式に偏りやすくなりますが、長期的なリターンを安定させるには資産配分を定期的に見直し、含み益が膨らんだ銘柄を一部売却して他資産へ振り向けるリバランスが有効です。
利益確定を焦る必要はありませんが、「許容リスクに合わせた比率」に戻すことが長期・複利の効果を守る鍵になります。

国内株:配当とインカムを意識
日本企業は株主還元強化を競っており、配当利回りが相対的に高い銘柄が多いです。
高配当株や自社株買い企業を中心にインカムゲインを意識したポートフォリオを組むことで、値動きが荒い局面でも配当が下支えになります。

米国株:ドルコスト平均で分散
米国市場はセクター間の温度差が大きく、一括投資はタイミングリスクが高いです。
定額積立によるドルコスト平均法でS&P500指数連動ETFなどを購入しつつ、バリュエーションが高いハイテク銘柄には比率上限を設けるなど、ルールを決めて臨むと過度な集中を避けられます。
債券・キャッシュポジション:金利動向を味方につける
日米ともにインフレのピークアウトが意識され、長期金利は方向感を探る展開です。
キャッシュを厚めに持ちながら、利率が上昇した安全資産で金利収入を確保する戦略が現実的です。
個人向け国債:利率上昇を活用
7月募集分の変動10年国債は年率0.96%と昨年比で大幅に改善しています。
固定費削減の一環でネット証券のキャンペーンを併用すれば、普通預金より有利な無リスク資産として機能します。
マネー・マーケット・ファンド(MMF)
円建てMMFや超短期公社債ファンドは、手元流動性を確保しつつ年率0.4%程度の利回りが期待でき、次の投資機会までの一時駐在先として有効です。
為替・FX:ドル高・円安への備え
米金利の再上昇観測からドル円は146円台半ばにあり、円安進行は輸入コスト増と外貨建て資産評価益拡大という二面性を持ちます。
為替ヘッジ付き投信
外貨建て債券や海外REITに投資する際、為替ヘッジ付き商品で為替変動リスクを抑えつつ利回りを狙う方法があります。
ヘッジコストが高止まりしている場合は、ヘッジ比率を50%程度に抑える選択肢も検討しましょう。
レバレッジ抑制と損切りルール
FXは小さい証拠金で大きな取引が可能ですが、ドル円1円の変動でも実効レバレッジ次第で資金を大きく失う恐れがあります。
最大レバレッジを10倍以下に制限し、1ポジションあたりの損失許容額を資産の2%以内に収めるなど、定量的なルールを設けると大きな損失を防ぎやすくなります。

NISA/iDeCo:長期分散投資の基本を守る
2024年に拡充された新NISAは、つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円で年間360万円、総枠1,800万円まで非課税で運用できます。
長期分散投資という制度趣旨を踏まえ、急激なポジション変更よりも「毎月の積立を継続し、定期的にリバランスする」ことが王道です。

成長投資枠の活用
値動きの大きい個別株やテーマ型ETFは、この枠で上限を決めて一括投資し、つみたて投資枠と合わせてポートフォリオのリスクを最適化します。

iDeCoのリバランス
60歳まで引き出せないiDeCoは、株式偏重になりやすいですが、債券ファンドや定期預金へのリバランスで値下げ局面の下落幅を和らげられます。
運用管理機関の手数料や信託報酬も定期確認しましょう。

コモディティ・インフラ:インフレヘッジと実物資産
原油価格は追加関税リスクで上値が抑えられていますが、インフレの再燃は完全に収束していません。
実物資産への一部投資はポートフォリオの分散に寄与します。
金ETF:ポートフォリオの5%目安
金は利息を生まない一方、地政学リスクが高まると買われやすく、株・債券と相関が低いです。
上限5%程度を目安にGoldETFを保有すれば、急落局面の緩衝材として機能します。

インフラファンド:安定配当とインカム源
国内外の再エネ・物流施設に投資するインフラファンドは、安定したキャッシュフローを背景に年4~6%の分配金利回りが期待できます。
金利上昇時には分配利回りの相対的魅力が低下するため、REITとの分散を意識しつつ総資産の10%以内に抑えるのが無難です。
国内ニュース
首都圏で豪雨 新幹線一時運転見合わせ
10日夜からの猛烈な雨で、東海道・東北新幹線が最大45分運転を見合わせました。
気象庁は関東地方に土砂災害警戒情報を発表し、自治体が避難を呼び掛けています。
外交・安全保障:中国軍機が自衛隊機に異常接近
防衛省によると、中国JH-7戦闘爆撃機が東シナ海上空で航空自衛隊の電子情報収集機に最接近70mまで接近しました。
日本政府は中国側に厳重抗議し、再発防止を要求しました。
政治:石破首相「対米依存を減らす」
石破茂首相は10日、エネルギーや食料安全保障で「対米依存を減らし、自立性を高める」と強調しました。
トランプ米大統領が日本製品に25%の追加関税を課すと表明したことへの対抗策として、国内生産と多角的貿易を推進すると述べました。
ジャパンエレベーターサービス株、公開価格の60倍に
保守・改修需要を背景に、ジャパンエレベーターサービスの株価が上場来高値を更新し、IPO調整後価格比で約60倍に達しました。
M&Aによる全国シェア拡大が評価され、トランプ政権の輸入関税の影響を受けにくい内需銘柄として海外機関投資家の買いも集まっています。
PERは約50倍と高水準にある一方、事業承継ニーズを取り込む成長余地が注目されています。
海外ニュース
ネパール洪水 チベット氷河湖の決壊が原因
国際山岳研究センター(ICIMOD)は、チベット側氷河湖の排水が9人死亡・多数行方不明の洪水を引き起こしたと発表しました。
衛星画像で湖水の急減少が確認され、専門家は温暖化で同様の事例が増えると警告しています。
EUで化石燃料依存が再拡大
欧州連合では2025年上半期、再生可能エネルギー発電量が天候不順で減少し、天然ガスと石炭火力の比率が上昇しました。
CO₂排出削減目標への遅れが懸念されています。
米国株高・航空株急騰、ドル高が進行
米国の航空大手は夏の旅行需要増を背景に業績見通しを上方修正し、株価が急伸しました。
同時にドル高が進行し、新興国通貨に下押し圧力が掛かっています。
豊田通商、米Radius Recyclingを完全子会社化
豊田通商は11日、北米大手スクラップ事業者Radius Recycling(米オレゴン州)の全株式を取得し、循環型資源ビジネスを北米で拡大すると発表しました。
自動車スクラップや非鉄金属のリサイクル網を取り込み、EV向け資源の安定供給と脱炭素サプライチェーンの強化を狙います。
買収完了後、RadiusはNasdaq上場を廃止する予定です。
日本製鉄、米国に新製鉄所建設へ
日本製鉄の橋本英二会長は朝日新聞のインタビューで、買収したUSスチールと連携し「米国内に最先端の製鉄所を新設する」と明言しました。
先端技術で生産効率と脱炭素を両立させ、中国勢との差別化を図る構想で、米国市場シフトをさらに鮮明にしています。
原油相場、小幅反発も関税リスクが重石
11日未明のアジア時間、WTI先物は66.83ドル、前日比+0.39%と小幅高で推移しました。
前日の2%下落はトランプ米大統領による追加関税表明とOPEC需要見通し下方修正が原因で、需要鈍化懸念が依然として重くのしかかっています。
私たちの生活に起こること
円安と米国株高を背景に、輸入食料品やエネルギー価格の上昇が家計を圧迫する可能性がある一方、国内観光業は円安メリットにより訪日需要の底堅さが期待されます。
近年、夏に豪雨災害が頻発する中、非常用持ち出し袋やモバイルバッテリーの備蓄と、避難経路の確認を怠らないことが重要です。
また、温暖化に伴う海外災害の増加はサプライチェーンに波及するため、企業は調達先の多様化とBCP(事業継続計画)の見直しが求められます。