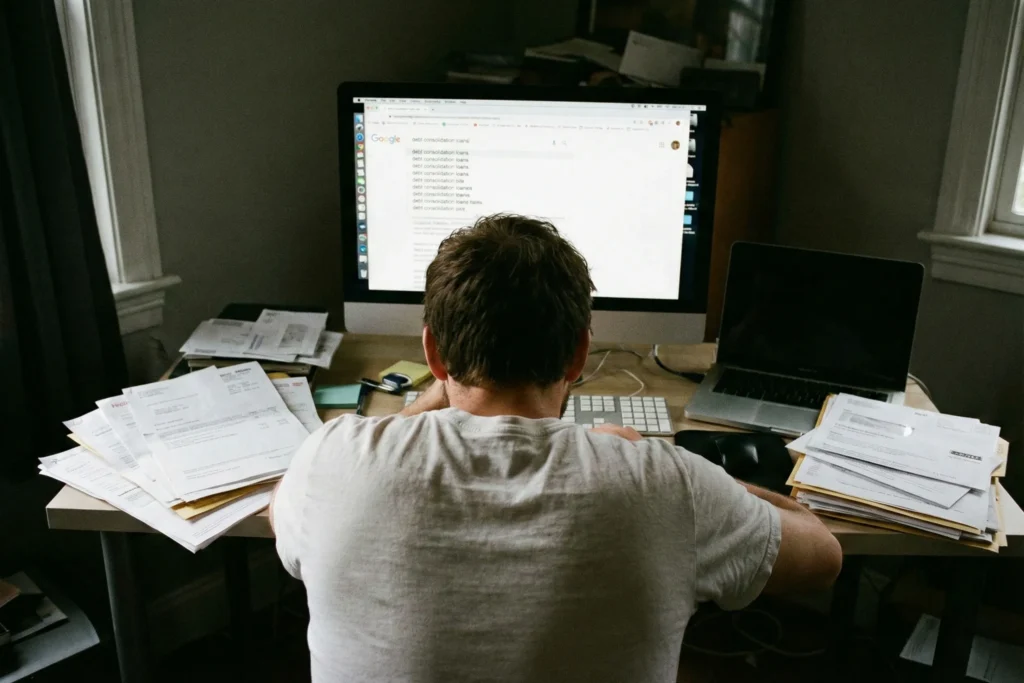【2025年7月24日】の経済・時事ニュースまとめ

7月24日の朝は、日米関税交渉の合意と米国株高の追い風を受けて日本株が大幅高で始まり、為替や債券市場にも波紋が広がりました。
国内では石破茂首相の退陣観測、国債利回り上昇が注目を集め、海外では米EU間の関税協議や欧州中央銀行(ECB)の金融政策スタンスが焦点となっています。
 ねくこ
ねくこ本稿では午前10時時点の主要指標と、過去24時間で報じられた重要トピックを解説します。
主要株価指数・為替レート(7月24日 午前10時時点)
| 指数/通貨 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 41,778.31円 | +606.99 (1.47%)円 |
| NYダウ | 45,010.29 | +507.85(+1.14%) |
| S&P500 | 6,358.91 | +49.29(+0.78%) |
| ドル円為替 | 146.60 | +0.04 |
日経平均:関税合意と半導体買いが牽引
米国と日本が自動車を含む相互関税を15%に設定することで合意したとの報道を受け、自動車株が幅広く買われました。
AI関連の好決算も追い風となり、寄り付き直後に前日比+486円の4万1,600円台へ急伸しました。
米国株:S&P500とナスダックが連日の最高値
米国市場ではS&P500が4営業日連続の最高値を更新。
エヌビディアなどAI関連が買われたほか、EUが15%関税で米国と歩調を合わせる可能性が浮上し、貿易摩擦の緩和期待が強まりました。
ドル円:観測報道と利上げ思惑で方向感乏しく推移
午前10時時点のドル円は146円半ば。
石破首相退陣観測による政治不安が円安圧力となる一方、日銀追加利上げ観測が円高要因となり、短期的に上下動しています。
資産運用をしている人がこの局面で心掛けるべきこと
①短期の市場変動に惑わされない姿勢
日米関税合意や大型M&Aは株式にポジティブですが、政治リスクや熱波による生産障害で急反落の可能性もあります。
現物株中心の人は一度に売買せず、期間を分散して売買する「時間分散」で平均取得価格を平準化することが有効です。
②金利上昇局面での債券・REITの点検
国内10年債利回りは1.6%近辺まで上昇しました。
保有債券の評価損リスクが高まるため、満期まで保有する方針か、市場売却して短期国債にシフトするかを整理しましょう。
住宅ローンは固定金利との差を再試算し、借換えや団信見直しを検討すると家計負担を抑えられます。
③為替ヘッジと外貨建て資産のバランス
ドル円146円台は輸入物価上昇を招く一方、外貨預金や海外ETFの円換算額を押し上げています。
外貨建て比率が高いポートフォリオでは、為替ヘッジ付き投信を一部取り入れて円高反転リスクを緩和する方法があります。
ただしヘッジコストが年率1%程度かかる点を考慮してください。
④長期制度投資(NISA/iDeCo)の継続
NISAは長期・分散が前提の制度であり、相場変動で焦ってリスク資産を売却すると複利効果を損ないます。
積立額の維持が難しい場合は一時停止でも構いませんが、解約よりも「積立額半減→生活防衛資金の確保→景気回復後に再増額」と段階的に調整するほうが合理的です。


⑤災害・気候リスクへの備え
猛暑は電力株や再エネ株の収益を押し上げる半面、生活費高騰リスクも孕みます。
家計支出の固定費(電気・通信)の見直しを行い、余剰資金でインフレ連動債やコモディティETFを5〜10%程度組み入れるとヘッジ効果が期待できます。
投資比率は年齢や収入に応じて調整してください。


上記は一般的な情報であり、投資判断はご自身のリスク許容度と目的に合わせて行ってください。
国内ニュース
石破首相、退陣観測報道を否定するも市場は警戒
毎日新聞が「石破首相が8月末までに退陣を表明へ」と報じ、為替と債券市場に動揺が広がりました。
その後、首相は「事実無根」と否定したものの、政局不透明感は残っています。
政治リーダー交代は歳出拡大につながる可能性があり、長期金利上昇の一因となりました。
国債先物急反落、10年債利回り1.595%に上昇
日米関税合意による「リスクオン」姿勢と日銀の追加利上げ観測が重なり、国債価格が下落。
10年債利回りは1週間ぶり高水準を付けました。
利回り上昇は住宅ローン金利や企業の資金調達コストを押し上げる可能性があります。
日米関税交渉、主な合意事項まとまる
関係筋によれば、日米関税交渉は自動車・農産品を含む相互関税を一律15%とすることで合意。
併せて日本企業による対米投資8兆円規模の枠組みも示され、米国側の雇用創出期待が高まっています。
「物流2024年問題」企業の7割が影響を実感
パレット輸送の推進や企業間連携が注目される中、uprが7月23日に公表した調査によると、回答企業のおよそ70%が「人手不足」「輸送コスト上昇」などの影響を実感しています。
とりわけ「人手不足」は3年前より17ポイント増え「質の高い人材確保」まで課題が深刻化しました。
企業は共同配送や外部パートナー活用へ舵を切りつつあり、物流コストの消費者転嫁が続く可能性があります。
北海道で熱中症搬送54人、 高齢者1人死亡
北海道斜里町では90代女性が室内で倒れ死亡、道内では23日だけで54人が搬送されました。
24日もオホーツクや十勝で気温40℃近くが予想され、自治体は冷房のない住宅への巡回や公共施設の開放を強化しています。
夏の電力需給タイト化や水道管破裂など二次被害にも警戒が必要です。
中小企業の資金繰り調査、成長投資の最大障壁は「余剰資金不足」
ROBOT PAYMENTの最新調査では、中小企業の成長投資意欲は高い一方で、最大の制約は資金不足との結果になりました。
運転資金「3か月未満」の企業が最多で、短期資金の圧迫がDXや設備投資を遅らせる原因になっています。
政策金融公庫や私募債の活用が進まなければ、好機を逃す企業が増える懸念があります。
海外ニュース
ECB、利下げサイクルを一時停止か
7回連続で利下げしてきたECB(欧州中央銀行)は、米国との関税協議の行方やインフレ見通しを踏まえ、今週の理事会で政策金利据え置きを検討中。
市場では年内にあと1回の利下げを織り込む声が多いものの、ユーロ高への警戒感も強まっています。
米石油大手シェブロン、ヘス買収後にヒューストンで575人削減へ
米石油大手シェブロンは、ヘスの550億ドル規模の買収完了からわずか5日で人員削減を公表。
オフショア油田ガイアナの取り込みによる効率化が目的ですが、地元雇用への影響と環境投資との両立が課題になります。
SaipemとSubsea7が合併契約を締結、売上約210億ユーロの新会社誕生へ
イタリアのSaipem(サイペム)とノルウェーのSubsea7(サブシーセブン)の両社はエネルギーサービス大手「Saipem7」を設立し、受注残430億ユーロ・年商210億ユーロ規模の世界最大級オフショア請負企業となる計画です。
完了は2026年下期見込みで、洋上風力やCCS(炭素回収貯留)分野でのシナジー3億ユーロを狙います。
R/GA、AIスタジオAdditionを買収し生成AI事業を拡大
独立系となったNY大手広告代理店のR/GAは、GoogleやAmazon向けのAIソリューション実績を持つAdditionを買収。
AIプロダクト部門を強化し「次世代クリエイティブ体験の核」に据える方針です。
広告業界でのAI人材争奪が激化しています。
私たちの生活に起こること
今回の合意で自動車の関税が下がれば、米国で輸入車の価格が下がり、日本の自動車メーカーの販売が伸びる可能性があります。
ただし、日本政府が約8兆円規模の対米投資を実行すれば、国内の設備投資が細る恐れもあり、雇用や下請け企業への波及を注視する必要があります。
また、円安が定着すると輸入物価の上昇で生活必需品が値上がりします。
家計防衛としては、電気料金の固定プラン見直しや、値上げ前の生活必需品のまとめ買いなどが有効です。
一方で賃上げの流れが広がれば可処分所得は増えるため、企業業績と賃金動向を同時に追うことが重要です。