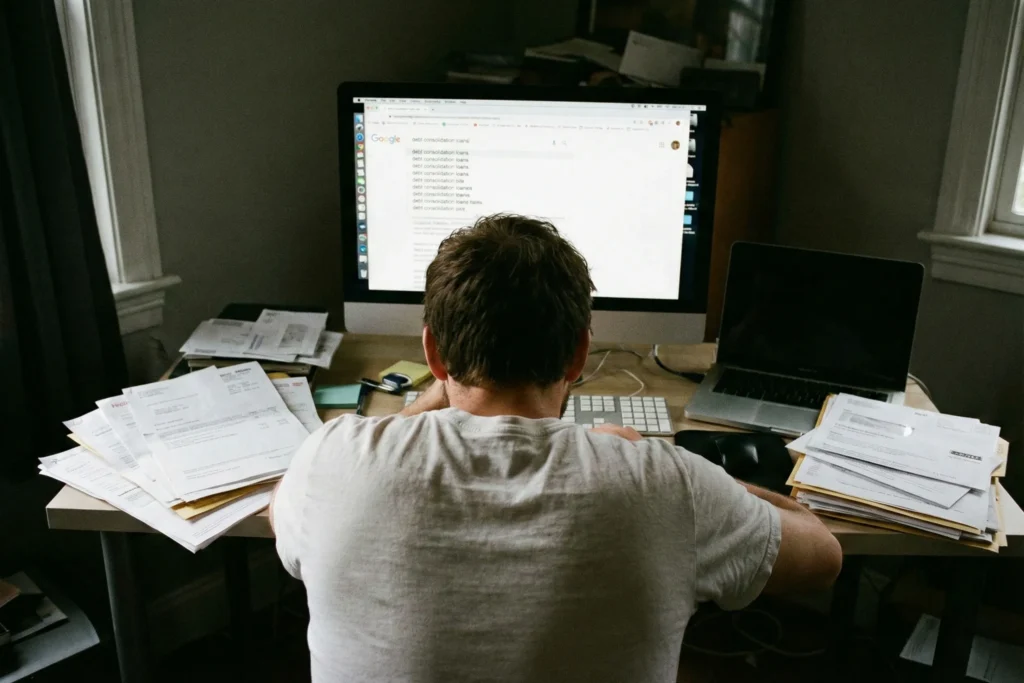【2025年8月13日】の経済・時事ニュースまとめ

きょう8月13日朝は、米7月CPIを受けて米株主要3指数がそろって最高値を更新し、その流れを映して日経平均も4万3000円台で史上最高値圏に入っています。
為替はドル/円が148円台前半でもみ合い。国内では7月の企業物価指数が前年同月比+2.6%と伸びが鈍化しました。
海外ではロシア軍のドンバス前進や、中国がカナダ産キャノーラに暫定関税を発表するなど地政学・通商面の材料も相次いでいます。
主要株価指数・為替レート(8月13日 午前10時時点)
| 指数/レート | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 43,329.45円 | +611.28 (1.43%)円 |
| NYダウ | 44,458.61ドル | +483.52 (1.10%)ドル |
| S&P500 | 6445.76ポイント | +72.31 (1.13%)ポイント |
| ドル円為替 | 148.13 円 | +0.37円 |
日経平均:最高値圏でしっかり
米CPIがおおむね想定線で、米株が記録的な上昇となったことを好感して東京市場へ買いが波及しました。
寄り付きから上げ幅を広げ、10時時点で前日比+611.28 円の43,329.45円。節目の4万3000円台を明確に回復しています。
寄与度上位はファーストリテイリング、アドバンテスト、ファナックなどの大型グロースで、輸出株にも買いが波及しています。値上がり銘柄数が値下がりを上回るなど幅広い物色が見られます。
米株:前夜のCPI受け主要3指数が揃って最高値
米7月CPIは前月比+0.2%、コア前年比+3.1%。インフレが大崩れせずも過度な加速でなかったとの受け止めから、S&P500とNASDAQは終値で過去最高、ダウも+1.1%高となりました。
CPI後、9月の利下げ観測が一段と織り込まれ、株高・ドル安の組み合わせが優勢に。金利低下観測はバリュエーションの追い風になっています。
空運・半導体の上昇が目立つ一方、個別では決算や資金繰りのニュースで明暗が分かれました。全体としてはリスクオンで広く買われる地合いです。
為替:ドル/円は147円台後半でもみ合い
東京10時のドル円為替は148.13 円前後。NY終盤からのレンジを引き継ぎ小動きが続いています。前日17時比ではやや円安方向です。
CPIを受けた米9月利下げ観測がドルの上値を抑える一方、コアの粘着性がドルを下支えするという綱引きで、日中は148円前後を中心とするレンジが意識されています。
今後は米金利動向と株価のリスク選好の度合いが焦点。材料待ちの間はテクニカルな上下が中心になりやすい局面です。
この局面で資産運用をしている人が心掛けること
米7月CPIが想定線で9月利下げ観測が強まり、株高・金利低下・やや円安という組み合わせになっている状況です。
また、中国のキャノーラ関税やウクライナ情勢などの地政学・通商リスクは、商品価格やリスク選好を乱高下させる可能性があるため、短期のブレは織り込んでおく前提にします。
さらに国内では企業物価の鈍化が確認され、先行きの消費者物価安定に一定の含みがある一方、食料分野の粘着性には注意が必要です。
長期の土台は崩さない(NISAの基本)
相場の上げ下げに合わせて拙速に方針を変えるより、コア資産は長期・分散・低コストの原則を維持します。
NISAの非課税メリットは長期で効いてきます。
制度の範囲内で無理のない定期積立と、急な相場に動じない資金管理を心掛けます。

「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を役割分担
つみたて投資枠はコアの長期分散、成長投資枠はサテライトでテーマや個別株の比率を抑えて活用します。
過度な一極集中や短期回転は避け、相場上昇時こそ配分比率を見直してリスクの偏りを整えます。

退職後資金の柱を固める(iDeCo)
iDeCoは税制優遇を生かしつつ、年齢に応じて株式と債券の比率を段階的に調整します。
相場高の局面でも積立は継続し、受給開始が近づくほど値動きの小さい資産へ比重を移す発想が有効です。

為替のボラティリティに構える(FXの注意点)
ドル/円は147円台後半でもみ合いです。
イベント時はスプレッド拡大や窓開けに警戒し、逆指値の徹底やポジションサイズ管理を優先します。
短期勝負はシナリオと撤退基準を事前に決め、睡眠時間をまたぐ保有は避けるなどの基本を守りましょう。

現金比率と「固定費」の整え方
含み益に頼らず生活防衛資金を確保し、突発支出に備えます。
物価や電気代の変動が落ち着くまでの間は固定費の見直し効果が効きやすいので、通信・保険・サブスクの棚卸しを優先しましょう。



上記は一般的な情報提供であり、特定商品の推奨ではありません。最終的な投資判断は、ご自身の資産状況とリスク許容度を確認のうえで行ってください。
国内ニュース
日銀の企業物価指数(7月):前年比+2.6%へ鈍化
日銀が7月の企業物価指数(CGPI)速報を公表。前年比+2.6%と4カ月連続の伸び鈍化、前月比は+0.2%でした。
農林水産物の伸び鈍化や電力・都市ガス・水道の下落が押し下げ要因。北米向け乗用車の輸出価格は前年比-18.4%と減少し、数量確保へ価格調整の動きが示唆されました。
川上の価格圧力はじわり後退。ただし電気料金などの下落が続くかはエネルギー相場次第。消費者物価へ波及するまでには時間差があります。
アクセルスペースHDが東証グロースに新規上場
小型衛星ビジネスのアクセルスペースホールディングスが本日8月13日に東証グロースへ上場しました。
公開価格は375円で、朝の取引開始直後は買い気配スタートとなっています。衛星製造から運用、画像データ提供まで一気通貫のモデルが特徴です。
公共・民間で地球観測データの需要が拡大しており、災害監視やサプライチェーン可視化などの用途が広がっています。国内発のスペーステック銘柄の資金調達環境に追い風となる可能性があります。
暮らしのトピック:大阪など18地域に熱中症警戒アラート
本日、近畿から沖縄の18地域に熱中症警戒アラートが発表され、厳しい暑さへの警戒が呼びかけられています。
都心でもWBGTが午前時点で「厳重警戒」水準となりました。
こまめな水分・塩分補給、屋外活動の短縮、エアコンの適切な使用など、基本動作の徹底が重要です。台風11号の影響が残る先島諸島では雨風や高波にも注意が必要です。
海外ニュース
米7月CPI:想定線で「9月利下げ観測」が強まる
総合は前月比+0.2%、前年比+2.7%。コアは前年比+3.1%。ガソリンの下落が総合を抑えた一方、サービス価格の粘着性が残りました。
CPIを受けて主要3指数が記録更新。短期金利先物では9月利下げの織り込みが厚くなりました。
金利低下観測は円高圧力に傾きやすい一方、日本株にはリスクオン継続の追い風も。為替と株のどちらが主導するかが当面の焦点です。
ウクライナ東部:ロシア軍がドンバスで前進、首脳会談前に緊張
ロシア軍がドネツク州ドブロピッリャ周辺で数km規模の進出。ウクライナは予備兵力を投入して応戦しています。
米露首脳会談を控え、圧力を強める動きとの分析も。欧州側は不利な条件での停戦を警戒しています。
地政学の再燃は商品市況や安全資産選好を通じて揺さぶり要因。イベントヘッドラインに注意が必要です。
中国、カナダ産キャノーラに暫定関税(75.8%)を発表
中国商務省はカナダ産キャノーラに暫定反ダンピング関税を14日から適用。ICEの先物は発表を受けて一時6.5%下落しました。
EV関税を巡る対立の延長線上で、対加報復の色彩が濃い構図。代替として豪州産の恩恵観測もあるが、全量代替は困難とみられます。
食用油の国際価格や飼料コストに波及する可能性。値決めのタイミングと在庫水準次第で国内価格への影響度が変わります。
私たちの生活に起こること
短期の注目点を順に整理
米インフレは粘着性を残しつつも過度な加速ではなく、9月利下げ観測が優勢。金利・為替・株の連鎖をまず押さえましょう。
また、ドル円147円台後半~148円台への推移は家計の輸入物価にタイムラグを伴って影響します。旅行代やガソリン、食料の中でも輸入比率が高い品目は注視を。
企業物価の鈍化は先々の小売価格安定化にはプラス。ただしエネルギーや原材料の外的要因でぶれやすく、急な値下がりは期待しすぎないのが無難です。
きょうからできる備え
価格改定が頻繁な品目は買い方を工夫し、特に食用油・乳製品など国際市況の影響を受けやすいものは特売やまとめ買いの計画性を高めましょう。
為替や相場の一時的な振れに過度に反応せず、家計の余裕資金と必要資金を分けて考えることが安定につながります。
 ねくこ
ねくこ指標日程とイベント(米金利、地政学)に合わせてニュースをチェックしましょう。