【2025年11月6日】の経済・時事ニュースまとめ
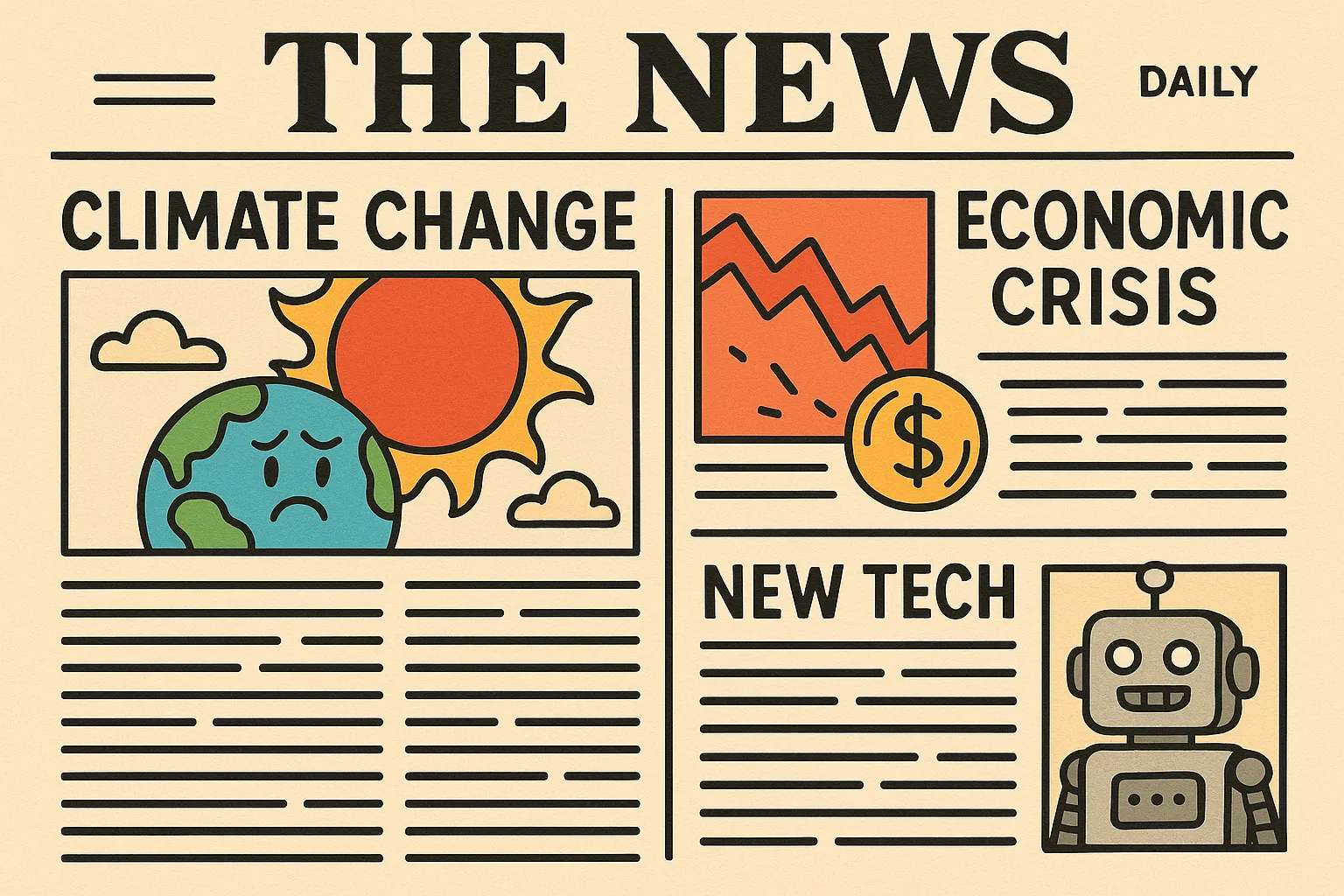
本日11月6日は、東京市場で日経平均が大幅反発し、米株主要3指数も前日に上昇して引けたこと、為替はドル円が153円台で推移していることが大きなトピックです。
英国では本日夜に英中銀の政策金利発表が予定され、中国は一部対米関税の停止を表明しました。
国内では外為法の改正方針、10月のサービス業PMI、9月の実質賃金が発表されています。
主要株価指数・為替レート(11月6日 15時時点)
| 指標 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 50,883.68 円 | +671.41(1.34%)円 |
| NYダウ | 47,311.00 ドル | +225.76(0.48%)ドル |
| S&P500 | 6,796.29 ポイント | +24.74(0.37%)ポイント |
| ドル円為替 | 153.75 円 | -0.33円 |
日経平均の変動要因
日経平均は大引けで50,883.68円と3日ぶりに反発し、ザラ場で上げ幅が一時1,000円超まで拡大しました。
前日の米国株上昇と、民間雇用やサービス業の底堅さを示す米経済指標を受けて、過度なAI関連の高値警戒が一服し、アジア株全体が反発基調となりました。
 ねくこ
ねくこ東京市場もその流れを引き継ぎ、主力株中心に買い戻しが優勢でした。
NYダウ/S&P500の変動要因
5米株は、ダウが47,311.00、S&P500が6,796.29、ナスダックが23,499.80で引け、いずれも反発しました。
ADP民間雇用の増加や企業決算の堅調さが投資家心理を支えました。
ハイテク高値警戒は残るものの、「健全な利益確定の範囲」との受け止めが広がり、幅広い銘柄に買いが戻りました。
 ねくこ
ねくこ米最高裁で争われた包括関税の合法性判断は、結論次第で企業コストやサプライチェーンに波及し得るテーマです。
中国の一部関税停止措置も同時に進むため、通商環境のニュースフローには引き続き注意が必要です。
ドル円の動き
ドル円は153.75円と、マルチマンス高圏からやや押し戻され前日比-0.33円でした。
米景気指標と国債利回りの反発を受けたドル高基調はいったん一服し、英中銀の政策判断待ちで様子見ムードが強まりました。
英中銀の結果や米長期金利の方向性が再びドル円のトレンドを左右します。
 ねくこ
ねくこ短期的には153〜155円台での上下を想定する声が多い印象です。
資産運用をしている人がこの局面で心掛けるべきこと
この局面の基本戦略
相場全体は外部要因への感応度が高い局面です。
大きく値動きした翌日は反動も出やすいため、時間分散や地域・資産の分散を機械的に続けることが、感情に流されない運用に有効です。
長期投資の基本
株式と債券、国内外の比率を「自分が睡眠を確保できるボラティリティ」に合わせて再点検し、急なリバランスではなく目標比率への漸進的調整にとどめるのが無難です。
為替が効く投信はヘッジの有無でリスク特性が異なるため、目論見書やファクトシートで確認しましょう。
短期の値動きへの向き合い方
AI関連の物色が激しい一方で、ニュース1本で方向が変わる場面もあります。
 ねくこ
ねくこ短期売買を行う場合は「損切り水準」「資金配分」「想定シナリオ」を事前に定義し、無理なレバレッジは避けるのが基本です。
制度・家計面のチェックポイント
つみたて中心の長期運用はNISAの枠組みを土台に、生活防衛資金と並走させるのが王道です。

老後資金づくりにはiDeCoの税制メリットも検討余地があります。

為替変動を積極的に取りにいくならFXの仕組みとコスト、ロスカット規則を先に理解することが欠かせません。

インフレ下では固定費の見直しが効きやすく、光熱費・通信費・保険料の契約条件やオプションの棚卸しが実質利回りを押し上げます。



※本節は一般的な情報提供であり、個別の投資助言ではありません。
最終判断はご自身の責任でお願いします。
国内ニュース
外為法(FEFTA)改正を2026年めどに検討
政府は外国投資審査の効率化と安全保障リスク対応の強化に向け、2019年の大幅改正以来となる見直しに着手しました。
IT分野の審査範囲をサイバー安全保障上重要な領域に絞り込む案や、間接取得や実質支配の抜け穴を塞ぐ案が議論されています。
目的は国家安全保障と投資の円滑化の両立で、審査の集約機能(米国のCFIUS類似)の創設も検討されています。
 ねくこ
ねくこ通常国会への法案提出が視野に入り、運用は2026年以降を想定するとみられます。
サービス業PMIは「53.1」で成長継続
10月のサービス業PMIは53.1と7カ月連続の拡大域を維持し、速報値52.4を上回りました。
新規受注は16カ月ぶりの低速化、コスト上昇圧力の再燃が示され、企業マインドは慎重化しています。
雇用は増加を続ける一方でペースは鈍化し、労働力不足や需要の弱さへの懸念が挙がりました。
 ねくこ
ねくこ家計の物価観の粘着性が、値上げと需要の綱引きを長引かせています。
9月の実質賃金は9カ月連続マイナス
実質賃金は前年比-1.4%とマイナスが続き、名目賃金の+1.9%を物価上昇が上回りました。
賃上げの定着度合いが2026年の金融政策に影響し得るとの見方が示されています。
 ねくこ
ねくこ春闘目標「5%以上」の賃上げ観測はあるものの、実質ベースの改善には時間を要する可能性があります。
消費者の実購買力の戻りが遅いと、小売や外食の価格戦略にも調整が入る局面です。
北日本でクマ被害、政府が自衛隊を派遣
今春以降のクマ被害拡大を受け、政府は秋田県などで自衛隊を投入し罠の設置や住民支援に当たっています。
人的被害は累計で死者12人、負傷者100人超に達しています。
対象地域では通学路や山林周辺の行動制限が継続中で、行政の防災情報の確認が推奨されています。
海外ニュース
米最高裁、包括関税の合法性に懐疑的な見解
米最高裁の口頭弁論では、1977年法に基づく広範な関税権限の是非が焦点となり、保守・リベラルの判事からも行政府の越権に対する問いかけが相次ぎました。
結論は世界のサプライチェーンと物価に波及し得るため、市場の関心は高いままです。
 ねくこ
ねくこ違憲判断が出れば関税体系の再設計が必要になり、企業の価格戦略や在庫政策に不確実性が生じます。
一方、他の法的根拠に切り替える可能性も示唆されています。
中国、一部対米関税を停止へ
中国は11月10日から一部の米国産農産物などへの追加関税を停止する一方、大半の10%賦課は維持し、米国産大豆への13%関税も残しました。
価格面の優位から、当面はブラジル産が主流との見方が強い状況です。
合意履行の一歩として歓迎される半面、実需の回復は関税体系と価格差の縮小が条件との見立てが主流です。
英中銀(BoE)、本日発表の金利判断は「際どい」情勢
市場は据え置きがメインシナリオながら、約3割の確率で25bpの利下げ観測も残ります。
インフレ鈍化や11月26日の予算で想定される増税観測が、決定を難しくしています。
今回からMPCメンバー見解の要約が新たに公表される予定で、先行きガイダンスの読み解きが一段と重要になります。
ドイツの鉱工業生産、9月は前月比+1.3%も予想未達
ドイツの鉱工業生産は四半期ベースでは▲3%と弱さが残り、欧州景気の回復テンポはなお鈍い状況です。
独政権はインフラ投資・減税・電力コスト軽減などの施策を打ち出しています。
私たちの生活に起こること
賃金の実質目減りが続く中でも、値上げの波は続いています。

家計は「必要な支出の優先順位付け」と「価格差の大きい分野の乗り換え(通信・電力・サブスク)」で実質可処分所得を守りましょう。
資産運用は短期の材料に過度に反応せず、積立や分散といった「続けられる仕組み」を守ることが、結果的に最大の防御になります。
 ねくこ
ねくこ外部要因としては、米通商政策や英金利の決定が物価や為替に波及し得るため、生活コストに関わる価格(ガソリン、食品、電気代)の動きにアンテナを立てておくとよいでしょう。
本稿は一般的な情報提供であり、特定銘柄や商品への投資助言ではありません。
最終判断は必ずご自身の責任でお願いいたします。











