団信(団体信用生命保険)とは?万が一に備える、金利タイプ別の住宅ローン選び方完全ガイド

最後まで読めばわかること
- 団信(団体信用生命保険)の基本と仕組み
- 一般団信・特約付き団信・ワイド団信の違いと、加入できないときの対策
- 変動金利・固定金利・フラット35など、金利タイプ別の「団信の考え方」とローン選びの順番
マイホームを購入する際に利用する住宅ローンでは、返済者に万が一のことがあった場合でも安心できるように、団体信用生命保険(団信)への加入が求められることが一般的です。
団信にはさまざまな種類があり、保障範囲や保険料のかけ方(金利に含まれているのか・上乗せなのか)が商品によって異なります。
また、がん団信や8大疾病保障付き団信のように、手厚い保障と引き換えに金利の上乗せが大きくなるケースや、そもそも持病や既往症があって一般的な団信への加入が難しいケースなど事情もさまざまです。
そのため、「結局、自分はどの団信にできる/すべきか迷う!わからない!」という人が後を絶ちません。
 MIYABI
MIYABIそこで本記事では、団信の基本・種類・健康状態ごとの選択肢・金利タイプとの相性・ネット銀行ごとの特徴を、購入前の方や初心者の方にも分かるように順番に整理していきます。
読み終わるころには、「自分はまず何から決めれば良いか」「どの金融機関を候補にすべきか」までイメージできるようになるのがゴールです。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品を推奨したり、お客さま個人の状況に応じた助言を行うものではありません。掲載している金融機関や商品は一例であり、すべての選択肢を網羅するものではありません。実際の金利・保障内容・手数料等は日々変動しますので、必ず各金融機関の公式サイトや商品説明書・重要事項説明書、窓口で最新情報をご確認ください(記載の情報は原則として2025年12月時点の公表内容をもとに作成しています)。最終的なご判断はご自身の責任で行ってください。
団信とは?基本の仕組みや種類を解説
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローン利用者にとって非常に重要な保険制度です。
万が一、返済者が死亡や所定の高度障害状態になった場合に保険金が支払われ、ローン残高の全部または一部が弁済されるのが大きな特徴です(具体的な保障内容や免責条件は商品によって異なります)。
 MIYABI
MIYABI結果として、返済者の家族に大きな住宅ローンを残さずに済むため、「もしもの時のお守り」としての安心感があります。
選び方のポイントとしては、ご自身の、
- 健康状態や将来のリスク
- 保険料(または金利上乗せ)
とのバランスを、総合的に考慮することが重要です。
団信とは?なぜ住宅ローンとセットになっている?
団体信用生命保険(団信)の定義
団信とは、住宅ローンの返済者が死亡または所定の高度障害となった場合に、保険会社がローン残高の全部または一部を支払う保険です(支払事由や支払割合は商品によって異なります)。
通常は、住宅ローン契約時に同時加入するケースが多く、多くの民間住宅ローンでは加入が事実上の必須条件になっています。
一方、フラット35では団信への加入は「任意」となっており、健康状態などの理由で加入できなくてもローン自体は利用できます。
団信が住宅ローンとセットになっている理由
団信が住宅ローンとセットになっている一番の理由は、住宅ローンが長期間の借入であり、借主に万が一のことがあったときの貸し倒れ(返済不能)リスクを抑えるためです。
銀行や金融機関は、返済者に万が一のことがあっても、団信からの保険金でローンが完済されることで、返済不能のリスクをコントロールしやすくなる仕組みになっています。
 MIYABI
MIYABI借りる側にとっても、万が一のときに「家族に住宅ローンだけが残る」という事態を防げるので、結果的に家族の安心につながります。
「団信」は借主が万が一の場合にローン残高が返済される仕組み
- 保険金の支払い請求
返済者が死亡または所定の高度障害状態になった際、遺族などが金融機関・保険会社に保険金を請求します。 - 保険会社による支払い
保険会社が審査を行い、支払い条件を満たしていれば、ローン残高に相当する金額の全部または一部を金融機関へ直接支払います。 - 住宅ローン完済
保険金が金融機関に支払われることで、住宅ローンは原則として完済扱いとなり、住宅ローンの返済を続ける必要がなくなるケースが一般的です(連帯債務や保証の有無など、契約内容によっては異なる場合があります)。
※フラット35(買取型)の団信(新機構団信)は任意加入であり、健康状態などの理由で加入できなくてもローン自体は利用できます。また、新機構団信制度に加入しない(できない)場合の借入金利は、新機構団信付き【フラット35】の借入金利から年0.2%差し引いた水準となるルールがあります(住宅金融支援機構公式FAQ参照)。制度や金利水準は見直される可能性があるため、最新情報は必ず公式サイトで確認しましょう。
団信には主に2タイプある
団信には、主に「一般団信」と「特約付き団信」の2タイプがあります。
一般団信は死亡・高度障害時のみを対象とした基本的な保障ですが、特約付き団信はがん・心筋梗塞・脳卒中などの病気やケガのリスクをより幅広くカバーするタイプです。
 MIYABI
MIYABIもし健康上の理由などで通常の団信に加入できない、もしくは団信が利用しにくいと判断された場合でも、ワイド団信やフラット35、別途生命保険などの代替策を組み合わせることでリスクを軽減できます。
以下に代表的な選択肢を整理します。
健康状態に問題がない場合:一般団信・特約付き団信
- 特徴:死亡・高度障害時にローン残高を保障。
- 注意点:がん団信・8大疾病などの特約を追加する場合は金利上乗せが発生するのが一般的。
持病や既往症がある場合:ワイド団信・引受緩和型団信
- 特徴:高血圧や糖尿病など軽度の持病があっても、一般団信より加入できる可能性を広げる目的で審査条件が一部緩和された団信。
- 注意点:金利上乗せ率が比較的高めになるケースが多く、代表的なネット銀行では年+0.2〜+0.3%程度の上乗せ例もあります※。
※ 実際の上乗せ幅は金融機関や商品タイプ、募集時期によって異なります。必ず各社の最新条件を確認しましょう。
一般団信・ワイド団信に加入不可:別途生命保険やフラット35で代替
- 特徴:
- 住宅ローン残高分をカバーする生命保険(収入保障保険・定期保険など)を別途契約する。
- 団信任意のフラット35を利用しつつ、自前の保険や貯蓄でリスクを分散する。
- 注意点:保険金は自動でローンに充当されないため、受取人の使い方次第では残債が残るリスクあり。
 MIYABI
MIYABIワイド団信は持病がある方にとって心強い選択肢ですが、金利上乗せの負担も必ずセットです。
総支払額がどのくらい増えるか、必ずシミュレーションしてから選ぶようにしましょう。
※別契約の生命保険は住宅ローンに自動で充当されないため、「保険金が出たのに住宅ローンが残る」可能性もあります。保険金の使い方や受取人をあらかじめ家族で話し合っておきましょう。
どれを選べば良い? 選定基準のポイント
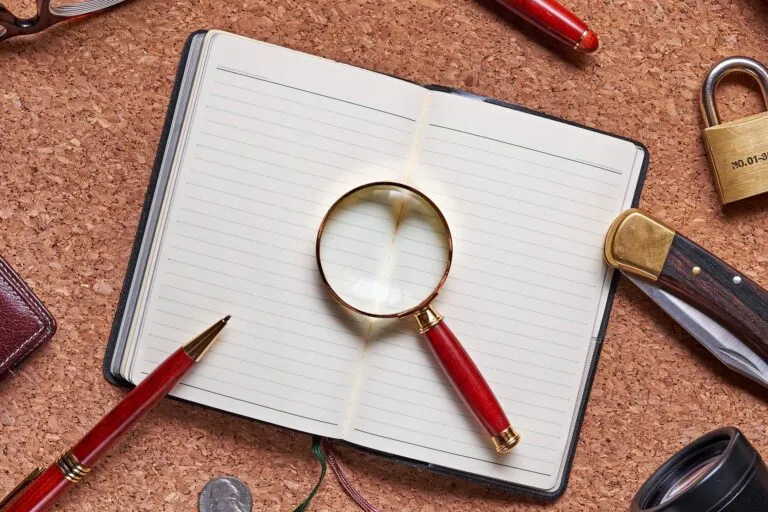
 MIYABI
MIYABI団信の選択は、単純に「保障が広いから良い」という話ではなく、保障内容 × 金利(保険料) × ご家庭の状況をセットで見て判断する必要があります。
迷ったときは、まず次の3つから整理してみましょう。
1. 自身の健康リスクと加入条件
- 健康診断の結果・既往症・服薬状況などから、一般団信に通りそうかを確認。
- 不安があれば、事前審査や「告知内容の相談」ができるかを金融機関や専門家に確認。
2. 家族構成に応じた「どこまで守りたいか」
- 小さなお子さんがいる、片働き家庭など、万が一のときの家計インパクトをイメージ。
- 教育費・老後資金など、「住宅以外に必要なお金」とのバランスも考える。
- 「死亡だけ守れれば良いのか」「働けなくなったときも守りたいのか」を家族で話し合う。
3. 保障内容と金利上乗せのバランス
- 「がん・3大疾病まで広げるのか」「全疾病型にするのか」など、どこまでリスクをカバーするかを決める。
- 上乗せ金利が年0.1%増えるだけでも、35年返済では総返済額が数十万〜百数十万円単位で変わるケースもある。
- 「今の安心」と「将来の支出」を天秤にかけて、納得できるラインを探す。
あとは、貸す側にとっては、
- 健康状態や既往症によっては、団信の加入審査が厳しくなる可能性がある。
- 扶養家族が多い場合は、返済者に万一があったときの家族の生活費も考慮する必要がある。
といった審査目線もあります。
 MIYABI
MIYABI最終的には、各保険商品の条件 × 自分たちの家計・ライフプラン × 金利タイプをしっかり照らし合わせて決めることが大切です。
ご自身の家族の状況に合わせ、具体的には以下のような団信プラン例が考えられます。
団信プラン例
| 健康リスクが高い加入者向け | 小さい子どもがいる家庭向け | |
|---|---|---|
| プランタイプ | ワイド団信+必要最低限の特約 | 3大疾病保障付き団信 or 全疾病保障付き団信 |
| 特徴 | 既往症などがあっても加入できる可能性を広げる目的で、審査条件が一般団信より一部緩和されている。 | 死亡・高度障害に加え、がんや脳卒中など長期療養リスクもカバー。 |
| メリット | 「団信に入れないから住宅ローン自体をあきらめる」という事態を避けやすい。 | 万一の際に家族全体を支える大きな保障を確保しやすい。 |
| 注意点 | 金利上乗せが大きくなりやすいため、借入額・返済期間とセットで負担額を確認する必要あり。 | 保険料・金利上乗せ分が高めになりやすいので、ライフプランに応じた見直しも前提にする。 |
 MIYABI
MIYABI団信は住宅ローン選びの「脇役」のように見えて、じつは総返済額・安心感・通せるローンの範囲に大きく関わる重要ポイントです。
ここまでの考え方を踏まえたうえで、次に「団信に入れない・通りにくい場合の対策」を見ていきましょう。
以下では、団信の種類や加入できない場合の対策について、もう少し具体的に解説します。
団信に加入できない場合、どうすればいい?
多くの方が不安に感じるのが、
という点です。
特約付き団信の種類と特徴
まず、健康状態に問題がなく、「保障を厚くしたい」というニーズの場合は、一般団信ではなく特約付き団信を選ぶ形になります。
ただし、特約付き団信は手厚い保障を受けられる一方で、金利の上乗せ幅が大きくなるなどコスト面の注意点もあります。
 MIYABI
MIYABIここで紹介する上乗せ幅はあくまで2025年時点の代表的な水準をもとにしたイメージであり、金融機関や商品改定によって変わる可能性があります。
| 特約付き団信の 種類(イメージ) | 保障内容のイメージ | 金利上乗せの一例 | 向いている人の例 |
|---|---|---|---|
| がん団信 | 所定のがんと診断された場合に、住宅ローン残高が全額または一部免除。 | +0.05%〜+0.2%程度の上乗せ例 例:auじぶん銀行の「がん100%保障団信」は年+0.05%(2025年時点の公表情報)。他行では年+0.1〜+0.2%程度とするケースもあります。 | 家族にがん罹患歴がある人、完済時年齢が高めの人、がんリスクが特に心配な人。 |
| 3大疾病・8大疾病 保障付き団信 | がん・急性心筋梗塞・脳卒中など、重い病気で長期間働けない状態になった場合に残高がゼロ、または返済を肩代わり。 | +0.2%〜+0.35%程度の上乗せ例 金融機関やプランにより大きく異なります。 | 幅広い重病リスクに備えたい人、子どもが小さく収入源が一つに偏っている家庭。 |
| 全疾病保障付き団信 | うつ病など一部を除き、多くの病気やケガで就業不能になった場合に、一定期間の返済を補償。商品によっては条件を満たすと残高がゼロになるタイプも。 | +0.3%〜+0.5%程度の上乗せ例 上乗せ幅は商品内容や年齢条件などにより変わります。 | 「働けなくなるリスク」に重きを置きたい人、自営業・フリーランスなど収入の波が大きい人。 |
※ 2025年12月時点に確認できた代表的ネット銀行数社の公表情報をもとにした概算イメージです。実際の上乗せ幅は金融機関・商品・募集時期によって異なります。
 MIYABI
MIYABIここでは有名な「がん団信」「3大疾病・8大疾病保障付き団信」を中心に紹介しましたが、商品名や細かな条件は各社によって違います。
気になるプランがあれば、必ずパンフレットや「重要事項説明書」で細かい条件を確認しましょう。
がん団信
がん団信は、所定の要件(診断確定・待期期間・対象となるがんの種類など)を満たした場合に、住宅ローン残高が全額または一部免除されるタイプを指します。
がん治療には高額な医療費や長期の療養が必要となるケースも多いため、住宅ローンの心配が減ることで、治療や生活費にお金を回しやすくなるメリットがあります。
8大疾病・3大疾病保障付き団信
8大疾病保障付き団信は、がん・脳卒中・心筋梗塞だけでなく、その他の難病・重篤な疾患(例:高血圧性疾患や慢性腎不全など)も保障対象に含めるプランが多いです。
8大疾病保障付き団信:がん・心筋梗塞・脳卒中などに加え、糖尿病や慢性腎不全など生活習慣病も対象となることが多い
 MIYABI
MIYABI重い病気で長期間働けない場合でも、ローン返済がカバーされる可能性が高まり、「病気になったら家を手放さないといけないのか・・・」という不安を減らしてくれます。
団信に加入できない場合の対策
団信は生命保険の一種であるため、必ず健康状態に関する審査(告知)があります。
 MIYABI
MIYABI持病や既往症がある場合、一般団信の審査に通らない可能性もあります。
そのときに「もう家は買えない」とあきらめる前に、取れる選択肢を整理しておきましょう。
加入審査が厳しい場合の事前対策(他の金融機関を検討するなど)
団信の審査基準は、金融機関や引受保険会社によって少しずつ異なります。
もし一社で加入が難しいと判断された場合、別の銀行の住宅ローンや、フラット35など異なるスキームを使ったローンも候補に入れてみましょう。
具体的には、以下のような手順が取りやすいです。
- ① 複数の金融機関に事前相談・仮審査
健康状態も含めて相談し、「一般団信で通りそうか」「ワイド団信になるか」の感触をつかむ。 - ② フラット35を候補に入れる
フラット35は団信の加入が任意のため、団信に入れない方でも利用できる可能性があります。 - ③ 専門家に相談
ファイナンシャルプランナーや住宅ローン専門の相談窓口に相談し、「団信+他の生命保険」を組み合わせたプランを一緒に考えてもらう。
持病や既往症がある場合:ワイド団信や引受緩和型団信の活用
健康状態に不安がある方でも、加入できる可能性を広げるよう設計されたのがワイド団信や引受緩和型団信です。
通常の団信より金利や保険料が割高(上乗せ率の目安:年+0.2〜+0.3%程度の例)になる場合が多いですが、その分、健康状態に関するハードルが一般団信より下がることがあります。
一方で、一般団信よりも保障範囲が絞られている場合や、完済時年齢などの条件が厳しめになっている場合もあるので注意が必要です。
ワイド団信の特徴
- 一般団信に通りにくい持病のある方でも、商品や条件によっては加入できる余地が広がる場合がある。
- 代表的な銀行では、金利上乗せを年+0.2〜+0.3%前後とするケースが多い(2025年時点で確認できた一例)。
- 完済時年齢に制限があるケースが多いため、借入期間の設定にも注意が必要。
金利タイプ別で考える「団信との付き合い方」

ここからは、変動金利・固定金利・フラット35などの金利タイプと、団信の選び方の相性を整理します。
 MIYABI
MIYABIいきなり「どの銀行が一番お得?」と考えるよりも、①金利タイプ → ②必要な団信の厚さ → ③具体的な銀行の順番で考えた方が迷いにくくなります。
変動金利 × 団信:低金利と「上乗せ」のバランスがポイント
変動金利は、当初の金利がもっとも低くなりやすい金利タイプです。
そのかわり、将来の金利上昇リスクを自分で負うことになります。
ここにがん団信や3大疾病団信を上乗せすると、低金利のメリットを一部削ってまで、追加の保障を取るかどうかがポイントになります。
向いているパターン
- 返済期間が長い(30〜35年)
- 子どもが小さく、収入の柱が1本に近い
- ある程度の金利上昇を許容しつつ、がん/3大疾病にも備えたい
避けた方が良いかもしれないパターン
- 将来の金利上昇が不安で、固定金利を強く希望している
- すでに別のがん保険・医療保険で十分にカバーできている
固定金利・10年固定 × 団信:安心重視派の組み合わせ
10年固定や全期間固定(フラット35含む)を選ぶ場合は、「金利の変動リスク」ではなく「ライフイベントのリスク」をどう守るかが団信選びのポイントです。
固定金利は変動金利より高めになりやすいため、団信の上乗せをどこまで許容できるかはよりシビアに見る必要があります。
一方で、毎月の返済額が変わりにくいため、病気や収入減があったときの資金計画を立てやすいメリットがあります。
フラット35 × 団信:団信任意だからこその「保険の組み立て」がカギ
フラット35は、全期間固定金利でありながら、団信は任意加入という特徴があります。
メリット
- 団信に入れない人でも住宅ローンを利用できる可能性がある。
- 団信に入らない場合、フラット35の金利が新機構団信付きの金利から年0.2%引き下げられる仕組みになっている(2025年12月時点)。
注意点
- 団信に入らない場合、死亡・高度障害になってもローンがそのまま残るため、別の生命保険や貯蓄で備える必要がある。
- 「団信なしで安く借りられるから」といって、家計の全体設計をせずに選ぶのは危険。
 MIYABI
MIYABIフラット35を検討している方は、「団信+別の生命保険」「団信なし+手厚い生命保険」など、保険全体をどう設計するかまでセットで考えると失敗しにくくなります。
団信に加入すると、具体的にどのくらい負担が増える?
団信の保険料は、多くの場合、住宅ローンの金利に含まれている(=一般団信は追加コストなし)か、特約分が「金利上乗せ」という形で加算されます。
 MIYABI
MIYABIどちらの方式でも、「0.1%の金利差」が長期の返済では意外と大きな差になります。
後ほど早見表も載せているので、自分の借入希望額とざっくり照らし合わせてみてください。
団信プランには「金利込み型」と「上乗せ型」がある
金利込み型(一般団信が金利に含まれる方式)
金利込み型は、一般団信(死亡・高度障害)の保険料が住宅ローンの金利にあらかじめ含まれている方式です。
表面上は「団信無料」と書かれていても、実際には金利の中に保険料分が含まれているケースがほとんどです。
金利上乗せ型(特約付き団信の場合など)
特約付き団信(がん団信や3大疾病・全疾病保障など)を選ぶ場合、一般団信込みの金利に対して年+0.05〜0.3%程度が上乗せされるケースが多く見られます(2025年時点に確認できた代表的なネット銀行の水準を参考)。
同じ金融機関・同じ金利タイプでも、どの団信プランを選ぶかで実質的な返済額が大きく変わることになります。
 MIYABI
MIYABI特に、特約付き団信については、上乗せ金利の幅(+0.05〜+0.3%程度の例)と、自分がどこまで保障を欲しいかを冷静に比べることが大切です。
金利差0.1%〜0.3%で総返済額はいくら変わる?早見イメージ
不動産情報サイト「ダイヤモンド不動産研究所」が、借入期間35年・元利均等返済・ボーナス返済なし・金利0.4〜0.7%という前提で試算した例では、金利差0.1〜0.3%で以下のような差が出ると紹介されています。
| 借入額 | 金利差+0.1%の増加額 (例:0.4%→0.5%) | 金利差+0.2%の増加額 (例:0.4%→0.6%) | 金利差+0.3%の増加額 (例:0.4%→0.7%) |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 約55万円 | 約110万円 | 約170万円 |
| 5,000万円 | 約90万円 | 約190万円 | 約280万円 |
| 8,000万円 | 約150万円 | 約300万円 | 約450万円 |
※実際の金利水準・返済期間・ボーナス併用の有無などにより数字は変わります。あくまで「0.1%の差でも35年ではこのくらい違う」というイメージとしてご覧ください。
団信負担を抑えるための工夫

 MIYABI
MIYABI「安心は欲しいけれど、なるべく支払いは増やしたくない…」という方は多いはず。
ここからは、団信の負担を抑えつつ、最低限の安心を確保するための工夫を紹介します。
① 他の金融機関や商品を比較検討する

問題の本質は、団信に入るかどうかではなく、必要な団信に入りつつ、どのくらい支払いを抑えられるかです。
団信の負担を軽減する第一歩は、複数の金融機関・複数の団信プランを徹底的に比較することです。
 MIYABI
MIYABI上記の関連記事では、代表的なネット銀行の基本金利+団信上乗せまでまとめています。
「この金利・この保障なら、うちの家計に合うかも?」という候補をまず2〜3社に絞ってみてください。
② 夫婦連帯債務・ペアローンの活用方法
- 連帯債務:夫婦共同で同じ借入金に対して返済義務を負う(1本のローンに2人とも責任を負う)
- ペアローン:夫婦がそれぞれ別のローン契約を組む方式(団信も別々に加入)
住宅購入において、返済の負担を二人で分担できる夫婦連帯債務やペアローンも有力な選択肢です。
これにより、団信の必要額が分散され、1人あたりの保障を少し抑える選択がしやすくなる場合もあります。
具体的なメリットと注意点は以下の通りです。
メリット
- 負担分散:住宅ローンの返済額を2人で分担することで、1人あたりの返済額・団信負担が軽くなる。
- 借入可能額の増加:2人の収入を合算することで、希望エリアの物件を選びやすくなる。
- ライフプランの柔軟性:将来どちらかが育児・転職などで収入が減っても、もう一方の収入でカバーしやすい。
注意点
- 連帯責任の重さ:どちらかが返済不能になっても、もう一方が全額返済義務を負う可能性がある。
- 離婚・相続時の手続きが複雑:名義変更や持分調整などが必要になり、手続きが煩雑になる可能性がある。
- 団信の設計がやや難しい:連帯債務・ペアローン・連生団信の違いを十分理解しておかないと、「どのパターンで誰がどのくらい守られるか」を勘違いしやすい。
 MIYABI
MIYABI夫婦でローンを組む場合は、「連帯債務+ペアローン+連生団信」の組み合わせまで含めて検討すると、コスパと安心のバランスが取りやすくなります。
ただし、それぞれの仕組みはやや複雑なので、専門家や金融機関の担当者と図を書きながら整理してもらうのがおすすめです。

また、夫婦でローンを組む場合は、夫婦連帯債務やペアローンのほかに、連生団信(夫婦連生タイプ)の有無や追加コスト、残債弁済パターンも選択肢として検討できます。
 MIYABI
MIYABI金融機関によっては金利上乗せや条件付きになることもあり、ペアローンでは使えない場合もあります。
「夫婦のどちらに・どのタイミングで何があったら、ローンがどうなるか」を必ず図示して確認してから契約するのが安心です。
③ 保障内容を「必要最低限」にする選択肢
特約付き団信は保障が増えるほど金利上乗せも増える傾向があります。
既に加入している生命保険・医療保険や、ご自身の健康状態を踏まえて、「住宅ローンのためにどこまで追加で保障が必要か」を一度立ち止まって整理するのも有効です。
具体的には・・・
- 一般団信+既存のがん保険・医療保険でカバー:がんや入院のリスクは既存の保険で十分という場合。
- 「がん団信」だけを付け、他は外部保険で調整:万一のときにローンだけは確実にゼロにし、細かい医療費などは医療保険でカバーする方法。
| 選択肢 | 特徴 | 主なメリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 基本保障プラン (一般団信のみ) | 死亡・高度障害に限定したシンプルな保障。 | 保険料(上乗せ金利)を抑えながら、最低限の安心を確保できる。 | がん・長期就業不能などは、別途の保険や貯蓄で備える必要がある。 |
| 必要な特約だけを絞って付けるプラン | 「がんだけ」「3大疾病だけ」など、本当に必要な特約に絞る。 | 過不足のない保障設計がしやすく、無駄な上乗せを減らせる。 | 必要なリスクを見落とすと、いざという時にカバー不足になる可能性がある。 |
 MIYABI
MIYABI保険は一度に全部を完璧にしようとすると負担が重くなりがちです。
今のライフステージで絶対に守りたいところだけを団信で押さえ、細かい部分は別の保険や貯蓄で調整するという考え方も、無理なく続けるためには大切です。
ここまでで、団信の仕組み・種類・金利タイプとの関係・負担を抑える工夫を整理してきました。
ここからは、実際にどの金融機関のどのプランを候補にすべきかを具体的に見ていきます。
団信の特徴を踏まえた住宅ローンの候補例を紹介
| 変動金利 | 固定金利 (10年) | フラット35 | 返済方法 | 5年ルール 125%ルール | 審査日数 | 事務手数料 | 一部繰上げ返済手数料 | 金利変更手数料 | つなぎ融資 | オプション | 公式サイト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
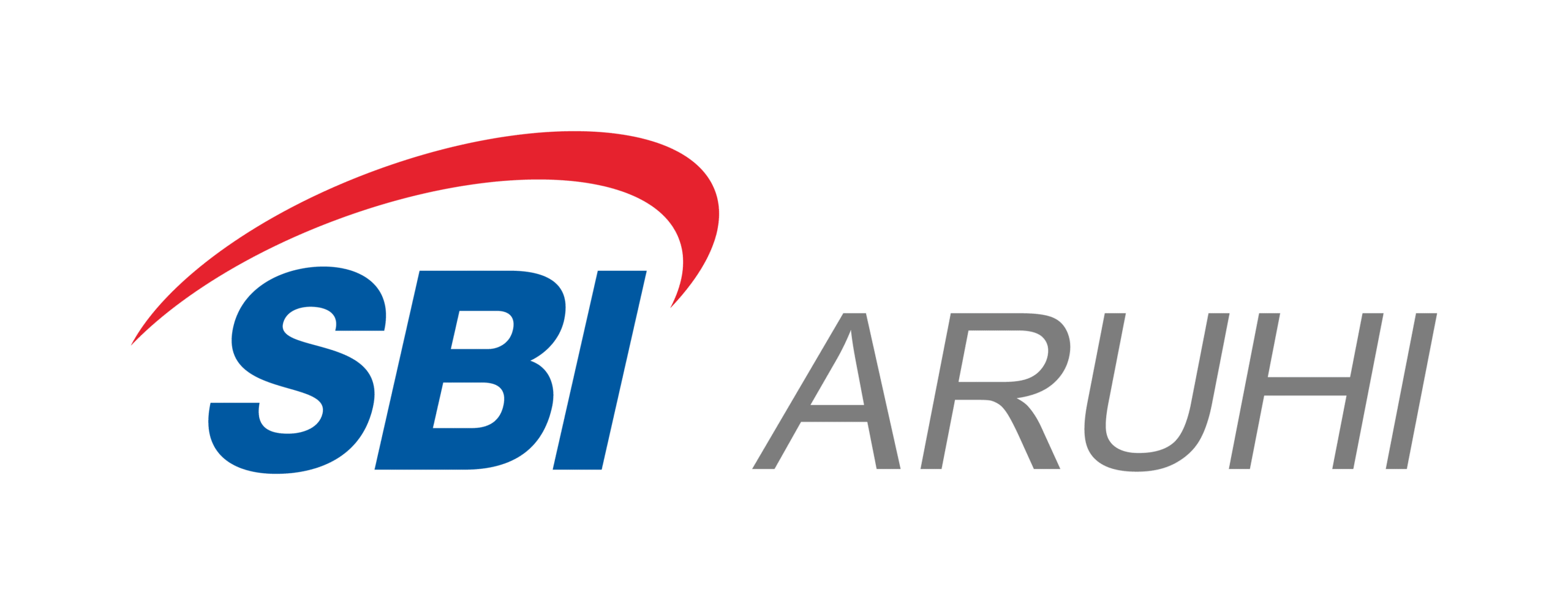 SBIアルヒ SBIアルヒ | 年1.050% ~ (半年型) | 年2.950% ~ | スーパーフラット:年1.820%~ フラット35:年1.580%(15年~20年)/年1.970%(21年~35年) | 元利均等返済/元金均等返済方式 | 記載なし | 事前審査が最短1営業日※ 本審査が最短3営業日※ | 借入金額×2.2%+消費税 ※最低事務手数料220,000円 最新の貸付条件はこちら | WEB受付は無料 電話受付は有料 | 金利固定化手数料5,500円(税込) | あり SBIアルヒフラットつなぎ | SBIアルヒ 暮らしのサービス 約40種類の優待特典 | 詳細を見る |
 PayPay銀行 PayPay銀行 | 年0.63% (新規・借換いずれも/全期間引下型) | 年1.84% | 取り扱いなし | 元利均等返済 | 取り扱いなし | 事前審査(当日~2営業日) 本審査(書類提出から3~10営業日) | 借入金額×2.20% | WEB受付は無料 電話受付は有料 | 手数料無料 | 取り扱いなし | ー | 詳細を見る |
 住信SBI銀行 住信SBI銀行 | 年0.698%~ (自己資金20%以上) 年0.948%~ (自己資金20%未満) | 年1.999%~ (自己資金20%以上) | フラット35(買取型):年1.550%~ フラット35(保障型): 当初5年間:年0.510%~ 6年目以降:年1.510%~ | 元本均等返済/元利均等返済 | あり | 仮査定なら最短当日 本審査1週間〜10日 | 借入金額×2.2%(税込) | 無料 | 手数料無料 | 取り扱いなし 土地先行プランあり | ー | 詳細を見る |
 SBI新生銀行 SBI新生銀行 | 年0.590%~ (自己資金10%以上) | 年2.00% | 取り扱いなし | 元利均等返済 | 取り扱いなし | 申し込み~借入:約1ヶ月半 | 借入金額×2.2% | 無料 | 固定金利選択手数料:5,500円 | あり | ー | 詳細を見る |
 楽天銀行 楽天銀行 | 年1.004%~年1.655% 住宅ローン(金利選択型) 借入金利「基準金利 − 金利引下げ幅」 | 年2.605%前後~ | 年1.870% (団信あり) | 元本均等返済/元利均等返済 | あり | 最短26日※フラット35は最短35日程度 | 事務手数料:一律33万円 ※フラット35は融資額×1.1% | 無料 | 手数料無料 | あり | 住宅ローン会員ランク特典 等 | 詳細を見る |
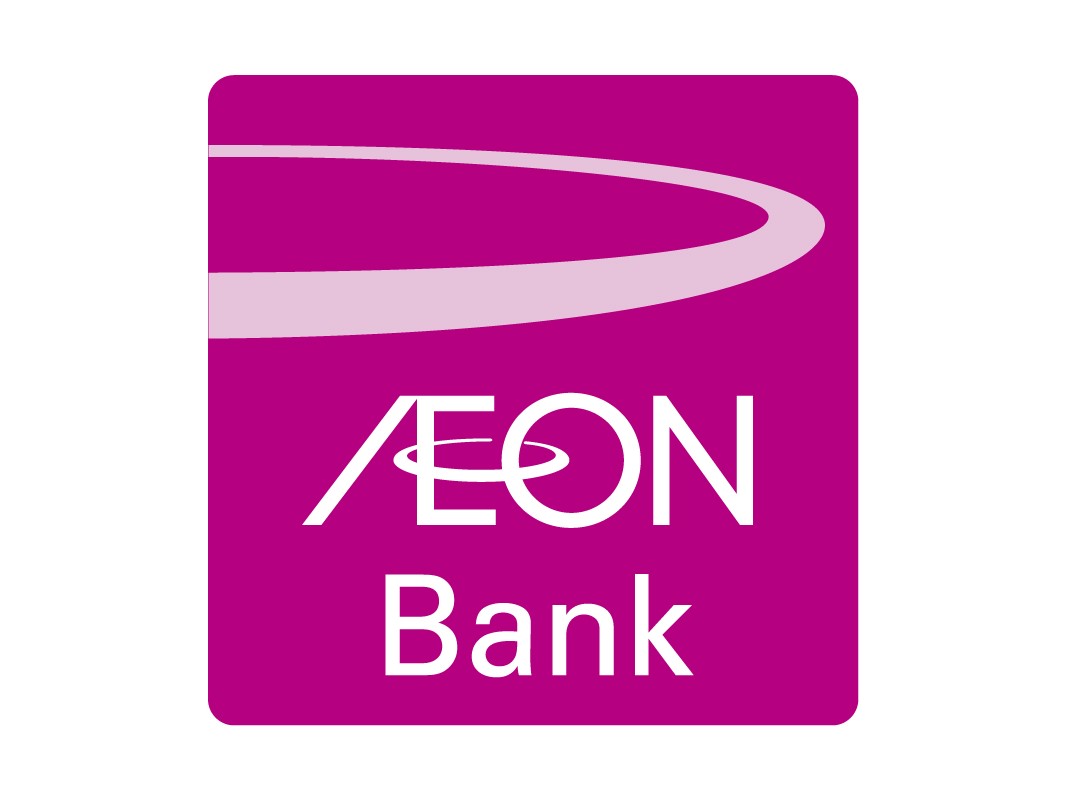 イオン銀行 イオン銀行 | 年0.78%~ (自己資金20%以上) | 年1.92%~ | 年1.89% | 元利均等返済 | あり | 事前審査最短翌日 正式審査1〜2週間 | <定率型> 借入金額×2.20%(税込) 最低220,000円 <定額型> 110,000円(税込) 定率型より年0.2%高 | 無料 | 手数料無料 | あり | イオングループ特典 等 | 詳細を見る |
 auじぶん銀行 auじぶん銀行 | 0.834%(LTV80%以下)/0.879%(80%超・借換) | 年1.30% | 取り扱いなし | 元本均等返済/元利均等返済 | あり | 仮審査 当日~3営業日 本審査 3~10営業日 | 借入金額×2.20%(税込) | 無料 | 手数料無料 | 取り扱いなし | 住宅ローン金利優遇割 | 詳細を見る |
※ 金利は毎月見直されます。多くの民間ローンと【フラット35】は『実行時金利』が適用されます(機構解説参照)。審査結果・融資率・団信プラン・優遇適用可否により実際の金利は異なります。
※ 審査・融資までの最短日数は物件・書類・審査状況等で前後します。
※スーパーフラット5では、就業不能保険 スタンダードにご加入いただくことが条件となります。就業不能保険 スタンダードの詳細はこちら(https://www.sbiaruhi.co.jp/product/option_insurance/syugyofunou_standard/)をご確認ください。
「自分の場合、結局どの住宅ローンが候補になりそうか?」という疑問を持った方に向けて、価値観・健康状態・重視ポイント別に、代表的なネット銀行の団信プランをいくつかの例として整理しました。
※本セクションは一般的な情報提供として、2025年12月時点の公表情報をもとに代表的な商品例を紹介しています。実際の金利や上乗せ幅、取扱条件は変更される場合があります。また、どの住宅ローン・団信が適しているかは、年齢・健康状態・勤務先・家計状況・他の保険加入状況・各社の審査結果などによって変わります。必ず各社公式サイトや商品説明書・重要事項説明書、窓口で最新情報をご確認のうえ、最終的な判断はご自身の責任で行ってください。
※以下の「こんな人に向きやすい一般的な傾向」は、あくまで一般的なイメージです。実際の適合度は人それぞれ異なりますので、必ず複数社の条件を比較し、必要に応じて専門家にも相談しながら検討してください。
① 保障をしっかり重視する場合➡住信SBIネット銀行(スゴ団信・3大疾病プラン)

特徴: 「スゴ団信」は死亡・高度障害+3大疾病+全疾病保障までカバーする、ネット銀行の中でも手厚い団信です。50歳以下なら、3大疾病50%保障+全疾病保障が上乗せ金利なし(基本付帯)で利用可能(2025年12月時点)。3大疾病100%プランにすると、年齢に応じて年+0.2〜0.4%程度の上乗せ金利で、がん・心筋梗塞・脳卒中リスクまでしっかりカバーできる。ワイド団信は上乗せ金利+0.3%で利用可能(健康状態に不安がある方向け。実際の可否は審査によります)。
こんな人に向きやすい一般的な傾向:
- 50歳以下で、「金利も保障もどちらも重視したい」方。
- がん・3大疾病・就業不能リスクまで一気にカバーしておきたい方。
- 持病があるが、まずは一般団信でチャレンジしたい方(難しい場合はワイド団信を含めて相談したい)。
\仮審査を申し込む!/
② 金利とがん保障のバランスを重視➡PayPay銀行(がん100%保障団信)

特徴: 「がん100%保障団信」は、がんと診断された場合に住宅ローン残高が全額0円になるタイプ(所定の条件あり)。 上乗せ金利は年+0.15%(がん50%保障団信は+0.05%)と、ネット銀行の中では比較的抑えめの水準(2025年12月時点)。 変動金利も、キャンペーン適用後の条件で年0.5〜0.6%台となっていた時期もあり、「低金利+がん100%保障」のバランスが良い候補の一つといえます(実際の金利は申込条件や時期により変動します)。
こんな人に向きやすい一般的な傾向:
- 比較的若く、健康リスクは低めだが、がんだけは手厚く備えておきたい方。
- 全疾病保障までは不要だが、がんでローンが残るのは避けたい方。
- 低金利も重視しつつ、がんリスクにコスパ良く備えたい方。

\仮審査を申し込む!/
※ 審査結果によりご希望に添えない場合があります。金利は実行時金利が適用されます。最新の適用条件は公式情報をご確認ください。
③ 上乗せ金利なしで全疾病保障を重視➡SBIアルヒ(住宅ローン【SBI信用保証】)

特徴: SBIアルヒの「住宅ローン【SBI信用保証】」では、全疾病付団信が基本付帯となっており、加入できない場合でも適用金利は変わらないと明記されています(2025年12月時点)。 死亡・高度障害・がんを含むすべての病気やケガ(一定の例外あり)に対して、就業不能時の返済をカバーする仕組み。 フラット35も扱っており、「固定金利で安心+団信もしっかり」を重視する人と相性が良い。
こんな人に向きやすい一般的な傾向:
- 上乗せ金利をできるだけ払わずに、就業不能も含めた広めの保障を確保したい方。
- フラット35や長期固定金利を軸に検討しており、「団信もそこそこ手厚い商品」を探している方。

\仮審査を申し込む!/
※ 審査結果によりご希望に添えない場合があります。金利は実行時金利が適用されます。最新の適用条件は公式情報をご確認ください。
④ 保障は一般団信で十分(低金利重視)➡auじぶん銀行

特徴: 2024年末以降、「50歳以下×一般団信(特約なし)」向けの低金利プランを展開しており、金利重視の人に人気(2025年12月時点)。 団信は、がん50%保障団信(上乗せなし)、がん100%保障団信(+0.05%)、がん100%保障団信プレミアム(+0.15%)など、複数プランから選択可能。 「がんと診断されたらローン残高100%保障」が年+0.05%で利用できるなど、オプション団信の上乗せ金利が比較的低いのが特徴。
こんな人に向きやすい一般的な傾向:
- 50歳以下で、まずは最低限の保障でとにかく金利を下げたい方。
- 既に別のがん保険・医療保険に入っており、団信側の追加保障は薄めで良い方。
- がんリスクにだけ少しプラスしておきたい(がん100%保障団信など)方。

\仮審査を申し込む!/
※ 審査結果によりご希望に添えない場合があります。金利は実行時金利が適用されます。最新の適用条件は公式情報をご確認ください。
【Q&A】団信(団体信用生命保険)の疑問に答える
ここまでの内容を、Q&A形式でおさらいします。
まとめ:団信の内容をよく検討して、「金利タイプ→団信→金融機関」の順で選ぼう
| 状況や重視ポイント | 有力な候補金融機関(例) |
|---|---|
| 疾病リスクをしっかりカバーしたい(特に50歳以下) | 🔴 住信SBIネット銀行(スゴ団信・3大疾病/全疾病保障) |
| 低金利とがん100%保障の両立を求める | 🔵 PayPay銀行(がん100%保障団信) |
| 上乗せ金利なしで幅広く疾病保障がほしい | 🟢 SBIアルヒ(住宅ローン【SBI信用保証】・全疾病付団信) |
| 低金利重視、最低限の団信でOK | 🟠 auじぶん銀行(一般団信/がん団信を薄く追加) |
※上記の金融機関は2025年12月時点の代表例です。他にも条件の良い住宅ローン・団信は多数ありますので、必ず複数社を比較検討してください。
今回は以上です。
住宅ローンを検討する際、団体信用生命保険(団信)の仕組みや保障内容を理解しておくことは、返済者や家族にとって非常に重要です。
一般団信と特約付き団信の違いや、金利への上乗せの有無、健康状態に応じた選択肢など、判断すべき要素は多岐にわたりますが、「金利タイプ → 必要な保障の優先順位 → 具体的な金融機関」の順で整理すると決めやすくなります。
 MIYABI
MIYABI記事を読み終えたら、まずは①自分たちの希望金利タイプを決める→②欲しい保障を3つまでに絞る→③本記事で紹介した銀行も含めて2〜3社をピックアップして仮審査という流れで動いてみてください。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品や契約についての勧誘や投資助言を行うものではありません。実際の金利・手数料・保障内容・税制・条件等は変更される場合がありますので、必ず最新の情報を各金融機関・保険会社・関係機関の公式サイトや商品説明書・重要事項説明書、窓口でご確認ください。また、保険・税金・法的な取り扱いについては、必要に応じて税理士・弁護士・社会保険労務士・保険募集人などの専門家へご相談ください。最終的なご判断はご自身の責任でお願いいたします。














