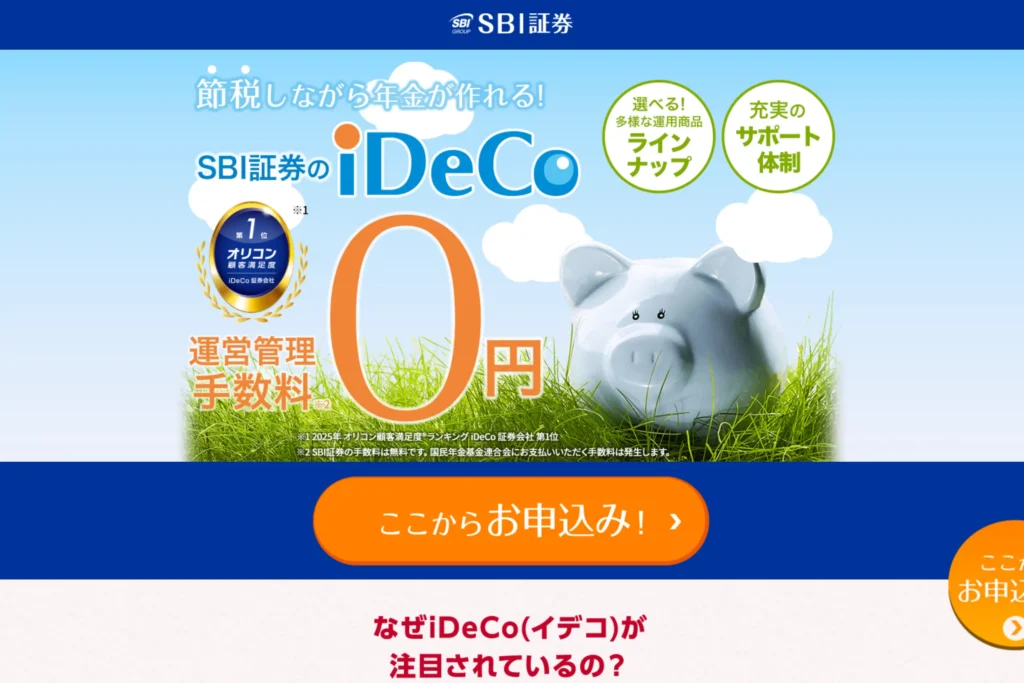独身に生命保険はいらない?検討すべきケースや備えるべきリスクを解説します

「独身に生命保険はいらない」と聞いたことはありませんか?
確かに、扶養する家族がいなくて貯蓄が十分にある場合、生命保険の死亡保障は必ずしも必要ではありません。
しかし貯蓄に余裕がない人や自営業で公的保障が手薄な人は、病気やケガで働けなくなったとき自分の生活を守るために、状況に応じた保障を備えておくことが大切です。
 ねくこ
ねくこ本記事では「独身は生命保険がいらない」といわれる理由とともに、独身者が検討すべき保障内容について詳しく紹介します。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の保険商品の勧誘ではありません。保険加入の可否や保険料は個々の状況・保険会社によって異なります。最新の制度や商品内容については公的機関や各保険会社の資料もご確認ください。
まずチェック!独身のあなたは生命保険が必要?診断チャート

独身の保険ニーズは、職業や貯蓄額によって大きく異なります。
 ねくこ
ねくこ以下のポイントを2分でセルフチェックしてみましょう。
扶養家族がいるか?
もし、扶養家族がいない独身者は、基本的に大きな死亡保障は不要です。
自分が亡くなっても養う家族がいなければ、生命保険本来の目的(遺された家族の生活保障)が当てはまりません。
 ねくこ
ねくこただし、高齢の親など経済的支援が必要な親族がいる場合は後述のとおり検討しましょう。
十分な貯蓄があるか?
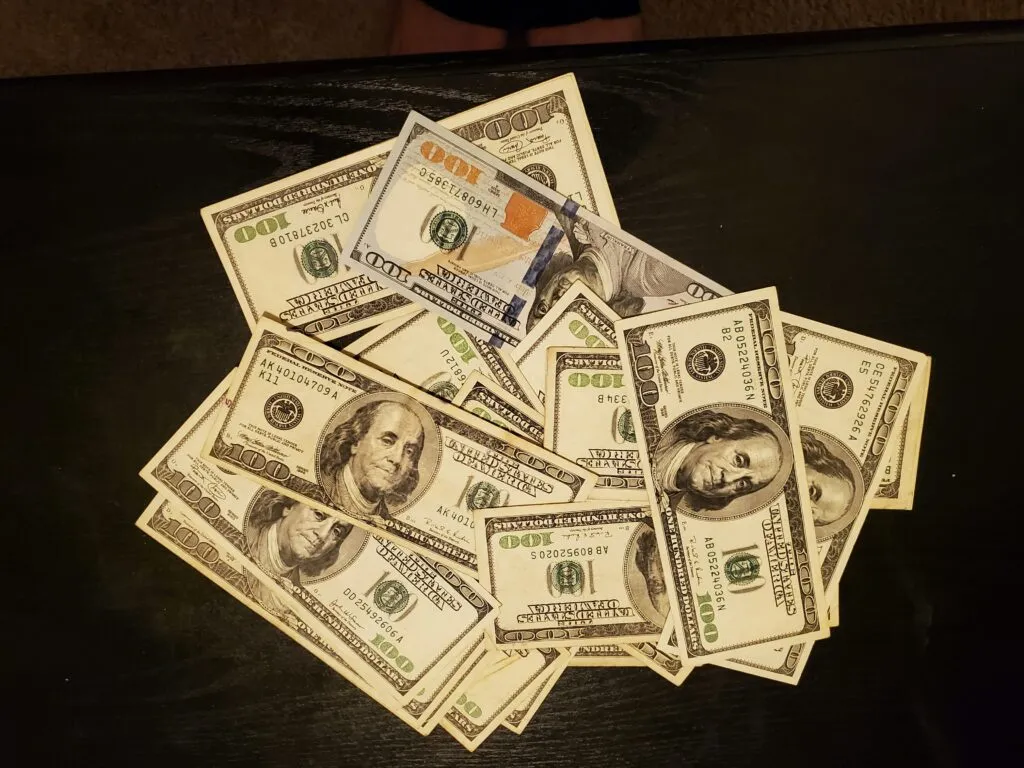
貯蓄が生活費の数ヶ月~年分あり、公的医療保険もある会社員の場合、医療費や一時的な収入減は貯蓄と公的保障でまかなえる可能性があります。
例えば会社員なら、病気やケガで働けない場合でも健康保険から最長1年6か月「傷病手当金」が支給されます。
高額療養費制度では、2025年8月診療分から70歳未満・年収約370万~770万円(3割負担)の月額上限は「88,200円+(医療費-294,000円)×1%」です。
たとえば医療費が100万円なら95,260円が上限※になります。
※直近12か月で4回目以降に該当する月は48,900円。
雇用形態(会社員か自営業か)も重要
雇用形態(会社員か自営業か)も重要です。
会社員であれば前述の傷病手当金など公的保障が比較的充実していますが、自営業・フリーランスは公的な収入補償がありません(国民健康保険には法定の傷病手当金制度がなく、原則として収入補償はないため※)。
 ねくこ
ねくこ自営業者ほど、働けなくなったときのリスクに備える必要性が高いといえます。
※国民健康保険の傷病手当金: 法律上は給付が定められておらず、各自治体の条例・規約による任意給付として支給される場合があります(例:新型コロナウイルス感染症での特例給付)。全国一律の制度ではありません。
老後資金をどう準備するか?
将来の生活資金に不安がある人は、貯蓄型の生命保険(終身保険や個人年金保険)で積立てる方法もあります。
ただし途中解約時の元本割れリスクや流動性の低さも把握しておきましょう。
 ねくこ
ねくこ積立てが苦手な人にとっては「強制的な貯蓄」として有用ですが、運用利回りや税制優遇の観点ではつみたてNISAなど他の手段との比較も必要です。


扶養家族がいない&十分な貯蓄がある独身者にとっては、生命保険は優先度が低い
以上の理由から、「経済的な扶養家族がいないかつ十分な貯蓄がある独身者」にとっては、生命保険は優先度の低い支出と言えます。
事実、ある調査では独身者の約4割が「生命保険未加入」または「医療保険など死亡以外の保障にしか入っていない」と回答しています(※詳細は後述)。
無理に保険料を払って保障を持たなくても、公的制度と手元資金で賄えるならそれに越したことはないからです。
 ねくこ
ねくこ一方、 「このままだと不安」 と感じた項目があるなら、そのリスクをカバーできる保険への加入を検討してみてください。
迷ったときは後述する専門家相談の活用もおすすめです。
独身でも生命保険への加入を検討すべきケース
一般的なイメージとは異なり、次のような独身の方は生命保険(主に医療系保障)加入を前向きに検討したほうがよいケースがあります。
当てはまるものがないか確認してください。
貯蓄が少ない人
十分な貯蓄がない場合、想定外の病気・事故で入院や手術が必要になったときに医療費の支払いが困難になる恐れがあります。
高額療養費制度で一定額以上はカバーされるとはいえ、入院時には食事代や差額ベッド代など自己負担が発生する費用も多くあります。
また治療費に貯蓄を充てて使い果たしてしまうと、退院後の生活費や通院費まで不足しかねません。
 ねくこ
ねくこ貯蓄が少ない人こそ、医療保険などで急な出費に備える必要性が高いと言えるでしょう。
高額療養費制度のカバー範囲に注意
高額療養費の対象外となる費用(保険適用外の費用)には注意しましょう。
差額ベッド代(「特別療養環境室」の室料差額)は公的医療保険が効かず全額自己負担です(患者の同意なく個室に入院した場合などは差額料を請求できません)。
また、先進医療の高度な治療技術にかかる費用(先進医療の「技術料」)は公的医療保険の給付対象外で全額自己負担※となります。
※ ただし診察・検査・薬剤・入院料など通常の治療部分は保険適用され、高額療養費制度の対象にもなります(先進医療特約を付ければこれらの技術料もカバー可能です)。
自営業・フリーランスの人

会社員等と比べて、自営業やフリーランスの人は収入が不安定で将来の予測が難しい傾向があります。
さらに前述のとおり公的医療保険でも収入補償(傷病手当金)が原則ありません。
こうしたリスクに備えるには、就業不能保険(所得補償保険)や所得補償保険への加入が有力な選択肢になります。
公的な障害年金もありますが、例えば障害等級2級でも月額約6.9万円(2025年度)程度で、働いていたときの収入を十分に補えないケースが多いです。
 ねくこ
ねくこ特に貯蓄が乏しい自営業者は、長期療養への備えとして民間の就業不能保険等を検討する価値があります。
扶養すべき親族(高齢の親など)がいる人
結婚して扶養する配偶者・子供はいないものの、たとえば高齢の両親の生活費を援助している場合や、障がいのある兄弟姉妹をサポートしている場合なども注意が必要です。
ご自身に万一のことがあれば、その親族の生活が立ち行かなくなる恐れがあるため、このような方は死亡保険による備えを検討しましょう。
独身の死亡保険金受取人は親や兄弟になるケースが多いですが、経済的支援が必要な家族がいるなら 「自分に何かあったとき、その人が困らないためのお守り」 として生命保険に入る意義はあります。
 ねくこ
ねくこまた、親族に対する死亡保障だけでなく、自分が病気・ケガで一時的に働けなくなった場合に仕送りや介護ができなくなるリスクも考えられます。
収入が止まることで生じるサポート断念のリスクについても、医療保険や就業不能保険でカバーできると安心です。
老後資金を保険で積み立てたい人
生命保険には、貯蓄機能を持つ商品もあります。
たとえば終身保険は解約返戻金がある程度貯まるため、一定期間支払った後に解約すれば払い込んだ保険料の一部(場合によっては同等以上)が戻ってくるものがあります。
また個人年金保険は老後に年金形式で受け取れる保険で強制的に口座引き落としで積み立てできるので、預金が苦手な方には手間なく資産形成できるメリットがあります。
貯蓄型保険は長期契約が前提

ただし注意点として、貯蓄型保険は長期契約が前提です。
契約からまだ年数が浅い段階で解約すると、返戻金が支払保険料総額より少なくなり元本割れすることがほとんどです。
また保険で積み立てる場合、資産運用の利回りは預貯金より高くないケースも多く、資金の流動性も低いです。
iDeCoやNISA等の制度とも比較検討

老後資金準備として保険を活用する場合は、iDeCoやNISA等の制度とも比較検討し、ご自身に合った手段かどうか判断しましょう。
 ねくこ
ねくこ以上のようなケースに該当する方は、独身であっても生命保険の加入メリットが大きいと言えます。
「自分は必要かも」と感じた場合、次章から独身者にとって特に備えておきたい保険の種類とその内容を確認してみてください。
独身者が備えるべきリスクと保障内容
最後に、独身の方に必要となり得る主な保障と、その保険商品について解説します。
ポイントは 「自分の生活を守るための保障」 を中心に検討することです。
具体的には 医療費負担・収入減少・葬儀費用 の3つのリスクに備える保険が柱となります。
① 病気やケガの医療費に備える:「医療保険」
医療保険は、病気やケガで入院・手術・通院した際に給付金を受け取れる保険です。
独身でも健康を害すリスクは誰にでもあります。
短期の入院・通院であれば貯蓄で対応できるかもしれませんが、治療が長期化すると医療費負担は増大し、仕事を休むことで生活にも影響が及びかねません。
公的医療保険の自己負担は3割とはいえ、例えば入院時に個室を利用すれば室料は全額自己負担になります。
また高度な先進医療を受ける場合、その技術料は全額自己負担で数百万円に及ぶケースもあるため、こうした公的保障のきかない費用も含め、病気やケガの際にお金の心配をしなくて済むよう備えておくことが大切です。
医療保険に加入しておけば、入院1日あたり○千円、手術1回△万円といった給付金が受け取れます。
給付金があることで自己負担分の医療費や入院中の雑費をカバーでき、貯蓄の目減りを防げます。
 ねくこ
ねくこ特に貯蓄が少ない独身者にとって、医療保険は安心材料となるでしょう。
特約の活用も検討を
医療保険にはオプションで先進医療特約を付けることができ、これにより先進医療の技術料(数百万円のケースもある)も実費補填可能です。
また、女性特有の病気に手厚い女性疾病特約や、退院後の通院治療を保障する通院特約などもあります。
ご自身の不安に合わせて必要な特約を付加することで、より万全な保障が得られます。
② 病気やケガで働けない期間の収入に備える:「就業不能保険」

就業不能保険(所得補償保険とも呼ばれます)は、ケガや病気で長期間仕事ができない状態になった場合に、毎月一定額の給付金(生活費の補填)を受け取れる保険です。
一般的に給付開始までに設定された免責期間(60日~180日程度が多い)継続して働けない状態になると支払い対象となります。
会社員の場合、健康保険から傷病手当金が支給される期間(最長1年6か月)はそれで賄えますが、自営業の場合は働けなければただちに無収入となってしまいます。
独身の自営業者・フリーランスにとって、長期の就労不能リスクは死活問題といえるでしょう。
公的な障害年金が受給できるケースもありますが、前述の通り2級で月約7万円程度では現役時代の収入をカバーするのは困難です。
そこで、特に自営業者やフリーランスの場合には就業不能保険への加入が強く推奨されます。
毎月の給付金額は契約時に設定でき、多くの商品では就業不能状態が続く限り契約で定めた一定期間(例:就業不能状態が続く限り最長で65歳まで)給付が継続する商品が多いです(支給条件や期間は商品によって異なります)。
 ねくこ
ねくこ独身で頼れる配偶者がいないからこそ、自分自身の「収入の保険」を用意しておくことが安心につながります。
補足
就業不能保険の商品によって、給付対象となる状態や免責期間、支給期間は異なります。例えば「精神疾患は対象外」「免責期間が3か月(90日)」「支給は最長2年まで」など制約もあるため、契約前によく約款を確認しましょう。
③ 万一の死亡や高度障害状態に備える:「死亡保険」(終身保険・定期保険)
独身の場合、前述の通り死亡保障の優先度は相対的に低めです。
しかし「自分の葬儀代くらいは用意しておきたい」「万一のとき親に迷惑をかけたくない」という考えから、お葬式代や死後の整理費用程度の保険金を用意しておく人もいます。
直近の調査(2024年)では葬儀には平均約119万円の費用がかかるとされています。
火葬だけで済ませる直葬なら数十万円ですが、一般的な葬儀では100万~150万円程度が一般的なようで、賃貸住宅の退去費用や遺品整理費などが発生すれば追加で数十万円かかるケースもあります。
こうした金額を念頭に置くと、死亡保険金を200万~300万円程度に設定しておけば、遺された親族にかかる経済的負担をほぼ賄えると考えられます。
死亡保障額設定の目安
独身者が死亡保険を検討する場合、以下の合計額を目安に必要保障額を計算してみましょう。
葬儀費用: 約120万円(葬儀の形式によりますが、全国平均は119万円)
整理費用: 約10~50万円(住居の明け渡し費用、遺品整理・お墓の手配等。規模により変動)
その他: 0~◯◯万円(死亡後に支払いが発生する未納医療費・公共料金などがあれば見積もり)
➡合計:約150~170万円+α が一つの目安になります。心配な方は少し多めに200~300万円の死亡保障を用意するとより安心でしょう。
死亡保険には一生涯保障が続く終身保険と、一定期間だけ備える定期保険があります。
葬儀代程度の保障なら終身保険で貯蓄兼用にしておき、将来不要になれば解約してお金を受け取るという活用も可能です(解約返戻金は加入からの経過年数によって増減します)。
一方、住宅ローンや事業ローンの保証人になっている場合など期間限定の責任に備えるなら、掛け捨ての定期保険で〇年間○○万円という保障を用意する方法もあります。
 ねくこ
ねくこなお、十分な貯蓄が既にあり「葬儀も貯金で賄えるし負債もない」という人は、あえて死亡保険に入らない選択ももちろんあり得ます。
独身者の死亡保障はあくまでオプション的な位置づけですので、自分の状況に照らし合わせて必要と感じるかどうかで決めるとよいでしょう。
【Q&A】独身の生命保険の疑問に答える
そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
「独身に生命保険はいらない」と聞いたことはありませんか?
一概に「いらない」とは言えません。
扶養家族がいない・貯蓄が十分なら死亡保障の優先度は下がりますが、貯蓄が少ない人や自営業など公的保障が手薄な人は、医療や収入減に備える保障が有効です。
独身のあなたは生命保険が必要?
必要かどうかは「扶養家族×貯蓄×雇用形態」で決まります。
家族を養っていない・貯蓄に余裕・会社員なら優先度は低め。
一方で貯蓄不足や自営業・フリーランスなら、医療保険や就業不能保険の検討価値が高いです。
扶養家族がいない場合は?
いないなら大きな死亡保障は原則不要です。
生命保険の本来目的は遺された家族の生活保障のためで、扶養者がいなければ必要性は低め。
ただし高齢の親など経済的支援先がある場合は死亡保障を検討しましょう。
十分な貯蓄がある場合は?
十分あれば公的制度とあわせて多くを賄えます。
会社員は最長1年6か月の傷病手当金があり、高額療養費制度で自己負担上限もあります(例:2025年8月以降、70歳未満・年収約370~770万円なら月の上限は「88,200円+(医療費-294,000円)×1%」で、医療費100万円でも自己負担は約95,260円)。
それでも差額ベッド代など対象外費用は残ります。
老後資金をどう準備するか?
「保険で積み立てる」は選択肢の一つです。
終身保険や個人年金保険は“強制貯蓄”になり得ますが、途中解約の元本割れや流動性の低さに注意。
つみたてNISA・iDeCoなど他制度との比較が前提です。
まとめ:独身でも「万一への備え」は状況に応じて必要
独身者の生命保険について、加入率のデータや検討すべき人の特徴、そして備えたい保障内容を解説しました。
繰り返しになりますが、たとえ独身でも病気やケガで働けなくなった際の生活費確保や、万が一自分が亡くなったときの葬儀費用など、様々なリスクへの備えは必要です。
もちろん、備え方は貯金や資産運用などさまざまな手段から総合的な判断とはなりますが、特に貯蓄が少ない方や収入が不安定な自営業者は、民間の保険加入を前向きに検討したほうがよいでしょう。
 ねくこ
ねくこ独身者が備えておくべき主な保障としては、以下のようなものが挙げられます。
- 医療保険: 病気・ケガでの入院費や手術費などに備える(高額療養費でカバーしきれない差額ベッド代・先進医療費用の補填にも役立つ)
- 就業不能保険: 長期間働けなくなった場合の収入減に備える(会社員より自営業者に重要)
- 死亡保険: 万が一自分が死亡したときの葬儀費用や整理費用に備える(必要性が低ければ無理に加入する必要はない)
最後に、生命保険は一度加入したら終わりではありません。
ライフスタイルの変化(結婚・出産・転職・老後の近づきなど)に応じて、必要な保障額や商品タイプは変わってきます。
 ねくこ
ねくこ独身の今は必要最小限の保障で済ませていても、将来家族ができたら手厚い死亡保障が要るかもしれませんし、その逆もあります。
定期的にご自身の状況を見直し、「今の自分に本当に必要な保障か?」 を考えて保険を選択・継続することが大切です。

保険選びや見直しなら、保険代理店の無料相談を受けてみると、プロの視点から保険の必要性や適切な保障額についてアドバイスを受けられます。
 ねくこ
ねくこ「独身ならこの保険はまだ必要ないですよ」といった率直な意見を言ってくれるFPは信頼できる存在です。
無理に勧誘される心配のない第三者の力も借りつつ、納得のいく保険プランを検討してくださいね。
※本記事で取り上げた内容は一般的な情報提供を目的としたものです。制度内容や金額などは変更される場合があるため、実際に契約する際は必ず最新の公的資料や各社の約款等を確認してください(本記事は特定の保険商品やサービスの勧誘を目的としたものではありません)。
参考資料・脚注 (※最新更新日時点)
[1] 生命保険加入率(男女計・男女別) – 2022(令和4)年度 生活保障に関する調査(生命保険文化センター) p.197【VI-1】より。全体79.8%(男性77.6%、女性81.5%)。(公表日: 2023年3月)
[2] 生命保険加入率(年代別) – 2022(令和4)年度 生活保障に関する調査 p.207【VI-3】より。30代~60代は男女とも加入率8割超。20代から30代での大幅上昇は結婚や出産によるニーズ増・収入安定によると推測。(生命保険文化センター)
[3] 高額療養費制度の自己負担限度額 – 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(令和7年1月23日資料)より。70歳未満・所得区分ウ(年収約370~770万円)で月額上限87,430円。(制度改定: 2025年8月〜)
[4] 公的年金の障害基礎年金額 – 日本年金機構「障害年金の受給要件」(令和7年度版)より。障害基礎年金2級 = 年額831,700円(月額約69,300円)、1級 = 2級の1.25倍nenkin.go.jp。(更新日: 2025年6月30日)
[5] 国民健康保険と傷病手当金 – 厚生労働省「国民健康保険制度(概要)」より。被用者保険と異なり国保には法定給付としての傷病手当金なし(ただし条例による任意給付で支給する場合あり)。(閲覧日: 2025年10月24日)
[6] 平均葬儀費用 – 公益財団法人生命保険文化センター「葬儀にかかる費用はどれくらい?」(鎌倉新書「第6回お葬式に関する全国調査」2024年)より。平均約119万円(前年111万円、コロナ禍経て増加)。形式別:一般葬161万円・家族葬106万円・直葬43万円等。
[7] 差額ベッド代(特別療養環境室料)の負担 – 厚生労働省通知(2016年)に基づく埼玉県「差額ベッド(特別療養環境室)について」解説より。患者の同意なしや治療上の必要による個室利用の場合、差額室料を請求できないと規定。
[8] 先進医療費用の自己負担 – 厚生労働省「先進医療の概要」より。先進医療の技術料は公的医療保険が適用されず全額自己負担。通常治療部分(診察・検査・薬剤・入院料等)は保険適用され、高額療養費制度の対象にもなる。先進医療特約で技術料もカバー可能。(確認日: 2025年10月1日現在)
[9] 就業不能保険の免責期間 – 公益財団法人生命保険文化センター「就業不能保障保険」解説より。就業不能状態が一定期間継続(例: 60日や90日)した時点から給付金支払い開始となる商品が一般的。免責期間は商品により14日~180日程度まで様々。