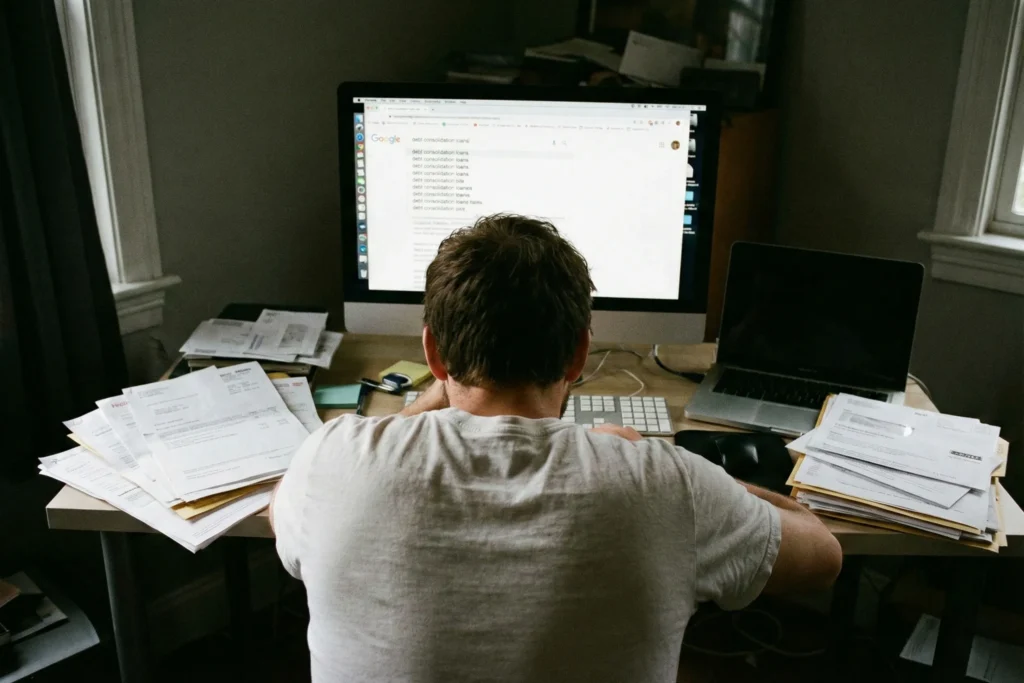【2025年11月20日】の経済・時事ニュースまとめ
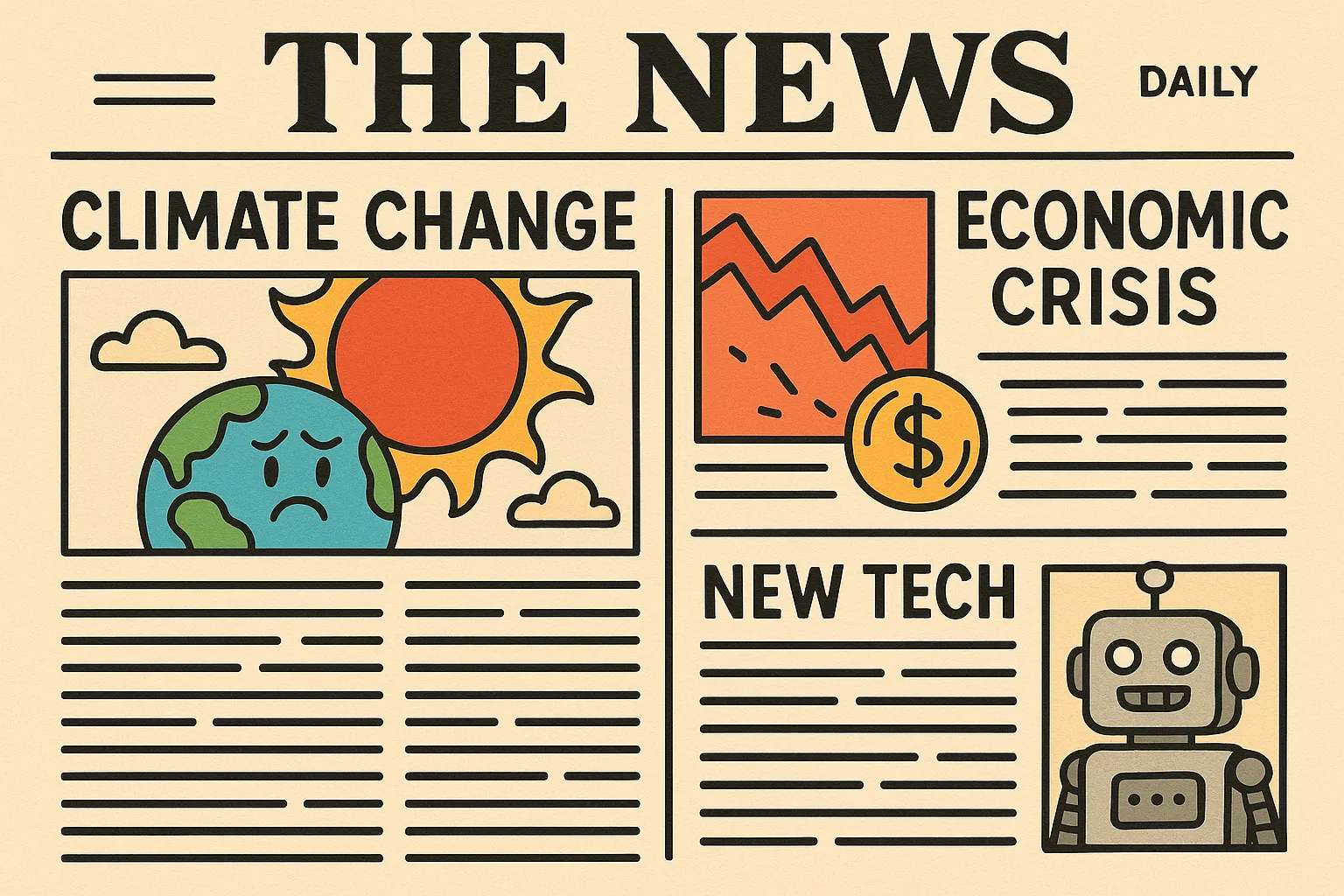
2025年11月20日の金融市場は、日経平均が一時5万円台を回復し、ドル円が157円前後まで円安が進むなど、株高・円安が同時に進んだ1日です。
背景には、米エヌビディアの好決算をきっかけとしたAI関連株の買い戻しや、米利下げ観測の揺らぎによる長期金利上昇、高市政権の大型経済対策を巡る期待と不安が重なっていることがあります。
一方で、中国による日本産水産物の事実上の輸入停止、英国の物価指標の鈍化、中国の政策金利据え置きなど、海外要因も日本経済や家計に影響を与えつつあります。
 ねくこ
ねくここの記事では、最新の株価指数と為替、資産運用で意識したいポイント、国内外の主なニュースと私たちの生活への影響を整理してお伝えします。
主要株価指数・為替レート(2025年11月20日10時時点)
| 指標 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 50,193.18円 | +1,655.48(+3.41%)円 |
| NYダウ | 46,138.77ドル | +47.03(+0.10%)ドル |
| S&P500 | 6,642.16ポイント | +24.84(+0.4%)ポイント |
| ドル円為替(ドル/円) | 157.35円 | +0.35円 |
20日10時時点の主要な株価指数とドル円レートを、日本時間ベースで一覧に整理します。
米国株は19日の取引で小幅に反発し、その流れとエヌビディア決算への期待を受けて東京市場では日経平均が大幅高となり、為替は円安基調が続いています。
日経平均はAI関連中心に急反発し一時5万円台を回復
日経平均株価は20日午前、前日比で一時2,000円超の大幅高となり、心理的な節目とされる5万円台を回復しました。
背景には、米エヌビディアが第4四半期売上高見通し650億ドルと市場予想を上回るガイダンスを示し、時間外取引で株価が5%前後上昇したことで、日本でもアドバンテストや東京エレクトロンなどAI関連銘柄への買い戻しが広がったことがあります。
前日の東京市場では、高市政権の大型経済対策を巡る財政悪化懸念から株・債券・円が同時に売られる「トリプル安」となっており、その反動もあって短期筋の買い戻しが膨らんだ面も指摘されています。
 ねくこ
ねくこ大きく下げた翌日に一気に戻す相場はニュースや投資家心理で値動きが振れやすく、短期売買で追いかけると想定より大きな損失につながるリスクが高い局面です。
米国株は利下げ観測の揺らぎをにらみつつ小幅反発
19日の米株式市場では、ダウ平均が前日比47ドル高の46,138.77ドル、S&P500が24.84ポイント高の6,642.16と、いずれも小幅に反発しました。
同日公表された10月FOMC議事要旨では物価2%目標への進展に懸念を示す声と景気下振れを懸念する声が交錯しています。
さらに、政府機関閉鎖の影響で10月と11月の雇用統計の公表が遅れる見通しが示されたことで、長期金利が4%台前半まで上昇し12月利下げ観測が後退しています。
こうした中でもエヌビディアなどAI関連の好決算期待が指数を下支えし、米株全体としては様子見と期待の綱引きの中で小幅高にとどまった形とみられます。
 ねくこ
ねくこ米国の金利やFOMCの見通しは世界中の株価や為替に波及するため、米株に直接投資していない人にとっても、長期金利やFRBの発言がどの方向を向いているかを押さえておくことが大切です。
ドル円は157円台前半まで円安が進み10カ月ぶりの水準
ドル円相場は19日のニューヨーク市場で一時1ドル=157円18銭前後まで上昇し、約10カ月ぶりの円安ドル高水準となりました。
20日10時時点の東京外国為替市場でもドル円は157.35円前後と高止まりし、円売り基調が続いています。
日銀の早期利上げ観測の後退に加え、高市政権の大規模経済対策による財政悪化懸念や米国の利下げ観測後退が重なり、海外投資家の「日本売り」が意識されていると指摘されています。
 ねくこ
ねくこ急激な円安は輸入物価を押し上げる一方で、外貨建て資産を持つ人には円換算で含み益が出やすいなど、家計への影響が人によって大きく異なる点にも注意が必要です。
資産運用をしている人がこの局面で心掛けるべきこと
相場が大きく動いた日ほど、短期の値動きに振り回されずに、自分のリスク許容度や家計の状況を改めて確認することが重要です。
 ねくこ
ねくこここでは、今日のような株高・円安局面で意識しておきたい一般的なポイントを整理します。
急騰局面でも「一気に買い増さない・売り切らない」
日経平均が1日で1000円以上動く局面では、値動きが大きいほど感情的になりやすく、一度に大きな金額を動かすと損失も増幅しやすくなります。
価格が急騰しているときは「今買わないと損をする」と感じがちですが、過去の相場でも大きな上昇の後に調整が入るパターンが繰り返し起きてきました。
売却についても、下落に耐えた直後の戻り局面で全てを売り切ってしまうと、その後の回復局面の恩恵を受けられないリスクがあるため、少しずつ分散して動くことが基本です。
 ねくこ
ねくこ大きく動いた日の夜ほど売買ボタンから一度離れて、翌日以降の資金計画やリスク許容度を紙に書き出して整理してみることをおすすめします。
NISAやiDeCoの積立は相場より「家計の計画」優先で考える
長期の資産形成に使われるNISAは、数十年単位での運用を前提とした制度であり、今日のような1日の値動きだけで積立額や商品を大きく変える必要は基本的にありません。

新しいNISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」をどう組み合わせるかが話題ですが、まずは毎月の貯蓄可能額と生活費を踏まえて、無理のない割合を決めることが大切です。

老後資金づくりを目的としたiDeCoは原則60歳まで引き出せない代わりに所得控除などの税制優遇があるため、教育費や住宅ローン返済など中期的な支出と重ならない金額の範囲で掛金を決めることがポイントです。

 ねくこ
ねくこNISAやiDeCoの活用を検討するときは、金融機関のパンフレットだけでなく、公的な解説ページや複数メディアの記事を見比べて、手数料や商品ラインアップの違いも確認しておくと安心です。
円安局面でのFXや外貨建て資産はレバレッジと通貨分散に注意
ドル円が157円前後まで円安が進んでいる局面では「今から外貨を持たないと出遅れるのでは」と感じる人も増えますが、為替相場は株価以上に短期で大きく振れることがあります。
レバレッジをかけて売買するFXでは少ない元手で大きなポジションを持てる一方、逆方向に動いたときのロスカットリスクも高く、特に初心者は資金に対して過大な取引になっていないか慎重な確認が必要です。

外貨建て投資信託や海外株式などの外貨資産は、長期保有を前提に日本円と外貨のバランスを整える目的で活用し、短期の為替差益を狙いすぎない方が家計全体のリスク管理という観点では無理が少ないと考えられます。
 ねくこ
ねくこ外貨の割合は「資産全体のうち何割を外貨で持つか」という視点で考え、家族構成や収入の安定度、住宅ローンの有無などから、自分にとって眠れる範囲のリスク水準を探してみてください。
国内ニュース
ここでは、直近24時間に報じられた日本国内の主な経済・政策関連ニュースを取り上げます。
高市政権の20兆円超の経済対策と「責任ある積極財政」
政府が近く決定する経済対策の規模は補正予算の歳出と減税を合わせて20兆円を超える見込みで、子ども1人あたり2万円の給付や所得税減税、ガソリン税の軽減などが盛り込まれると報じられています。
高市早苗首相は「責任ある積極財政」の名の下で家計支援と成長分野への投資を同時に進める方針ですが、国債増発による財政悪化懸念から長期金利の急上昇や円安進行につながっているとの指摘も出ています。


市場では、経済対策が景気を下支えする一方で、持続可能な財政運営と両立できるかどうかが焦点となっており、今後の補正予算審議や日銀の政策運営に注目が集まっています。
 ねくこ
ねくこ家計の立場からは、給付金や減税の一時的なプラス効果だけでなく、将来の増税や社会保険料負担の可能性も含めて、トータルで家計にどんな影響があり得るかを冷静に考えておくことが重要です。
政府・日銀の三者会合で「市場動向を緊張感を持って注視」
19日には片山財務相、城内経済財政担当相、日銀の植田総裁が就任後初の3者会合を開き、急速な円安や金利上昇を踏まえ、市場動向を「高い緊張感を持って注視する」方針を確認しました。
会合では為替水準や国債市場への具体的な介入策には触れていないものの、政府と日銀が市場とのコミュニケーションを丁寧に行うことを再確認したとされ、過度な金利上昇や急激な円安をけん制するメッセージと受け止められています。
市場では今後も円安が進む場合には為替介入や臨時の国債買い入れオペなど具体的な行動に踏み切るかどうかが焦点となり、投資家は政府・日銀の発言内容を細かく追う展開が続きそうです。
 ねくこ
ねくこ個人としては、為替介入の有無を当てにして短期売買を繰り返すよりも、為替や金利が上下に振れる前提で家計やポートフォリオを組み立てておく方がストレスを抑えやすいと考えられます。
中国による日本産水産物輸入停止と地方経済への影響
中国政府が日本産の水産物輸入を事実上停止する方針を日本側に伝えたことが明らかになり、ホタテやナマコなどの輸出に依存してきた産地では驚きと落胆の声が広がっています。
背景には、高市首相の台湾有事に関する発言に対する中国側の強い反発に加え、福島第一原発の処理水海洋放出をめぐる技術資料が十分でないとする中国側の主張があり、外交問題が貿易や観光に波及している構図です。
中国はかつて日本産ホタテの最大の輸出先であり、前回の輸入停止時と同様に在庫滞留や価格下落が懸念されるため、国内消費拡大や新たな輸出先の開拓を支援する政策が急務となっています。
 ねくこ
ねくこ特定の国への依存度が高い産業では、地政学リスクが顕在化したときの影響が大きくなりやすく、地域の雇用や賃金にも波及し得るため、家計としても収入源の分散や職業選択の視点がますます重要になっています。
海外ニュース
国外でも、金融政策や物価、地政学リスクをめぐる動きが相場に大きな影響を与えています。
ここでは、直近24時間の海外での主な経済・金融トピックを3つに絞って整理します。
米FOMC議事要旨と雇用統計遅延で利下げ観測が後退
米連邦準備制度理事会が公表した10月のFOMC議事要旨では、物価2%目標への進展に懸念を示す参加者と、景気下振れリスクを警戒する参加者の意見が分かれていたことが明らかになりました。
さらに米政府が10月と11月分の雇用統計を12月会合前に公表できないとしたことで、FRBが十分なデータを持たないまま判断を迫られるとの見方から国債利回りが4%台前半まで上昇し12月利下げ観測が後退しています。
金利先物やSOFRオプション市場では12月の0.25%利下げに備えるポジションも残っており、市場とFRBの見通しのギャップが今後の価格変動を大きくする要因になりそうだと報じられています。
 ねくこ
ねくこ米国の利下げタイミングは世界の株価や為替、特に新興国市場への資金流れを左右するため、日本で投資信託や外国株を利用している人にとっても重要なチェックポイントです。
英国の10月CPI鈍化で12月利下げ観測が一段と意識
英国の10月消費者物価指数は前年比3.6%と、市場予想3.5%をわずかに上回ったものの9月の3.8%から伸びが鈍化し、インフレのピークアウトが意識されています。
英中銀のピル主席エコノミストは物価上昇圧力は総合CPIほど強くないとの見方を示しつつも、現時点での追加利下げには慎重な姿勢を崩しておらず、12月会合での判断に注目が集まっています。
物価鈍化と景気減速懸念のはざまで利下げ時期を探る構図となっており、ポンド相場もインフレ指標や金融政策コメントのたびに上下に振れやすい状態が続きそうです。
 ねくこ
ねくこ日本からの英国旅行や留学、現地不動産投資などを検討している人にとって、ポンド安はチャンスにもなり得ますが、現地の物価や金利動向を合わせてチェックすることが重要です。
中国のローンプライムレート据え置きで景気てこ入れは小出し
中国では20日、最優遇貸出金利であるローンプライムレートが公表され、1年物3.0%、5年物3.5%と前月から据え置きとなり、市場予想通りの結果となりました。
不動産不況や輸出の伸び悩みを背景に一段の景気てこ入れを求める声もある中で、当局は大幅な利下げが人民元安や資本流出を招くリスクを警戒し、金融緩和は小出しに続けるスタンスを維持しているとみられます。
中国経済の減速は日本企業の輸出やインバウンド需要にも影響し得るため、製造業や観光関連の決算や経営方針に対する市場の評価が今後の日本株の物色方向にも影響を与えそうです。
 ねくこ
ねくこ中国経済は統計の透明性が十分とは言えない面もあるため、単一の指標ではなく輸出入、企業業績、観光など複数のデータを組み合わせて、少し長い目で動きを追う姿勢が大切です。
エヌビディア決算とAI関連株を巡る世界市場の神経質な動き
米半導体大手エヌビディアは19日発表の決算で売上高が前年同期比62%増となったうえ、第4四半期の売上高見通しを650億ドルと示し市場予想を上回ったことで、時間外取引で株価が5%前後上昇しました。
この好決算を受けてエヌビディア関連のAI銘柄や米ハイテク大手にも買いが波及し、先物市場や時間外取引でS&P500先物が上昇、日本の寄り付きでもAI関連株への買い戻しが日経平均の上昇をけん引しました。
一方でエヌビディア株はここ数年で急騰し、AIバブル懸念もくすぶっていることから、決算内容は好調でも「成長が長く続くのか」という点を巡って強気派と慎重派の見方がせめぎ合っています。
 ねくこ
ねくこAI関連銘柄は期待が高い分、決算やガイダンスの一言で株価が大きく動きやすいため、個別株に集中しすぎず投資信託やETFなどで分散投資する方法も選択肢の1つです。
私たちの生活に起こること
今日のニュースは株価や為替だけでなく、物価や給料、税金、将来の年金といった私たちの生活に直結するテーマとも深く関わっています。
ここでは、想定される影響と今からできる準備のヒントを整理します。
円安と物価高は家計の「支出の中身」にじわじわ影響
ドル円が157円台まで円安が進むと、輸入品や原材料価格の上昇が数カ月後の食品や日用品、ガソリン料金などにじわじわと波及する可能性があります。

一方で企業は人件費や光熱費の上昇も抱えているため、賃上げと価格転嫁の両立が課題となり、家計にとっては名目の給料が増えても実質的なゆとりはあまり増えない状況が続くリスクがあります。
海外旅行や海外留学、輸入車や外貨建て保険などドル建ての支出を予定している人は、円安が続いた場合の予算増加もシミュレーションしておくと安心です。
 ねくこ
ねくこ物価上昇の波を完全に避けることは難しいため、食費やレジャーなど変動費の見直しだけでなく、家賃や通信費、保険料といった固定費も含めて家計全体のバランスをチェックしてみるタイミングと言えます。




給付金・減税と将来の負担増をどう見分けるか
今回の経済対策では子ども1人あたり2万円の給付や所得税減税など家計にとって短期的にプラスとなる施策が予定されていますが、その財源は国債発行など将来世代の負担に回る部分もあります。
手元に入るお金をすぐに消費に回すのか、一部を貯蓄や投資に回すのかは家庭ごとに事情が異なりますが、数年先の税金や社会保険料の動きも意識したうえで配分を考える視点が大切です。
特に住宅ローンや教育費、老後資金づくりなど長期のライフイベントが控えている場合は、一時的な給付や減税をきっかけに将来の資金計画を家族で話し合う機会にしてみてもよいでしょう。
 ねくこ
ねくこ給付金の使い道に「正解」はありませんが、少なくとも一部は非常時の生活防衛資金や将来のための積立に回すと、後で自分を助けてくれる可能性が高まります。
今日からできる3つのチェックポイント
1つ目は家計簿アプリや通帳を見直し、手取り収入と毎月の支出、貯蓄や投資額のバランスが今の物価水準に合っているかを確認することです。


2つ目は勤務先の給与明細や賞与の見込み、社会保険料の負担額の推移を把握し、今後の昇給ペースや転職や副業の可能性も含めて収入サイドの選択肢を考えてみることです。

3つ目はNISAやiDeCoなどの制度を活用している場合、今回のような相場変動を「長期の積立を続ける意味」を家族と共有するきっかけにし、リスクの取り方について共通認識を持っておくことです。
 ねくこ
ねくこ相場や政策はコントロールできませんが、情報を知った上で自分と家族にとって納得できる選択を積み重ねることは、どんな環境でも続けられる最も大切な資産形成の土台になります。
本記事は2025年11月20日時点で入手可能な情報に基づき作成した一般的なニュースおよび情報提供であり、特定の金融商品や投資行動を勧誘または推奨するものではありません。
将来の市場環境や政策、企業業績などは予測と異なる可能性があり、本文の内容は将来の投資成果を保証するものではありません。
実際の投資や資産運用に関する最終判断は、ご自身の判断と責任において行い、必要に応じて金融機関や専門家等への相談もご検討ください。