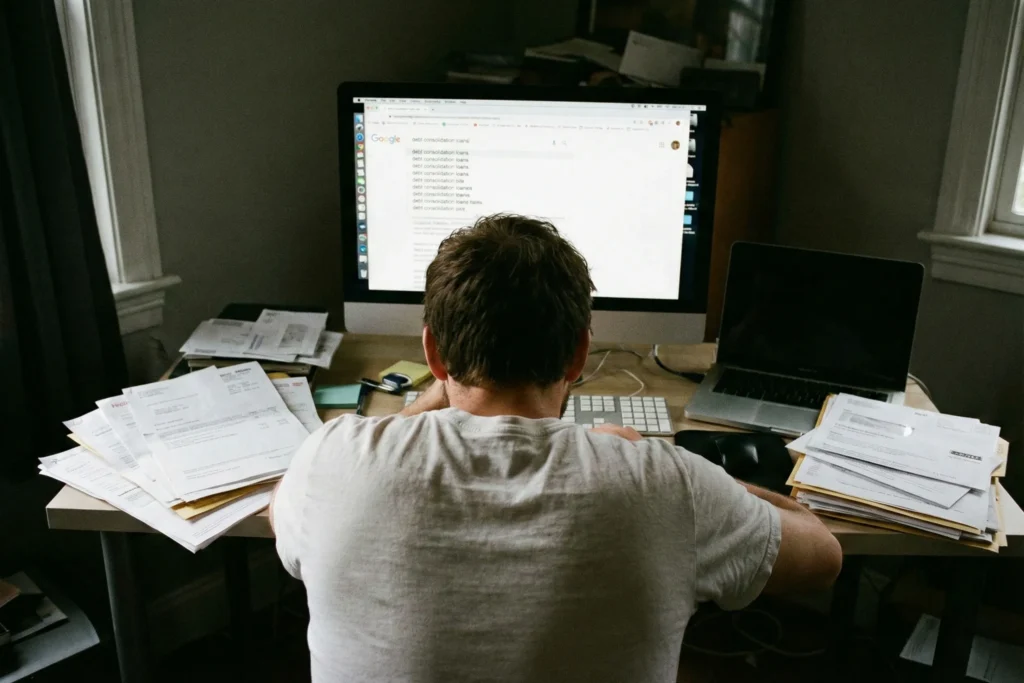今日から家庭でできる節電・節ガス術を大公開!〇円浮かせる節約術とは?

家計を預かる立場として、電気代やガス代の節約は気になるテーマですよね。
でも、「ちょっと温度を調整するだけで本当に意味があるの?」「毎日コツコツやっても大した効果はないのでは?」と感じている方も少なくありません。
実際は、日々の小さな工夫や習慣の見直しで、年間数千円から数万円単位の節約ができるケースが多くあります。


たとえばエアコンの設定温度や照明の使い方、シャワーの使い方を少し意識するだけで、毎月の光熱費は大きく変わります。
ここでは、公的機関や大手エネルギー会社の最新データをもとに、代表的な節電・節ガスアクションごとの「具体的な金額効果」をわかりやすく解説します。
 編集部マスクY
編集部マスクY「これならできそう」と思える実例も紹介するので、ぜひ今日からの家計管理に役立ててください。
節電・節ガスは具体的にどのくらいのインパクトがある?
毎月の電気代やガス代は、家計の中でも負担が大きい項目の一つ。
「節約しよう」と思っても、「どのくらい効果があるの?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、日常のちょっとした工夫で年間数千円から数万円単位で光熱費を減らすことも珍しくありません。
 編集部マスクY
編集部マスクYここでは、最新の公的データやエネルギー会社の試算をもとに、主な節電・節ガスアクション別の“お金”の効果を紹介します。
家庭でよく使われる節約アクションと年間の光熱費削減額
【試算前提】
電気31円/kWh・都市ガス約180円/m³目安。地域・機種・外気温・使用時間で±30%程度のブレあり。各数値の出典URLは表中に併記。
| 節約アクション | 年間の光熱費削減額(目安) | 参考出典 |
|---|---|---|
| エアコン冷房の設定温度を1℃上げる | 約940円 | 環境省 COOL CHOICE |
| エアコン暖房の設定温度を1℃下げる | 約1,650円 | |
| 冷蔵庫の設定を「強」→「中(冬場は弱)」に | 約1,910円(年間61.72kWhの削減) (周囲温度22℃・電力単価31円/kWh) | 東京ガス |
| 浴槽の追い焚きを1日1回減らす | 約6,190円 (200L・2時間放置で4.5℃低下を再加熱する想定) | 資源エネルギー庁 |
| シャワーを1人1日1分短縮 | 約3,210円(ガス約2,070円+水道約1,140円) 4人家族で約1.3万円/年。 | |
| LED照明へ全交換(白熱灯から) | 5,000円以上(全体換算)も現実的 | 東京電力 |
家庭全体でどれくらい安くなる?
上記は一例ですが、複数の節約アクションを組み合わせることで、一般家庭(4人世帯)では年間1~3万円以上の光熱費削減も十分可能です。
例えば、上述の
- 冷房設定+1℃
- 暖房設定-1℃
- 冷蔵庫の温度適正化
- 追い焚き削減
- シャワー短縮
などを併せて実践すると、
月々1,000円~2,000円の差が生まれ、年間だと約12,000円~24,000円の節約効果になります。
 編集部マスクY
編集部マスクY特に「お風呂の追い焚きを減らす」「シャワーの使い方を見直す」など、“水まわり”の工夫は即効性が高く、目に見えて請求額が減るため「まずここから」と始める家庭も多いです。
具体的なイメージがわく!こんな人はこう変わった
- 4人家族で「シャワー1分短縮+浴槽の追い焚き1回減」を徹底した場合、年間1万円近く光熱費が安くなったとの声も。
- エアコンの設定温度調整&フィルター掃除を続けて、夏冬トータルで5,000円以上節約できた家庭も多いです。
“ちりも積もれば大きな差”になる
1つひとつの節電・節ガス行動は「年間数百円~数千円」と、最初は小さな金額に見えるかもしれません。
しかし家族みんなで協力してコツコツ積み重ねていくと、1年後には2万円、3万円といった“プチボーナス”になることも珍しくありません。
 編集部マスクY
編集部マスクY浮いたお金は、外食やレジャー、旅行費用などに回すこともできます。
暮らしの楽しみが増えるのも、節約の大きな魅力です。
節約は「まず1つ」から始めてみましょう。
小さな工夫が1年後には大きな違いとなって家計を助けてくれる——それが、家庭の節電・節ガス術のリアルなインパクトです。
リビングでの節電・節ガス術|コツと裏技を紹介

リビングは家族が集まる場所だからこそ、電気やガスの使い方を工夫すれば節約効果も大きくなります。
ここではエアコンや照明、ガス暖房など、日常生活で取り入れやすい節電・節ガスの具体的なポイントを紹介します。
 編集部マスクY
編集部マスクY「無理なくできる」「家族で続けやすい」アイデアを参考に、今日から一歩ずつ始めてみましょう。
エアコンの上手な使い方
夏場に活躍するエアコンは、設定温度を見直すだけで大幅な節電につながります。
たとえば室温の目安を夏は室温28℃、冬は室温20℃程度を目安に保つことで、冷暖房の消費電力を効果的に抑えることができます。
冷房時に設定温度を1℃上げれば約13%、暖房時に1℃下げれば約10%も電力を減らせるというデータもあります。無理のない範囲で温度設定を調整するのがポイントです。
また、エアコンのフィルターは2週間に1度ほどお手入れするのが理想です。(冷房約4%/暖房約6%の削減効果)
フィルターの目詰まりを解消すると風量が回復し、冷暖房効率が上がって電力のムダを防げます。
さらに扇風機やサーキュレーターを併用して空気を循環させることで、設定温度を極端に下げなくても部屋全体を快適に保ちやすくなります。
冷房時は扇風機の風を上向きに、暖房時は下向きにすると、部屋の空気が効率よく対流し体感温度も均一になります。

お部屋の断熱対策もエアコン効率アップには欠かせません。
窓には厚手のカーテンや断熱シートを活用し、外から熱気や冷気が伝わりにくいよう工夫しましょう。窓周りの断熱強化は、冷暖房費の節約に直結します。
また、エアコン室外機の周辺に物を置かないよう整理し、吹き出し口の風通しを確保してください。
室外機は直射日光による熱で効率が下がるため、夏場は日よけで日差しを遮るのも効果的です(ただし風通しは妨げないよう注意しましょう)。
さらに、短時間の外出であればエアコンは「つけっぱなし」にした方が、結果的に有利になる場合もあります。
特に30分程度の外出なら、こまめなオンオフより付けっぱなしの方が電力消費が少なく済むという検証もあります。(住環境次第(断熱・外気温差・機種))
帰宅後に再度冷やすエネルギーを考慮し、状況に応じて賢く運転しましょう。
照明の節電ポイント
照明はLED化と使い方の工夫で確実に節電できます。
白熱電球や従来型蛍光灯をお使いなら、消費電力の少ないLED照明への交換を検討しましょう。
LED電球の消費電力は同じ明るさの白熱電球の約8分の1と非常に効率的です。(機器・明るさにより差)
またLEDは寿命も長いため交換コストも抑えられます。
加えて、不要な照明はこまめに消す習慣を身につけましょう。
「つい消し忘れる」という方は、人感センサー付きライトの活用やタイマー設定も有効です。
 編集部マスクY
編集部マスクY部屋を出る際にスイッチを切るクセをつけるだけでも積み重ねれば大きな節電効果があります。
ガス暖房機器の節約ポイント

冬場に活躍するガスファンヒーターなどのガス暖房を使う際も、少しの工夫でガス代を節約できます。
まず設定温度を必要以上に高くしすぎないようにしましょう。室温20℃程度を目安に、厚着をするなど衣服で調節すれば快適さを保ちつつガス消費を抑えられます。
暖房器具は窓際に設置すると冷気の侵入を和らげ、部屋全体を効率よく暖めることができます。
窓からの冷気が直接部屋に広がらないぶん、暖房効果が高まり無駄が減ります。
また、タイマー機能を上手に活用しましょう。
就寝時や起床時のタイミングに合わせてオンオフを自動化すれば、つけっぱなしの消し忘れを防いだり、必要のない時間帯に運転し続けたりするのを防げます。
例えば就寝30分前にオフ、起床前にオンという設定にしておけば、一晩中つけっぱなしにするより大幅にガスを節約できます。
 編集部マスクY
編集部マスクY安全面では一酸化炭素中毒防止のため定期換気は必須。就寝時の連続運転は避けましょう。
ガス暖房は空気を消費しますので、適切な換気を行いながら効率的に使いましょう。
キッチンでの節電・節ガス術|コツと裏技を紹介

キッチンは家電やガスの使用量が多い場所ですが、ちょっとした工夫で大きな節約効果を得られます。
ここでは冷蔵庫や調理など、身近な場面でできる節電・節ガスのポイントを紹介します。
冷蔵庫の節電ポイント

キッチンの中でも24時間稼働している冷蔵庫は、省エネ設定と収納方法の工夫で電気代を減らせます。
まず庫内の詰め込みすぎに注意しましょう。
冷蔵室は容量の約7割程度に収めて冷気の流れ道を確保すると効率よく冷やせます。ギュウギュウに物を詰め込むと冷気が行き渡らず温度ムラが生じて、食品の鮮度も落ちるうえ余計な電力を消費してしまいます。
一方で冷凍室は例外で、隙間なくパンパンに詰めた「満杯収納」が推奨されています。
冷凍庫内は詰まっている方が冷えた食品同士が保冷剤の役割を果たし、開閉時の温度上昇も抑えられるため効率的です。
製氷皿や保冷剤などで空間を埋めて冷凍効率を上げましょう。
また、熱いものは冷ましてから冷蔵庫に入れるのが鉄則です。
調理直後の熱々の鍋をそのまま入れてしまうと庫内温度が一気に上がり、設定温度に戻すまでコンプレッサーが余計に稼働するため電力を浪費します。
鍋料理などは粗熱を取ってから保存容器に移すようにしましょう。
調理での節約ポイント
毎日の調理でもガスや電気の節約につながるテクニックがあります。
火にかける際は蓋や落とし蓋を活用
まず、鍋やフライパンを火にかける際は蓋や落とし蓋を活用しましょう。
蓋をすることで熱が逃げにくくなり、調理時間が短縮されます。実際、鍋に蓋をするだけでガスの使用量を1割以上削減できるというデータもあります。
煮物では落とし蓋を使うことでさらに時短・節約につながります。
中火〜弱火が基本
火加減にも注意が必要です。強火で調理し続けると、炎が鍋底からはみ出している部分の熱が無駄になります。
鍋底に炎が収まるくらいの中火〜弱火が基本です。
特に煮込み料理では、一度沸騰したら弱火でも十分に煮えるので、必要以上の強火は避けましょう。
調理時間そのものを短縮する工夫も◎
調理時間そのものを短縮する工夫も有効です。
電子レンジや電気ケトルを活用して下ごしらえをする、圧力鍋を使うなどでガスや電気の使用量を抑えられます。
お湯を使う料理は一度に複数種類ゆでる、一度の調理で多めに作って残りを冷凍保存するなど、「まとめて調理」を心がけるとコンロの稼働回数も減り、効率的です。
お風呂・給湯での節電・節ガス術

給湯やお風呂は家庭のエネルギー消費の中でも大きな割合を占めるため、ちょっとした工夫で年間の光熱費を大きく減らすことができます。
ここでは給湯器の設定や、お風呂・シャワーの使い方で簡単にできる節約術を紹介します。
給湯器の設定見直し
給湯設備は家庭のエネルギー消費の中でも大きな割合を占めるため、設定温度の見直しだけでも節約効果は絶大です。
給湯器の温度設定は季節に応じて適切に調整しましょう。たとえば食器洗いや手洗いに使うお湯は高温すぎると危険ですし、無駄にもなります。
夏場であれば給湯温度は40℃前後でも十分な場合が多く、必要以上に熱くしないことがポイントです。
設定温度を1℃下げるだけでもガス消費を数%抑えることができます。
冬場はやや高めに設定しつつも、安全で快適な最低限の温度に留めることが節約につながります。
また、長時間家を空けるときや旅行・帰省などで数日以上お湯を使わない場合は、給湯器の電源をオフにしておきましょう。
待機中のパイロット点火や保温によるロスを防ぐことができます。
特に、旧式の給湯器は待機時にもガスを消費するものがあるため、使わないときはオフにする習慣が有効です。
お風呂とシャワーの節約術

毎日のお風呂でもガス代の節約ポイントがいくつかあります。
まず、追い焚き(お湯の再加熱)回数を減らす工夫です。家族で順番に入浴する場合は、できるだけ時間を空けずに続けて入るとお湯が冷めにくくなり、追い焚きの回数を減らせます。
保温シートや浴槽のフタも活用しましょう。入浴の合間にフタをするだけでお湯の放熱を防ぎ、次に入る人のお湯がぬるくなりにくくなります。
特に冬場はフタ+保温シートで追い焚きいらずを目指しましょう。
シャワーの使い方も見直してみましょう。浴びる時間を短くすることが、何よりの節約になります。
シャワーを1人あたり1日1分短縮するだけでも、1年で数千円のガス代削減が可能です。
4人家族なら年間8,000円以上の節約につながる場合もあります。さらに、シャワー時間を減らすことで水道代も同時に抑えられます。
シャワー時間を減らすコツとしては、洗っている間はこまめに止水すること。
「流しっぱなし」をやめるだけでも大きな効果があります。最近は手元スイッチで簡単に止水できる節水シャワーヘッドも多く、こうした製品に交換することで水の出る量が30~50%削減できるタイプもあります。
水圧や使い心地もチェックしながら、ご家庭に合った節水タイプを選びましょう。
【Q&A】家庭の節電・節ガス術の疑問に答える
そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
家庭での節電・節ガスはどのくらい効果があるの?
年間数千円~数万円の節約が可能です。
例えばエアコン温度調整やシャワー時間短縮など、日常の工夫で月1,000~2,000円の差が出ます。
エアコンの設定温度を1℃変えるとどれくらい節約できる?
冷房+1℃で約940円/年、暖房−1℃で約1,650円/年(2.2kW機・使用9h/日、外気温31℃/6℃想定)の想定になります。
消費電力は冷房時で約13%、暖房時で約10%減らせます。
冷蔵庫の温度設定を見直すとどれくらい節電できる?
「強」から「中」へ変更するだけで約1,910円/年の節約になります。
冷蔵室は7割収納、冷凍室は満杯収納が効率的です。
浴槽の追い焚きを減らすとどれくらい節約できる?
1日1回減らすだけで約6,190円/年の節約になります。
保温フタやシートを活用するとさらに効果的です。
シャワー時間を短縮するとどれくらいお得になる?
1人1日1分短縮で約3,200円/年(ガス+水道)が節約可能。
4人家族なら年間8,000円以上浮く場合もあります。
照明をLEDに変えるとどれくらい節電できる?
白熱灯からLEDに全交換すると年間5,000円以上の節約になります。(機器・明るさにより差)
消費電力は白熱灯の約1/8で、寿命も長いです。
給湯器の設定温度を下げると効果はある?
1℃下げるだけでガス消費を数%削減できます。
夏は40℃前後に、使わないときは電源オフが有効です。
調理で節約するにはどうすればいい?
鍋に蓋をして調理時間を短縮、中火~弱火を基本にするとガス使用量を1割以上減らせます。
圧力鍋や電子レンジも活用しましょう。
おわりに|無理なく今日から節約を始めよう
以上の節電・節ガス術は、どれも日常生活で気軽に始められるものばかりです。
最初は意識するのが大変かもしれませんが、習慣になれば自然と光熱費の削減につながります。
浮いたお金は他の出費に回したり貯蓄に充てたりできますし、省エネは地球温暖化対策にも貢献できます。
ぜひ、できることから一つずつ実践してみてください。
家族と協力して楽しみながら取り組むのもコツです。
「今月は先月より○○円安くなったね」と成果が見えるとモチベーションも上がるでしょう。

なお、更なる節約のためには、省エネ性能の高い家電への買い替えや電気・ガス契約プランの見直しも有効です。実際、電気とガスをセット契約にして料金を安くできるプランも存在します。
そうした工夫も併せて検討しながら、無理のない範囲で長く継続することが大切です。
毎日の小さな節約の積み重ねが、年間では大きな節約効果となってあなたの家庭を助けてくれるはずです。