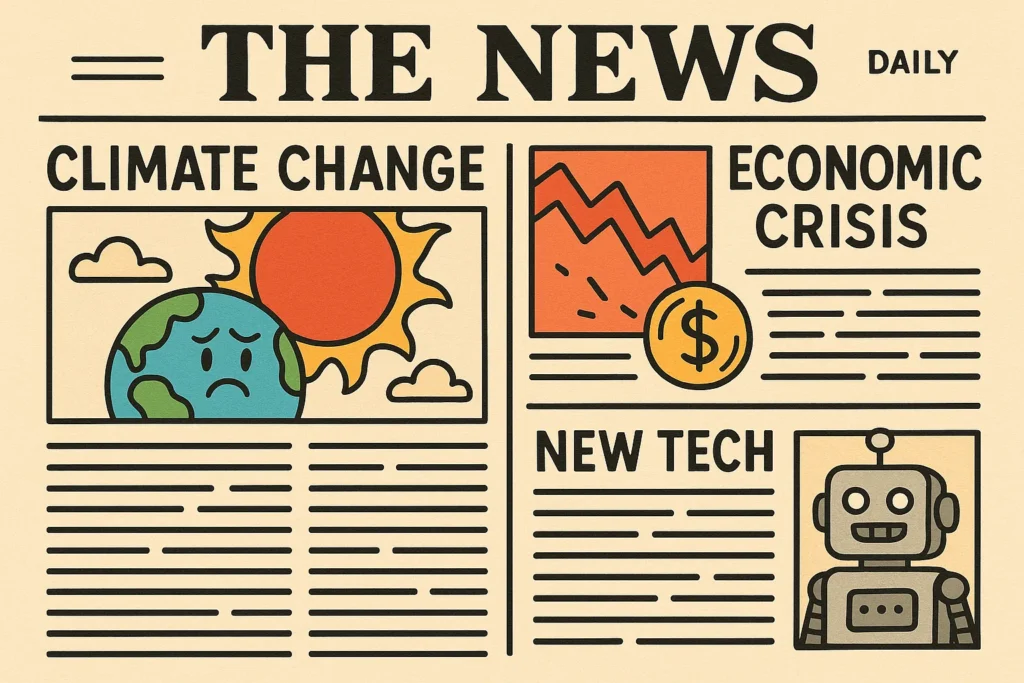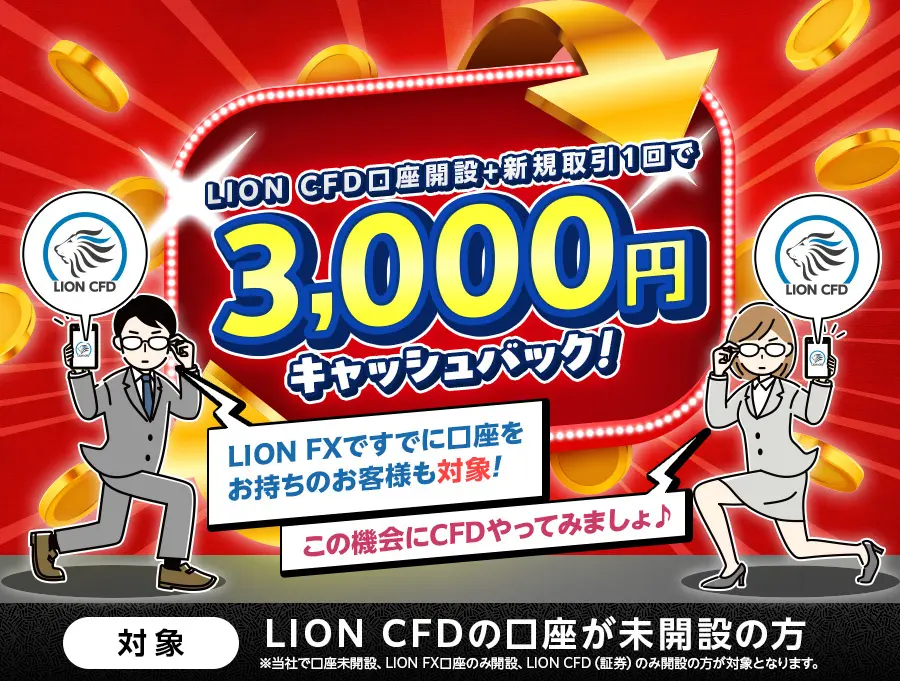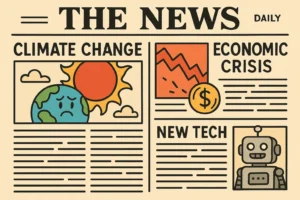【2025年10月20日】の経済・時事ニュースまとめ
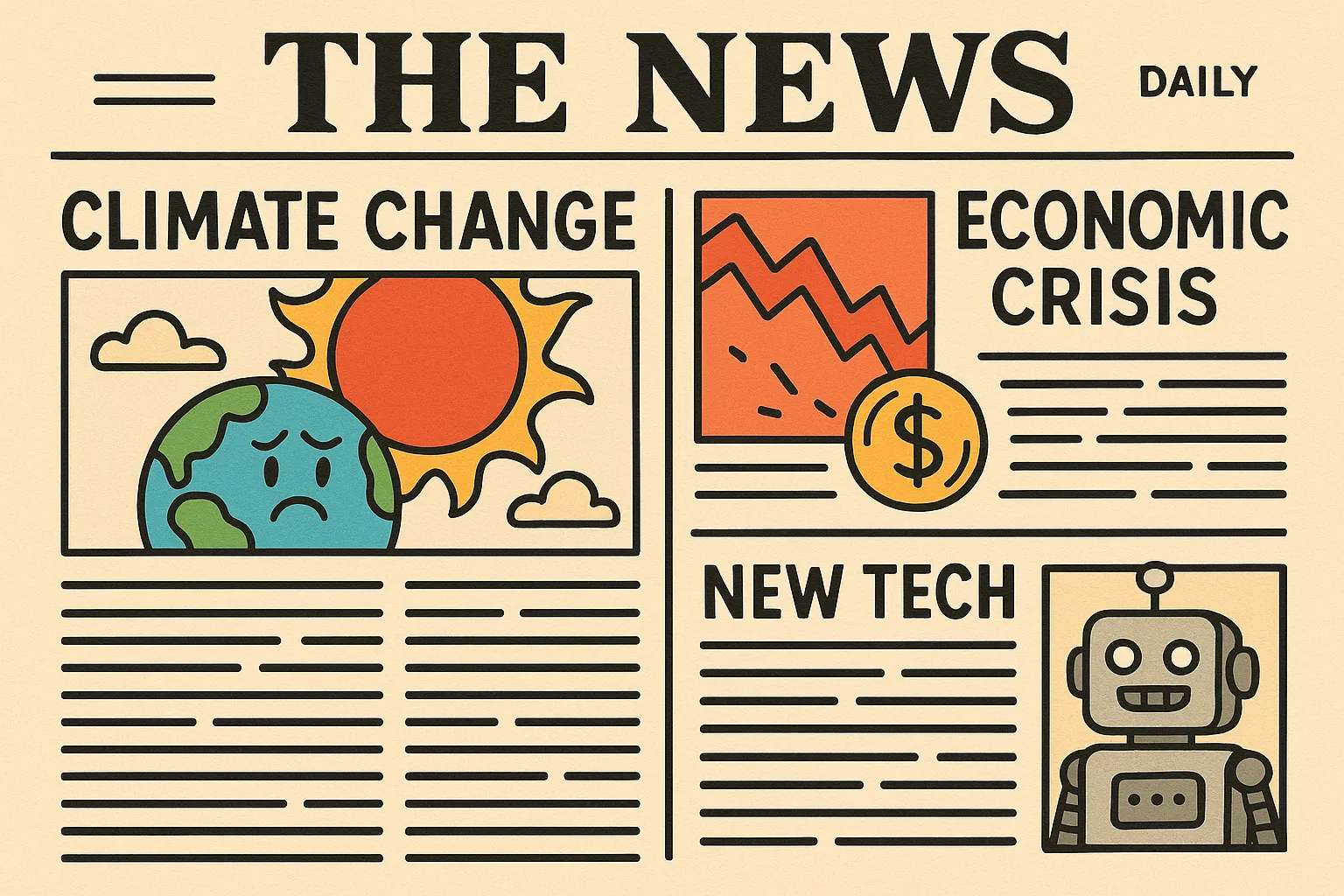
きょう10月20日は、国内で自民党と日本維新の会の連立合意が大詰めを迎え、政策期待を背景に株高・円安が進んでいます。
海外では中東情勢の緊張や米中通商を巡る「新常態」の見方が報じられ、リスク資産の方向感にも影響が出ています。
 ねくこ
ねくこ本稿では、10時時点の主要指数と為替の動き、資産運用での留意点、国内外の主要ニュースをわかりやすく整理します。
主要株価指数・為替レート(10月20日 10時25分時点)
| 指標 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 48,791.03円 | +1,208.88(2.54%)円 |
| NYダウ | 46,190.61ドル | +238.37(0.52%)ドル |
| S&P500 | 6,664.01ポイント | +34.94(0.53%)ポイント |
| ドル/円為替 | 151.08円 | +0.66円 |
日経平均の上昇要因と見通し
自民党と日本維新の会の連立合意が報じられ、政策不確実性の一部後退と景気対策期待が株式市場を押し上げています。
アジア株全体も米金融政策の緩和観測や企業決算への期待で底上げされ、東京市場の追い風になりました。
NYダウとS&P500の手がかり
米国ではTeslaやNetflix、Ford、Intelなどの決算が控え、ガイダンスと在庫・需要コメントが指数変動のカギになります。
金利動向と合わせて先物は小動きで、決算待ちの姿勢がにじむ状況です。
 ねくこ
ねくこ米10年金利の低下がリスク資産の下支えとなる一方、通商摩擦のヘッドライン次第でボラティリティが高まりやすい地合いです。
ドル/円の高止まり
ドル/円は150円台後半で推移し、政策期待と金利差を背景に円がやや軟化しています。
市場では政権発足後の補正や減税の有無、財源手当の示し方が注視されています。
 ねくこ
ねくこ日銀・上田総裁は判断材料の積み上げを強調しており、10月会合へ向けたガイダンスが為替の方向感に影響し得ます。
資産運用をしている人がこの局面で心掛けるべきこと
長期分散の軸はずらさない
政治イベントや地政学で短期の値動きは大きくなりますが、長期分散・積立という軸を保つほど結果のブレは小さくなります。
 ねくこ
ねくこ直近の株高・円安も「イベントドリブン」の色彩が濃く、ポートフォリオ全体のリスクを先に点検する姿勢が有効です。

NISAなどの積立投資は相場の上下を「時間分散」でならす機能があります。
制度面では非課税枠の使い方を年内も点検しておく価値があります(銘柄選択は各自で検討)。
為替の影響を想定する
円安局面では外貨建て資産の円評価額は増えますが、為替が反転すれば逆回転も生じます。
外貨比率や為替ヘッジの有無を、家計の将来支出通貨と照らして選ぶ発想が重要です。
足元の円安は輸入価格を通じて生活コストに波及し得るため、投資額を増やす前に、家計の流動性と非常時資金の厚みを優先するのが安全運転です。
金利上昇に備える
今後の金利経路が不確実なため、デュレーションのとり方は段階的に行い、クレジットリスクと利回りのバランスを見直します。
インカム狙いの配分は、金利上昇時の価格下落に耐えられる範囲で設定しましょう。

iDeCoなどの私的年金制度による老後資金の土台は積立期間の長さが成果を左右します。
資産配分や手数料水準を年に数回は見直し、ライフイベントに沿ってリスクを調整しましょう。
※本節は一般的な情報提供であり、特定商品の勧誘や投資助言ではありません。
国内ニュース
自民×維新が連立合意へ
自民党と日本維新の会が大枠で連立に合意し、きょうにも正式化される見通しと報じられました。
維新は当面、閣外からの協力となる可能性が示されています。
物価・賃上げに資する景気下支え策や寄附規制の見直しなど、政策折衝の行方が注目されます。
円安進行と「タカイチ・トレード」

政策期待から株高・円安の組み合わせを意識した売買が広がり、ドル/円は150円台後半で推移しました。
円安は輸入コスト増を通じて物価に上振れ圧力となり、家計と企業収益にプラス・マイナスの両面効果をもたらします。
為替の方向感は日銀のスタンスと財政運営の透明性に左右されやすい局面です。
東京市場の上昇基調
アジア株は総じて堅調で、東京は政治の先行き見通し改善や米利下げ観測を追い風に上昇しました。
企業決算シーズン入りで、ガイダンスと設備投資・賃上げの持続性が評価軸になります。
バリュエーションは金利や為替と連動しやすく、イベント前後の変動に注意が必要です。
海外ニュース
イスラエルとガザの停戦を巡り緊張再燃
イスラエルは停戦違反を理由に空爆を実施後、停戦と人道支援再開に戻ると表明しましたが、情勢はなお不安定です。

原油や安全資産への資金シフトを通じ、投資家心理に断続的な影響を与える可能性があります。
続報の政策対応と各国の仲介努力が注目されます。
米中通商を巡る「ニュー・ノーマル」
米中の対立は激化と緩和を繰り返しつつ、関税・輸出規制・サプライチェーン再編が恒常化する「新常態」に入ったとの見立てが示されました。
日本企業は調達と販売の多元化を加速する一方、国内投資の呼び込みやコスト高対応が課題になります。
為替と貿易フローの不確実性はしばらく続く見込みです。
韓国の不動産抑制策が短期債市場を刺激
韓国当局の住宅市場冷却策が、短期国債需要の押し上げ要因として意識されています。
アジア債券全体のイールドカーブにも連想が広がり、金利感応度の高いセクターのバリュエーションに注意が必要です。
ルーブル美術館で王冠宝石の大胆窃盗
パリのルーブル美術館で王冠宝石が白昼に盗まれ、犯行は数分で行われたと報じられました。
文化財の物理・デジタル両面の防犯体制や保険の在り方が改めて問われています。
観光・文化産業のリスク管理も幅広い議論が必要です。
私たちの生活に起こること
家計の視点
円安が続くと輸入品やエネルギー価格の上振れが家計を圧迫し、賃上げの実感を相殺する場面があり得ます。

定期代や保険、サブスクなど支払いの見直し余地を把握し、固定費の引き下げで可処分所得を守ることが重要です。



 ねくこ
ねくこ支出は「固定費→変動費→嗜好品」の順で削ると効果が早く、次に緊急資金の確保、最後に投資額の微調整を検討する手順が実務的です。
投資と貯蓄のバランス
イベント前後の値動きに合わせた過度な売買はコストと機会損失を招きやすく、目標資産配分に引き戻す「リバランス」の徹底が有効です。
一次情報と複数メディアをクロスチェックし、日付や時刻、統計の定義を確認する習慣がリスク低減に直結します。
中小企業・個人事業主
輸入コストの上振れと金利上昇は資金繰りに波及します。

在庫回転と価格転嫁の方針を、為替前提を含めて見直すタイミングです。
仕入れ価格の前提為替を契約に明示し、価格改定の条件を事前合意しておくことでトラブルを減らせます。
※投資判断はご自身の責任で行い、必要に応じて金融機関等の専門家にご相談ください。